- 2023年07月10日

この記事をシェアする
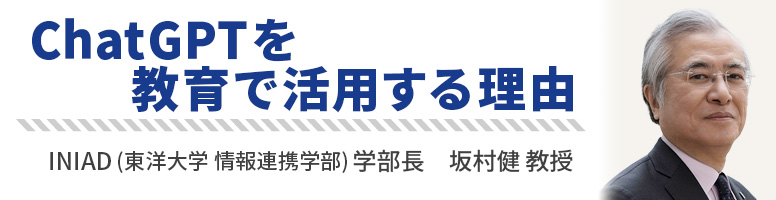
ChatGPTは思考を補助するパートナー
AIとの対話を通じて自分の考えを深める
- この記事のポイント!
-
- 1
- 生成系AIとの対話を繰り返し、思考を深める
- 2
- 利活用は、利便性・危険性の両面で議論
- 3
- これから求められるのは問題設定能力
ChatGPTは
考える力を増強するツール
本学部では、全学生がChatGPT-4(以下、ChatGPT)を学修で活用できるよう、AI利用教育システムを開発しました。リサーチ、ブレーンストーミング、資料の作成、プログラミング工程のコーディングなど、さまざまな場面で自由に使ってよいことにしています。さらに、学生だけでなく教職員も、授業や研究、学部の運営などで活用します。
積極的に活用している理由は、ChatGPTを「自分の頭で考えること」をサポートするツールだと捉えているためです。「自分の頭で考える」上で重要なことの一つに、別の立場から問題を捉えるということが挙げられます。ChatGPTを壁打ちの相手にして、違う角度から考えを深めたり、思考を整理したりすることで、より高度な思考力を身につけられると考えています。
私は本学部で哲学の授業を担当していますが、今年度は「なぜ人を殺してはいけないのか。ChatGPTと4回以上やりとりして、ユニークな検討を行い、検討過程の記録を提出せよ」という課題を出しました。ChatGPTの活用を前提に、課題の出し方を変えたのです。
ChatGPTは、質問に応じて異なる回答を用意します。そのため、単にレポート課題をそのまま投げるのでなく、「これと対立する意見を教えてください」「これまでの議論を整理してください」など、学生が行う質問・指示によって、検討内容やその質が変わってきます。対話の記録も提出させることで、学生がどのような質問をしたか、思考が深まっているか等を評価することができます。 こうしたAIとの対話を繰り返す中で、学生は自身の考えの深め方や対話の仕方を身につけていきます。
また、ChatGPTは、学生それぞれに合った相談相手や教師になることも利点です。人間はどんなに親切な教師でも1人の学生から1日に100も200も質問を受けることはできません。しかし、ChatGPTは好きなときに、好きなだけ質問でき、対話を続けることができます。

実際に使用し
危険性と利便性の両面を知ることが重要
ChatGPTをはじめとする生成系AIの活用で、懸念される事柄のひとつに、誤ったことがもっともらしく回答される「ハルシネーション」があります。そこで、私は学生に対し「わざとハルシネーションを起こさせるような質問をいくつか行い、なぜハルシネーションが起こったかを考察せよ」という課題を出しました。ハルシネーションの起こる原理や危険性を理解するとともに、ハルシネーションを起こさない質問のスキルを習得するのが狙いです。ただ、生成系AIの世界も、日進月歩でハルシネーションや差別的回答をしないように進化しており、この課題もしばらくすると出せなくなるかもしれません。
生成系AIを使う上での課題として、もう1つよく指摘されるのが、本来自分で考えるべきことをAIで代替することの弊害です。しかし、この点は生成系AIにも、意外というと何ですが「常識」があります。例えば就職活動のエントリーシートをChatGPTに書かせる是非を尋ねてみたところ、エントリーシートは何のための書類であるかを説明した上で、「AIはあなたという人間を知らないので一般的なものしか書けない」など利用するリスクとその根拠を3つ挙げ、最後に「したがって、ChatGPTを使ってエントリーシートを作成する補助にするのはいいが、丸投げすることはお勧めできません」と回答してきました。このように、倫理的な問いにも良識的な回答をしてくれます。
ほかに、論文・レポートで剽窃につながる危険性なども懸念されていますが、それは生成系AIの活用に限らず、守らなければならない社会のルールです。現在、当たり前に使用しているインターネットも、民間での活用が可能になった当初は、各大学で同様の議論が盛んに行われました。この点については、生成系AIを使うかどうかというよりも、倫理とかマナーという点で議論すべきではないでしょうか。
教育における生成系AIの導入には賛否ありますが、危険性や利便性を知った上で、それぞれが議論し方針を出せばよいと思います。
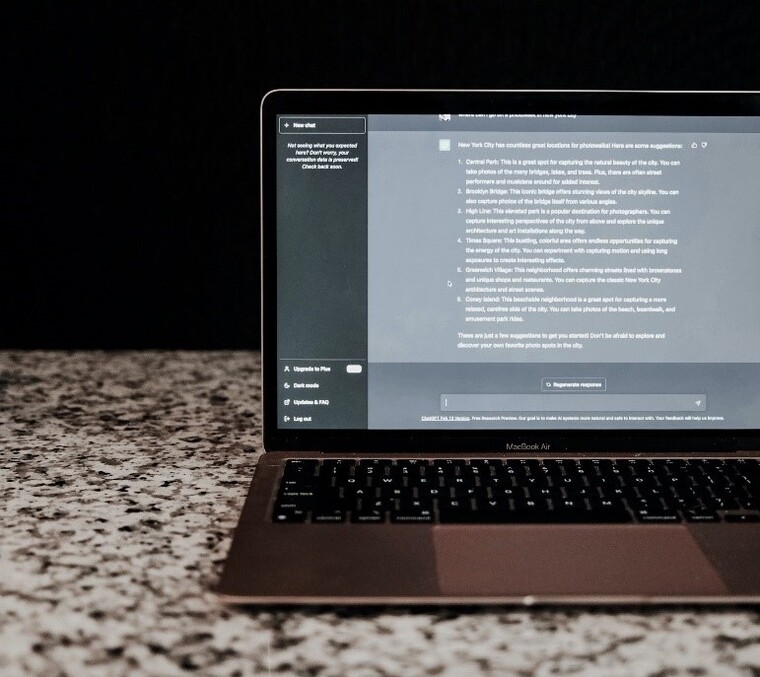
大学のプラットフォームで
学生は有料版を安全に利用
ChatGPTでは、有料モデルのGPT-4と無料モデルとは性能が大きく異なります。もし、経済力のある学生とそうでない学生との間でGPT-4を利用できるか否かの差が生じると、それがそのまま学修上の不平等となります。またプロンプト・エンジニアリングを教えるにしても、学生が使うモデルがバラバラではうまく指導できません。そこで、本学部では、全学生がGPT-4を利用できるように、教育プラットフォーム上でChatGPTにアクセスするAI管理用プラットフォーム「AI-MOP」(AI Management and Operation Platform)を開発しました。
使い方は簡単で、学内で学生とコミュニケーションをするために使っているSlack (スラック)のbot(ボット)を通して、いろいろなAIモデルとチャットできます。また、利用した内容は、ChatGPTのサーバーに保管されないようになっており、安全性が担保されています。このプラットホームについては、他大学や企業への提供も視野に入れて、Slack以外の組織内チャットやOpenAI以外のAIのAPI(Application Programming Interface)との接続や、利用者ごとの利用AIや利用量の設定などの、細かい管理機能を実現しています。
生成系AI普及後
求められる問題設定能力
最後に、生成系AIが普及し、考えることをAIがサポートする社会が到来した際、人間に求められるのは、「何をしたいか、社会をどうしていきたいか」という問題設定能力でしょう。AIには何かをしたいという欲求がありませんから、問題提起はできないのです。人間が問題を提起した上で、どうしたらよいかを考える際に、生成系AIを活用することになります。そして、問題を解く力をAIが担う時代には、「決められた問題を解く力でなく、問題を設定する力を養う」という、以前から言われていた日本の教育の課題が、より一層重要になると考えられます。
今後は、自ら問題を設定し、目的に応じて生成系AIを使いこなす人材が重要となります。問題を他者との連携──対話を通してチームで解決する人材の教育が「情報連携学部」の目的でしたが、その連携対象にAIが加わるというわけです。そのために、本学部では 生成系AIなどの先端技術を研究開発する人材はもちろん、その活用に長けた人材、すなわち生成系AIと対話を重ねて有益な回答を引き出すスキルをもった「プロンプトエンジニア」 の育成にも力を入れていきます。

- INIAD キャンパスの様子
- 関連リンク
-
- INIAD(東洋大学情報連携学部)Webサイトはこちらから
- 生成系AIに関するINIADの見解(INIAD Webサイトにリンクします)
- ChatGPT等の生成AIに関するアンケート調査結果概要
河合塾が5月に実施したアンケートです。ChatGPT等の生成AIを学生や生徒が使うことに対する意見などについて伺いました。
この記事をシェアする



