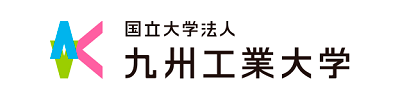活用事例No.1 九州工業大学
J-Bridge System活用で、学ぶ意欲とコンピテンシーの高い入学者を選抜
九州工業大学 入試課長 播磨 良輔 様
- 所属及び役職等はインタビュー当時(2022年度入試)のものです。

導入のきっかけとその後の推移
総合型選抜での導入から学内利用を拡大
本学は優れたエンジニアの輩出をミッションとしています。エンジニアは一人の力だけでは仕事を成し遂げることはできず、同僚や異分野のエンジニア達と協働しながら力を発揮することが求められます。このような観点から、本学ではグローバル化した社会で活躍し続けられる能力としてGlobal Competency for Engineerを定め、それらを育成するカリキュラム開発を進めてきました。
同時に、入学者選抜においても単なる教科学力だけではない、学びに対する主体性を含む広い意味での「学力」を評価することも志向してきました。しかし、こうした力の評価にはコストがかかります。
J-Bridge Systemを用いることでコストを抑えつつ主体性等の評価が可能と考え、2019年度の工学部・情報工学部の総合型選抜Ⅱから導入しました。2020年度からは情報工学部の学校推薦型Ⅰと帰国生徒選抜、2021年度からは情報工学部での高等専門学校等からの3年次編入学にも利用を拡大し、J-Bridge Systemを利用した志願者数は2019年度108名、2020年度369名、2021年度448名へと着実に増えてきています。
実際の活用法
J-Bridge Systemを活用して高精度な評価を実現
これらの選抜では、主として「高校または高等専門学校等での入学後の活動」の中で「具体的に何をして、何を身につけたか、また、九州工業大学での学びにどう活かすか」について記述してもらい、評価します。例えば、総合型選抜Ⅱでは、第1段階選抜(書面審査)において高校入学以降に志願者本人が取り組んだ3つの活動について、それぞれ300字以内で記述したものを評価することとし、そのために4観点5基準からなるルーブリックを作成しています。これによって評価の「揺らぎ」を抑え、精確さの向上を目指しています。
具体的には1名の志願者の1つの活動について4名の教員が評価し、3つの活動がありますから計12名の教員が1名の志願者を評価する仕組みです。総合型選抜Ⅱは年末の忙しい時期にわずか3日間で評価していますが、J-Bridge Systemの利用により、教員は集合することなく、学内の個室で評価をおこなえます。このような短期間で多数の教員が関わる評価が可能となっているのは、J-Bridge Systemだからこそと感じています。
また、評価分布を確認する機能を活用して、評価者は自分自身の評価結果の分布をリアルタイムで確認できるため、より精度の高い評価が実現できています。
利用後の感想
意欲の強い入学者の選抜と評価業務の効率化を実現
まず入学後の学生に関してです。J-Bridge Systemを利用した総合型選抜Ⅱにより入学した第1期生は4年生となりました。全員の成績がずば抜けて優秀、というわけではありませんが、PROGテストで調べてみると全般的にコンピテンシーが高い傾向にあることが明らかになっています。数字だけでは見えにくいこともあり検証を続けていますが、総じて「対人能力が高く粘り強い上に、学びたいものを持っているので目的意識が強くモチベーションの高い学生」の選抜に成功していると考えています。
その点でJ-Bridge Systemは、アドミッションポリシーとマッチした入学者の選抜に寄与するツールだと捉えています。
また、実務的な面ではJ-Bridge Systemの導入によって、①提出状況のリアルタイムでの把握、②評価者への配付資料(提出書類や評価用シート等)作成作業の不要化、③評価進捗状況と評価結果のリアルタイムでの可視化、④評価用シートの回収及び入力作業の不要化等、作業ミスの防止と入試業務の効率化を幅広い工程で実現できています。
これら業務効率化によって評価の所要期間が短縮されたことで、出願期間も延長できました。
今後の課題
評価能力向上、一般選抜利用、更なる効率の追求
J-Bridge System導入により、評価結果のデータに基づいて、4観点の独立性や評価の妥当性などを分析して、次年度の選抜に活かしています。また同時に、教員間の評価結果のギャップ等の問題点を可視化しつつ、より適切なルーブリックへと継続的に改善していくためにも、J-Bridge Systemから得られるデータは欠かせません。
一般選抜における主体性等の評価も課題としてきましたが、23年度選抜より一般前期にて本学での学びとのマッチングをしっかりと確認してから出願してもらうために「志望理由書」を任意提出の出願書類として追加し、これまでの実績から、その提出でもJ-Bridge Systemを利用することに決めました。
今後の課題としては、面接の評価結果入力・集計の事務作業効率化がありますが、これにもJ-Bridge Systemの活用ができないかを検討しています。
- 関連リンク
-
-
国立大学法人 九州工業大学(公式サイト)

-
J-Bridge Systemを活用し、アドミッションポリシーにマッチした、単なる教科学力だけではない、学びに対する主体性を含む広い意味での「学力」を持つ、学ぶ意欲とコンピテンシーの高い入学者を選抜しています。
-
国立大学法人 九州工業大学(公式サイト)
-
- J-Bridge System(JBS)
-
河合塾によるJ-Bridge System(JBS)のご案内。Webを通じて、受験生の多様な資質や主体性を示す情報をデータとして獲得し、有効かつ効率的な評価の実現を支援するシステムに関する情報をお届けします。
-
- 大学入学者選抜改革セミナー
-
JBSを活用したイベントや研修・セミナーの情報を掲載しています。アーカイブ動画も公開中です。