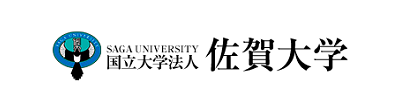活用事例No.2 佐賀大学
導入後4年間のデータ分析で、アドミッション・ポリシーに合致した意欲的な志願者の入学が明らかに
佐賀大学 副学長 アドミッションセンター長
教授 西郡 大 先生
佐賀大学 入試課長 扇谷 俊弘 様
佐賀大学 入試課 藤澤 和貴 様
- 所属及び役職等はインタビュー当時(2022年度入試)のものです。

導入のきっかけ
多面的評価の高度化・効率化のために
2017年から河合塾とJ-Bridge Systemの開発を共に進めてきました。
J-Bridge System導入の意義は、個別選抜における多面的・総合的評価の高度化と効率化です。人間の情報処理能力を補うことで、より丁寧な評価が可能です。具体的なメリットとして①事務作業の効率化による評価期間の短縮、②効率的な採点作業と採点者の得点分布をリアルタイムで把握・修正できることによる評価の精度の向上、③受験者にとってアピールできる材料の広がりがあげられます。
ドキュメントだけでなく写真、動画、音声等の資料提出が可能となり、豊富な情報をもとに丁寧な評価をしたいと考える募集単位にとっては有効で、面接試験などと組み合わせれば、より掘り下げた評価も可能です。
実際の活用法
J-Bridge Systemを利用して特色加点制度を導入
佐賀大学では、2019年度より一般入試で特色加点制度という仕組みを導入しています。
これは志願者に、大学受験までに力を入れた取り組み(活動や実績)の中で身につけたスキルや経験が、大学入学後にどのように活かせるかを記述させて評価し、入試の成績に加点するものです。申請は任意であり、実際には学力試験における合否のボーダーライン上にいる志願者のみを対象に評価をして、より本学のアドミッション・ポリシーにマッチしている志願者を選抜しようという仕組みです。
この特色加点制度は当初は理工学部と農学部の一般入試でスタートしましたが、現在では教育学部、経済学部、そして芸術地域デザイン学部・地域デザインコースに拡大し、学部学科の特性から採用していない芸術地域デザイン学部・芸術表現コースと医学部を除くすべてで導入されています。
また、総合型選抜においても理工学部と農学部においては活動実績報告書と志望理由書の提出にJ-Bridge Systemを利用しており、本学の全志願者の過半がJ-Bridge Systemを利用していることになります。
利用後の感想
単なる選抜を超え、教育的入試に
2019年に特色加点制度を利用して入学した学生は、すでに4年生になっています。また利用する学部も広がり、データが集まってきたので分析しました。それを紹介します。
①これまでの3年強の間に特色加点制度を利用して入学した学生で、退学した学生は1人もいません。
②2021年度入学者の1年次終了時点でのGPAは、申請者の方が未申請者よりも有意に高いという結果が出ています。
③2021年度入学者のアドミッション・ポリシーに対する理解は、申請者74.4%に対して未申請者49.0%の約1.5倍です。
④自律性やリーダー性も、申請者の方が未申請者よりも高いことがアンケートに表れています。
⑤申請書を自ら作成することで、「志望学部・学科等のアドミッション・ポリシーを調べた」「学びの内容やカリキュラムを調べた」「自分が頑張ってきたことを振り返る契機となった」等の志願者の心理的変容が明らかになっています。
⑥5点満点のアンケート調査では、「(申請により)志望学部への入学意思が固まった」との回答が4.25ポイントに達しており、これが大学・学部・学科選びにおけるミスマッチの解消につながっていると分析しています。
このように申請書作成という行為自体が志願者の成長を促しており、特色加点制度が選抜のためであると同時に教育的入試でもあるという側面を有していることが明らかになっています。
また、J-Bridge System導入によって入試事務の大幅な効率化が実現できていますが、2021年度からはJ-Bridge Systemに蓄積されたデータを自動でダウンロードしてPDF化し、大学のサーバーに保存するRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を独自に開発して運用しています。これによって、データのバックアップ機能も補完されています。
今後の課題
データ化で拡がる分析の可能性と入学前教育への活用
特色加点制度を申請せずに入学した学生を対象に「なぜ申請しなかったのか」を調査すると、「申請しなくても学力試験だけで合格圏内だと思った」という回答以外に、「学力試験は不安だったが申請が面倒であった」という回答もありました。これは、「面倒であっても、アドミッション・ポリシー等を調べて特色加点の申請書類を書くことを選んだ志願者は、佐賀大学で学びたいという意欲が高い」ということを示す結果になりました。
しかし、それらの回答以外に「特色加点制度を知らなかった」という入学者も2~3割に達していました。これについては、今ご紹介した特色加点制度を利用した入学者の傾向を、高校等への説明会でもしっかりと説明するなどして対応していきたいと考えています。
また、J-Bridge Systemで得られたデータはデジタル化されているので、他のデジタル化されたデータとの紐付けが容易です。調査書や共通テストの結果などがデジタル化されれば、それらと紐付けることで発見される事実もあると思います。それだけでなく申請内容をAIで分析して、例えば高校でボランティア活動に熱心に取り組んだ学生の入学後の成長予測ですらできるかもしれません。
今後は特色加点制度への受験テクニック的な対応もおこなわれるようになるかもしれませんが、これもデータが蓄積してAIで分析すれば対応可能になると考えています。
加えて、本学は今年度から入学前教育に力を入れていく方針です。この入学前教育にJ-Bridge Systemで得られたデータが活用できるかどうか検討したいと考えているところです。
- 関連リンク
-
-
国立大学法人 佐賀大学(公式サイト)

-
J-Bridge Systemを活用し、志願者が任意で高校時代の活動と、アドミッション・ポリシーとの繋がりに関して記述する「特色加点制度」を導入し、大学にマッチする志願者を選抜しています。
-
国立大学法人 佐賀大学(公式サイト)
-
- J-Bridge System(JBS)
-
河合塾によるJ-Bridge System(JBS)のご案内。Webを通じて、受験生の多様な資質や主体性を示す情報をデータとして獲得し、有効かつ効率的な評価の実現を支援するシステムに関する情報をお届けします。
-
- 大学入学者選抜改革セミナー
-
JBSを活用したイベントや研修・セミナーの情報を掲載しています。アーカイブ動画も公開中です。