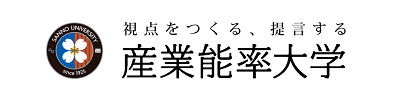活用事例No.6 産業能率大学
未来構想方式での導入が好評で、総合選抜型、学校推薦型へ導入を拡大
産業能率大学 入試企画部 部長 林 巧樹 様
- 所属及び役職等はインタビュー当時(2023年度入試)のものです。

進学情報誌 Guidelineに掲載されました!
導入のきっかけ
一般選抜での主体性等評価を低コストで実現
本学は、2021年度入試の一般選抜・未来構想方式(全2学部3学科で実施)で初めてJ-Bridge Systemを導入しました。1999年度よりAO入試を開設し、2007年度入試でキャリア教育接続方式(全2学部3学科で実施)、2013年度入試ではアクティブラーニング方式(マーケティング学科で実施)を総合型選抜として導入しています。本学のアドミッションポリシーである「グローバル化している社会の動きに高い関心を持っている」「自分の将来キャリアを真剣に考え、常に向上心を持っている」「主体的に課題を発見し、他者と協働して取り組むことができる」を評価するためです。
一方で、一般入試では「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度(以下、主体性等)」については評価していませんでした。文部科学省から一般入試でも主体性等を評価すべきという指示もあり、未来構想方式では一般入試の枠組みの中で知識、思考力、判断力等に加え主体性等も真正面から評価することとし、そのために同システムを導入しました。
正直に言えば、同システム導入時は、どんな成果や効果があるかよく分かりませんでしたが、導入にあたってイニシャルコストがかからず、費用負担も少ないのも踏み切れた大きな要因でした。受験生からの評判も良く、未来構想方式で入学した学生たちにヒアリングをしてみると、「WEB出願をしてそのままJ-Bridge Systemにスムーズに遷移できるので、ストレスなく記述できた」「400~600文字の記述で、残り文字数が表示されるのも書きやすかった」等の感想が多くありました。また、評価する教員からも、それ以前の他の選抜方式での事前課題が紙への手書きだったのと比べると、読みやすいと好評だったので、2年目以降も継続して利用してきました。
2023年度入試での導入の拡大
未来構想方式の成功により総合型選抜にも拡大
一般選抜・未来構想方式で受け入れたいと狙った学生が入学してくれていることから、2023年度入試ではこのやり方を総合型選抜でも採用しました。それが他大学との併願可とした経営学部マーケティング学科の総合型選抜MI(マーケティング・イニシアチブ)方式です。
従来、本学の総合選抜型は専願型のみであり、事前に課す記述量がかなり多いという特徴がありました。一方、併願型は他大学の一般選抜も視野に入れる受験生にも本学を受験してもらうことになり、そうした必ずしも本学を第一志望としない受験生に、志望理由を書いてもらうのは無意味です。そのため、志望理由を必須とせず、かつ事前課題の記述量も減らし、本学を受験しやすくしました。
本入試区分においても、手書きよりも入力の方が受験生は、何度も書き直すことも可能で、スマホでも作成できることから、J-Bridge Systemを採用することにしました。手書きの場合は原稿が確定してから清書しますが、同システムを利用することで、提出期限まで何度も修正して完成度を高めていくので清書というプロセスが不要です。本学にそれほど強い志望動機を持っていなくても、簡易な入力であればストレスも少なく、総合型選抜で出願してみようと考える受験生もいるはずで、そうした受験生を取り込むことも同システム導入の狙いの1つでした。このため、MI方式開設とそこへの同システムの導入を機に、総合型選抜でもWEB出願を導入しました。
2024年度入試では時代の変化に対応しさらなる拡大
新たな入試方式に順次拡大
2024年度入試ではJ-Bridge Systemの導入をさらに拡大し、情報マネジメント学部現代マネジメント学科で新しく開設する学校推薦型公募制方式一般推薦(併願型)と従来から実施する総合型選抜AO方式でも採用します。
学校推薦型公募制方式一般推薦(併願型)も併願型であるMI方式と同様に志望理由書を無くし、記述量をMI方式以上に減らす方針です。同学科が従来から実施している学校推薦型公募制方式一般推薦(専願型)には面接があり、その材料を得るために提出課題での記述量を多くしています。一方、今回開設する併願型では面接は実施せず、高校生活での取り組みを簡潔に記述してもらい、基礎学力と併せて評価します。
専願型のAO方式での導入は、未来構想方式に初めて同システムを導入した3年前には全く考えてもいないことでした。同方式は書類と面接のみで選抜するため記述量も多く、「字は人を表す」という考え方もあり、手書きへのこだわりがあったためです。これが変わった理由は時代の変化への対応です。教育DXが言われる中で「『情報』が学部名に付くのに今なお手書きにこだわり、デジタルとの違いに価値を置くということでいいのか」という議論がありました。今まで、「デジタルではコピペができるからダメだ」等と考えていましたが、実は時間さえかければ手書きでも書き写し可能なわけです。「面接があるのだから、そこで書いている内容が真実かどうかは判断できるはずだ」という結論になりました。
AO方式では事前課題の記述量が多い上に、同システムに入力できるのは出願から入試前までの期間に限られています。そのため、ホームページでの募集要項の公開と同時に事前課題の内容も公開することにしました。これにより、受験生は出願開始前からスマホやPCで時間をかけて文章作成し、出願が開始されたら、余裕を持ってそれを同システムの入力箇所にコピペすることもできます。
同システムを利用することは、事務部門にとっても小さくも重要なメリットがあります。AO方式では事前課題とは別にMicrosoft Word®️で作成してもらう書類があります。従来はこの書類が提出されたら、コピーをとって面接者に配布していましたが、コスト削減のために原則モノクロコピーとし、必要な場合のみカラーコピーとしていました。しかし同システムのアップロード機能を通じて提出してもらうことで、面接者は各自パソコン等で提出書類を実際のままで確認できるようになりました。さらに、提出された事前課題を面接前に評価する先生方に確認してもらう必要がありますが、これまでは提出された紙の事前課題を人数分コピーし、用意していたので時間がギリギリでした。それが2024年度からは、同システムを使ってデジタルで迅速に処理できるため、余裕が生まれ事務的にも大いに助かります。
今後の課題
認知的能力も非認知的能力も高い学生の受け入れ
本学としては、認知的能力も非認知的能力も高い学生を受け入れたいと考えていますが、そうした学生にとって自分を表現しやすい、使いやすいツールが欲しいと考えてきました。
J-Bridge Systemは受験生にとっても評価者や事務にとっても使いやすい上に、完成度が高く汎用的なので、本学の入試に合わせるための開発も不要です。導入も使用も容易にできるので、2024年度入試が目論見通りに進めば、さらに同システムを採用する入試区分の拡大も検討したいと考えています。
- 関連リンク
-
-
産業能率大学(公式サイト)

-
時代の変化に対応し、さまざまな入試方式でJ-Bridge Systemを活用、認知的能力も非認知的能力も高い学生の受け入れを行っています。
-
産業能率大学(公式サイト)
-
-
高校生の探究活動と進路選択(情報誌Guideline2022年7・8月号)
 大学入試における主体性等評価と河合塾の支援(情報誌Guideline2021年7・8月号)
大学入試における主体性等評価と河合塾の支援(情報誌Guideline2021年7・8月号)
-
探求活動の実績や、探求力を評価する入試の事例、および河合塾が開発したJ-Bridge Systemを導入して一般選抜で主体性等を評価している大学の事例として、Guidelineで紹介させていただきました。
-
高校生の探究活動と進路選択(情報誌Guideline2022年7・8月号)
-
- J-Bridge System(JBS)
-
河合塾によるJ-Bridge System(JBS)のご案内。Webを通じて、受験生の多様な資質や主体性を示す情報をデータとして獲得し、有効かつ効率的な評価の実現を支援するシステムに関する情報をお届けします。
-
- 大学入学者選抜改革セミナー
-
JBSを活用したイベントや研修・セミナーの情報を掲載しています。アーカイブ動画も公開中です。