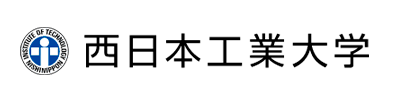活用事例No.9西日本工業大学
主体性等評価を一般選抜で導入するには、採点期間を考慮するとJ-Bridge Systemが不可欠
西日本工業大学
入試広報部長 高見 徹 工学部教授
西日本工業大学
入試広報課長 中村 直登 様
- 所属及び役職等はインタビュー当時(2026年度入試)のものです。

J-Bridge System導入と現在の活用法
段階的に全ての入試でJ-Bridge Systemを導入
初年度はJ-Bridge Systemを一般選抜の自己エントリー提出に先行導入
次年度から年内入試の自己エントリー提出にも活用を拡大し、評価利用も開始
同じく次年度から年内入試の面接の評価にも活用開始
本学では2021年度入試からJ-Bridge Systemを導入しました。最初は一般選抜での、志望理由書と高校時代の活動報告書を兼ねた自己エントリーの提出(提出は任意)からJ-Bridge Systemの利用を開始しました。導入当初は、その評価はしておらず、参考にとどめていました。現在では、一般選抜に加えて年内入試(総合型・学校推薦型選抜)での自己エントリーの提出にも利用範囲を拡大し、それらの評価にも利用しています。さらに年内入試での面接の評価にもJ-Bridge Systemを利用するようになりました。
実は導入当初から、全ての入試区分でJ-Bridge Systemを活用しようという考えはあったのですが、一般選抜を先行させることにしました。理由は、一般選抜の受験生は書くことに対するリテラシーが比較的高いと推測したことと、年内入試で課す自己エントリーの記入には高校の先生方の指導が入ることが多く、高校現場に混乱をきたすことを憂慮したことにありました。そのため、まずは一般選抜で先行導入して様子を見ようということにしました。
結果、利用初年度の一般選抜でのJ-Bridge System利用による自己エントリーの提出率が80%を超え、混乱もありませんでした。これを受け、翌年度から年内入試での自己エントリーの提出にも利用することにしました。同時に自己エントリーの提出件数が大きく増える一方で、せっかく受験生が一生懸命作成し、提出してくれた提出書類を評価しないことは不誠実だと考え、J-Bridge Systemを利用してこれらの評価も開始しました。またJ-Bridge Systemでの評価入力作業の簡便性から、年内入試での面接における評価にも利用することにしました。
J-Bridge System導入で解決したかったこと
「紙ではできない。システムが必要だ」
自己エントリーの評価は紙でおこなうには労力がかかりすぎ、軽減したかった
面接の評価も、評価者による事前の資料読み込みが直前にしかできず、
評価の記入・集計等にも時間がかかっていた
J-Bridge Systemを活用しようという計画は、評価する教員の側からの強い要望から生まれました。それ以前のような紙で自己エントリーを提出する場合は、参考資料にとどめざるを得ませんでした。評価に要する手間が、膨大になることが予想されたからです。紙で運用する場合には、手書きやWordファイルをプリントアウトして提出された書類を、人数分コピーして評価担当教員に渡すことになります。そのコピーだけでも相当に大変だったでしょう。そして教員が評価したら、評価結果を記入した紙を回収して本部でまとめて集計することになります。評価してから結果が出るまでの時間が長くかかり、教員の気持ちとしても、ずっと待機していなかればなりません。集計作業での入力ミス、計算ミスも許されません。
このため、自己エントリーを評価することになった段階で、「紙ではできない。システムが必要だ」ということになり、J-Bridge Systemが適しているという結論になりました。J-Bridge Systemを利用すれば、評価にあたっての時間や場所の制限がありません。また受験番号と紐づけられているので評価をしたらすぐに反映され、集計も即時におこなわれます。何より集計作業でのミスの心配もありません。経験のある大学関係者であればご理解いただけるかもしれませんが、このことはかなり重要であったりします。
さらに面接の評価についても、J-Bridge Systemの利用により業務プロセスが飛躍的に効率化され、かつ評価の確度も向上しました。以前は、受験生の自己エントリーを人数分コピーして評価者に直前に渡し、それを評価者も直前に10~20分かけて読んでから面接に臨んでいました。直前に読むだけでは、なかなか踏み込んだ質問に繋がりにくかったと思います。そして評価者は評価結果を紙に書き、全受験生の面接が終わってから、本部でこれらを回収し集計していました。評価から集計までの時間も長くかかっていたわけです。
J-Bridge Systemを導入してからは、評価者はPCで面接の何日も前に自己エントリーを読み込み、あらかじめ質問を考えておくことができます。そして面接中もタブレットで自己エントリーを見ながら掘り下げた質問をしつつ、同時にタブレットに評価を入力しています。面接が15分で終わり次の受験生が入室してくる前には、大抵の場合、評価も終了しています。紙の時代よりも自己エントリーの事前の読み込みがじっくりでき、質問のクオリティーも高まっていると思います。また評価は即時に集計され、評価の提出と同時に手離れするので、評価者にとっても大きな負担の軽減になっています。
加えて危機管理という点でも、紙運用によるアナログでの評価はミスが起こりやすい。コピー機を使うことについても、そのデータがどこかのサーバーに残っていることも考えられます。その点で、デジタルで完結するJ-Bridge Systemはセキュリティを確保しやすく、ミスを防げることもメリットでした。
J-Bridge Systemの活用の拡大
高校生向けの教育プログラム マナビバへの注力が可能に
総合型選抜の各入試前に体験型イベントを開催し、レポート提出と評価に活用
入試本番前にも評価をおこなうことで、じっくりと多面的に評価が可能に
本学の総合型選抜は、2026年度入試から大きく変わります。2025年度入試における総合型選抜は、「総合・多様型選抜」「ものづくり特別選抜」「デザイン特別選抜」「スポーツ特別選抜」「教員志望選抜」の5種類でしたが、2026年度は「文理総合型」「実績評価型」「アスリート型」「教員志望型」「高大接続型」「女性活躍推進型」の6種類になります。それぞれの入試の内容に応じて、河合塾のシステム運用チームからのアドバイスを受けながら、J-Bridge Systemの利用による、受験生にとって、私たちにとって最適な入試運営を現在検討中です。
現在私たちが注力している取り組みの1つとして、高校生向けの教育プログラム、マナビバがあります。大学での実践的な学びをひと足先に体験できる参加型特別授業で、AI、IT、ロボット、ものづくり、防災、デザインなど、大学ならではの知識とスキルを体感できる講座をいくつも用意しています。この教育プログラムは、総合型選抜の入試区分である「高大接続型」入試と連動した企画で、いずれかのプロジェクトを受講し、定められたプレゼンやレポートなどを提出し修了すると、当該選抜の受験資格と特別奨学生へのエントリー資格が得られます。
「高大接続型」入試では、出願時にマナビバで作成したプレゼン資料やレポートを提出してもらい、これらを評価します。あらかじめ受験生の提出物の評価をおこなった上で入試を迎えるわけですが、受験生の確保はもちろん、受験生と大学とのミスマッチを防止することも本入試の大きな目的となっています。この一連の運営についても、J-Bridge Systemがなければ相当な労力を要することになると思われます。
今後の展開
入試改革と入学後の活用
「高大接続型」入試で提出するマナビバの学習成果の提出・評価はJ-Bridge Systemで
J-Bridge Systemを通じて獲得した入試データを入学後の学修成果とひも付けてIR分析
質問の高度化により、総合型選抜自体の質を高めたい
本件に関わる今後の展開のポイントとして、以下の3点が挙げておきます。
1点めとして、現段階では、「高大接続型」入試でのマナビバで作成したレポート等の提出は、Word等で作成した文章ファイルを、J-Bridge Systemにアップロードして提出してもらうことを予定しています。ただし、各プロジェクトでのレポート等の提出フォームを統一できれば、J-Bridge Systemに設問フォームを設定し、そこに直接入力してもらう形にしたいと考えています。
2点めとしては、まだ実現に至ってはいませんが、せっかく入試での提出資料等の記録をアーカイブしているので、このデータと入学後の学修成果のデータとをひも付け、IR分析につなげていきたいと考えています。
3点めとして、2026年度入試より、総合型選抜で課してきた筆記試験を廃止し、自己エントリーと面接のみで評価する形態に刷新します。このことは、理系・文系を問わず本学で学ぶ意欲のある受験生を、より受け入れていきたいという本学の決意を示しています。これにより、知識・技能以外の部分、思考力・判断力・表現力や、いわゆる主体性等と言われる部分をより重視した総合型選抜となり、自己エントリーや面接の評点の比重が今まで以上に大きくなります。
そのため、入試ではこれまで以上に質の高いアピールを受験生に求めたいと考えています。例えば、自己エントリーの記述にあたっては、これまでは単に、高校時代の活動実績について記載してもらっていたところを、その活動を入学後の学びにどうつなげていきたいのかというところまで言及してもらったり、面接ではこうした観点からより掘り下げた質問を問うたりしたいと考えています。
- 関連リンク
-
-
西日本工業大学(公式サイト)

-
デジタルトランスフォーメーション(DX)の動きにあわせ、J-Bridge Systemを導入・活用し、受験生の専門分野への強い関心や意欲など、筆記試験では把握できない主体性等を明らかにしています。
-
西日本工業大学(公式サイト)
-
-
西日本工業大学 マナビバ!

-
高校生参加型の学び~チャレンジ授業~マナビバ!は、西日本工業大学の"実践的な学び"を、ひと足先に体験できる参加型特別授業です。
-
西日本工業大学 マナビバ!
-
- J-Bridge System(JBS)
-
河合塾によるJ-Bridge System(JBS)のご案内。Webを通じて、受験生の多様な資質や主体性を示す情報をデータとして獲得し、有効かつ効率的な評価の実現を支援するシステムに関する情報をお届けします。
-
- 大学入学者選抜改革セミナー
-
JBSを活用したイベントや研修・セミナーの情報を掲載しています。アーカイブ動画も公開中です。