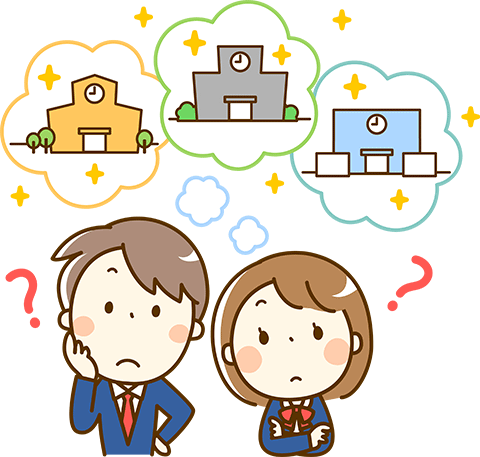Family Academy文系・理系は素直に選ぶ方がトータルでの満足度は高くなります (2022栄冠めざしてFamilyより)
多くの高校生は進路選択の最初の分岐点として、高校1年生から2年生にかけて、文系・理系どちらのコースに進むかの選択することを迫られます。文理選択は受験科目や入学後に学ぶ専攻・分野にもつながり、その先の就職にも影響を与えるため、とても大きな決断といえます。そのため、どのように決めたらよいかに悩む高校生も少なくありません。そこで、著書『文系と理系はなぜ分かれたのか』の中で、文系と理系がいつどのように分かれたのかという歴史的経緯や日本を含む各国の事情について、新卒学生の就活や産業界の動向、ジェンダー役割とステレオタイプなどの視点から解説している、名古屋大学大学院経済学研究科隠岐さや香教授にお話をうかがいました。

名古屋大学大学院
経済学研究科教授
隠
岐
さ
や
香
- P R O F I L E
- 東京都出身。東京大学大学院総合文化研究科博士課程満期退学。博士(学術)。現在、名古屋大学大学院経済学研究科教授。科学が社会の中でどのような位置づけを与えられてきたかという問題関心から、職業としての「科学者」について17~18世紀の科学アカデミー史研究により行っている。その著書に、『科学アカデミーと「有用な科学」―フォントネルの夢からコンドルセのユートピアへ』(名古屋大学出版会、2011年)、『文系と理系はなぜ分かれたのか』(星海社新書、2018年)がある。
- 所属、役職などはすべて取材時のものです。
学ぶ対象とおもしろさで分かれるが、つながりもある
文系・理系の区分は、大学の専攻ですので、学ぶ対象と学ぶおもしろさの違いで分けられます。大まかにいうと学ぶ対象は、文系が「人間社会や人間が作ったもの」、理系は「物(ものづくり)や自然」といえるでしょう。ただ、同じ文系でも社会科学と人文科学では、研究の仕方や学び方もかなり異なるため、関心などによって選ぶ専攻も変わります。たとえば、経済学では、貨幣や企業など人為的に作られたものが学ぶ対象ですので、それらに関心のある学生が集まります。
また、医学系は別として、理系は「物(ものづくり)や自然」ですが、この2つはかなり異なります。ものづくりは工学系ですが、明確に物質として作れることが学生にとって大事な価値観となります。一方、自然を対象とする理学系は、自然現象を理解することが大事なので、自身の外にある宇宙や森羅万象の理解におもしろさを感じる学生が多いです。
しかし、おもしろいことに文系の文学部と理系の理学部の人たちは意外と相性がよいといわれることが多いのです。どちらも、自らの知的好奇心や感動を軸に学ぶ志向性があり、社会の反応やビジネスなどを第一の目的にしないところが合うのかもしれません。同じようなことが工学部と経済学部、経営学部にもいえます。これらの分野の人は実際に物を作ったり、うまく商品や貨幣が流通する仕組みを作るなど、むしろ社会に働きかけることに関心が強いです。また、数学と哲学の一部の分野はかなり内容が近いともいわれています。このように文系・理系は、学ぶ対象やおもしろさで分かれた先で、さらに研究の仕方や学び方で分かれますが、単にバラバラになるのではなく、どこかでつながる部分があります。
日本は近代化のため文理別に人材を育成
日本における文理分けを歴史的にみると、明治期以降の近代化の歴史が影響していると考えられます。日本は近代化のために、人材育成を急ぐような形で明治時代、大正時代に大学の制度を整えました。当時は高等学校も文科、理科で分けられており、これ以降、大学入学試験の準備段階で文系・理系に二分する方式が定着していきます。そして、20世紀初頭の公務員試験も文理で分かれていきました。専門的な教育を行って優秀な官僚を育てる、それも文官と技官を育てるコースを早くから作っていたのです。同じ時期のドイツやイギリスの大学はそこまで分化していません。つまり、日本では近代化のために専門特化した人材育成のコース制度を持っていたことが、現在の文理分けにも影響しているとみることができます。
ただ、年長世代の方々と話をすると、当時、文理のコースは分かれていたが、現在のような文理の断絶ともいえるようなことはなかったといいます。文系・理系の行きすぎた分化には、別の理由もあると思われます。おそらくそれは大学進学率の上昇と関係があるのではないかと思います。幅広い学力層の高校生が大学進学をめざすようになる過程で、学校教育の現場で受験勉強の効率を高めるため、一部の分野の勉強を省略するなど、過度に合理化が行われたためではないかと思います。その影響によって、文系・理系に対する意識が、ある世代以降から変化したのではないでしょうか。まだ十分に研究が進んでいないためこれは推測の段階ですが、受験の効率化を求めた結果の弊害とも考えられます。
日本は文理に分かれた状態が後々まで残る
日本の学生の特徴として、自身が文系か理系かを18歳ぐらいで自覚した後、そのままの状態が後々まで続くという傾向がみられます。海外の受験制度をみると東アジアでは日本の制度が影響しているため、文理に分けていますが、ヨーロッパでは文系・理系ではなく、文学系と社会科学系と理工系という分け方もみられます。あるいは、イギリスやアメリカなどは、多くの科目の中から自分が志望する学部が指定した科目を選択受験するなどの仕組みです。欧米は多様な仕組みのため、一見すると文系・理系の区分はないというイメージを日本で持たれているのではないかと思いますが、このように海外でも文理分けのような仕組みはあります。ただ、日本のようにそれが後々まで尾を引くようなことはありません。
冒頭で文系・理系の区分は、大学の専攻だといいましたが、学問分類自体は日本も含め各国での違いはほぼありません。大学の学問構造は比較的似ていて、英語圏の場合はSTEM(Science・Technology・Engineering・Mathematics)か、STEMではないかという区分で理解するので、ある種の文系・理系ともいえます。しかし、日本ほどその意識は強くありません。日本は一度、文理を選択するとやり直しが利き難い制度になっているということも関係しているかもしれません。
また、欧米では大人になってから学び直す文化もあります。たとえば、金融の仕事をしていたビジネスパーソンが退職して大学院で美術史を学んで学位を取るといったようなことも少なくないですが、日本ではあまりみられません。人生の多様化とそれを支える制度の違いがあるのでしょう。そのため、日本の場合は18歳ぐらいで人生を決めるという雰囲気や意識が強くなるのかもしれません。
学際的な人材を中心にそれぞれの強みを生かす
大学では、この20~30年で文理融合の学際的な学部が増えています。こうした学際的な大学・学部が文系・理系のイメージを変えていきつつあります。学際的な大学・学部で学んだ学生はものの見方が違います。ただし、大学卒業後に大学院に進学する際、その段階で専門分化することはあります。こうしたことはアメリカの大学教育で顕著にみられます。特にアメリカのリベラルアーツカレッジなどの場合、大学(学部)の間は専攻を厳密に決めないで、学びたい人は大学院に入ってから専門分野を深く学ぶという仕組みです。レイト・スペシャライゼーション(遅い専門化)といわれますが、その方が望ましいという考え方も最近はでてきています。学問の裾野が広がり、一つの分野でも学ぶことが多くあり過ぎて、広い知識がないと理解できないことが増えているからです。そのため、できるだけ広く学んだうえで、それを生かして専門化する形をよしとする流れが、世界的にみてもあるように思います。
学際化は大学教育だけでなく研究でもみられるようになっています。たとえば、歴史の研究で資料をデジタル化して、分析を機械的に行うという手法も用いられています。そのために、プログラミングを学び、実際に自分でデータベースを構築している歴史の研究者もいます。こうした学際的な人材は、歴史学の研究者とも情報学の研究者とも話ができます。そのため、研究者同士のつながりが広がって、大きな研究プロジェクトに発展することもあります。学際的な人材を中心に、それぞれ強みのある、まったく別の深い専門性を持つ人たちが集まり、力を発揮できることは望ましいことではないでしょうか。
今後、学際化によって、受験期における文系・理系の区分は徐々に弱まると考えられますが、それは専門性が不要ということではありません。尖った専門性、深い専門性を学際人材がつなぐことで新しい発見に結び付くのだと思います。
大学教育も視野を広げる方向に変わり始めた
近年の大学教育では、主に理工系の大学で学際化に近い、新しい試みがみられます。理工系の難関大学である東京工業大学では、歴史や哲学など人文系の教育にも力を入れています。その目的は優秀なエンジニアを育成することです。いろいろな人とコミュニケーションができ、社会的な課題も認識していなければよいものづくりはできない時代になったという判断があって、教育内容を大きく変えています。その背景には、科学技術が発展し、人間社会に与えるインパクトが大きくなったことで、技術者も社会的課題と無縁という訳にはいかない共創の発想があると思います。
理工系以外では、医学部でも医学的な知識だけではなく、人類学など人文・社会科学の授業を必須にするような動きもみられます。こうした動向は海外でも同様にみられます。さらに、人文・社会科学系の大学・学部で情報科学やデータサイエンスを否応なく学ぶ動きが日本でも広がっています。すべての人が学際的人材になる必要はありませんが、視野は広げておく必要があるということでしょう。
素直に選んだ方が、トータルでの満足度が高い
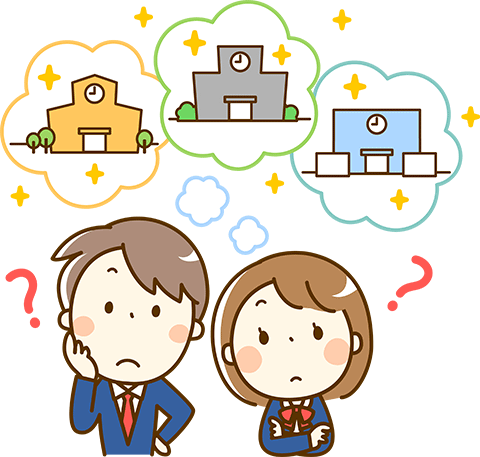
高校生が文理選択をする際、迷うパターンがいくつかあると思います。たとえば、文理の両分野に広く関心があるタイプの人は、一方だけを選ぶことができないという思いがあるでしょう。その場合は、数は多くはありませんが、学際系など広い分野を学べる学部もありますので、そうした観点で情報を探してみるとよいでしょう。
なかには、何に対しても関心が持てなくて、文理を選ぶことができないというタイプの人もいるかもしれません。自分の関心が何にあるのか分からないというのは、順応力が高いタイプだと肯定的にとらえてよいと思います。これといった思い入れやこだわりがないというのは、嫌いなものがないということです。おそらく、こういう人はどんな分野に行っても順応していけます。私はある種の才能だと思っています。
また、高校生にとって保護者の意見は大きく影響します。たとえば、本当は文学部を希望していたのに、保護者からつぶしが利くからという理由で経済学部を勧められたなどというのはよく聞く話です。先程の順応力が高いタイプの場合は、それでも大丈夫でしょう。でも、お子さん自身がどうしても嫌だと思っていると大学に入学した後の4年間が辛くなり、留年するリスクがあります。どの大学・学部でも残念ながら留年する学生は一定数います。やはり合わないものには無理に合わせることはできないのです。留年すると学費もさらに必要となりますが、なによりもお子さん自身が葛藤に苦しみます。周囲の大人の価値観を無理強いすることなく、お子さんが関心を持てることから素直に進路を選ぶ方がトータルでみたときに満足度は高いと思います。