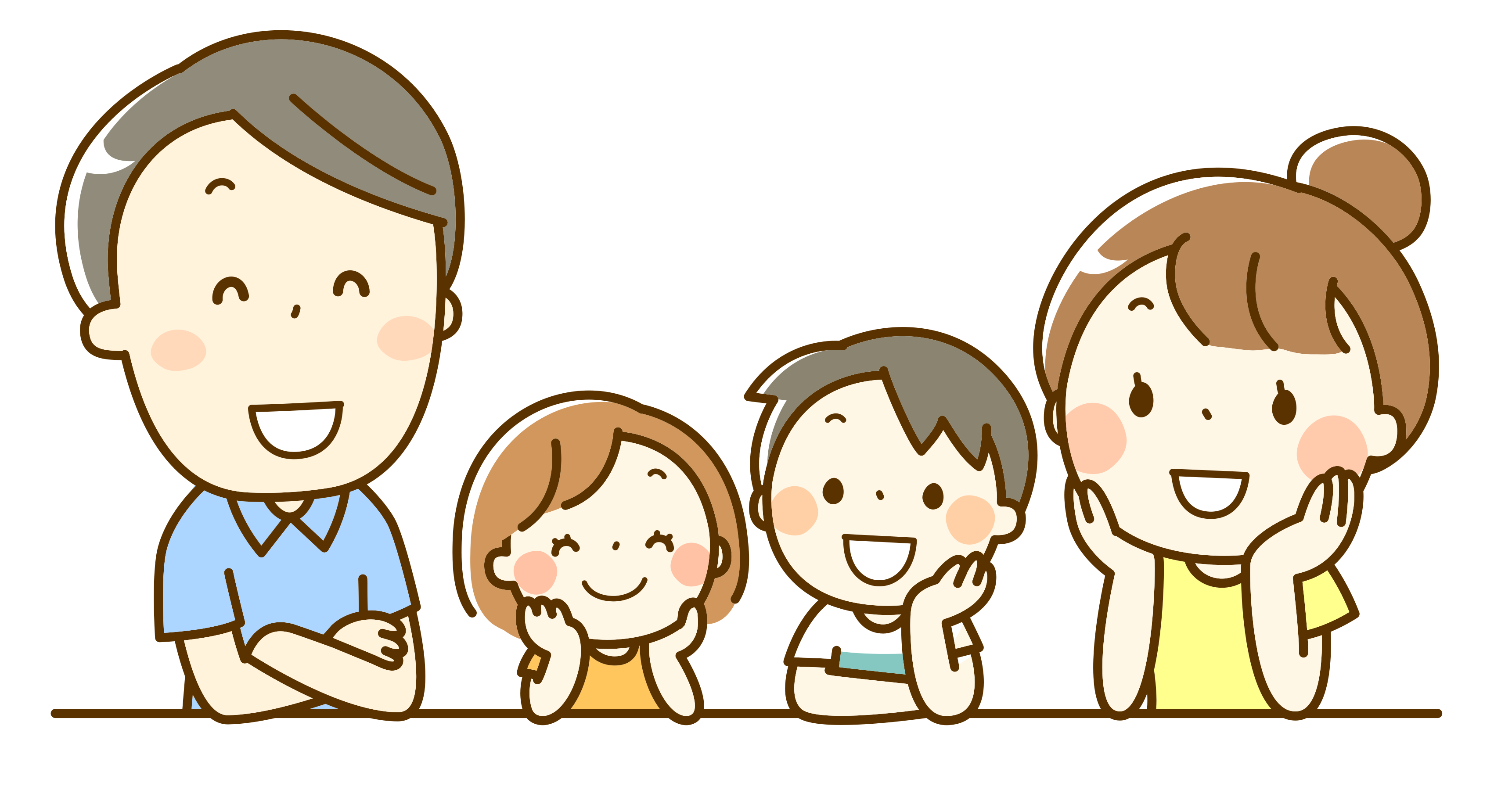Family Academy生成AIは上手に使えば人間の能力拡張をサポートしてくれます (2024栄冠めざしてFamilyより)
昨今、「AI」という言葉がメディアで取り上げられない日はないと言っても過言ではありません。日本社会は、今まさに国をあげて情報技術を活用したDX(デジタルトランスフォーメーション)化を進めています。そのため、働く大人だけではなく、これからの社会を生きる高校生も、AIを始めとした新しい技術と無縁ではいられません。今、学校などの教育現場でも生成AIの活用が進みつつあります。これから私たちは生成AIとどう付き合っていけば良いのでしょうか。教育における生成AIの活用を研究する、早稲田大学教職大学院教授 田中博之先生にお話をうかがいました。

早稲田大学
教職大学院教授
田
中
博
之
- P R O F I L E
- 1960年北九州市生まれ。大阪大学人間科学部卒業後、大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程在学中に大阪大学人間科学部助手となり、その後大阪教育大学専任講師、助教授、教授を経て、2009年4月より現職。主著に、『「主体的・対話的で深い学び」学習評価の手引き』(教育開発研究所)、『NEW学級力向上プロジェクト』(金子書房)、『教科別でわかる!タブレット活用授業』(学陽書房)、『子どもの自己成長力を育てる』(金子書房)、『教師のためのChatGPT活用術』(学陽書房)、他多数。研究活動として、「主体的・対話的で深い学び」の授業開発、学級力向上プロジェクトの研究、子どもの学習改善と学習評価の開発研究、子どもの自己成長力を伸ばす授業づくり、生成AIの教育利用の研究等、これからの学校に求められる新しい教育手法を作り出していく先進的な研究に従事。
- 所属、役職などはすべて取材時のものです。
人間の知的作業を代行するAI、新たな知を生む生成AI
「AI」は日本語では人工知能と訳されます。AIの定義はさまざまありますが、コンピュータが人間の知的な作業を人間に代わって行ってくれる仕組みであると言えるでしょう。初歩の研究は1960年代に始まっています。長い開発の歴史の中で人工知能は高度になり、今や私たちの生活の中にも多く取り入れられています。スマートフォンに話しかければ、おすすめのレストランを教えてくれたり、エアコンが自動で温度調節をしてくれたり、さらにはがん検査で画像診断をしてくれるなど、人間社会の隅々にまで人工知能が入っており、人間の知的作業をサポートしてくれています。
では、「生成AI」とはどういうものでしょう。昨年、生成AIのChatGPT(チャットGPT)が大きな注目を浴びました。それは生成AIに質問をした時、あたかも本当に人が回答しているかのように対話が自然で、また、パターン化された回答を選んで答えているのではなく、自由かつ創造的に言葉を繰り出して回答してくれることに社会が衝撃を受けたからです。
つまり、生成AIは自分で何かを生み出す機能を持っているところがこれまでのAIとは異なる特徴として際立っているのです。さらに、膨大な数の情報や知識、言葉、数字などの関係性・構造性を自ら学習してどんどん進化しています。私も論文を書く際、先行研究など多くの論文や文献を調べたり、読んだりしますが、人間が調べられる範囲は限られています。生成AIは人間を超えた範囲で日々学習しており、普通の検索だけでは知り得ないほどの専門的な知識も持っています。そのため、生成AIの回答を我々が見ると、新しい発見のように見えることもあります。
生成AIは知識と知識をつなげて新しい概念を生み出す力がある
私は生成AIが回答や文章を生成するだけではなく、新しい知識や知恵を自ら生み出す可能性を感じています。
ひとつの例を紹介します。私の専門は教育学です。私は日本の道徳教育が、すぐに役立つ道徳的な行動や考え方を求める傾向にあるため、子どもたちが深く考えることにつながらないのではないかという問題意識を持っていました。日本の道徳教育について生成AIを使って調べていると、生成AIが、日本の学校教育における道徳は「短期的な道徳的判断」を求める授業だと回答してきました。この「短期的な道徳的判断」という言葉は、行政文書や国内外のさまざまな論文まで調べてみたところ、これまで一度も使われていないものでした。また、「短期的な道徳的判断」の対義語として「長期的な道徳的判断」という言葉も示してきました。
確かに日本の道徳教育は、「約束を守るか破るか」といった究極の選択を迫るような教材が用いられることがあり、「約束は守るもの」と教えています。これを生成AIは短期的な道徳的判断と表現しました。道徳的に考えれば、約束は守らなければなりませんが、やむを得ず約束を破らなければならない場面は必ずやってきます。相手に約束を守れないことをお詫びし、再調整するなど、長期にわたり人間関係を調整する能力が必要となります。生成AIは、これからの学校教育は、長期的な道徳的判断や長期的な道徳的行動ができる人間関係調整力を身につける方が大切なのではないかとアドバイスしてきました。私は生成AIに道徳教育の現状を伝えただけですが、生成AIはそれを新しい言葉で概念化したのです。このように研究者レベルの概念形成や発見を促し、支援してくれる能力も持っているのが生成AIです。
高校の探究活動や英作文の添削に生かせる生成AI
生成AIは、チャットGPT以外にも複数のIT企業がサービスを提供しており、それぞれ回答の精度は異なります。どの会社の生成AIを使うかで得られる結果が変わる可能性はありますが、高校生が日々の学習で十分に利用することはできると思います。私は主に次の2つの利用方法があると考えています。
1つは、「総合的な探究の時間」での活用です。総合的な探究の時間では、高校生が自ら問題意識を持ち、自ら仮説や研究課題を設定して活動に取り組み論文にまとめます。近年、大学と連携し、大学生や大学院生に仮説の善し悪しについてのアドバイスや研究論文の書き方などのサポートをしてもらう高校が増えています。ただ、それができない高校もあるし、いつでも会いに行けるわけではありません。しかし、生成AIがあれば、いつでもどこでもほぼ大学院生と同等あるいはそれ以上のアドバイスが個々に得られます。一人ひとりに研究のための個人チューターやメンターが得られる環境が整うのです。こうした総合的な探究の時間でのサポート役として、生成AIは役に立つと思います。これは高校生だけではなく、高校の先生にとっても、よりきめ細かく生徒の指導をするためには有益でしょう。
もう1つは英作文です。文法ミスの修正、より自然な英語の文章、あるいは内容的に補足すべき観点の例示など、生成AIからいろいろなアドバイスをもらえます。生成AIの中には、先生が事前に回答を設定できる機能を持つものがあり、実際に英語の授業のエッセイ・ライティングで使用している学校もあります。生成AIは主にアメリカで開発されているため、当然ですが英語は得意です。うまく使えば、私は英語学習の革命が起きるのではないかと思っています。
依存し過ぎると思考力・判断力・表現力が育たなくなる
使い方によって非常に有益な生成AIですが、注意が必要な点もあります。以前に比べてかなり改善されましたが、事実に基づかない情報を生成する現象が稀に起こることがあります。生成AIの回答内容についてのファクトチェック(情報の真偽検証)は必須です。また、一番の危険性は、生成AIの回答やアドバイスの精度があまりにも高いためについ頼りすぎてしまうことです。たとえば、探究課題の相談ではなく、課題設定からレポート作成まですべて生成AIにお願いすることも仕組みの上では可能です。AI依存症とも言える状況ですが、こうなってしまうと思考力・判断力・表現力が育たなくなってしまいます。こうした力が最も伸びるのは高校時代です。その伸び盛りの時期に、英作文の力も論文作成能力も思考力も何も育たなくなります。
私を含め教員にとって、提出物が生成AIによるものかを判別するのは難しく、恐らくは無理でしょう。そのため、私の大学の授業では、最初から生成AIを必ず使ってレポートを書くよう指示をしています。そうすればお互いに疑う必要もありません。ただし、生成AIの活用によって元のレポートがどのように改善されたかについての「生成AI活用レポート」もセットで提出してもらいます。この活用レポートも生成AIで書くことはできますが、そこまでは疑わないことにしています。
この他に、個人情報を入力した結果、それが別の人への回答として表示されてしまう可能性もゼロではありません。クラスの友人関係や成績順位などでも個人情報に当たる場合がありますので注意が必要です。また、生成AIは文章だけではなく、画像や音楽なども生成してくれます。著作権に問題がないように処理をしてから出力するアプリケーションソフトもありますが、そうではない場合、出てきた画像などを安易に自身のSNSにアップしてしまうことで著作権の侵害となる可能性があります。その場合、保護者が知らなかったとしても、責任の一端を担う必要があります。
賢い利用方法を家庭で一緒に考えることが大切
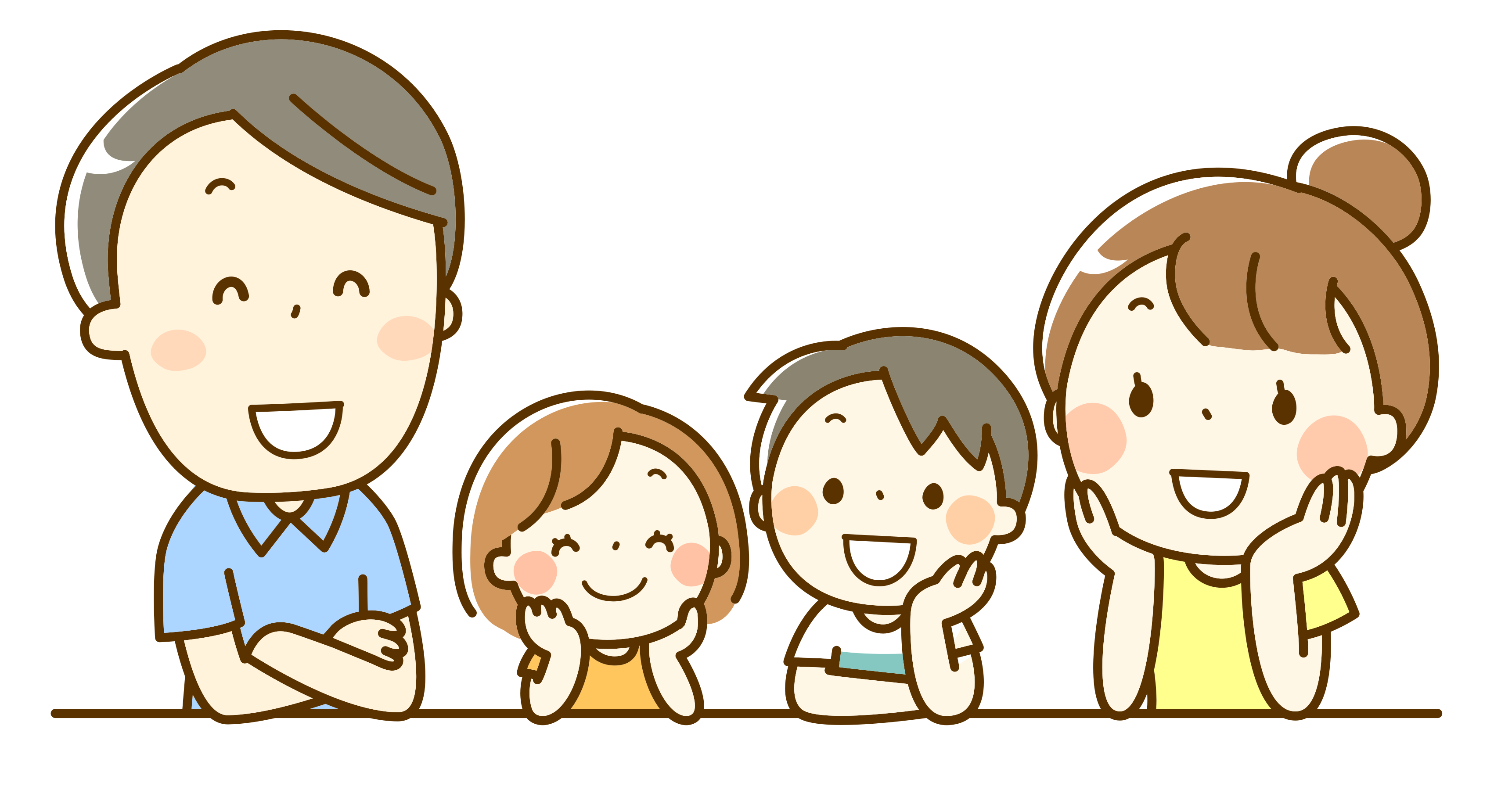
最後に、生成AIと上手に付き合っていくためのアドバイスについてお話しします。前述したように、頼りすぎて依存症になってしまったり、思いもよらず著作権法違反や個人情報漏洩など、法律に触れてしまう結果になってしまったりと、生成AI利用の危険性については、大人からのアドバイスとして保護者が伝えておく必要があるでしょう。高校でも情報リテラシー教育は行われますが、高校での生成AIの活用については、学校によって、また県や自治体によって対応が大きく異なっているのが実情です。そのため、家庭の役割がより大きくなると思います。
危険性があるからと言って、生成AIを活用しない方が良いというわけではありません。かつてスマートフォンやSNSがそうであったように、新しい技術やサービスは否が応でも普及します。その時に適切な利用ができる能力をしっかりと身につけておくことが肝要なのです。リスクをゼロにすることはできませんが、賢い利用方法を保護者も一緒になって考えることはできます。保護者の皆さんも試しに生成AIに質問してみたり、相談してみたりすると良いかもしれません。また、取り組むべき課題を生成AIに丸投げするのではなく、最初は自分で一生懸命に考え、その後にアイディアを補ってもらいながら内容を改善・修正し、最後は自分の成果物として責任をもって世に出すという大事なルールを家庭内で話し合っておくこともおすすめします。
生成AIは、例えるならばマラソンにおけるペースランナーのような存在です。適切にうまく活用することで、人間の能力を拡張することにつながります。それによって、専門家でも考えつかない新しいクリエイティブなアイディアが出てくることもあります。そして、そのクリエイティブなアイディアが、将来、人類を幸せにしたり、ウェルビーイングを高めてくれたりする、そういう可能性を持っていると思います。