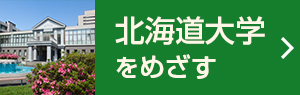北海道大学 学習アドバイス
河合塾講師からの学習アドバイス
教科別の学習対策について、河合塾講師がアドバイスします。
※出題範囲は募集要項、大学ホームページ等で必ずご確認ください。
英語
最近の出題傾向
- ①長文読解
- 長文2題の出題からなる。どちらも、記述式・客観式併用の総合読解問題である。英文の内容は「文化・社会」をテーマにしたものがよく出題されている。2025年度の2題を合わせた英文の総語数は約1,440語で2024年度に比べると70語ほど増加したが、それでも2023年度と比べると200語程度少ない。2023年度のように、それぞれが800語を超える文が出題されることを前提に準備する方が賢明であろう。設問に関しては、2025年度も2024年度に続き、客観式問題が特に易しかった。やはり、この傾向が続くとは思わず準備をする方がよいだろう。
- ②英語表現
- 例年400~500語の英文を読み、それに対する英文の指示に答えることになる。主にQuestion A・Bは本文の内容に合うように英文を完成させる問題である。下線部の前後 に与えられている英文から書くべき英文の形がある程度決まってしまう場合が多い。したがって、大学側が求めている書き換えの型を即座にかつ適切に判断する必要がある。また、書き換えるにあたっては、特に動詞の語法の知識が必要になることも多い。Question Cは英文の内容を基に自分の考えを70~100語の英文で述べる問題であるが、あるテーマに関して「肯定的に捉えるか、否定的に捉えるか」を述べる設問が多い。与えられる英文の内容は主に「生活・社会」に関するものであり、2025年度の「外国人観光客の増加」のように自由作文の定番といえるテーマのものもよく出題されている。大問3英語表現に割ける時間は25分程度であろうから、英文を書き慣れていないと時間内に終えることは厳しくなる。
- ③要約文の空所補充
- 550~700語程度の対話文を読んで、その要約文(300~400語が多い)の空所を補充する形式である。2025年度のように24の選択肢から12の空欄を埋めるという形で出題さ れることが多いが、空所ごとに4つの選択肢があるという形で出題されることもある。したがって、どちらの準備もする必要があるだろう。会話のテーマとしては「日本における男女平等問題」や「企業のワークライフバランスの問題」といった日本社会が抱える問題が出題されることが比較的多い。
2026年度入試予想・対策
- ①長文読解
- (1)英文の構造把握(2)文と文のつながりの把握(3)段落の構成の把握(4)文章全体の論旨の把握、それぞれに関わる問題がまんべんなく出題される傾向に変わりはないだろう。
- 「下線部訳」や「内容説明や要約」の解答においては、文の構造を正確に捉えることが第 1 条件である。何となく単語をつないで雰囲気で訳しているようでは、減点は避けられない。正しく構造を把握したうえで、文脈に合った訳をつくる訓練をしてほしい。その際、実際に手を動かしてみることが大切である。
- 「表現のつながり」と「論理のつながり」を意識した読み方を普段から実践する必要がある。また抽象的な内容の表現や文に出合ったら、前後関係から「つまりどういうことか」を考える読み方をすることも大事である。この場合も実際に手を動かして、その内容を日本語で書いてみたり、英語で書き換えてみたりするのがよい。そのような英文こそが「書き換え問題」や「内容一致文選択問題」で問われることが多いからである。
- 長文化が進んでいるなかで特に求められているのは「段落の構成」の意識であろう。段落のなかで「抽象的な文」と「それを説明している文」との関係を捉え、前者に重点を置いた読み方をすることで、時間の節約を図りたい。
- ②英語表現
- Question A・Bの英問の答えを英文で書く問題では、対応箇所の英文の形を書き換える力が重要となる。したがって、「句と節の転換」「主語の転換」「態の転換」「品詞の転換」などの基本的な書き換えのパターンを身につけておく必要がある。さらに、単純に形を書き換えるだけではなく、意味を読み換えることが求められることもある。したがって「英文→概念→ほかの英文」の演習も適宜行う必要がある。この力は普段の授業のなかで養っていくのが最もよいだろう。
Question Cは本文の内容に基づいて出題されるので、文中の考えに賛成するにしても、反対するにしても「述べられている意見とその根拠」を的確に把握していないと、適切な意見が書けない場合が多い。その意味では読解問題の要素があることになる。したがって、読解の学習の際に筆者の主張と根拠を日本語や英語でまとめてみるのは非常に効果的な勉強である。それに対して賛成または反対の内容の英文を書いてみるのはさらに実戦的である。
そのうえで、Question Cの対策として「環境・医療・教育・IT・生活」などの頻出テーマに関しては相反する立場から共通テーマを論じる演習をしておく。これは試験場での柔軟な発想に役立つであろう。また、自分の主張を説得力のあるものにするために「内容や理由」を説明したり、「事例」を挙げたり、必要があれば「譲歩や対比」を使ったりすることが必要になる。そのような書き方を身につけるためには、モデルとなる解答例の分析が有効である。様々なテーマのモデルを観察し、自分のものにしておくことを勧めたい。 - ③要約文の空欄補充
- 24択形式に対応するためには、空欄に入る品詞を予測する力が必要である。その力を養うためには、英文を読む際に「文の形」にも注意を払わなくてはならない。また単語や語句は単語集だけではなく、できるだけ文のなかでも覚えるようにすることで空欄に入る語の判断力が上がる。特に動詞は後続要素とのつながりが重要となるので、単語集などで基本的な動詞の語法の確認もしておきたい。さらに、普段の読解のなかで「文と文のつながり」を意識した読み方をすることが、対話文を参照しなくても空欄を埋める力をつけることになるだろう。
文系数学
*北海道大学では理系の一部(医学部−看護学専攻と作業療法学専攻)の受験生も数学Ⅰ・Ⅱ・A・B・C(ベクトル)を範囲とする文系学部と同じ問題を解答している。しかし、対象となるのは文系学部の受験生の方が多いので、ここでは『文系数学』と表記する。
最近の出題傾向
- ①出題範囲と傾向
- 大問4題で出題範囲のほぼ全体から幅広く出題しようという姿勢が続いていて、実際に様々な分野の問題が出題されている。そのため、どの分野が重点分野なのかはまったく読めない。しかし過去30年程度の長い期間で見てみると、数学Ⅱの『微分法・積分法』と数学Aの『場合の数・確率』の2つの分野は、ほぼ毎年出題されると見てよいだろう。
- ②その他の特徴
- 以前から文系・理系の「共通問題」がほぼ毎年出題されていた。最近は問題の設定は同じであるが設問は文系と理系で異なり、理系の設問がやや難しい「類似問題」がよく出題されている。2025年度も「類似問題」からの出題であったから、2026年度も続くと考えるのが妥当だろう。「類似問題」は文系の方が易しめの設問であるため、比較的解きやすいことが多い。過去問を利用して「共通問題」や「類似問題」の傾向とレベルを知り、「類似問題」ではできればワンランク上の理系の設問までカバーしてきちんと対策をしておくべきだろう。
2026年度入試予想・対策
かなり難しかった2023年度に対して、かなり易しかった2024年度と続き、2025年度は予想どおり難化したが、それほどでもなかった。最近は難と易が交互に繰り返されている。易しかったときは高得点の争いで、ちょっとのミスが命取りになり、ひとつの計算ミスだけで不合格になるということもよくある話である。一方、難しかったときは問題が完答できなくても部分点をしっかり獲得するだけで合格した者が中心だったと聞いている。難易に関係なく、自分が試験場でできることをしっかりミスなくやり切ることが大切である。
- ①「図形問題」の攻略
- 北海道大学の数学の問題は、文系・理系を問わず図形やグラフ・座標が関係する問題の割合が非常に高い。4題中3題が関係したこともあったが、1題しかなかったときもあり、とても流動的である。2026年度は標準的に半数程度の問題が図を描いて考える問題であると予想し、きちんと準備しておいて、本番ではしっかり図を描いて考えよう。
- ②『頻出ではないタイプの問題』にも負けないように!
- 2025年度には他大学の類題を探してもほとんど見つからない「関数方程式」の問題が出題された。文系受験生は何をすべきかまったく見当もつかない問題だったといわれている。また、この過去20年の間に3回も出題された「三項間漸化式」は、他大学の文系学部ではあまり出題されておらず、教科書では【発展】などで扱われることが多い内容である。この実績を踏まえると、北海道大学を受験する者は、文系であっても、できれば教科書の【発展】で扱われている内容までをきちんと学習しておくべきなのかもしれない。
このような『頻出ではないタイプの問題』は受験生にとって難しいことが多く、出来はそれほどよくないと聞いている。多くの受験生ができないということは、これらの問題の出来・不出来が合否に直接影響することは少ないが、確実に得点できる設問が含まれていることも多いので、めげずに、慌てずに、粘り強く部分点を狙ってほしい。
理系数学
最近の出題傾向
- ①出題範囲と傾向
- 大問5題で高校数学のほぼ全範囲を問うことを目標とし、幅広い範囲から出題しようという姿勢がずっと続いている。
以前から数学Ⅲの『微分法・積分法』をとても重視している大学であり、かつてはこの分野から毎年ほぼ2題がコンスタントに出題されていた。最近は1題しか出題されないことが多くなったが、理由は不明である。2023年度は2題出題されたが、ともに「微分法」からの出題だった。一方、「積分法」からの出題はしばらく少なかったが、2024・2025年度は2年連続して部分積分の計算が出題され、かなり盛り返してきている。したがって、最近の数年の動きだけで傾向が変化したと語るのは気が早いので、しばらくは過去の傾向から判断して、『微分法・積分法』の対策は、「微分法」と「積分法」はもちろんだが、「極限」を含めた全体をきちんとやっておくべきである。 - ②その他の特徴
- かなり長い間『図形と方程式』や『場合の数・確率』の問題が文系・理系でまったく同一の「共通問題」としてほぼ毎年出題されていた。最近は同一の設定で文系・理系の設問を変えて理系を難しくするという「類似問題」の出題ばかりになってきている。「類似問題」の学習は、文系の易しめな設問から理系の難しめな設問までを一緒に並べて解答するのが効果的である。2026年度も「類似問題」の出題があることを想定し、過去問を用いてしっかりと準備しておきたい。
2026年度入試予想・対策
2022・2023年度の難化は長く続かず、2024年度は完答ができるレベルの問題が並び、易しくなった。2025年度もほぼ同じレベルだったので、このレベルの問題で十分に差がついているのだろう。
最近の受験生は、難しくて問題を最後まで解き切ることができなかったときでも、部分点をしっかり確保して合格圏に突入しているそうだ。この姿は以前からほぼ変化していない。実に頼もしい。問題の難度が不安定だからこそ、2026年度も完答することだけを目標とせず、解ける設問はきっちり解いて部分点を狙い、合格をめざしたい。
- ①いろいろなタイプの「図形問題」の攻略
- 北海道大学の数学の問題は、文系・理系を問わず、図形やグラフ・座標が関係する問題の割合が非常に高い。5題中4題のときもあったがこれは例外と見るべきで、2026年度は標準的に2・3題で図形やグラフ・座標と関係するもの(図を描いて考えるもの)が出題されるとして準備をしておき、本番ではしっかり図を描いて考えよう。
- ②数学Ⅲの『微分法・積分法』を得点源に!
- 北海道大学で出題される数学Ⅲの『微分法・積分法』の問題は、典型的な問題であることが多いので、まったく手を出せないことはないだろう。古くから「『微分・積分の問題』は裏切らない」といわれているが、それは確かにうそではなく、しっかりと学習してきた者が『微分・積分の問題』をきっちりと完答して合格したという例が数多く存在する。「数学Ⅲの『微分法・積分法』の問題を完答することが北海道大学に合格するためには欠かせないことなんだ!」と強く信じて、典型問題を中心とした学習によってぜひ完答をめざしてほしい。
現代文
最近の出題傾向
- ①問題文の傾向
- 近年の北海道大学の現代文には、多様なジャンルの文章が出題されている。2008年度入試までは〈哲学+言語論〉、2009~2012年度までは〈言語論+社会論〉という組み合わせで、それぞれ出題されていた。ところが、2013年度以降は、学問論、(文学・表現・翻訳などに関する)言語論、芸術論、科学論、社会・文化論、哲学というように、問題文が多様化している。そして、2025年度入試では、大問一に、死をめぐる人間の在り方を論じた哲学的なエッセイが、大問二には、「法学」を論じつつ、法律学の観点から科学的合理性について論じられた学問論が、それぞれ出された。近年はエッセイ(的な文章)も多く出題されており、問題文の種類には特定の傾向らしきものは見られず、幅広い分野から、様々なテイストの文章が採用されている。
- ②設問の傾向
- 2025年度入試の特徴としては、次の3点が挙げられる。
(1)従来7問であった漢字問題が4問になったこと、(2)2023・2024年度入試にはなかった「抜き出し問題」が出されたこと、そして、(3)2024年度入試では(2020年度以来、久しぶりに出されていた)「文中の言葉を用い」た説明を求める問題がなかったこと―以上の3点である。
他方、傍線部の内容説明や理由説明を求める問題といった、オーソドックスな設問が多いのは従来どおりである。また、字数制限が厳しい問題が出されることにも変化はない。
2026年度入試予想・対策
- ①論理的読解力の習得
- 傍線部に含まれる語句が、本文のどの言葉とつながっているのかを読み取ることができなければ、すなわち、文章を論理的に読解できなければ、内容説明問題でも、理由説明問題でも、高得点は望めない。
そして、2025年度入試では、大問一・問五で〈文章全体の論旨を踏まえて〉という条件のある問題が出された。この種の設問では、傍線部や設問条件につながる論理を本文全体から読み取り、解答に反映させねばならない。そのためには、語と語、文と文のつながり(=論理)だけでなく、段落と段落や、本文の前半と後半のつながりも理解する必要がある。したがって、本文を詳細に理解する〈ミクロの読解力〉のみならず、本文全体を大局的に捉える〈マクロの読解力〉の習得も必要である。 - ②文章表現力の訓練
- 先述のように、ここ数年の設問の特徴として、厳しい字数制限がある。たとえ、本文や設問条件を理解し、解答の根拠となる要素を特定できたとしても、それらの要素を過不足なく解答に反映させなければ、高得点にはつながらない。こうした意味でも、本文にある文言を端的にまとめる要約力が必要である。あるいは、傍線部(や設問条件)に応じた説明にするためには、根拠となる本文の要素を再構成する表現力も不可欠である。平生の学習において、コンパクトに言い換えたり、説明する順序を考えたりすることを意識してもらいたい。
- ③多様な文章の読解
- 〈最近の出題傾向〉にも記したが、北海道大学の現代文では、様々なジャンルの文章が出題されている。ゆえに、多様な文章を読み解き、苦手分野をつくらないようにしておくことも、必要であろう。
古文
最近の出題傾向
- ①問題文の傾向
- これまで、中古・中世・近世の様々なジャンルの作品から出題されている。2025年度は、鎌倉時代の紀行文『海道記』から出題された。本文の長さは500~1,000字程度で、和歌を含むことが多い。
- ②設問の傾向
- 基本的な古典文法や単語の知識を重視した設問も多いが、その一方で本文の趣旨を明確に把握できているかどうかを問う説明問題も出題されている。設問数は4問程度で、現代語訳・抜き出し・傍線部の内容説明・登場人物の心情説明・理由説明・経緯説明・相違点説明などが問われる。小問の記述字数は20~70字の範囲であることが多い。
2026年度入試予想・対策
- ①まず「基本的な知識」を習得しよう
- 古典文法についての理解を踏まえていることを前提とした問題が出題されているので、助動詞や助詞、敬語を中心とした文法事項の習得は不可欠である。また基本的な語彙の意味を問う問題も多数出題されており、重要単語の意味については確実に習得しておく必要がある。さらに和歌に関連した問題が出題される可能性が高いので、掛詞や縁語などといった和歌の修辞法についても必ず理解しておかなければならない。そのうえで、本文中の和歌を正しく解釈し訳出できるだけの力をしっかりと身につけておく必要がある。
- ②様々な文章に接し、正確な「文章解釈力」を身につけよう
- 本文の趣旨を正確に把握できた受験生と、本文の内容を読み間違えてしまった受験生との間で、得点に大きく差のつく問題が例年出題されている。古典文法や単語についての十分な知識を習得するだけでなく、日記や説話を中心に、様々なジャンルの文章に接し、本文の趣旨を的確に把握する力を身につけなければならない。そのためには古典常識についての一定の理解も必要になってくる。省略されている主語を、前後関係を踏まえて正しく把握する力も要求される。さらに、本文全体の趣旨やテーマを正確に理解する力を身につけるとともに、登場人物の心情説明や傍線部の理由説明といった、多様な設問に対応できるだけの読解力を養成する必要がある。設問で問われている傍線部と、その前後の内容を踏まえたうえで、出題者の意図に応じて、解答として必要なポイントを本文から正しく抽出できるよう、十分な読解演習を積み重ねておかなければならない。
- ③設問要求に応じた適切な解答を「記述する力」を養おう
- 古典文法や重要語の正しい理解、文章全体の趣旨の把握がたとえ十分にできていたとしても、答案そのものが、単なる直訳の記述にとどまり、出題者の意図や設問要求に対応しきれていない答案になっていては、高得点を獲得することはできない。何が問われているのかを見極めて、与えられた制限字数内に、必要な要素を過不足なく盛り込んだ解答作成をするためには、実戦的な問題演習をしっかりと積み重ね、十分な記述力を身につけておくことが不可欠なのである。
漢文
最近の出題傾向
- ①問題文の傾向
- かつては『史記』『漢書』『後漢書』などといった正史からの出題が目立ったが、近年は、説話・伝記・随想・志怪小説・書簡など様々なジャンルから出題されている。2025年度は、南北朝時代の志怪小説『述異記』から出題された。本文の長さは例年200字前後である。
- ②設問の傾向
- 設問数は4問程度で、語句の読み・書き下し・現代語訳・内容説明・理由説明・語句の具体化・抜き出しなどが出題されている。現代語訳においては「『之』の内容を明らかにして」といった条件が付され、指示語の具体化が求められることもある。なお、説明を求めるラスト問題の記述字数は、近年75字で一貫している。
2026年度入試予想・対策
- ①基本的な語句や句形など必要な知識を身につけよう
- 2025年度は書き下し文を要求する問題が出題されなかったが、2024年度までは一貫して出題されており、2026年度においても出題される可能性は否定できない。書き下し問題に対しては、まず前提として、動詞や助動詞の接続や活用といった古文における基礎的な文法知識を身につけておくことが不可欠である。そのうえで、再読文字や様々な句形についてもしっかりと理解しておかなければならない。
- ②正確な現代語訳ができる力を身につけよう
- 基本的な語彙や句形などの知識を確実に身につけておかなければ、正しい現代語訳は望めない。しかしそれだけでは、「指示語の具体化」など様々な条件を付したうえで現代語訳を求める設問には十分に対応しきれない。傍線部とその前後との論理関係や文章全体の趣旨を把握したうえで、本文の文脈と調和する訳出を心がける必要がある。文意を誤解していたり、訳文としての体をなしていないような解答は、たとえ部分的に句法の正しい理解ができていたとしても、高い評価は望むべくもない。句形や重要語句といった知識事項を丁寧に学習するとともに、本文全体の趣旨を踏まえた訳出に留意するといった大きな視点も、解答作成においては不可欠なのである。
- ③限られた字数で的確に説明する力を身につけよう
- 本文の具体的な事例を踏まえて、論旨を正確に把握できたかどうかを問う設問が出題されることが多い。したがって、本文のテーマや論旨を把握するための「読解力」と、出題者の要求に応じて、必要なポイントを過不足なく答案としてまとめ上げるための「記述力」を身につけておくことが不可欠である。本文中の具体的な事例を通して、筆者が主張していることを、その根拠とともに的確に読み取り、それを正しい論理展開に基づいて記述するといった、実戦的な演習を十分に積み重ねる必要がある。本文の文脈から逸脱していたり、採点者に意味が伝わらなかったりするような答案では合格ラインに達しないことはいうまでもない。
物理
最近の出題傾向
- ①出題分野と出題形式
- 例年、力学と電磁気から各1題、熱または波から1題の、合わせて大問3題が出題されており、2025年度前期は力学、電磁気、波が出題された。一方、後期は力学、電磁気、熱が出題されており、原子分野からの出題はなかった。各大問の分量には差が見られず、配点はほぼ均等になっていると考えられる。前期・後期ともに、大問はすべて問題文の空所補充形式で構成されており、2025年度は後期に40字以内の論述が出題された。
- ②難易度と分量
- 2022年度まで易化・減少傾向にあったが、2023年度から2024年度にかけて前期・後期ともに一転して難化した。2025年度はその難化傾向にやや歯止めがかかったかたちとなった。形式的には大問3題となっているが、各大問にテーマの異なる問題が2つずつある場合があり、実質的に大問4題以上である。全体の空所数自体は増加していないが、誘導となる空所が減っており、類題に取り組んだことがなければ時間内に解き切ることは難しいだろう。
2026年度入試予想・対策
- ①基本的物理法則の理解
- 公式を丸暗記することで埋められる空所はわずかであり、それだけでは合格点に到達できない。公式や法則を覚えることは必要だが、それらをどのような設定のときに用いるのか、なぜ用いることができるのかを考えながら普段の学習を進めてほしい。問題文の空所は一問一答の繰り返しではなく、誘導するように並んでいる。その誘導の意図を読み取るために、物理法則の理解は不可欠といえる。
- ②典型的標準問題の演習
- 北海道大学では、入試で頻出のテーマが出題されることも多い。頻出テーマに対して何が問われやすいのか、どのような式を立てるのかは身につけておきたい。空所補充形式の問題に慣れることも必要であるが、普段の学習では設問形式の典型的な標準問題を問1、問2、問3…と解き進めて、各問のつながりや誘導の仕方に着目してみよう。
また、一見目新しいテーマで出題されることもあるが、空所にはよく知っている数式が入ることが多い。あくまでも、自分が学習してきた基本法則の組み合わせで解けるように問題がつくられている、ということを忘れないでほしい。 - ③2026年度入試
- 2年連続、3年連続で同じテーマが出題されることもあるが、全体的には幅広く出題されている。また、比較的珍しいテーマの問題は、5〜10年前に出題されていることもあり、過去問演習は有効である。
力学では「放物運動」の出題頻度が多く、「円運動」や「2物体の衝突」と組み合わせるパターンもある。エネルギー保存則や運動量保存則の立式は確実にできるようにしておきたい。また、「慣性力」に対する理解も必須である。
電磁気では「コンデンサー」「電磁誘導」の出題頻度が高い。電磁場中での点電荷の運動も押さえておきたい。また、2015・2018年度には、力学分野の「力のモーメント」と組み合わせて出題されており、他分野との融合問題も十分考えられる。
熱では「気体の状態変化」が中心であり、ポアソンの式を用いることもある。また、マイヤーの関係式を導出する流れや、それを用いた式変形もここ数年はよく出題されている。波では「干渉条件」を水面波、音波、光で立式できるようにしておこう。熱・波ではグラフ描図も出題されやすい。2023年度後期に波・熱・原子の融合問題が出題されているので、原子分野についても基本的事項は確認しておきたい。
化学
最近の出題傾向
- ①出題分野
- 理論・無機から大問2題、有機から大問1題である。各大問はⅠとⅡに分かれているため、実質6題に相当する。全範囲からバランスよく出題されているが、特に理論の気体、反応速度・化学平衡、有機の構造決定は頻出で、ほぼ毎年出題されている。
- ②出題形式
- 設問は選択・計算・記述のほかにグラフの描図など、様々な形式で出題されている。なお、論述問題は出題されたとしても20~40字程度である。
- ③難易度と出題量
- 例年、基本~標準問題が中心だが、試験時間に対して分量が多い。そのため、制限時間内で要領よく得点する能力が要求される。
2025年度は、例年どおり標準問題が中心だった。2024年度と比べて、計算の処理に時間のかかる問題は減り、平易な計算問題が増加した。しかし、知識問題で「すべてを選べ」という問題が多く出題され、知識が曖昧なために失点する受験生が多かった。
難問(=相当な思考力や読解力が必要な問題)が出題されたこともある。例えば、2020年度には「目新しい実験装置を用いた浸透圧と気体の複合問題」が出題され、受験生は苦戦した。しかし、最近(2021~2025年度)は、それほどの難問は出題されていない。
2026年度入試予想・対策
- ①化学全般
- 合格に必要な学力は毎年ほぼ一定で、合格点を取る近道は基本〜標準問題で得点を重ねることである。難問(思考力の必要な問題)に目が行きがちだが、実際にはほとんど差がつかないのでこだわりすぎない方がよい。
まんべんなく出題されるので、不得意分野をつくらないことが重要である。教科書を中心に基本を完全にマスターし、標準問題を中心に練習を十分に行い、幅広く問題に対応できる力を身につけたい。
知識の選択問題では、「すべて選べ」というものが多く出題されている。消去法は通じないため、知識は完全に理解して、正確に覚えておく必要がある。 - ②理論化学
- 計算ミスで得点差がついている場合が多い。制限時間のなかでもミスをしない正確な計算力を身につけることが重要である。特に、物質量・溶液の濃度・気体の計算などは化学全般に関わることなので十分に練習を積んで自信をつけておきたい。
- ③無機化学
- この分野は対策が遅れがちであるが、教科書を中心に据えて基本的な知識をしっかり身につけることが重要である。重要事項を絞っていけば暗記量は意外と少なくて済む。ただし、教科書に記載されている細かい知識が問われることもある。例えば、2025年度では炭素の同素体について出題された。問題文の図から物質名「グラフェン」や「カーボンナノチューブ」などを答えるものであった。基本的だが、侮れない。
- ④有機化学
- 有機化合物の構造決定を中心に十分に問題演習を行い、読解力を身につけておくことが重要である。また、基本的な異性体を正確に書き出す練習も十分にしておきたい。
2025年度は合成高分子・糖類・タンパク質が総合的に出題された。2024年度は合成高分子化合物・糖類、2023年度はアミノ酸・タンパク質、2022年度は糖類に関するものが出題された。どの分野もまんべんなく対策を立てる必要がある。 - ⑤時間対策
- 時間に対して分量が多いので、時間切れを想定する必要がある。過去問などを利用し、試験問題全体を見渡して問題の難易度を判断し、優先順位を考える。制限時間内で、できるものから解答し、手間のかかりそうなものを後回しにするという要領を身につけることが重要である。
特派員の声 ~合格の秘訣!!~
総合理系 1年 はるのいもこ特派員
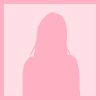
- とにかく添削してもらおう!
- 英語の大問3の英作文の対策として、毎週必ず一つは英作文を書いてネイティブの先生に添削をしてもらっていました。英作文を書き慣れることだけでなく、ネイティブの先生は文法的にはあっていても、より明快なフレーズを学べるのでとても良いと思います。また、数学は自分で書いた答案を先生に見てもらうことで、自分の考え方が伝わる書き方ができているか、書かないといけないことを飛ばして書いていないか、他にもっと良い考え方があるかを知ることができました。自分で書いた答案は先生に見てもらうことをお勧めします。
法学部 1年 りり特派員
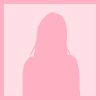
- 小論文講座
- 小論文の授業を河合塾でとっていたことで定期的に小論文を書く機会ができ、実力アップにつながりました。
河合塾の難関大学受験対策
北海道大学をめざすあなたに向けて、受験対策のポイント・イベント情報・合格した先輩たちの声などをご紹介します。