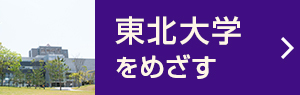東北大学 学習アドバイス
河合塾講師からの学習アドバイス
教科別の学習対策について、河合塾講師がアドバイスします。
※出題範囲は募集要項、大学ホームページ等で必ずご確認ください。
英語
最近の出題傾向
- ①長文の語数の増加傾向
- 大問Ⅰでは長文の語数が2024年度より150語、Ⅱでは200語増えた。1,000語以上の本文全体の内容がまんべんなく問われる。その一方で和訳問題や説明問題など記述問題が減り、客観式問題が増えている。空所に英文を補充する問題、内容一致など読解力を問う問題のほかに、語句整序問題や文法的な誤りを含む英文を選択させる問題など、文法・語法力を問う問題も課される。記述問題での失点を最小限に防ぎ、客観式問題で確実に得点することが鍵となる。
- ②英語表現力の重視
- 大問Ⅲの自由英作文と大問Ⅳの和文英訳問題でⅢ・Ⅳの配点の5割を占める。設問の要求を満たし、文法・語法上の破綻のない英文を書き上げることが求められている。
2026年度入試予想・対策
大問Ⅰ・Ⅱ(長文)の素材は、科学(技術)・IT・文化・歴史・言語・教育・心理学などが中心。2025年度入試では大学での学び(Ⅰ)と、人が睡眠をとる理由(Ⅱ)がテーマ。Ⅲでは、会話やディベートなどコミュニケーション場面の英文を素材とした客観式問題と、英語による記述(要約か自由英作文)が課される。Ⅳでは少なくとも1問の和文英訳と何らかの客観式問題が予想される。
- ①下線部和訳:構文の把握力と日本語の表現力で差
- 主に関係詞・分詞構文・比較・仮定法、そして強調構文などを含む英文が素材となる。2024年度入試に続き代名詞の指示対象の明示が課された。標準的ではあるが、直訳では通用せず、直訳を基に自然な日本語に仕上げる練習が不可欠。語彙力の強化も必須。
- ②内容説明:文脈理解が鍵
- 2025年度入試では下線部(筆者の主張)の内容と理由を問う問題のほかに、本文の要約を図表化したものに適語を入れる問題が出された。Ⅱでは筆者の主張の根拠となる具体例の説明も課された。本文全体の論理展開・文脈を把握することが求められている。他大学の過去問も活用し、様々なタイプの説明問題に触れ、設問の要求に沿ったまとめ方も練習しよう。
- ③客観式問題の多様化と難化
- 英文補充、内容一致、表題選択など、読解力を問う客観式問題は、正解率が必ずしも高くない。私立大学の過去問も利用し、強化に努めよう。
- ④自由英作文・要約英作文:設問の条件に沿い、明快な説明を
- 2025年度入試では、オーバーツーリズムに対処する方法が問われた。理由を2つ挙げることと60語以上書くことが条件。具体的で、読み手が自然に納得できる説明が鍵。過去問などでタイプの違う問題にも触れ、対応力をつけよう。
- ⑤和文英訳:問題文の正確な解釈が必須
- 大問Ⅳの和文英訳問題では、英語に直訳できない文章が出題される。2025年度入試では問題文が長くなり、「瞬時に切り返す言葉が『論破』としてもてはやされ」「~という光景だ」など、受験生に相当の工夫を求める出題になった。2021年度以前の長めの文章2題に対応できる力を過去問演習で育成しよう。また、大問Ⅳでは語句整序問題が定着した。苦手意識のある受験生は問題演習をこなして対策しよう。
- ⑥教材としても魅力的な過去問
- 東北大学の入試問題は着実な学習が正当に報われる良問である。しかも、英文は読むだけで啓発される素材が厳選されている。受験勉強の枠を越えた知的体験を楽しみながら取り組んでほしい。
文系数学
最近の出題傾向
- ①出題範囲全体からバランスよく出題されている
- 制限時間は100分で、大問は 1 ~ 4 の4題である。出題される「分野」について特別な偏りはなく、指定の範囲全体からまんべんなく出題されているといってよい。2025年度は、 1 が「確率」(反復試行における確率を求める)、 2 が「数列」(連立漸化式を満たす数列の一般項を求める)、 3 が「空間ベクトル」(立体の体積比、線分と線分の交点のベクトル表示、線分の長さなどを求める)、 4 が「積分」(3次関数のグラフと放物線が交わってできる2つの部分の面積が等しくなる条件を求める)という出題であった。
- ②問題は典型的なものが中心だが、手強いものもある
- 標準的な学習参考書や問題集でよく見かけるような、いわゆる典型問題が出題の中心ではあるが、考え方自体が典型的でも、場合分けが必要だったり計算が重たかったりするものが出題されることもあるので、付け焼き刃ではないきちんとした学習と対策が必要である。
2026年度入試予想・対策
2026年度もこれまでと同様に、数学の各分野を代表するオーソドックスな問題が中心の出題となるだろう。過去の出題傾向を見る限りにおいては、「微分・積分(数学Ⅱ)」と「場合の数・確率」が特に出題される可能性の高い分野であるが、ほかの分野についても対策をおこたってはならない。学習計画をしっかり立て、試験範囲となる出題分野のすべてに対して理解を深め、準備をしておきたい。
- ①基本事項・公式は正しく覚えて使いこなそう
- 高校数学の教科書を入念かつ丁寧に復習し、基本事項や公式を身につけ直そう。定義・定理・公式の正確な理解は非常に重要であり、その理解の度合いや反復練習の量は入試問題を完答できるかどうかに直結するものである。例えば、「絶対値記号の外し方」「三角関数の加法定理、およびそこから派生する種々の公式とそれらの使い方」「指数関数・対数関数の計算法則」など、苦手意識のあるものや理解の具合に不安があるものについては教科書の例題や計算練習の問題などを通して、自力でこれらを使いこなせるような水準になるまで繰り返し練習しよう。
- ②難問に挑むことよりも典型問題の解法の習得を優先しよう
- 東北大学の数学の試験においては、ヒントが皆無であったり、特殊な手法や知識を用いないと解けなかったりするような難問・奇問が出されることはなく、どの大問にも典型的かつ標準的な問題が必ず含まれている。そうしたところをすべて確実に正解し、得点にしていくことが先決である。したがって、難度の高い問題集ばかりにいたずらに取り組むことよりも、まずは、教科書の各単元の例題の解き方をしっかり身につけていくこと、そのうえで、標準レベルの参考書や問題集を活用して、典型的な問題の解法や答案の書き方を確実に身につけていくことを心がけたい。その際に用いる参考書・問題集については、問題の解答のみではなく詳しい解説も掲載されているものを使うのが望ましい。類題が用意されている場合にはそれらも解いてみて、覚えたことを自力でアウトプットできるかを確かめながら先に進んでいこう。
- ③問題演習は丁寧に行おう
- 出された問題に対する解答の指針が思い浮かんだとしても、それを遂行するだけの計算力と表現力が伴わなければ完答には至らない。問題演習をする際に、自力で解けなかった問題の模範解答を見るのは構わないが、目を通すだけで終わりにするのではなく、きちんと手を動かし、その解答で示唆されている計算の内容、論述の内容を確認し、自分自身の手で完全な答案を仕上げるようにしよう。また、見直しや検算を行う習慣を日頃からつけておくことも大切である。
- ④過去問を解いてみよう
- 東北大学の過去の入試問題については、最低でも直近の2024・2025年度のものには取り組んでおこう。実際の試験においては、解きやすい設問を的確に見抜き、解答時間内にそれらを確実に解くことが大切である。そのためにも、実際の入試問題の形式を早期に確認し、難易度や分量などがどのくらいのものであるかを把握しておくべきである。
理系数学
最近の出題傾向
- ①出題される分野に特別な偏りはない
- 制限時間は150分で、大問は 1 ~ 6 の6題である。出題 される「分野」について特別な偏りはなく、指定の範囲全体からまんべんなく出題されているといってよい。2025年度は、 1 が「確率」(反復試行における確率を求める)、 2 が「数列」(連立漸化式を満たす数列の一般項を求める)、 3 が「微分(数学Ⅱ)」(4次関数が極大値を持つ条件を求める)、 4 が「微分・積分(数学Ⅲ)、数列の極限」(接する2曲線とx軸が囲む領域の面積とその極限を求める)、 5 が「空間ベクトル、図形と方程式」(空間内の直線とxy平面および球面との交点の座標を求める、空間内の直線とxy平面の交点が描く軌跡に関する証明)、 6 が「三角関数、図形と計量」(同じ外接円を持つ2つの異なる正五角形が重なる部分の周の長さの最小値に関する証明)という出題であった。
- ②極端な作業量・計算量の大問が1題程度含まれている
- 具体的には、2025年度の大問 6 、2024年度の大問 6 、2023年度の大問 6 、2022年度の大問 2 などがそれに該当する。これらの問題は、教科書に載っていないような知識や高度な発想が必要になるというわけではないのだが、作業量や計算量の観点から見たときに非常にハードで、短い時間で最後まで解き切ることは(大半の受験生にとっては)困難なものである。面倒な場合分けや緻密な分析、重たい計算の一つひとつを粘り強く実行できる忍耐力を東北大学が受験生に求めているのではないかという見方もできるのだが、6題で1セットという試験内容、および150分という試験時間を鑑みたとき、そのような問題に心血を注ぎ込むよりは、完答できそう、より多く解けそうなほかの大問に時間を費やす方が肝要であろう。
2026年度入試予想・対策
2026年度もこれまでと同様に、数学の各分野を広く網羅した出題となるだろう。過去の出題傾向を見る限りにおいては、「微分・積分(数学Ⅲ)」と「場合の数・確率」が特に出題される可能性の高い分野であるが、ほかの分野についても対策をおこたってはならない。学習計画をしっかり立て、試験範囲となる出題分野のすべてに対して理解を深め、準備をしておきたい。
また、出題傾向の項目においても述べたように、ここ数年の傾向として、時間内に解き終えることが難しい大問が1題程度含まれることがある。問題の難易度の判断は試験中であってもつけやすいので、解き切れそうな問題に対してしっかり時間を注ぎ込むことを心がけたい。
- ①基本事項・公式は正しく覚えて使いこなそう
- 高校数学の教科書を入念かつ丁寧に復習し、基本事項や公式を身につけ直そう。定義・定理・公式の正確な理解は非常に重要であり、その理解の度合いや反復練習の量は入試問題を完答できるかどうかに直結するものである。特に理系学部の入試においては数学Ⅲの「微分・積分」や「数列・関数の極限」の分野は避けて通ることはできない。微分・積分の計算の仕方や極限にまつわる公式を身につけることはもちろん、それらが問題のなかでどのように利用されているのかということもしっかり理解しておかなければならない。
これらに限らず、苦手意識のある部分や理解の具合に不安がある部分については、教科書の例題や計算練習の問題などを通して、自力でこれらを使いこなせるような水準になるまで繰り返し練習しよう。 - ②難問に挑むことよりも典型問題の解法の習得を優先しよう
- 東北大学の数学の試験においては、ヒントが皆無であったり、特殊な手法や知識を用いないと解けなかったりするような難問・奇問が出されることはなく、どの大問にも典型的かつ標準的な問題が必ず含まれている。そうしたところをすべて確実に正解し、得点にしていくことが先決である。したがって、難度の高い問題集ばかりにいたずらに取り組むことよりも、むしろ標準レベルの参考書や問題集をやり込み、典型的な問題の解法や答案の書き方を確実に身につけていくことを心がけたい。その際に用いる参考書・問題集については、問題の解答のみではなく詳しい解説も掲載されているものを使うのが望ましい。類題が用意されている場合にはそれらも解いてみて、覚えたことを自力でアウトプットできるかを確かめながら先に進んでいこう。
- ③問題演習は丁寧に行おう
- 出された問題に対する解答の指針が思い浮かんだとしても、それを遂行するだけの計算力と表現力が伴わなければ完答には至らない。問題演習をする際に、自力で解けなかった問題の模範解答を見るのは構わないが、目を通すだけで終わりにするのではなく、きちんと手を動かし、その解答で示唆されている計算の内容、論述の内容を確認し、自分自身の手で完全な答案を仕上げるようにしよう。また、見直しや検算を行う習慣を日頃からつけておくことも大切である。
- ④過去問を解いてみよう
- 東北大学の過去の入試問題については、最低でも直近の2024・2025年度のものには取り組んでおこう。実際の試験においては、解きやすい設問を的確に見抜き、解答時間内にそれらを確実に解くことが大切である。そのためにも、実際の入試問題の形式を早期に確認し、難易度や分量などがどのくらいのものであるかを把握しておくべきである。
現代文
最近の出題傾向
過去5年間(2021~2025年度)を見てみると、それまでほとんど〈一、評論、二、小説〉の組み合わせであったのが、2024年度に〈二、随筆(エッセイ)〉が出題されている(もちろん小説から大きく離れた出題ではない)。いずれも、実績ある著述家、研究者、あるいは戦後作家が選ばれている。2024年度までの本文字数は3,000~4,000字程度、解答字数は25~90字であった。2021年度より国語の試験時間が30分延長され、本文の分量も増えた。2025年度の出典は、評論が松井哲也『AIの手を掴むくらいなら溺れて死ぬ』より、小説が木内昇『剛心』より、であった。
- ①評論
- 漢字の書き取りが5問、論述による説明問題が4問出題される。オーソドックスなタイプの問題が多いが、字数は25~90字と幅広い。本文の表現を流用するだけでは字数オーバーになる危険性が高く、簡潔かつ明確な表現に言い換えて説明する力が必須である。また、毎年ではないものの、最終問題(問五であることが多い)では、本文全体に関わる出題がされることが多いので意識しておきたい。なお、2025年度の制限字数は、問二が40字、問三が45字、問四が60字、問五が75字であった。
- ②小説・随筆(エッセイ)
- 意味の問題が2〜3問、比喩の説明や理由説明、心情説明などが4問出題される。意味の問題は文脈に即した解答が求められるので、辞書的な意味を意識しながらも文脈に合わせた表現を工夫しなければならない。説明問題は小説・随筆としてはオーソドックスながら、文脈を丁寧に追って受験者の主観を交えずに記述する必要があり、苦手とする受験生も多いだろう。また、本文に隠された主題(メッセージ)を読み取ることも必要となる。小説も評論と同様、字数制限が厳しく、最終問題(問五)が本文全体に関わる出題であることが多い。なお、2025年度の制限字数は、問二が40字、問三が60字、問四が40字、問五が90字であり、問五で本文全体の内容を踏まえる問題が出題された。
2026年度入試予想・対策
2021年度に試験時間が延長されてあまり時間が経っておらず未知数な部分もあるが、現在のところ傾向は大きくは変わっていないので、この傾向が続く前提で考えてみたい。
- ●評論問題のポイント
- 例年、思想的な文章、文化論的な文章、文明論的な文章が出題されている。
①「身体と精神」「自己と他者、世界」「歴史」「知性と感性」「近代」「教養」「言語」などの文化・思想の基本タームを理解し、それを用いて思考し、文章として表現する力が求められている。良書に触れる機会を増やし、読解や思考の基礎訓練をしよう。②漢字の練習は不可欠である。常用漢字はすべて書けるように、かつ意味も即答できるように、練習しよう。加えて文脈で漢字を判断する訓練もしておきたい。③哲学的、思想的、文化的、文明論的な文章を選び、本文全体を要約する練習をしよう。本文の語句を用いても構わないが、なるべく簡潔でわかりやすい表現を選ぼう。④最後に、本文全体で筆者が何を言おうとしているのか、思い切って100字程度でまとめてみよう。⑤過去問などを用いて、正確に読み、「わかりやすく」表現する(=説明する)実践的訓練をしよう。 - ●小説・随筆(エッセイ)問題のポイント
- 本文は一見読みやすくわかりやすい物語が多いように見えるが、そこにある「深い意味」を問う問題になっている。とすれば、①登場人物の心理の動きを、ほかの登場人物や背景(事実や自然などの表現)との関係のなかで細やかに読み取る練習が必要である。②あわせて比喩表現の意味を読み取る練習も行おう。とりわけその表現に込められた登場人物や筆者の思いに注意しよう。③物語の背景となっている事実・自然や④登場人物の「行動」「会話」を関連づけて、隠された「意味」を読み解く練習をするとよいだろう。最後に、本文全体で言わんとしているだろうことを100字程度でまとめてみよう。これができればいわゆる「深い読み取り」ができたということである。過去問はもちろん、東北大学以外の国公立大学の小説問題も取り上げて、積極的に練習していこう。
古文
最近の出題傾向
- ①久しぶりに中古からの出題
- 過去5年間の出典は『かなめいし』(近世・仮名草子)、『俵藤太物語』(中世・御伽草子)、『花月草紙』(近世・随筆)、『一休ばなし(近世・仮名草子)』、『源氏物語』(中古・物語)である。中世および近世の随筆・説話集・物語からの出題が多いが、2025年度は、2009年度に『源氏物語』が出題されて以来、久しぶりに中古の物語からの出題であった。また、2016年度以降見られなかった、和歌の理解を問う問題が出題された。難易度については、ここ10年程度で見ると2019・2021年度はやや難しめであったが、それ以外の年度は比較的易しめで、難問といえるようなものは、2016年度を最後に出題されていなかった。しかし2025年度は、本文、設問ともにかなり難化した。
- ②2021年度から試験時間が150分に
- 2021年度入試からは、より一層「論理的な思考力・判断力・表現力等」を適切に評価するため、国語の試験時間が120分から150分に変更された。その影響か、2021年度以降は本文の分量が多くなっている。
2026年度入試予想・対策
- ①まずは、基礎的な語彙力・文法力の養成を
- 東北大学の設問形式は、次のようになっている。(1)単語・語句の意味を問う問題、(2)現代語訳問題、(3)理由・内容・心情の説明問題、(4)まれに文法などの知識問題。(1)~(4)のいずれに対しても、まずは基礎的な語語彙力・文法力を養成することが肝要である。重要古語については、多義語であればあるほど、その語の根本的な意味や語源などに着目し、それと本文のコンテクストの交わりを意識するよう心がけること。
- ②木を見て、森も見る
- とかく受験生の多くは、単語・文法ばかりにこだわって、全体の文脈を無視しがちである。すなわち、ミクロ的視点ばかりでマクロ的視点を失いがちなのである。木(単語・文法)を見ることも大事だが、森(文脈)を見ることも忘れてはならない。問題文を読む際にも、解答を作成する際にも、絶えず、全体の文脈は意識しておこう。東北大学は、部分の理解を問う設問を重ねたうえで、全体の理解を問う説明問題を立てることが多い。
- ③表現力を身につけよう
- 東北大学の古文は、文章の難度は高くないことが多いし、年度によってはかなり易しいことさえある。しかし、内容は読み取れても、それを的確に表現するのに苦慮させられることが多い。
従来、厳しい制限字数内で過不足なくまとめるというタイプの問題が好んで出題されており、この傾向は今後も続くと思われるが、その一方で、80字クラスの長い記述を要求する出題の可能性も無視はできない。
いずれにせよ、本文の内容を正しく理解したうえで、要領よく、過不足なくまとめる練習が必要である。そのために、東北大学をはじめとする、40~80字程度の論述問題を出す国公立大学二次試験の過去問を解き、考え得る最善の答案を自分でつくってみよう。その後で、河合塾のものをはじめ、市販されている問題集などの模範解答を参照し、自分のつくった解答と比較して、共通点と相違点を確認してみる。解答の内容を構成する要素は何か、その優先順位はどうなのか、どのように流れをつくるのかなどをよく検討し、自分は何ができていて何ができていないのか、正面から向き合ってみること。
漢文
最近の出題傾向
- ①出題分野
- 過去5年間の出題は、明・潘士藻『闇然堂類纂』、明・陶望齢「養蘭説」、宋・葉適『水心文集』、宋・蘇洵「諫論」、清・銭泳『履園叢話』である。いずれも宋代以降の文章であり、ジャンルは随筆・論説・伝記・訓話などから出題される傾向が続いている。
- ②出題形式
- 問題文は200字台後半に及ぶ長文が出題される傾向にある。各設問では、語句の意味、白文の書き下しといった基本事項の理解を問うものから、口語訳、文脈理解に基づく指示語の内容把握や内容説明など、文章全体の趣旨を精密に読解し、25~75字で端的にまとめて説明する記述力を求めるものが出題されている。こうした出題形式には近年大きな変化は見られず、難易度についても2024・2025年度ともに標準的なレベルが維持されている。
2026年度入試予想・対策
- ①ジャンルを問わず長文の読解に慣れる
- 東北大学の漢文では、随筆・論説・伝記・訓話など、多様なジャンルからの出題が見られ、どのようなタイプの文章にも柔軟に対応できる読解力が求められる。また、問題文には200字台後半に及ぶ長文が用いられており、相応の分量を着実に読みこなす力が不可欠である。その力を養うためには、教科書や過去問、模擬試験を通じて多様な漢文に触れ、一字一句に気を配り、読み飛ばさずにじっくりと向き合う姿勢が重要である。
- ②基礎事項の確実な習得と文脈理解の徹底
- 書き下し文や口語訳はほぼ毎年出題され、これらで確実に得点するためには、基本句形に加え、「以」「之」「為」「与」などの多義語の訓み分け・訳し分けの習得が不可欠である。近年では、説明問題に限らず、語句の意味を問う場合でも、文脈を理解したうえで口語訳する力が問われている。そのため、習得した知識を機械的にただあてはめて訳すのではなく、常に前後の文脈や問題文全体の趣旨を意識して解答を作成する姿勢が重要となる。
- ③記述力の向上に向けた実践的訓練を
- 東北大学の漢文では、2019年度以降、40~70字ほどの説明問題に加え、20~35字といった短めの記述も出題されており、全体としては100字以上の記述が求められている。この傾向は2025年度も変わらなかった。したがって、字数の長短にかかわらず、必要な内容を的確に整理し、過不足なくまとめる記述力が必須となる。この力を養うためには、解答例を確認して、「何となく答える方向性はわかる」などと、漠然と解答の方向を思い描くだけで終わらせず、自ら手を動かして解答を書き出し、表現を練り上げる訓練を積む必要がある。また、添削指導を受けながら自分の解答を推敲することで、学習効果は一層高まる。日常的にこうした実践を繰り返し、より完成度の高い答案作成をめざしてほしい。
物理
最近の出題傾向
- ①出題分野
- 例年大問3題が出題されている。第1問は「力学」、第2問は「電磁気学」、そして、第3問は「波動」もしくは「熱力学」である。2022~2025年度は波動と熱力学が交互に出題されており、「原子物理」固有の知識を必要とする問題が直近10年間では出題されていない。単一テーマのみで完結する大問はほぼなく、ひとつの大問で物理の様々なテーマが総合的に試される。
- ②出題形式と難易度
- 解答用紙は「考え方や計算の過程」と書かれた白紙部分が大半を占め、最後に結果を指定箇所に明示する完全論述形式である。また、グラフの選択問題と描図問題も目立ち、これらに対しても「考え方や計算の過程」あるいは「理由」の欄が与えられている。全設問に対して思考過程の詳細な評価がなされると思ってよいだろう。
2026年度入試予想・対策
- ①読解力の養成
- 東北大学の物理は、普段目にしない実験装置や現象が多く取り上げられるため、最初にその物理的状況を正確に把握することが必要不可欠である。これには問題文の導入部分を注意深く読み、一見複雑に見える図やグラフの急所を見抜く能力が求められる。そのためには、学習の初期段階ではシンプルな設定と短い問題文の問題を容易に解けるようにしてから、段階的により複雑な設定と長文の問題へと練習を進めていくことを勧めたい。問題文を読むときは、その内容を図や式に変換していく作業を同時並行で行っていくことが最も効果的で、常に「読みながら手を動かす」ことを意識して普段の学習を続けていこう。
- ②全分野にわたる広く深い理解を
- 出題傾向で述べたように、試験では分野横断型の総合問題が登場する。このため、極度に苦手な分野があると、大問の前半にある標準レベルの設問でさえ手が止まってしまうだろう。特に浮力、干渉、交流電流、電気振動、熱力学第1法則、原子物理などは受験生が後回しにしがちな分野なので手薄になりやすいため気をつけよう。また、力学は物理全体の基礎となるため、電磁気学や熱力学の問題でも力学的視点から考察するといった多面的アプローチが有効である。
- ③答案の書き方も訓練しよう
- 完全論述式は採点者が受験生の思考プロセスを評価するための手段である。最も避けるべきは計算式だけを連ねた解答である。解答用紙は計算のためのものではない。計算用のスペースは問題冊子の白紙ページとして与えられているので、そこで計算を含めた分析と試行錯誤を進めるべきである。物理の解答では、(1)自分で導入した文字の定義、(2)法則名または立式根拠、(3)式、(4)結果という4つの要素が柱になる。初めは簡単な問題でも、この4要素を基本フォーマットとして解答を組み立ててみるとよい。そして先生に自分の解答を添削してもらい、論述内容の過不足を修正していこう。こうした訓練を重ねることで論述形式の解答は洗練され、引き締まった答案が書けるようになる。
化学
最近の出題傾向
- ①理論、理論と無機、有機の大問3題の構成
- 大問の一部が〔Ⅰ〕と〔Ⅱ〕のように分割されていることもあるが、例年、全体の設問数に大きな変化はない。無機化学では典型元素と遷移元素の両方が扱われ、有機化学では高分子に関する設問を含めた構成での出題が目立つ。理論、無機、有機を含めて全般的には基本〜標準問題が中心であるが、応用的思考力が試される問題がいくつか含まれることもある。
- ②結晶、酸化還元、化学平衡、構造決定は頻出
- 結晶に関連する出題では結晶格子についての設問が目立ち、酸化還元に関連する出題では滴定、電池、電気分解などの主要なテーマのいずれかを例年見ることができる。なお、2025年度では新課程で扱われるようになったエンタルピーに関する設問が見られた。旧課程においても類似の内容に関する出題が少なくはなかったこともあり、今後も出題が目立つようになる可能性はある。有機化学では構造決定問題の出題が続き、異性体に関する問題も出題されやすい。
2026年度入試予想・対策
- ①理論分野の演習強化
- 結晶、酸化還元、化学平衡のほかでは、化学結合の出題率も高い。ただし、希薄溶液の性質に関する問題やコロイドの問題が過去に2年続けて出題されたこともあり、理論分野は弱点箇所をつくらないことが大切である。基礎を積み上げ、さらに標準的問題の演習を重ねることで、幅広く問題に対応できる確かな思考力を身につけていくようにしたい。化学現象に対する考察力を問う問題が出題されることもあり、さらなる高得点をめざす場合には、現象を化学的根拠に基づいて説明できる力を養っていくことも大切である。
- ②有機分野の演習は構造決定問題が中心
- 有機分野の出題は、標準的といえる難易度の構造決定問題も多く見られるが、2024年度のようにやや難しい内容も見られる。対策としては、まず基礎力を充実させながら、標準レベルの構造決定問題の演習を重ねていくことが重要である。また、以前に出題されたバイヤー・ビリガー酸化が2019年度にも出題されたように、過去と類似した内容が見られることも少なくはないため、過去問を用いた演習はとても大切である。異性体に関する問題も出題されやすいため、異性体を考える練習も充実させたい。さらに、2022年度では見られなかったものの、高分子化合物に関する出題が続いているため、高分子化合物の基礎知識も定着させておきたい。なお、無機分野についても出題率の高い金属イオンの分離と気体の製法を含め、基本をしっかり身につけておくことが大切である。
- ③計算過程の記述、論述問題対策
- 計算過程を記述する設問、および論述問題の数は近年、1、2問程度であり、2022・2023・2025年度のように論述問題が見られないこともある。しかし、計算過程の記述、論述問題ともに対策は講じておきたい。ポイントを的確に捉えて要領よく整理された記述をすることを意識した、日頃からの練習が大切である。論述問題対策としては、法則、原理など基本事項を理解するときに、簡潔明瞭な文章で説明する練習を心がけておきたい。それは基礎力を充実させることにもつながる。
生物
最近の出題傾向
2025年度入試では例年同様、大問が3題出題された。出題形式も、選択、記述、論述の形式で、基本的には例年同様の出題であったが、グラフを描く問題が2問出題されていた。出題量はやや減少したものの、実験考察に関する難度の高い論述問題が多かったため、「読む、把握する、考える、解答する」のに時間が費やされ、十分な答案が作成できなかった受験生が多かったと思われる。
- ①論述の難化
- 例年同様、論述問題の出題量が多く、考察論述の内容が難化したため、全体的に解答に要する時間がかかる問題が多く、得点しにくい構成となっていた。考えて説明する力、表現力を問われる傾向が続いており、教科書的な知識を要する論述を練習するだけではなく、説明すべき内容を列挙し、組み立てて答案を作成する力を養っておきたい。
- ②出題分野・難易度
- タンパク質や遺伝子に関する分子生物学分野から出題される傾向があり、教科書の基本知識を踏まえて実験内容を把握させて考察させる構成の出題となっている。字数が多く要求される論述問題が多く、試験時間内で十分な解答を作成することは難しい。
2026年度入試予想・対策
- ①出題形式・難易度
- ●出題形式と出題分野の傾向
- 大問が3題出題される形式は変化しないと思われる。前述したメインテーマのなかで、教科書の様々な分野から小問が出題される傾向があり、出題分野については幅広く押さえておきたい。なかでも遺伝子分野、タンパク質に関する設問は頻出であるので、タンパク質が関係する代謝や恒常性、免疫の分野なども押さえておきたい。グラフや図を描く練習もしておくとよいだろう。
- ●問題の構成
- 大問の構成は、教科書の基本的な用語や仕組みを問う問題と、実験などの考察問題が中心となっている。問題の本文に空欄があり、基本知識や用語を答える問題が20問程度、基本知識に関する問題、選択式正誤問題が出題され、残りは論述問題などの考察系問題が出題されている。この出題バランスは大きく変化していないので、2026年度入試でも同様の出題構成と予想される。基本知識、用語問題の配点が2~3割となっており、論述など考察系の問題が7割程度を占める。用語を答える問題は標準的なものばかりなので、基本知識問題で失点せず、考察系の問題で得点を伸ばすことが合格の鍵となるだろう。
- ②学習対策
- ●空欄補充問題への対策−基本知識論述のススメ
- 空欄補充など、用語を答える問題が配点の2割程度出題されており、これらは教科書の基本レベルの用語ばかりである。難しい用語を覚えようとするのではなく、教科書の基本用語や仕組みなどをノートに抜き出し、用語は100字程度、仕組みは200字程度を目安に論述練習をしよう。それによって問題文を読んで理解する力も養うことができ、問題文を読んで理解する、基本的な問題に答える、論述問題に対応できる、解答時間の短縮など一石四鳥以上の効果が期待できる。ぜひ実行してほしい。
- ●計算問題への対策−遺伝・集団遺伝の対策はしっかりと!
- 計算問題はそれほど多く出題されていない。例年1〜3問程度の出題である。できなかった計算問題がどうしても気になってしまうという印象が強く残ってしまいがちだが、一般的に頻出の計算問題ができるように練習しておけばよいだろう。ただ、東北大学では遺伝や集団遺伝などの分野からの出題も見られるので準備が必要である。難しい計算問題ではなく、問題集などでも頻出の基本的な計算問題を解けるように練習しておきたい。
- ●実験データ、グラフなどの読み取り練習で総合力を養おう
- 教科書に載っている代表的な実験、グラフを覚えるのではなく、これらを題材にして、なぜこのような結果が得られるのか、原因は何か、このことから何がいえるのか、などを考える練習をしておこう。グラフを見て「なぜそうなるのか?」を考えて説明する練習をしておくことで、読み取る力、説明する力が養われていき、少しずつ実験問題に対応できるようになっていく。
特派員の声 ~合格の秘訣!!~
法学部 2年 だっち特派員
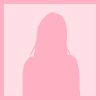
- とにかく基礎を徹底!わからなくてもとにかく書いてみる
- 和文英訳が毎年出題されるが、数年前からは参考書にも載っているようなあまり捻りのない作文が出ているので、そこは絶対満点近く取れるように基本的な単語や文法は完璧にマスターしておく。
数学では、ぱっと見難しそうと思っても糸口があるはずなので、無理矢理な解法でも試してみる価値があると思う。
工学部 1年 N.N特派員
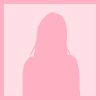
- 物理で差をつけられないようにする
- 東北大学の物理は難しい問題が多いですが、途中までは標準的な問題があります。そこで確実に点を取り、合格者が落とさない得点を取れるようにしました。物理が苦手でも、ここは確実に取りたいです!
河合塾の難関大学受験対策
東北大学をめざすあなたに向けて、受験対策のポイント・イベント情報・合格した先輩たちの声などをご紹介します。