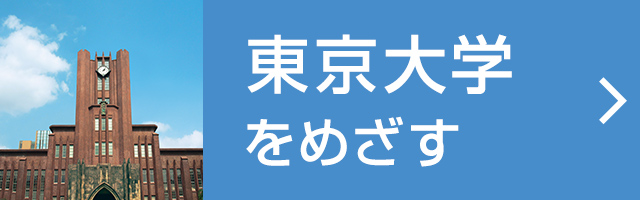東京大学 学習アドバイス
河合塾講師からの学習アドバイス
教科別の学習対策について、河合塾講師がアドバイスします。
※出題範囲は募集要項、大学ホームページ等で必ずご確認ください。
英語
最近の出題傾向
- 「要約」「読解総合」「英作文」「リスニング」「英文和訳」「文法・語法問題」が出題され、受験生の英語力が多角的に試される。苦手分野をつくらないよう各出題形式を十分演習する必要がある。読むべき英文の語数は約3,000あり、記述式問題も多いため時間内で全問を解くには迅速な処理能力も必要である。2020~2024年度までの5年間は設問の構成・形式・数が同じだったが、2025年度は大問5で設問の構成や形式に変化が見られた(ただし、過去の形式が再び出されたもので、新傾向の出題ではない)。
2026年度入試予想・対策
2025年度の入試に多少変化があったとはいえ、基本的にはこれまで出題された形式への対応ができていれば、特に問題はない。いわゆる難問がないので、過去問などを活用して演習を積めば確実に得点は上がる。
これより大問別対策を述べるので学習の参考にしてほしい。
- ●要約問題
- 最近では、英文量は多いが制限字数が厳しいため、字数内でまとめるのに苦労するという問題が続いている。ただし、要約は演習を重ねれば必ず答案作成の力がつくので、しっかり取り組むとよい。慣れてきたら、時間内に7割程度得点できる答案が書けるかといった実戦的な演習に切り替えるとよいだろう。
- ●空所補充型の総合問題
- 解答を確定する手がかりや文章の展開などを意識して取り組むことで、空所補充問題の対応力は上がる。語句整序については、前後の文脈と文法・語法の両面から解答を導くようにすること。空所補充、語句整序ともやや易化傾向にあるので、きちんと演習しておけば高得点が期待できる。
- ●英作文
- 英作文を書くのに必要な語法・文法・構文の知識と、その確実な運用力が求められる。設問の要求を確認し、展開を決めてから書きだすようにする。和文英訳では、与えられた日本語をなるべく忠実に英訳することを心がけよう。どちらもスペリングミスなど基本的なミスがないよう気をつけること。
- ●リスニング
- リスニングに関しては、英語を聞き、設問に答えるという実戦的な演習を続けること。選択肢の内容を吟味して、正確に答えが出せるようにしておこう。本番では、放送前に問いと選択肢をチェックするための時間を確保することも大切だ。
- ●文法・語法問題
- 「正誤判定問題」では下線部だけに目を向けず、文構造を踏まえて正誤を検討すること。2024年度から「内容上の誤り」も含まれるようになった。出題されるポイントはほとんどが基本的なものであるので、正誤問題の頻出事項などの整理をしておくとよい。
- ●和訳問題
- 英文中の3ヵ所の下線部を和訳する問題が出題されている。英文の構造は把握しやすいものだが、単語や熟語の知識不足での失点が多くあるので、語彙の拡充が必要である。また、正確に訳すには、下線部前後の文脈の把握も欠かせない。
- ●総合問題
- 特に難解な英文ではないが、長文であるため、情報を整理しながら迅速に読む演習が必要だ。エッセイや小説が出題されることが多く、状況、人物関係、心情などに留意して読むことを心がける。選択問題でも説明問題でも、解答の根拠となる箇所をしっかりと確認したうえで解答するようにしよう。また、語彙に関する設問にも対応できるようにしておくこと。
文類数学
最近の出題傾向
- ①難易度に大きな変化なし
- 100分で4題の出題形式が定着している。2020年度に難化した後、2022年度までは同程度の難しさが続いていた。その後2023年度はやや易化して分量も減少し、2024年度と2025年度は再びやや難化した。
2026年度がどうなるかはわからないが、標準難易度の問題が2題、「やや難~難」のレベルの問題が2題出るつもりで準備しておくとよいだろう。 - ②総合問題が多い
- 出題範囲である数学I・Ⅱ・A・B・Cからバランスよく出題されている。基本的な問題、よく見かける問題もあるが、それらが組み合わされて、総合的な出題となっていることもある。
2026年度入試予想・対策
- ①易しい問題を確実に
- 4題とも手のつけられない難問ということはないので、易しい問題は確実に解いておきたい。難しい問題をそこそこに頑張りながら、易しい問題で計算ミスなどの取りこぼしをする人は意外と多い。気をつけたいものである。
- ②要注意分野
- 組合せ・確率と微分・積分はほぼ毎年出題されている。確率の問題は、日常的な話題をモデル化したような設定の問題が多く、与えられた設定を正確に読み解くことが大切である。微分・積分の問題は、計算力が要求される。整数もしばしば出題されており要注意である。
図形問題では、初等幾何・座標・ベクトルなどを自由に応用できるようになっておきたい。
例を挙げる。2017年度の第2問(正六角形に関する問題)は、ベクトルを設定するときれいに解けるが、座標を設定して計算力で突破することも可能である。2020年度の第3問(平面座標)の(2)は、座標で処理しようとすると大変だが、初等幾何的に考えると簡単である。2023年度の第4問(空間図形)は、初等幾何的に考えることもできるが、適切な座標を導入すれば内積計算で簡単に解ける。2024年度の第3問(平面座標)の(1)は、三角比を利用する方が見通しがよい。このように、必要に応じて、座標の設定やベクトルの利用などを自在に行えるように、分野横断的な学習を普段からしておくとよい。 - ③普段の学習での心構え
- 基本的な問題の解法を研究することは大切だが、単に解法のパターンを覚えるだけでは、応用がきかず融合的な問題に対応することができない。解法のポイントとなる基本的なアイディアは何か、ということを考えながら学習するとよいだろう。また、最初は簡単なものでよいから、あまり誘導のついていない融合的な問題に取り組むとよい。
理類数学
最近の出題傾向
- ①難しいレベルが維持されている
- 150分で6題の出題形式である。2023年度はやや難化し、2024年度はやや易化し、2025年度は2024年度と同程度の難しさであった。よって、難度のレベルは維持されているようである。
そうはいっても、すべての問題が難問ということはない。年度により多少の変動はあるものの、大まかにいって、普通の問題2題、少しばかり難しい問題2題、かなり難しい問題2題、といった感じである。数学の実力差が点数にはっきり反映される問題セットとなっている。 - ②総合的な力量が問われる
- 素朴で自然な設定の問題が多い。設問を解読して、どういう内容であり、何をすればよいのか、を自分で考えることが要求されている。誘導的な設問がある問題も増えているが、だからといって必ずしも易しいとはいえない。元々の問題の難度が高いために誘導的設問がついている、ということがあるからである。各設問がその後にどのようにつながるのか、どういうヒントになっているのか、などを考えることが必要になってくる。
- ③出題分野
- 出題範囲からバランスよく出題されている。「場合の数・確率」は2018年度から4年連続して出題されなかったが、2022~2025年度は出題された。
空間図形と整数もよく出題されている。また、近年の東京大学理類は数学Ⅲの比率が高く、積分計算の技術も大切である(2019年度の第1問、2021年度の第3問(2)、2022年度の第1問、2024年度の第2問、2025年度の第2問も積分計算の要素が強い)。
2026年度入試予想・対策
- ①要注意分野
- 空間図形と整数は、出題率が高い割には、高校での演習が足りないことが多いと思われる。自分で補っておくことが肝要である。空間図形に関しては、球、円柱、円錐、角錐などといったよくある図形の見取り図を描くこと、断面の形を調べること、などが自由にできるようになっておきたい。積分法との融合で立体の体積を求める問題もよく出題されている。整数に関しては、素数、約数倍数の関係、余りによる類別、格子点などに慣れておきたい。二項係数の数論的性質もよく出題されている。
数学Ⅲでは、不等式や近似値が要注意である。不等式を利用して極限を求める問題(いわゆる「はさみうちの原理」を利用するもの)にも慣れておきたい。 - ②計算力をつける
- ごく普通の標準的な問題も出題されるが、このような問題で案外と差がついている。差がつく理由のひとつとして計算力がある。微積分を中心に、計算力を鍛えておきたい。
- ③問題に取り組む姿勢
- 基本的な問題の解法を研究することは大切だが、単に解法のパターンを覚えるだけでは、応用がきかず融合的な問題に対応することができない。解法のポイントとなる基本的なアイディアは何か、ということを考えながら学習するとよいだろう。また、問題を解く際には、一般的な枠組みのなかでその問題を捉えることと、その問題特有の状況を利用することの両面が大切である。一般原則を研究するとともに、個別の問題に即して工夫を凝らすことを普段から行っておくとよいだろう。
2022~2024年度の第6問は、かなりの難問であったが、いずれも、やや難解な問題文の意図するところを直感的に把握し、結局のところ簡単なことを表現しているのだと理解することが解法の糸口となっている。2026年度も同様の難問が出るかはわからないが、できれば、このような訓練もしておくとよいであろう。
現代文
最近の出題傾向
- ①出題形式はあまり変わらず
- 2025年度も例年同様、文類では第1問と第4問、理類では第1問のみで、第1問は文理共通という出題形式であった。すべて論述形式である。設問数は、第1問も第4問も2024年度と変わりはない。問題文の難易度に関しては、第1問はやや易化し、第4問はやや難化したが、大きな変化は見られない。設問については、例年どおり解答のまとめ方に苦労する設問が多い。とりわけ第1問の(四)は、傍線部周辺の精緻な読解と、本文全体の論理的な読解の双方を要求するため、日頃からの学習の積み重ねがものをいうだろう。
- ②評論文と随筆の組み合わせが基本に
- 2025年度の第4問では小説が出題されたが、例年の傾向としては、第1問では硬質の評論文が、第4問では随筆風の文章が出題されている。第4問では、芸術家や文学者の手による芸術論や文化論が出題されることもあるので、随筆だけでなく、芸術・文化系の様々な文章にも親しんでおきたい。
- ③簡潔で論理的な解答が要求される
- 東京大学の現代文の設問形式は、シンプルに「どういうことか」「なぜか」と問われる場合が多く、極めてオーソドックスなものである。だからといって問題自体が易しいわけではない。解答への道筋が複雑で書きにくい問題もある。それを、簡潔で論理的に筋の通った答案に仕上げることが要求される。
2026年度入試予想・対策
難易度に関しては、第1問はやや難化した問題が、第4問は2025年度と同程度の問題が出題されるだろう。文章のジャンルとしては、第1問では、ときに自然科学を扱った文章が出題されるので注意しておきたい。第4問については、小説の問題が今後どれほどの頻度で出題されるかは予想できないが、おそらく随筆が出題される可能性が高いと思われる。したがって、ここではその内容如何にかかわらず通用する対策を掲げておく。
- ①文章の焦点を見極める訓練を
- 解答のポイントを安易に傍線部周辺に探って済ませてはならない。東京大学の現代文の問題では、他大学以上に本文全体の適切な読解が必要とされる。本文の全体構造のマクロな読解(全体の把握)を踏まえてこそ、傍線部に収斂する文脈のミクロな読解(局所の把握)が成立する。第1問ではとりわけ論理的に厳密な読解が、第4問では論理的な読解に加えて表現の微妙さに配慮する読解が必要となる。〈論理の道筋〉をしっかりと捉える視線と、〈比喩表現などのニュアンス〉をくみ取る視線の双方を訓練しておこう。
- ②簡潔で論理的な答案作成の訓練を
- 答案作成においても、論理と表現に目を配らなければならない。解答のポイントが適切だからといって、それらを安易に並べただけでは評価されない。各ポイントがきちんと論理的につながっていることも重要となる。そのうえで、表現が曖昧になっていないか、比喩表現をそのまま使っていないか、もっと適切な表現に言い換えられないか、言い換えすぎていて焦点がずれていないか、ということに注意しよう。答案作成の鍵となるのは「ポイントの適切さ」「論理構成の適切さ」「表現の適切さ」である。
- ③基本的な知識・表現法をしっかり身につけよう
- 東京大学入試では様々なジャンルの文章が出題される。そこで、①の訓練のために、普段から文化論・社会論・科学論・芸術論などの入門的な書物(新書など)を手に取り、そのジャンルでどんなことが論点となっているか、どんなキーワードが使われているかを頭に入れておこう。さらに②の訓練として、的確な解答を作成するためにまずは語彙力をつけ、東京大学入試に即応した問題集などに取り組もう。
古文
最近の出題傾向
- ①文理での問題の違い、出典となる作品の傾向
- 文理共通の文章が出題されること、設問が現代語訳と内容説明とで構成されること、理類の設問は文類の設問の一部を用いるかたちで出題されること、という点で、近年は安定した傾向にある。これは2000年度以降の大きな流れであり、文理間の試験時間の差や、配点の違いなどに変更がない限り、この傾向は当面大きくは変わらないものと考えられる。
出典となる作品は、多く、古代後期(平安時代)から中世(鎌倉時代~室町時代)の「物語」や「説話」であり、またそれと連続性・類似性を持つ作品である。複数の登場人物が登場し、様々な出来事が起こるなかで、登場人物の関係性や状況・心情を読み取ることが狙いとなっている。したがって登場人物の性格・心情・思考を理解すること、人間関係の在り方やそこに起こる出来事の意味・経緯を読み取り、要領よく説明することが求められる。
なお、2025年度の出典は『撰集抄』で、2024年度に平安時代の女流日記から久しぶりに出題された後、2023年度同様に説話からの出題となった。宝日上人が奇矯な行動を重ねるのは、無常を悟るがゆえに名利を離れ遁世するためであったことを正確に理解し、設問の要求に対して過不足のない解答を作成することが必要であった。 - ②設問の傾向
- 問一は現代語訳の問題で、例年3問の小問からなる。そこでは、古文単語の意味、助動詞や助詞を中心とした文法事項、敬語、和歌表現等の知識が求められる。ただし単なる知識だけでなく、それを本文に即した表現にまとめることも求められる。
問二以降の問いでは、登場人物の心情や文章中の出来事の説明が求められる。多くは直接に説明を求める設問だが、傍線部の現代語訳という体裁を取りながら説明を加えることを求める場合もあって、そこでは単なる現代語への置き換えだけではなく、登場人物の心情や出来事の内容説明が必要となる。また、和歌の内容や大意が問われることもある。なお近年の問題では、答えるべき内容を指定し、誘導する形式も増えてきている。
理類の問題は、文章の大きな流れが明らかになるように設問が選ばれており、対して文類の問題はそれに加え、やや細かく心情や内容に踏み込んだ問いが設定される。
2026年度入試予想・対策
- ①文章の内容把握を心がけること
- 2026年度入試でも、「物語」や「説話」の作品が出題される可能性は高いと思われる。ただし、2024年度のように「日記」などほかのジャンル、あるいは平安・鎌倉期以外の時代の作品が出題されたとしても、「物語」や「説話」の応用で読めるような作品であると考えてよいだろう。その対策としては、平安時代・鎌倉時代の「物語」「説話」の問題を中心に取り組むこと、そして場面状況の把握、登場人物の心情の読み取りをめざす学習を積むことが大切である。ただしこれは、ほかのジャンルの学習を軽んじてよいということではない。「日記」「歌集」の心情表現や、「随筆」「歌論書」の論理・思考は、「物語」や「説話」の表現や内容に通ずるところがあるので、それらの作品を通してトレーニングを積むことも有効である。
- ②語彙力・文法力を磨くこと
- 設問に解答するうえで直接的に大きな意味を持つのは、やはり、古文単語の知識や、助動詞や助詞を中心とした文法力、そして敬語の訳出や敬意の方向の理解、掛詞などの和歌表現に習熟することである。これらについては覚えることと同時に、それを使って実際の文章を理解し、表現を分析することが極めて有効である。ぜひ積極的に多くの文章、表現に触れて、理解することを心がけてほしい。
漢文
最近の出題傾向
- ①2025年度入試の特徴
- 漢文は2006年度以降、文理共通した文章からの出題であり、2025年度も同一の素材文であった。文類の問題が理類の問題の設問に一題加わったかたちであった点も、ここ数年と変わりはない。2025年度は、明の雲棲袾宏の『竹窓二筆』からの出題であった。筆者は学問や弓、お手玉、琴、囲碁から書道、絵画に至るまで様々な例を挙げながら、「執着」することの必要性を論じる。そして仏道へと議論を進めていくのだが、最後に筆者は、漫然と対象にとらわれてしまう「執着」などあってはならないとする一方で、一心不乱に対象に専心する「執着」こそなくてはならないのだと結んでいる。雲棲袾宏は中国の仏僧であり、本文の「参禅」「三昧」や注の「仏の観想」などといった仏教用語も散見されるやや固めの文章であった。過去に遡ってみると、2020年度『漢書』、2023年度『貞観政要』はストーリーを含んだ文章であったものの、それ以外は議論や論説の文が多く出題されており、特に2021年度以降は政治論が続いていた。概して硬質な論説文は解きにくさを感じる受験生も多いようである。2024年度では段落分けがなかったが、基本的には丁寧に段落分けがなされており、2025年度も3段に分けられていて、読み取りやすくしようとする配慮はうかがえるが、それでも2025年度はテーマが捉えにくかったのではないだろうか。
- ②設問について
- 2025年度は(一)に短い語句の現代語訳の問題が3問出題された。2016年度以降、(一)では現代語訳や意味をたずねる問題が続いているが、2025年度は2023・2024年度に続いて「平易な現代語に訳せ」となっており、単なる逐語訳ではなく、より文脈に即した解答が求められている。(一)以外でも(二)で現代語訳の問題が出題されていたが、こちらは傍線部中の「之」の内容を明らかにすることが要求されており、やや説明的な傾向がある。また、文類用の問題に比喩に関わる問題があったが、2024年度も(一)と文類用の問題に比喩に関わる問題があり、漢文では比喩が用いられることが比較的多いことを踏まえれば、注意が必要であろう。また最後の設問では、文章の構造から、全体の結論にあたる箇所に設問箇所があり、本文の主旨を踏まえなければならないことは明らかである。どの設問も決して奇をてらったものではないので、過去問などを利用した対策が有効であることはいうまでもないであろう。
2026年度入試予想・対策
- ①基本句形や重要表現、そして漢文常識や常識的な語彙に習熟する
- 2016年度以降(一)では、2018・2019年度は短い語句の意味、それ以外の年度では短い語句の現代語訳の問題が3問ずつ出題されているので、(一)については2026年度も短い語句の現代語訳の問題が3問出題される可能性が高いと思われる。また、2025年度のように(一)以外で現代語訳の問題が出題される可能性も高く、さらに内容説明、理由説明の問題などの出題が考えられる。これらの設問については、もちろん文脈に即した内容、表現が求められていることはいうまでもないが、まずはきっちりとした直訳をつくらなければならない。そのためには基本句形、重要表現、そして漢文常識や常識的な語彙にしっかりと習熟しておく必要がある。
- ②要点を把握し、簡潔・的確な解答を
- (一)を含め、現代語訳や内容説明、理由説明問題など東京大学の漢文の問題では、こなれた日本語で的確な解答を作成することが求められている。2022年度までの(一)のように、設問が単に「現代語訳せよ」、あるいは2018・2019年度の(一)のような「意味を現代語で記せ」などの問題では逐語訳的な解答が要求されていると考えてよいが、設問が「平易な現代語に訳せ」「わかりやすく現代語訳せよ」などとなっている現代語訳の問題では、必要に応じて省略されている主語・目的語を補充したり、指示語を具体化して、一文で意味が通じるようにすることが大切である。また内容説明や理由説明などの問題では、傍線部自体、または対応する箇所を訳出し、その内容を簡潔にまとめて提示する能力が問われている。要点を正確に把握して、簡潔で的確な解答をつくる訓練が何よりも大切であるが、現代語訳同様、こなれた日本語で表現する必要があるのはいうまでもない。
- ③過去問もおこたりなく
- 近年は、やや硬質な評論文や論説文からの出題が多いが、遡れば史伝・史話、志怪小説、随筆・随想、そして漢詩など多種多様なジャンルから出題されている。また2021年度のように日本漢文から出題されることもあるし、朝鮮の漢文や、さらにはヨーロッパ人の記した漢文から出題されたこともある。時代についても、2025年度のように明のものが出題されたかと思えば、2023年度は唐、2022年度は秦の作品から出題されているように、様々な時代の文章が出題されている。このように、ジャンル、時代に拘泥することなく出題される東京大学入試の漢文については、ある程度の数の問題をこなすのが一番だが、そのためにも東京大学の過去問にはあたっておきたい。過去問の読解は、どのような時代、ジャンルの文章や詩が出題されても対応できる読解力を養うのに最適である。ぜひとも有効に活用してもらいたい。
物理
最近の出題傾向
- ①問題文が長く、初めて見る問題が出題される
- 近年の東京大学の物理では、問題文が長く、受験生としては初めて見るような問題が出題されている。そのため、問題文に書かれている状況・設定を理解できるかどうかが鍵となる。問題文を丁寧に読み、常に一から考えていくことが重要である。問題の難度は高いといえるが、難しい物理の知識を必要とするわけではない。多くの場合、設問自体が誘導となっていて、1問1問を理解しながら順に解いていけば、そこまで難しくはないともいえる。
- ②原子分野からも出題される
- 例年、大問3題が出題される。第1問は力学分野から、第2問は電磁気分野から、第3問は熱分野もしくは波動分野から出題されるが、ほかの分野を含む融合問題として出題されることもある。原子分野については、過去においてはほとんど出題されていなかったが、最近はほかの分野の問題に含まれるかたちで出題されている。2023年度は第1問で核分裂、半減期、2021年度は第3問で光子、2020年度は第1問でボーアの量子条件が出題されている。原子分野を含む全分野の学習が必要である。
2026年度入試予想・対策
- ①頻出のテーマ
- 力学分野では、ばねを含む装置の問題や単振り子の問題など、単振動の問題が最も多い。続いて、エネルギーや運動量の保存則の問題、円運動や万有引力の法則を用いる問題などの出題頻度が高くなっている。電磁気分野では、電磁誘導の問題が多く、コンデンサーの問題がこれに続いて多くなっている。他大学では頻出ではないが、交流回路の問題、ダイオードを含む回路の問題も出題されているので注意が必要である。熱分野では、気体の状態変化の問題が多くを占めている。波動分野では、屈折の法則を用いる問題が多いが、波の干渉・回折に関する難問が出題されるというのが東京大学の物理の特徴のひとつである。
- ②問題の特徴
- 典型問題が出題されることもあるが、見慣れない設定の問題や、物理の本質を深く考えさせる問題が多く出題されている。2021年度に出題された光ピンセットなど、最新の研究成果に基づく問題も出題されている。また、2020年度に出題された面積速度の問題のように、原理的なところから考察する問題も出題されている。いずれにしても、物理現象を本質的に捉え、基本原理から論理的に考察する習慣を常日頃から身につけておく必要があることに変わりはない。
- ③実力養成に向けて
- まずは、物理の全範囲について基本法則を理解し、典型的な問題が解けるようにしておこう。難度が高い問題であっても、必要な物理の知識は基本的である。そのうえで、問題文が長く、初めて見る問題の対策になるが、過去の東京大学の入試問題や、「東大入試オープン」などの予想問題を解いてみよう。初めは時間制限にこだわることなく、状況を図にまとめるなどしながら丁寧に解いていこう。もしも、基本事項に不安があるときは、関連したより易しい問題を解き直してから、過去問や予想問題に戻ればよい。また、単に問題を解いて答え合わせをするだけでなく、背景となる物理現象を深く考察してみよう。そのような考察が、真の実力養成には必要である。
- ④答案作成の練習もしておこう
- 東京大学の物理は論述形式である。解答用紙には各設問の問題番号もなく、ノートのような横線があるだけである。多くの設問では、解答用紙には答えのみではなく、その途中経過も簡潔に記述しておく必要がある。また、論述形式のため、正解に至らなくても部分点がもらえる可能性がある。このことを意識して、1点でも多く得点することを目標に、答案作成の練習もしておこう。
化学
最近の出題傾向
- ①理論分野のウエイトが高い
- 大問3題で、2020~2024年度は各大問がⅠ・Ⅱに分かれていたが、2025年度は第1~3問のいずれもⅠ・Ⅱに分かれていなかった。2020~2024年度は第1問が有機分野、第2問が理論・無機の融合問題、第3問が理論分野の出題であったが、2025年度は第1問と第3問が入れ替わり、第1問が理論分野、第3問が有機分野の出題であった。出題分野のウエイトは理論>有機>無機の順である。
- ②思考力が重視される
- 東京大学入試の化学では、見慣れないテーマや物質を題材とする問題が多く出題されることが特色であり、既習の原理・法則と関連づけて解答を導く思考力が重視されている。また、計算過程を書かせる問題や論述問題が多く出題されるなど、問題解決のプロセスや得られた結論を客観的に記述する科学的な表現力が重視されている。さらに近年ではグラフ問題の出題が顕著に増加している。なお、設問単位で見ると、入試頻出の典型問題の出題も少なくないが、試験時間に対して問題の分量がかなり多いため、これらの典型問題は迅速に解く力が要求される。
2026年度入試予想・対策
- ①化学の全範囲にわたって典型問題を迅速・確実に解く力をつける
- 典型問題を取りこぼす受験生が意外に多いが、まずは化学の全範囲にわたって頻出の典型問題を確実に解く力をつけよう。「じっくり考えると解ける」では時間不足に陥るので、迅速に正解できるように訓練しておく必要があり、計算力も十分につけておきたい。
理論分野はウエイトが高いので、重点的に学習しておく必要がある。頻出の公式や解法については、とどこおりなくスラスラと運用できるように準備しておきたい。ただし、単に公式を暗記するのではなく、問題演習を通じて原理・法則に関する理解を深め、見慣れない問題にも対応できる応用力を養っていこう。
無機分野は、物質の性質・反応・製法などの知識を、系統的に整理して覚えていくようにしよう。さらに、問題演習を通じて知識を拡充し定着させるとよい。
有機分野は、脂肪族および芳香族化合物の性質、反応、製法を把握するとともに、並行して問題演習を行い、分子式から異性体を並べたり、問題文の情報から化合物を絞り込む構造決定問題のアプローチの仕方を十分に身につけよう。また、天然有機化合物、合成高分子化合物の出題も少なくないので、準備をおこたらないようにしよう。できるだけ早いうちに重要事項を覚えたうえで、計算問題も含めた解法を習得しよう。 - ②過去問演習を積み重ねよう
- 一通りの学習が済んだ後は、過去問と東京大学型の模試・問題集を利用して応用力・得点力を高めよう。
見慣れない題材の問題では、既習の原理・法則と関連づけて考えることがポイントである。問題文や図表、グラフで与えられた情報・条件について、原理・法則との関係を見いだしながら分析・読解して考察を推し進めるようにしよう。また、答えに至る過程を簡潔に記述したり、ポイントを明確に論述できるように訓練しておく必要がある。さらに、分量が多いので、理科全体での時間配分のイメージをつかみ、設問単位で難易を見極め、平易な問題は確実に得点できるように十分に訓練しておこう。 - ③答案作成の練習をしておこう
- 東京大学は他大学と異なり、罫線のみが入った答案用紙に、一から記述・論述式の答案を作成するため、答案の書き方次第で大きく得点差が生じる。試験場でいきなりうまく書けるものではないので、答案作成の練習をしておく必要がある。
生物
最近の出題傾向
- ①大問3題が出題され文章量が多い
- 大問3題から構成されるのは、30年以上変化がない。各大問はそれぞれがいくつかのテーマを含んでおり、文章が長く、設問文も文章量が多い。問題前文では受験生にとって初見の実験やデータが扱われることが多く、出題される小問も実験やデータについて考察するものが多い。
- ②論述量が多く複雑な計算問題もある
- 解答形式は論述問題が中心で、論述量は合計で600~1,000字程度(2025年度は合計600~800字程度)であり、解答時間の割に分量が多い。その他、記述・選択・計算問題が出題され、近年は選択問題が増加している。また、出題される計算問題は定型的な解法で解けるものが少なく、複雑な処理を要求されることが多い。
2026年度入試予想・対策
- ①出題が予想される分野・テーマ
- 近年は、「遺伝子・発生」「細胞・代謝」「進化・系統」「生態」の分野からの出題が多く、ここ数年は特に遺伝子と他分野の融合問題の出題が増えている。また、毎年少なくとも大問1題は植物を題材とした出題がある。基本的には2026年度入試もこの傾向を踏襲した出題になると考えられるので、これらの分野に関しては特に入念な準備をしておこう。また、新しいテーマが出題される頻度が高く、例えば2025年度であれば、第1問で線虫の学習と遺伝子の関係について出題されたが、これは近年の研究の成果を基にした出題である。また、2023年度は第3問で新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関して出題され、2022年度の第1問の「チャネルロドプシン」を用いた解析や第3問の「DNA紐」を用いた解析も、近年、生物学界で話題となったテーマである。このほかにも近年の生物学の研究成果を基にした出題が多くあり、特に遺伝子分野でこの傾向が顕著であるので、一般向けの科学雑誌などで最近の生物学の動向などを知っておくとよいだろう。
- ②論述問題に対する対策を進めよう
- 出題の中心となるのは論述問題であるが、まずは知識を問う典型論述を固めよう。また、考察した内容を論述する問題については、論点を明確にして簡潔な文章を作成することが必要となるが、初めから自分の力だけでこれを身につけるのは難しいので、自分の書いた答案を生物の先生などに添削してもらう習慣をつけるとよいだろう。
- ③独特の問題形式に慣れよう
- 東京大学の入試で高得点を狙うには、長文の問題文や実験データを正しく解釈することが必須であるので、過去問の演習などを通して、初めて見るデータの読み取りの練習を重ねよう。このとき、実際の試験時間(理科2科目150分)を意識して、時間内にできるだけ多くの内容を読み取れるように努力しよう。問題を解いた後には必ず解説を熟読し、解答の根拠となるデータの読み方を理解する作業を繰り返すことが、考察力を身につける最善の方法である。
生物は比較的短期間で実力を伸ばすことが可能な科目である。以上を参考に、最後まで努力を重ねよう。
日本史
最近の出題傾向
- ①全時代均等に出題される
- 大問4題からなり、古代・中世・近世・近現代から1題ずつ出題される形式が踏襲され続けている。大問のなかには設問が置かれる。設問数は1つ、あるいは、設問がA・Bのように枝問に分かれることも少なくない。解答の分量は1大問あたり5~6行(1行は30字)で、設問ごとでは最小で1行(30字)、最大で6行(180字)となる。論述字数は多くない。
- ②古代~近世は条件文の分析、近現代は資料の読み取りに注意
- 古代~近世の問題では、提示された4~5本ほどの短文(条件文)を分析し、それに日本史の知識を加味させながら解答を構成する形式がほぼ定着している。一方、近現代は、グラフなどの統計資料や文献史料を読みつつ日本史の知識を問う形式が多い。また、これらの形式以外にも、年表の分析や、指定された語句を解答に織り込ませて論じさせるものも見られる。どのような形式であっても、問題に提示された情報を漏れなく使って解答を組み立てていく意識を持ちたい。
2026年度入試予想・対策
- ①問題文形式への対策と簡潔な文章表現への意識
- 問題文形式への対応力を高めたい。東京大学では、要求される日本史の知識は基礎的なものであり、そのなかでより高得点を生む答案を作成するためには設問要求に沿った論理構成力が必須である。「知っていることを書く」のではなく、「問われていることを書く」ことを意識して、過去問研究に取り組んでほしい。
また、前述のとおり、東京大学日本史の論述字数は多くない。が、その分、答えるべきことを過不足なく簡潔にまとめる力が必要とされる。過去問演習の際には、余計な修飾表現や同内容の繰り返しなどの冗漫な叙述に陥っていないかどうか、主語の抜けなど書くべき要素が漏れていないかどうか、用語の羅列のみの文章になっていて主述関係や因果関係の逆転などで意味が通らなくなっていないかなど、解答例を参照して作成した答案の不備を洗い出したい。 - ②各時代のテーマ
- 総じて、社会の変化に注目しながらその前後の相違や変化の契機・背景などを考察させる問題が目立つ。これら社会の全体像を把握するために、政治・経済・文化などが互いに関連・影響し合っていることを意識しつつ知識の習得に努めたい。以下、各時代に分けて見ていこう。
- ●第1問(古代)
- ヤマト政権時代の氏族制から大宝律令の成立に象徴される律令制への転換や、律令国家の支配の特徴、10世紀頃より顕著となる律令制の変質を分析する問題が定番といえる。外交面では、東アジア情勢の変動に連動した日中・日朝関係や、中国文化の受容の在り方に注目した問題が多い。古代史の全分野に関わるといっても過言ではない律令国家の展開について、時期ごとの特徴を把握し、時期間の相違点・共通点などを説明できるようにしておきたい。
- ●第2問(中世)
- 武家政権をテーマとした問題が多い。鎌倉時代では御家人制・惣領制の在り方や承久の乱を画期(時代の区切り)とする社会の変化などが、室町時代では守護大名の在り方や、応仁の乱を画期とする社会の変化などが問われる。また、文化史や経済史の出題も散見される。一方で、外交史を正面から扱ったものはあまり見られない。鎌倉時代を中心とする問題と室町時代を中心とする問題が年度ごとに交互に出題される傾向がある。ちなみに2025年度は、室町幕府の土一揆への対応をテーマとする問題だった。
- ●第3問(近世)
- 近世社会の基盤である幕藩体制・石高制などの知識を踏まえつつ問題文を分析させる問題や、貨幣経済の発展に伴う農村社会の変化をテーマとした問題が頻出といえる。また、社会・経済の変化が文化に及ぼす影響や、鎖国制度・外国船来航問題など、外交をテーマとした問題も散見される。例えば、農村社会の変化がそのときの幕政にどう影響したかなど、分野間の関係性を意識した知識の整理が望まれる。
- ●第4問(近現代)
- 政治面では明治憲法体制や明治・大正期の政党政治の動向、経済面では明治期の産業革命や昭和恐慌前後の金融政策(井上財政・高橋財政)、昭和恐慌が各方面に及ぼした影響などが頻出テーマである。また、戦後史の出題が今後増えていくと思われる。前述のとおり、第4問では統計資料などを用いる問題が多いが、2025年度は明治政府の音楽教育をテーマに、資料と条件文を組み合わせた問題が出題された。第4問は形式が多様なので、過去問を数多く解くことで対応力を高めたい。
世界史
最近の出題傾向
- ①「世界史B」から「世界史探究」へ ~本質的な難易度に変化なし~
- 2025年度の入試は、「世界史探究」の初年度の入試となった。ただし、一部に「世界史探究」らしい出題が見られたものの、東京大学の入学試験で求められている能力は、本質的に何ら変わっていない。
- ②第1問の傾向 ~2問に分けて出題する形式が定着か~
- 第1問では、2023年度まで15~22行の大論述が1問出題されてきた。そのうち、2019年度に22行(660字)の出題がなされた以外は、2014~2023年度まで20行(600字)の出題が続いてきた。しかし、2024年度は12行と5行の2問、計17行の出題となり、2025年度は12行と8行の2問、計20行の出題となった。2問に分けて出題する形式が今後も定着するのかは、まだ判断できない。
2020・2024年度の第1問では資料が扱われており、これからも資料を扱った出題がなされる可能性がある。また、2023年度には2つの時期(1815年頃と1914年頃)について、計6枚の地図を考察することが求められた。こうした出題形式にも慣れておきたい。 - ②第2・3問の傾向 ~資料・地図・図版・グラフなどの対策を~
- 第2問は、短い論述が数問出題される。2025年度の問題は、これまでの「世界史B」から「世界史探究」へ移行したことを反映してか、資料・地図・図版などを扱った問題が出題された。今後もこうした出題を想定し、普段から地図・図版・資料に慣れていることが求められる。第3問は、一問一答の平易な短答記述形式である。ただし、第3問でも「世界史B」から「世界史探究」への移行を反映してか、資料・地図・グラフなどを扱った出題がなされた。ただし、解答の難度そのものが上がったわけではない。
2026年度入試予想・対策
- ①安易な予想を求める受験生に合格はない
- 東京大学受験者として当然のことであり、どの範囲が出題されても合格できるように日々学習を重ねることが求められる。よって、以下に第1~3問の対策を記す。
- ②第1問対策 ~知識の体系化・俯瞰する能力を~
- 第1問で求められている知識量は、さほど多いわけではない。具体的には、旧センター試験や、共通テストの過去問で満点近く得点できるだけの実力があれば十分である。2023年度の東京大学が発表した出題意図でも「対象とする地理的範囲はかなり広くなっていますが、指定された語句はどれも高等学校の世界史でなじみのあるものばかりです。」とある。ただし、東京大学発表の出題意図から引用すれば「国・地域別、時代別、テーマ別にただ知識として持つのではなく、より広い空間の長期的な歴史について、人や社会の関係性を考えたり、また比較して考えたりする力」(2022年度)や「教科書のなかでは異なった部分で説明されていることも、自分なりに整理して把握すること」(2021年度)は求められる。つまり、時間軸・空間軸上で歴史上の事象を大きく俯瞰し、具体的な知識を体系化して、分析・再構成する能力を磨くべきということだろう。東京大学の出題意図でも「史実の的確な理解とともに、大きな視野で論理的に思考することを心がけてほしい」(2025年度)とある。普段から、複数の地域・国家の「関係」を考察したり、「比較」を試みたりする学習を積んでほしい。
2020年度は資料、2023年度は地図、2024年度は資料を扱う出題となったが、それぞれ特別な事前の準備が求められているわけではなく、与えられた地図や資料に対して熟慮して読み解きつつ、解答を作成する姿勢が問われている。過去問対策は必須だが、過去問しかやらなかったり、過去問の解答例を数十年分自らの考察もなく丸暗記したりするような姿勢では合格できない。 - ●第2・3問対策 ~緻密さとスピードの両立を~
- 第2問では、具体的な知識をしっかり習得していることを前提として、題意に沿って正確に史実を説明することが求められている。出題内容から判断すると難度が高いわけではないのだが、限られた試験時間のなかで手際よく高得点の答案を作成することは、そこまで簡単ではない。また、小さな減点が積み重なって第1問以上に得点差が開く恐れがあるのが第2問である。短い論述(第2問対策)の鍛錬は、第1問で高得点を取るうえでの土台となる実力を育むことにもつながるので、軽視してはいけない。
第3問で合格者が決まるわけではないが、不合格者はほぼ決まる。内容は1~2問を除いて平易であり、全問正解を狙いたい。ただし、2024年度に『オリエンタリズム』の著者・サイードが出題されたように、全範囲の学習が求められる(だからこそ、予想などに頼ってはいけない)。「世界史探究」への移行に伴って資料・図版・地図などが多用されたとしても、時間がかかるだけで難度自体はそれほど上がらないだろう。共通テストで満点近く取る実力があれば、第3問の対策は不要である。
地理
最近の出題傾向
- ①出題形式
- 大問数は例年3題で、選択式・記述式・論述式からなり、論述式が中心である。選択式・記述式の客観式問題は、基本的な知識や思考力を問うものが多く、比較的易しい。解答数については15前後あり、配点でも60点中10~15点前後を占め、後に続く論述式の問題とつながっている場合もあるため、取りこぼしには注意が必要である。論述式の解答分量は、全体で900~1,200字程度で、30~90字の論述問題が15問程度出題される。図や表など資料を用いた問題が頻出だが、受験生が初めて見るものがほとんどで、判読には相応の思考力が求められる。また、問われている内容に対して与えられた解答字数は少なく、問われていることに簡潔に答える力が求められる問題が多い。問われる内容が多岐にわたり、分量も多いため、限られた時間のなかで的確に処理する力が必要である。
- ②出題分野
- 大問の構成は、年度によって若干異なるが、高校の地理で学習する内容がほぼ網羅されており、以下のとおりである。第1問:自然と人間生活に関する問題、第2問:世界の様々な国について資料を用いて資源・産業・環境問題などを問う問題、第3問:主に日本の変化や地域性などに関する問題が多く、いずれも様々な資料を用いて、その読解力も含めた総合的な思考力を問う。大問は、A・Bに分割されることが多く、全体で5~6のテーマから出題されている。
2026年度入試予想・対策
- ①与えられた資料を読解し、自分の知識と重ね合わせる思考力を身につける
- 第1問で主に出題される自然と人間生活に関する問題では、2025年度第1問の自然環境への人間活動の影響の設問Aにおいて、「北半球における近年の地上気温の変化」を示した分布図を用いた問題が出題されたように、受験生が初めて見る資料を用いたものが多く、戸惑うかもしれない。しかし、学習してきた知識から判読できるものがほとんどである。地図帳に掲載されている地形や気候・植生・土壌などの分布図と問題の図を重ね合わせたり、産業や人口などで学習した知識をあてはめたりすることで解答の道筋は見えてくる。第2・3問も同様であるが、資料と自分の知識や学習してきたことを重ね合わせる思考力を持ち合わせておきたい。
- ②産業の特徴や、国・地域はタイプ分けして整理する
- 第2問では、2025年度は経済・余暇活動が問われ、設問Aでは衣類の企画・生産・消費が、設問Bでは余暇活動が問われた。産業に関する問題が出題されることもあり、産業の特徴や、その産業の立地の変化、産業に関連する課題などを整理しておきたい。
国別や地域別の統計もしばしば出題されるが、必ずしも個々の国の細かい知識が求められているわけではない。2024年度第2問では、世界の地勢と人口の変化に関する問題が出題され、設問Bでは人口1億人以上の14ヵ国(2020年時点)の人口変化率を示した表とともに、人口動態に関する国の特徴を比較する問題が問われたが、いずれも主要国に関する基本的な事項が理解できていれば解答できる問題であった。図表からどのような特徴を持つ国・地域かを判定し、グループ化された国や地域ならば、それらの共通点を抽出する能力が必要である。出題される国は、ある程度決まっており、そのタイプの国・地域の特徴や抱えている問題点を指摘できるようにしておきたい。 - ③日本についての変遷や地域性を系統地理的な知識と結びつける
- 第3問で主に出題される日本に関する問題では、その変化や地域性を理解するとともに、系統地理的な知識と結びつけられるようにしておきたい。2025年度は、首都圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)の人口集中地区(DID)の変化に関する問題が出題された。2023年度第3問では居住と自然環境に関する問題が出題され、設問Aで自然災害(土砂崩れ)が発生した地域の地形図を用いて災害や対策が、設問Bで日本の居住(住宅総数の変化など)について問われた。日本の変化については、第2次世界大戦以降、1960年代の高度経済成長期や1970年代の石油危機、1985年の円高、1990年代の東西冷戦の終結やバブル崩壊、2000年代の新興国の台頭とそれに伴う世界の多極化など、大きな変化が起こった時期と国内の各種産業が受けた影響などを押さえておこう。地域性については、大都市圏と地方圏、大都市圏における都心と郊外、地方圏でも中心的な役割を果たしている地域と過疎化が進む周辺地域など、人口動態や産業の現状などで地域ごとの特徴を踏まえるだけでなく、統計データとしてどのような違いが現れるのかを確認しておこう。
- ④問題に即した速く、的確な表現力
- 出題傾向のところでも述べたように、東京大学の論述問題は問題数も多く、問われる内容に対して字数が少ないものが多い。各問の解答として書くべき内容はオーソドックスなものが中心であるが、時間内にまとめるスピードと、指定字数内で的確に要点をまとめる文章力が求められる。見慣れない資料の判読などから答案に必要なところを読み取り、指定された語句を用いてまとめるのは、相応の実力が必要である。自分の知っている知識を並べるだけでなく、問われていることに合わせて知識を整理して、まとめなければならない。東京大学の過去問演習を繰り返すことや、「東大入試オープン」の過去問を通して論理的な思考力や読解力、表現力を身につけてほしい。
特派員の声 ~合格の秘訣!!~
文科一類 1年 くま特派員
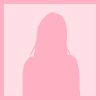
- 過去問を大切に
- 基礎力・応用力がついたら早めに過去問演習をスタートしたことで、ゴールを意識した勉強をすることができました。そのため、最終的にどのような力・知識を得なければならないのかを理解し、勉強を効率化することができました。また、高3になってからは、過去問を何回も解くことを通じて足りない知識やなかった考え方を得ることができました。
理科三類 1年 ぷらする特派員
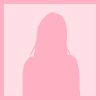
- 懸けられるものをすべて懸けること
- 人間の持てる欲求のすべてを、「合格」にかけることで、パフォーマンスを最大化していました。そうするとモチベーションが切れるということがないので、長期にわたる苦しい受験勉強を継続することができると思います。「合格」という目標の達成を第一の目標とするならば、この手段は有用だと思います。
河合塾の難関大学受験対策
東京大学をめざすあなたに向けて、受験対策のポイント・イベント情報・合格した先輩たちの声などをご紹介します。