東京科学大学 学習アドバイス
河合塾講師からの学習アドバイス
教科別の学習対策について、河合塾講師がアドバイスします。
アドバイスは、理工学系の募集入試によるものです。
※出題範囲は募集要項、大学ホームページ等で必ずご確認ください。
英語
最近の出題傾向
- ①記述式が中心だが客観式も定着した
- 大学統合後の初めての入試であったが、「東京工業大学の出題形式」を踏襲している。大問2題という構成で、記述式の設問として、1~2行程度の下線部和訳・英訳ならびに内容説明問題が出題されている。2010年度から英文の総語数が大幅に増加し、2019年度から7年連続して3,000語を超えており、試験時間内で処理するにはかなりの速読力が要求される。超長文での出題が定着し、それに伴い、内容一致や空欄補充など、客観式の設問の比重も高くなっており、150点満点のうち3分の1程度を占めると思われる。
- ②内容説明問題は得点差が開きやすい
- 内容説明問題は、2025年度も大問ごとに1問出題されている。文脈を踏まえたうえで本文中の具体例を用いて解答する必要があり、的確な文脈把握と日本語の表現力が要求されており、制限字数(大問Ⅰは「85字以内」、大問Ⅱは「70字以内」)でまとめるのに苦労すると思われる。
2026年度入試予想・対策
- ①幅広いジャンルの英文を数多く読みこなす
- 出題される英文は、科学系の論説文が中心となるが、エッセイやニュース記事が出題されることもあるので、日頃から幅広いジャンルの英文を数多く読みこなしておく必要がある。ただし、英文自体の難度はそれほど高くないので、標準レベルの読み物で十分に対応できるだろう。
- ②文脈を把握したうえでの和訳・英訳を心がける
- 和訳では、特に難解な構文や語彙が試されるというわけではなく、見た目は平易な問題に思われるものが多い。しかし、実際に訳語を確定していく段階になると、文脈を正確に把握していることが前提になるので、下線部だけに目を奪われることなく、文章全体の流れをきちんと追う必要がある。英訳も同様で、特に東京科学大学の場合は、英文中の一部が和文英訳として出題されるので、文脈に即した構文や語彙を正確に使いこなせるかどうかがポイントとなる。基本例文の暗記に努め、ケアレスミスのない英文を書く練習を十分に積んでおくことが大切である。
- ③語彙力の拡充を図る
- 和訳や英訳で語彙力が試されるのはいうまでもないが、内容一致や空欄補充など客観式の設問対策としても、語彙力の拡充は不可欠である。代表的な訳語を覚えるだけでなく、文脈に照らしてその語が持つ意味合いを把握することが大切で、できれば英英辞書を活用して、その単語の持つニュアンスにまで踏み込んだ理解に努めてもらいたい。
- ④まずは実際に答案を書いてみること
- 和訳においてもいえることであるが、とりわけ英訳では、まずは自分で答案を実際に書いてみないことには始まらない。頭のなかで答案を思い描くのと、実際に答案にまとめる作業は別問題である。さらに内容説明では、出題者の意図にかなった答案にまとめる必要があるので、過去問をできるだけ数多くこなして、出題の狙いや設問のレベルに精通しておくことが大切である。出題者の要求を過不足なく満たす答案をつくるには、「どの部分」を「どのように」まとめればよいか、十分に注意する必要がある。
数学
最近の出題傾向
2012年度入試から試験時間が180分になり、2013年度入試からは大問5題というスタイルが定着している。分題化されていない大問は、2013・2017年度に2題ずつ、2019・2022・2024年度に1題ずつ、2023年度に3題あった。
分題化されていない問題は、「自力で方針を立て、最後まで解き切る力」を測れるため、数学を重視している東京科学大学としては出題したいはずである。しかし、分題化されていないということは、方針が立たないと部分点がつかないことを意味し、一部の生徒しか得点できない恐れもある(例えば、2019年度入試の第2問では、部分点を得ている答案がほとんどなかった)。数学の平均点が下がっては、入試科目に占める数学のウエイトが低くなってしまう。それを防ぐには、分題化する必要が出てくる。東京科学大学は、このジレンマを解決するために、毎年試行錯誤しているものと想像される。
2026年度入試予想・対策
- ①解くべき問題を解く
- 難しい問題ばかり出されるとの印象を受けるだろうが、確実に得点すべき問題も一定数出されている。たとえ最後まで解き切るのが難しくても、部分点を取るべき問題はある。まずは、このような問題をしっかり攻略することが重要である。典型問題が少し捻られても、本質が大きく変わることはない。日々の学習において、表面的な理解で満足するのではなく、問題の本質を捉えることが、これらの問題を攻略するための鍵となる。実は、一見地味なこれらの問題を確実に押さえることが、合格への近道であることを念頭に置いておこう。
- ②強固な処理力と推論
- 相当な処理力を求める問題も頻出である。ゴールまでの道のりが長いと、途中で「計算や推論に誤りがあるのではないか?」と心細くなるものである。これを克服するためにも、日頃から「自分の書く内容には責任を持つ」ことを意識して答案をつくることを心がけたい。易しい問題であっても、「なぜこの変形をするのか?」「与えられた条件を同値に処理できているのか?」などを意識し、自分の力で解き切ったと実感できる解答を書くことが重要である。
- ③初見の問題にひるまず!
- 素朴な題材を基にしてつくられている問題も散見される。例えば、2017年度には、折り紙を題材とする問題が出され、A4の紙が配られた。斬新ではあるが、その場で対処することで十分に得点できる問題である。しかし、再現答案を見ると、合格者であっても、ここで部分点を確保しているものは少数であった。初めて見る問題であっても、恐れることなくその場で対処するだけの柔軟性と瞬発力、そして勇気を身につけてほしい。
- ④過去問研究の重要性
- 東京科学大学はしばしば、過去に出題した問題の類題を出す。これは、ひとつには、「ただ過去問を解くのではなく、しっかりと本質を理解してほしい」というメッセージではなかろうか。すべての問題を覚えるのは不可能だが、その問題の本質を捉え、ほかの問題にも応用できるかたちとして取り込むことは可能である。過去問に限らず、日頃の演習でもこのことを意識することが、合格の可能性を高めることになるのはいうまでもない。
物理
最近の出題傾向
- 大問3題形式で出題される。試験時間は120分だが、計算量が多いので、解答時間が十分ということはない。B4の解答用紙の枠内に解答する。途中過程も書かせる論述式となっているが、一部に選択形式や、空所補充の形式も混在する。
- ①第1問「力学」、第2問「電磁気」はほぼ定位置。第3問は「熱」「波」「原子」のいずれかから出題される。
- ②問題文も長く、小問数で7〜10問が出され、近似計算も含め計算量が多いので、完答は容易ではない。
- ③問題図も教科書や市販の問題集に載っている定番のものではないので、初見で問題解決できる対応能力を問われる。
2026年度入試予想・対策
いよいよ統合された東京科学大学としての入試が始まったが、理工学系に関しては従来の東京工業大学の入試を想定しておけばよい。第3問の分野として2019年度以来、2023年度の例外を挟んで、熱の分野からの出題が6年続いている。波動分野からの出題確率が高まっていると見るのが自然であろう。もちろん、どの分野が出題されてもいいように準備を進めておくことは肝要である。分野ごとの準備の重点ポイントを次に挙げる。
①力学分野:2025年度は「粗い回転円錐面上での物体の運動」がテーマであった。2025年度は単体の運動であったが、頻度からいうと束縛系の多体問題、衝突、単振動などは最頻出である。さらに傾向として、遠心力、浮力絡みの問題も多い。力学的エネルギー保存則、運動量保存則などの基本法則を利用する問題には特に慣れておきたい。
②電磁気分野:2025年度は「コンデンサーの極板間での導体円板の運動」がテーマであった。コンデンサーを扱うのは2021年度以来である。電場や電位、静電エネルギーの理解を深めておきたい。磁気分野では、荷電粒子の運動、および電磁誘導を含む回路の問題が頻出である。
③波動分野:この数年出題が見送られているが、伝統的に工夫された創作的な問題が出題される。特に「波の干渉」が中心となる。波の式、位相概念には慣れておこう。
④気体・熱分野:2025年度は「ジュール・トムソンの実験」がテーマであった。2025年度もそうであったが、断熱変化のポアソンの法則は要暗記事項として扱われる。高校の化学で学ぶことになったエンタルピーが扱われ、新傾向となりそうである。この分野の出題テーマとしては、熱力学第1法則を通して気体の状態変化を考察させる問題が中心。他分野との融合問題として出題されることもある。
⑤原子分野:2023年度に一度出題があるが、可能性は低い。最低限、原子分野の典型的な問題は目を通しておきたい。
各分野とも、公式を丸暗記することで対処できるほど単純な問題ではない。元になる物理法則に立ち返って現象を説明する論理構成力と、近似計算式を含めた計算能力に磨きをかけておきたい。また、得られた結果をグラフ化したり、条件や視点を変えて考察する習慣を身につけ、理解を深化させておくことも大事である。論述式の答案が要求されるので、論理に飛躍を感じさせない、見やすく簡潔な答案を書く訓練も意識的にやっておきたい。
化学
最近の出題傾向
2025年度は東京科学大学になって初めての入試であったが、前身である東京工業大学の入試を踏襲した出題であったため、以下では、2025年度の東京科学大学(理工学系)の入試と2024年度以前の東京工業大学の入試を区別せずに分析した。
- ①ほとんどがやや易~標準レベルの問題である
- 第Ⅰ~Ⅲ問(配点各50点)の大問3題からなり、それぞれの大問は5つの問題から構成されている。例年、第Ⅰ問(問題1~5)が理論・無機分野、第Ⅱ問(問題6~10)が理論分野、第Ⅲ問(問題11~15)が有機分野である。2025年度も、例年と同様の出題傾向であり、分量・難易度ともにほとんど変化は見られなかった。2013年度までは思考力を要する問題、時間を費やす煩雑な問題が多く出題されていたが、近年はほとんどがやや易~標準レベルの問題である。
- ②理論分野のウエイトが高く、特徴的な正誤問題が出題される
- 多くの設問は、選択肢または計算結果の数字を1つの枠に1つ記入する特徴的な解答形式である。例年、出題分野のウエイトは理論>有機>無機の順である。東京科学大学(理工学系)の化学の特徴ともいえる、正解が1つまたは2つの正誤問題が7~8問出題されており、正確な知識と理解の質が要求される。また、文字式や構造式を記述する設問もそれぞれ1問ずつ出題されるため、対策を講じておく必要がある。2023~2025年度は出題されていないが、2019~2022年度は、解答の有効数字の桁数の指定がなく、問題文で与えられた数値から有効数字の桁数を判断して解答する問題も出題されている(2019年度は2問、その他の年度は1問)ので、留意しておきたい。
2026年度入試予想・対策
- ①時間配分に注意し、わかる問題を確実に得点しよう
- 試験時間120分で15問とすると、1問あたりの解答時間は8分なので、時間配分に注意する必要がある。1つの設問に時間をかけすぎず、難しい設問や時間を要する設問は後回しにしよう。設問の難易を迅速に見極め、解きやすい問題から確実に得点を積み重ねていくことが重要である。答えのみを記す出題形式なので、計算などでのケアレスミスは禁物である。また、解答形式が独特なので、事前に確認しておく必要がある(模試でも単純な計算ミスや解答形式の指示違反が非常に多い)。
- ②過去問演習を積み重ねよう
- 2026年度も2025年度と同様にやや易~標準レベルの問題が多く出題されるものと予想される。したがって、化学の全範囲にわたって、やや易~標準レベルの問題を迅速かつ確実に解けるようにすることが最優先である。重要事項の確認と問題演習を反復することで、知識を定着させるとともに、法則や公式を適切に運用する力を養い、典型問題の解法をしっかりと身につけていこう。東京科学大学(理工学系)の問題には、一見難しそうだが「あることに気づけば実は簡単」といった問題も少なくない。また、類似したパターンの問題が繰り返し出題されることもある。したがって、対策のための素材としては、過去問が最も適している。標準レベルの問題の演習を一通り終えた後は、過去問の演習を通じて、解答へ至るための着眼点・糸口を発見するコツをつかみ、解法のパターンに習熟するとともに、化学の原理・法則に関する理解を深めていこう。さらに、時間配分や解答形式に慣れておくことも重要である。
以下は分野別の頻出テーマである。学習する際の参考にしてほしい。
理論分野:結晶格子、化学反応とエネルギー、電池と電気分解、反応速度と化学平衡(電離平衡を含む)が頻出である。
無機分野:金属イオンの性質と反応、気体の製法と性質、化学工業に関する問題が頻出である。教科書の記載内容から出題されるので、教科書を繰り返し読み、知識の整理・拡充に努めたい。
有機分野:脂肪族および芳香族化合物の性質、反応、製法と関連づけて、分子式や構造式を決めたり、異性体を数えたりする問題が多い。また、天然有機化合物と合成高分子化合物も出題頻度が高いので、準備をおこたらないようにしよう。
特派員の声 ~合格の秘訣!!~
工学院 2年 ニュータスク特派員
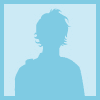
- 理系なら数学を
- 合格への秘訣は、理系ならやはり数学を極めるべきだと思います。理科や英語も試験科目ではありますが、それらは受験者平均より若干高めに取ることが出来れば御の字だと思います。受験における数学の力は基礎を何回も復習し、十分な基礎力つけて発展問題に取り組むことで伸びます。不安定な基礎力のまま発展問題を解いたところで何も身につきません。
生命理工学院 3年 みかん特派員
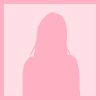
- あきらめない
- 理系にも関わらず数学がとても苦手で模試の成績もあまり良くなかったが、最後まであきらめずに勉強し続けたことが合格の秘訣だと思う。自分の成績で悩んでいる時間があるなら、前を向いてとりあえず勉強するべきであると思う。



