一橋大学 学習アドバイス
河合塾講師からの学習アドバイス
教科別の学習対策について、河合塾講師がアドバイスします。
※出題範囲は募集要項、大学ホームページ等で必ずご確認ください。
英語
最近の出題傾向
- ①全体の構成
- 2025年度は、試験時間が120分で、読解総合2題と自由英作文1題という3題構成。2025年度からリスニング試験が廃止されたが、それに伴う新たな大問の出題はなかった。なお、文法問題は、2020年度以降独立した大問としては出題されていない。
- ②読解総合
- 2020年度までは600~800words前後のものが2題、2021~2023年度は1,500words前後の超長文1題だったが、2024・2025年度は2題の出題(それぞれ700~800words程度)に戻っている。2025年度は2024年度に続いて、大問Ⅰが記述式問題(和訳問題と内容説明問題)のみ、大問Ⅱが記号選択式問題(空欄補充問題と語句整序問題など)のみという形で出題された。このように大問の構成や小問の比率の変化があっても、出題される小問のレベルでは大きな変化はなく、記述式および記号選択式の様々な形式が出題されている。
- ③自由英作文
- 与えられた3つのトピックのなかから1つを選んで、100~140語の英語で述べる自由英作文問題が出題されている。近年は出題形式が毎年のように変わり、2022・2023年度は画像を描写する問題、2024年度は英語の疑問文に対して与えられた選択肢から解答を選んで答える、一橋大学ではこれまで出題されたことがない珍しい形式の問題、2025年度は与えられた状況でその当事者に宛ててメッセージを書く問題が出題された。これは2017年度に出題されていた手紙を書く問題に近い。
2026年度入試予想・対策
- ①「出題傾向」は変わり得ることを前提に
- 2025年度からリスニング試験が廃止されたが、それに伴う新たな大問の出題はなかったため、2025年度は、英文と設問の分量が試験時間に対して例年より少なかった。2026年度は、これを受けて受験生の能力を的確に判定できるようマイナーチェンジが行われることもあり得る。長文が超長文化する、文法問題の独立した大問が復活する、といったことも想定しておこう。英作文の出題形式についても、毎年のように変化している。
しかし、一橋大学の出題傾向は安定しないのは確かだが、変化しているのはもっぱら大問の構成であり、読解問題で出題された小問はこれまで出題されたことのある形式ばかりである。「語彙や文法の正しい知識に基づいて英文を読み、内容把握に基づいて日本語で的確に解答をまとめる力」が問われることは一貫している。2026年度入試に向けても、表面的な変化に惑わされず、土台となる英語力を高めることに注力してほしい。 - ②日本語で記述する問題を練習しよう
- 他大学に比べて配点に対して設問が少ない一橋大学では、1問あたりの配点が大きいと想定される。したがって、記述式のそれぞれの小問の採点では、複数のポイントに部分点が設定されていると考えられるため、それぞれの部分点をいかに確保していくかが合否に大きく影響を与えることになる。
対策として、一橋大学の英語の一番の特徴といってよい内容説明問題については、設問が求める内容を正しく把握したうえで、本文中に複数存在し得る該当箇所を把握し、場合によってはそれをただ抜き出すだけでなく、制限字数に合わせて自分の言葉でまとめる、といった練習を積んでいこう。そのために、論説タイプの英文を、初めは短めのものから順に長いものへと、論旨の展開を追いながら読む練習に取り組もう。また、「読めること」と「解けること」は必ずしもイコールではない。日本語での記述式の問題に不慣れな人は、添削指導を受けるなどして、字数制限内で過不足なくまとめる日本語の表現力を磨いてほしい。 - ③自由英作文は様々な形式の問題に取り組もう
- 自由英作文の出題内容は近年流動的で、定期的に形式が変わると考えておいた方がよい。2025年度は2017年度と似た問題が出題されたが、2024年度は一橋大学ではこれまで出題されたことがない形式の問題だった。今後も新しい形式の問題が出題される可能性もあるので、一橋大学の過去問だけでなく様々な形式の問題に取り組み、初見の問題にも動じない柔軟な対応力を養っていこう。
数学
最近の出題傾向
- ①文系では最高レベルの難しさ
- 2025年度は、2024年度よりも大幅に難しくなった。易しい問題が1題もなく(例年は方針も立てやすく、処理も軽めの問題が1題か2題ある)、どれもが標準以上の問題である。入試問題としての難問は 1 の整数だけかもしれないが、受験生にとって完答しにくい問題が並んでおり、経済学部の合格者レベルでも高得点を取るのは困難であろう。全体には一橋大学が好む問題(整数、軌跡、絶対値、多変数、確率)が出題されているので、河合塾の講習会で勉強した受験生には既視感のある問題群であっただろうが、どの問題も分量が多く、時間切れになってしまったのではないだろうか。
1 は、例年どおり整数の問題であり、内容も大変面白い。(3)は一般の素因数分解の一意性を利用する問題で難問である。(2)までは解きたい。
2 は、典型的な軌跡の問題であり、2025年度のなかでは最も“普通”の問題である。しかし、解法によっては分数形のパラメーター表示になるので、手慣れていないとその後の処理に手間取るし、何より解き切るのに時間を要する。したがって、出題者が期待したほどには点数が出ていないと思われる。
3 は、絶対値のついた関数の積分の問題であり、見た目は普通である。3通りに場合分けして、正しく積分するところまでは解答したい。しかし、その後の処理が分量の点でも数学的にも難しい。完答するには30分以上必要であろう。
4 は、空間ベクトルの問題である。2つのパラメーターで表された点の軌跡をまず捉えるという一橋大学が好む問題である。慣れていれば難しくないのだが、受験生が苦手なタイプの問題であるので、出来はよくないと思われる。逆に数学が得意な受験生にとっては差をつけることができる問題である。
5 は、例年どおり確率であった。いわゆる確率漸化式の問題であるが、偶数回目と奇数回目とで起こる事象が限られることに気づかないと厳しい。これも差のつく問題である。また入試問題としては(1)だけで十分なレベル・分量だと思うのだが、(2)も出題されており、(2)まで解くとかなりの時間を必要とする。
以上が2025年度の概略である。見た目は普通なのだが、受験生にとっては「やや難」が並ぶ厳しいセットといえよう。各分野を深く理解して納得して解くことが最良の一橋大学対策といえる。
整数、確率は例年レベルの高い問題が出るので、しっかりと対策したい。ほかの分野は、定番の問題を誘導のないかたちで演習したい。また、空間図形は、2025年度はベクトルとして出題されたが、過去の出題頻度は高く、差もつきやすいので対策が必要である。 - ②数学Ⅰ・A、Ⅱ・B、ベクトルから幅広く出題される
- 数学Ⅰ・A、Ⅱ・B、ベクトルから幅広く出題され、複数の分野にまたがることも多い。整数と確率の問題は例年見られる。図形の問題も頻出で、基本的な図形感覚を必要とし、三角比、図形と式、ベクトルと絡めて出題されることが多い。さらにほかの大学と違い、小問のつかない問題の割合が多いので解答の全体像を把握して解かなければならず、相当な実力が必要である。
- ③計算力・数式の運用力も必要
- 微積分、図形と式の問題では、計算量も多くなるので、計算力も鍛えておきたい。また、文字の対称性や循環性などの式の特徴に着目して、式を扱うセンスも必要である。
2026年度入試予想・対策
- ①難易度を測り、易しい問題から解く
- 手強い問題群なので、易しめの問題は確実に解き、難しめの問題はいかに部分点を取るかが重要である。
難易度の順に並んでいるとは限らない5題から、的確に易しいものを選び取るには、普段から解き始める前に難易度を推し量り、解いた後、その判断が正しかったかどうかを振り返ってみる習慣を身につけるとよいだろう。
また、確実に得点するには計算力が必要である。計算力は、スポーツでいえば体力のようなものであり、数学の大切な実力のひとつである。普段の勉強でケアレスミスをしたときは、消しゴムで消さず、赤ペンで直すとよい。それを繰り返すと、自分のミスの傾向が把握できる。その傾向を意識するだけで、ミスを減らせるはずである。 - ②典型的な入試問題をしっかり理解して解く
- 出題分野としては、整数、確率、図形が頻出である。
整数については典型的な手法を教科書の例題や市販の問題集で学んだうえで、過去の一橋大学の入試問題にあたるとよい。
確率は、一般の個数nで出題されることが多いので、状況を把握するためにnが1、2、3といった最初のいくつかのときを考えておくと、意味もつかめるし、最終値のチェックにもなる。また、数列の内容を使う(漸化式やシグマ計算など)こともあるので数列の力も必要である。
図形問題については、問題文を読んで図形を描き、さらに図形の動きを把握しよう。そして、初等的に攻めるのか(つまり、幾可的性質を見抜いて解くのか)、あるいは解析的に攻めるのか(つまり、座標やベクトルを設定して計算するのか)を選択する。普段から、平面・空間を問わず図を描いて図形の直観力を磨いてほしい。問題集には、図形の動きを捉えることが主題となる問題はあまり載っていない。一橋大学の過去問(後期にも図形問題が多い)を解いて、図形問題を克服するとよい。
データの分析も出題の可能性があるので用語の確認をしておこう。定義や基本的な公式の確認には、教科書が役立つ。特に整数、確率、データの分析に苦手意識を持っている人は、(この分野は特に定義がポイントになることが多いので)教科書の内容を確認するとよいだろう。
そのうえで、ハイレベルな入試問題集を1冊仕上げよう。問題集を利用して、よく使われる考え方・手法を身につけよう。演習する際は、解答の流れを理解して、見た目の異なる問題に応用できるような解法のエッセンスを修得してほしい。最後に、一橋大学の過去の入試問題で実力を高めよう。また、後期試験にも良問が多いので、余裕がある人はここ数年の後期試験の過去問の演習もお勧めである。
現代文
最近の出題傾向
- ①問題一は多様なジャンルの評論
- 2025年度の問題一では、近代の日記のなかに、日本人の心性を探るという、評論文が出題された。だが、社会論、学問論などを中心にしつつも、多様なジャンルからの出題を特徴とする一橋大学の傾向を逸脱した新奇なものというわけではない。
また、それほど読みづらい文章ではなかった点も最近の一橋大学の傾向に沿うものだったといえる。エッセイ風の文章が出題されることもあるが、おおむねそれほど長くない評論が出題されるという傾向とも合致する。 - ②字数条件の厳しい設問
- 2025年度の設問は、定番の漢字5問と30・40・50字以内という厳しい字数条件の設問が各1問ずつ出題された。また最後の設問(問い四)は、「文章全体をふまえて」という条件のついた設問が出題された。傍線のある部分だけではなく、文章全体の論旨を反映させる必要がある。それらをどう構成するか、諸君の解答構成力を問う一橋大学らしい出題である。問題一の難易度は、おおむね2024年度と同レベルといえよう。
- ③要約問題は必出
- 問題三の要約問題は、3,000字を超えるやや長い問題文だったが、平易な文章であった。真偽を識別するポジティブなメディアリテラシーと、曖昧な情報を受けとめ、不用意な発信を行わないネガティブなメディアリテラシーとの対比をしっかり押さえれば、きちんとした要約が書けたはずである。問題三も2024年度と同程度の難易度だったといってよい。
2026年度入試予想・対策
- ①厳しい字数制限に対応する表現力・語彙力の養成は必須の課題
- 〈問題一の設問は25~50字程度の字数条件の厳しい設問〉という定番の出題形式は2026年度も変わらないだろう。それに対応するには〈解答の要素を自分の言葉で言い換え、簡潔な解答をつくる力〉を身につけることが第一の課題である。日頃から論述問題を解きながら、あえて自分で字数条件を厳しくしたり、本文表現を自分の言葉で少しでも言い換えたりして、それが的確であるかを、先生や講師に見てもらう、という積極的な問題演習をしてほしい。
- ②視野を広く持ち、的確に複数の解答要素を入れよう
- 2025年度の問い四の「文章全体をふまえて」というような設問は、2026年度も出題される可能性が高い。これに対応するためには、本文全体の論理展開を視野に入れて解答を作成する能力を身につける必要がある。得てして傍線部の前後だけで解答を作成してしまう受験生が多いが、設問数が少なく、1問ずつの配点が大きいことが想定されるので、必要な要素の多い解答を作成することが求められる。そのためにも文章全体を見渡し、傍線部と関連する内容を解答に書くことを意識しよう。
- ③要約問題の対策
- 問題三が要約問題というパターンも変わらないだろう。要約の練習は、まずは評論の要約、次にエッセイの要約を行い〈要約の基本〉を身につけたい。3,000字程度の教科書や問題集の文章を使い、要約の練習を行うとよい。
ただし、単に論点を列挙するだけの箇条書きのような解答では不十分である。先に書いた〈要約の基本〉を以下に示すので、これらを意識して練習していこう。- (1)文章の主旨を確実に押さえ、何を中心に述べているかを意識すること。
- (2)文章の構成・論理を大まかにつかみ、その文章構成に即して重要な内容をピックアップする(ただし文章に出てくる要素の順番を組み替えた方がよい場合もあるので、柔軟に対応する)こと。
- (3)整理した要点を、意味のよく通る、しかも簡潔な文言で言い換え、まとめること。
- (4)論理を明確にするために、適宜、接続語や指示語などを用いて文同士のつながりをつくること。
- (5)本文で繰り返されている内容は簡潔にまとめ、内容の重複がないようにすること。
古文・漢文
最近の出題傾向
- ①近代文語文の出題は必須
- 国語・問題二は、近代文語文(明治期の漢文訓読体の文)の出題が極めて優勢である。ここ10年ほどの出題を見てみると、2016年度には現古融合文(竹西寛子『続・往還の記』)、2022年度には近世の文章(三熊花顛『続近世畸人伝』)が出題されたが、この両年度以外の出題はいずれも近代文語文である。大学側から毎年発表される「出題の意図等」では、問題二について「いわゆる近代文語文は、近代の日本社会に深く関係しており、当時の知識人が新しい課題にどのように取り組んだかを知る上で重要である」と記されていることからも、近代文語文の出題を重視する傾向が見て取れ、2026年度以降も近代文語文の出題が続くと思われる。
- ②近代文語文問題の本文と設問の概要
- 本文のジャンルは様々であり、文学や芸術についての評論も出題されたが、哲学や思想、政治や社会、教育などについての評論の出題が多い。
設問数は3問である。冒頭の設問は語句の意味(3問程度の枝問形式)あるいは現代語訳の問題(3問程度の枝問形式で短めの現代語訳を問う場合もある)、ほかの2問は内容説明、理由説明である。説明問題には30~60字程度の字数制限が設けられるとともに、「この段落の内容をふまえて」「文章全体をふまえて」などの条件が付されることが少なくなく、論の趣旨を把握する力、それを表現する力が問われている。
2026年度入試予想・対策
- ①どんな文章が出題されても対応できるように準備する
- 近代文語文の出題率がかなり高いことは確かであるが、近世の文章の出題もあり得るし、現古融合文が出題される可能性もまったく消えたわけではない。
前記の文章のうち、受験生にとって最も取り組みにくく、学習を敬遠しがちであるのは、恐らく近代文語文であろう。しかし、出題頻度の最も高いのが近代文語文であるから、近代文語文を正確に読み解く力を確実に養うことが肝要である。加えて、近世の文章、現古融合文にも対処できるように、準備しておきたい。 - ②古典(古文・漢文)の総合的な学力を養成する
- 一橋大学の文語文の問題に取り上げられる作品は、一般的な入試問題では扱われることの少ない出典が目立つので、過去問の十分な演習が大切である。過去問を演習することで様々な文語文の作品に触れ、内容を正しく読み取り、趣旨を確実に把握する訓練を積んでおきたい。
そのためには、通常の古文・漢文の学習を通じて古文と漢文の重要語(特に漢語)、文語文法、基本句形や慣用句をしっかりと習得しておくことが前提となる。直接的には語の意味の問題や現代語訳の問題に対する備えであるが、説明問題への対応は、語意や文法に忠実な読解と内容把握によるほかないからである。問題二は、近世の文章、近代文語文、あるいは現古融合文、いずれの出題もあり得るのだから、古典、ひいては国語の総合力が問われると考えればよい。 - ③答案の表現力を磨く
- 最後に付言しておきたい。答案はすべて現代語で作成するのであるから、様々な文体の文語文を読みこなす読解力に加えて、制限字数内で要求されている内容を要領よくまとめる現代語の表現力も磨いておこう。読み取ったことを上手く表現できて、初めて高得点につながるのである。
日本史
最近の出題傾向
- ①出題形式
- 大問3題(各400字)、大問のなかにいくつかの小問を設定(一部は単答問題)、という形式で、「すべてで400字以内」という設定に合わせて各小問の字数配分を考える必要がある。史料や表・グラフを題材とした出題が目立つ。
- ②Ⅰ:近世からの出題と古代・中世・近世テーマ史が中心
- 2025年度Ⅰは「古代・中世の災害と地域の政治経済・生活」という、今までにない古代・中世のみの出題であった。基本的には近世からの出題が多く、前近代テーマ史も見られる。近世中心に、古代・中世も含めた学習が求められる。
- ③Ⅱ・Ⅲ:全体の3分の2が近現代、歴史総合にも注目
- 2025年度Ⅲ「韓国併合と第一次世界大戦後の委任統治《史料》」は歴史総合の出題で、世界史との同一問題であった。全体の3分の2を占める近現代史の習得が重要で、歴史総合の分野に視野を広げながらの学習が求められる。
2026年度入試予想・対策
- ①繰り返し出題されているテーマに注目し、過去問の研究を
-
Ⅰにおける頻出テーマは、以下のとおり。
- (1)近世の農村(支配と自治、身分、一揆、生産)
- (2)近世の商品経済(流通や貨幣経済、都市の構造)
- (3)江戸期の政治(幕藩体制、幕政改革と藩政改革)
- (4)律令と武家法(律令制度、式目、江戸幕府法令)
- (5)前近代の文化(宗教・学問・思想・文学と背景)
Ⅱ・Ⅲにおける、明治・大正期のテーマは以下のとおり。
- (1)明治期の産業革命(繊維業、寄生地主制と労働)
- (2)大正期以降の経済(大戦景気、井上・高橋財政)
- (3)近代外交(条約改正、第一次大戦後の国際秩序)
- (4)明治憲法体制(天皇大権、議会制度、軍制)
- (5)社会運動(女性解放・労働・農民運動、社会主義)
- (6)近代文化(学問・思想・教育・生活と社会状況)
Ⅱ・Ⅲにおける、昭和・戦後期のテーマは以下のとおり。
- (1)15年戦争(ファシズム、総動員体制・翼賛体制)
- (2)占領政策(民主化・非軍事化、戦争責任、憲法)
- (3)冷戦下の政治・外交(55年体制、安保体制)
- (4)戦後の経済(経済民主化、戦後復興、高度成長)
これらのテーマを念頭に置きつつ、教科書・用語集を調べながら過去問を解き、問題ごとに重要事項をノートにまとめるといった学習を実践しながら過去問研究を進めよう。
- ②Ⅰ:社会経済史を軸に、政治や文化との関連を把握
- 近年のⅠにおける近世の出題には、2024年度「江戸時代の町と享保期の救民政策」、2023年度「経世論と江戸時代の政治・社会《史料》」がある。社会・経済を軸とする頻出テーマに重点を置きつつ、関連する政治・文化の動向も把握しよう。また、前近代テーマ史では、2021年度「前近代の土地制度と税制」、2019年度「前近代の産業の歴史」がある。政治制度を中心とする法制史にも注目しよう。
- ③Ⅱ・Ⅲ:政治・社会を軸とする総合的な問題にも注目
- 近年のⅡ・Ⅲにおける政治・外交の出題には、2025年度Ⅱ「近代の日本とロシアとの関係《史料》」、2020年度Ⅲ「明治憲法下での議会制度」があり、社会・経済では、2024年度Ⅲ「戦後の物価賃金上昇率の推移《グラフ》」、2021年度Ⅱ「近現代における東京の人口《表》」がある。政治・外交・経済の頻出テーマを習得する学習が有効である。また、近現代の政治・社会状況を軸とする出題には、2024年度Ⅱ「近代の弾圧法令《史料》」、2023年度Ⅱ「政府とマスメディアとの関係」がある。政治と社会状況の関係を軸に、外交・経済・文化も幅広く問う出題が増えている。
- ④歴史総合:基本知識を習得し、日本史との関連を意識
- 新課程への移行にあたり、一橋大学では歴史総合を重視する姿勢が見られた。まずは、歴史総合(世界史分野)に関して共通テストで問われるレベルの基本的知識を習得することを目標にしよう。また、日本近現代史を学習するとき、歴史総合(世界史分野)と関連する部分を見つけながら進めていくことが、有効である。
世界史
最近の出題傾向
- ①出題形式
- 大問3題で字数は各400字の論述問題であり、合計400字、総文字数1,200字は例年と変わらない。2024年度までは「世界史B」からの出題であったが、2025年度入試においては新課程に合わせて「歴史総合、世界史探究」からの出題範囲となった。Ⅰ・Ⅱは従来の出題傾向を踏襲するものであったが、Ⅲが歴史総合からの出題となり、これは「歴史総合、日本史探究」との共通問題となったほか、問1の単語記述問題と問2の論述問題を合わせて400字という構成であった。一方、Ⅲで受験生に求められている知識は従来の傾向と変わりはなかった。
- ②Ⅰ・Ⅱ:中世~現代の西洋史が中心
- 2025年度は、Ⅰ「ウェストファリア条約の内容と国際関係に及ぼした意義」、Ⅱ「市民結社が発展した背景と政治文化史的な意義と限界」が出題された。2024年度はⅠで史料の出題が見られたが、2025年度入試においてはⅠ・Ⅱでの史料の出題は見られなかった。ただし、後述するⅢで史料の出題が見られたことから、一橋大学の入試問題においては、最低でも1題は史料の読み取りを前提とした出題が見られると覚悟した方がよいだろう。また、出題される史料の特徴としては、一橋大学関係者の著書からの出題が見られ、2024年度入試においてはかつて同大学の第5代学長を務めた増田四郎の著書からの出題であった。Ⅰは一橋大学の受験生にとっては書きやすいテーマであった。一方、Ⅱは受験生にとって盲点となる「市民結社」に焦点をあてたうえに、「政治文化史的な意義と限界」が問われており、「政治文化史」を「政治と文化」と誤読した受験生も多かったのではないかと思われる。主要な教科書には「市民結社」についての記述があるものの、その説明には歴史用語としての印象が薄いため、読み飛ばしていた受験生が多かったのではないだろうか。日頃から教科書の記述を丁寧に読み込む学習習慣を定着させよう。なお、本問の「政治文化史的な意義」としては、市民結社が身分制を否定する啓蒙思想と結びついたのに対し、その一方で市民結社に集う人々がたしなむ植民地物産は奴隷などによって生産されていることを「限界」として指摘するユニークな出題であった。Ⅰ・Ⅱは、過去10年間で経済・社会史的な視点からの出題が増加しているので、今後もこうした傾向が続くと思われる。
- ③Ⅲ:「歴史総合」分野からの出題 ※2024年度以前は近世以降の東洋史(特に中国・朝鮮史)が中心
- 2025年度は「韓国併合と第一次世界大戦後の委任統治」が出題された。出題形式としては、問いが2つに分割されており、問1で歴史用語を書かせる出題、問2で史料の読み取りを前提とした論述問題で、問い2つを合わせて400字という出題であった。こうした出題形式は、2022年度に小問3問・字数配分を任意とする新傾向の出題が見られたが、2023・2024年度入試においてはひとつの問いに400字で解答させる出題であった。また、「歴史総合、日本史探究」との共通問題となったものの、世界史探究の知識と史料の読み取りによって十分に解答を作成できるものであった。2024年度入試以前の傾向としては、中国や朝鮮の近現代史を中心とする出題が目立った。
2026年度入試予想・対策
- ①Ⅰ:注目すべきヨーロッパの中世・近世史!
- 2025年度入試においては「ウェストファリア条約の内容と国際関係に及ぼした意義」、2024年度「中世都市の社会経済史的意義」、2023年度「英仏百年戦争とフランス王国の変化」、2022年度「皇帝フリードリヒ1世の勅法」、2020年度「ルターとドイツ農民戦争」、2019年度「主権合議体としての議会」の出題は、従来のⅠの形式に則っているといえる。ここ数年、時代範囲としては8〜11世紀からの出題がなく、地域もイギリス、フランス、ドイツなどに比重が置かれている点に注目したい。過去に出題されたピレンヌ=テーゼやオットーの戴冠、叙任権闘争の歴史的意義などのテーマを基に、時代範囲や設問条件を変更して出題することも十分あり得るので、過去問対策を十分にこなしたい。中世東欧世界や東方植民、レコンキスタなども確認しておこう。
- ②Ⅱ:特定の時代やテーマに絞るのは厳禁!
- 出題分野について見ていくと、2025年度入試「市民結社が発展した背景と政治文化史的な意義と限界」や2021年度「レンブラント時代とゲーテの時代」、2018年度「歴史学派経済学と近代歴史学の相違」は文化史、2024年度「(黒人側から見た)奴隷解放の問題点」と2023年度「1970年代以降のアフリカの新興国」、2020年度「20世紀の米英覇権の交替」、2019年度「第2次英仏百年戦争」は政治史、2022年度「20世紀アメリカの経済政策」は経済史を中心とした出題で、時代・地域・出題分野もバラバラなうえに難易度にも差がある。また、2023年度は第二次世界大戦後のアフリカ史が地図と一緒に出題される新傾向の出題が見られた。しかし、出題傾向から外れても「設問要求を正しく読み取り、書ける内容をしっかり書く」ことが何よりも重要である。そのため、闇雲に様々な地域を手あたり次第勉強するのではなく、過去問研究に重点を置きつつ出題されてきたテーマへの理解を深めることを優先してほしい。16世紀〜第二次世界大戦後のヨーロッパ史とアメリカ史、ラテンアメリカ史の対策をおこたらないようにしたい。万が一、入試本番で、過去問で触れたことのないテーマや時代が出題された場合も慌てず、まずは設問要求を分析し、書くべき内容を想定した後に教科書の標準的な知識を思い出しながら書けるところまで書くことが重要である。
- ③Ⅲ:歴史総合からの出題!「歴史総合、日本史探究」との共通問題!
- ここ数年は中国と朝鮮半島・韓国に関する近世以降の歴史と日本を絡めた出題が多々見られ、こうした事例は2023年度「中国の半植民地化と孫文=ヨッフェ会談」、2022年度「近世以降の朝鮮史」、2021年度「文化大革命の経緯と〈4つの現代化建設〉の影響」、2020年度「朝鮮王朝の中華意識」、2019年度「中国共産党・国共内戦の歴史」、2018年度「三・一独立運動と五・四運動」に表れている。一方、2024年度は「10~12世紀の東アジア世界の政治的・社会的変動」というテーマが出題され、2017年度の「ザイトンをとりまく国際関係」以来の明清以外からの出題となったうえに、中国中世史は過去30年間で出題実績がなかった。そして、2025年度入試においては、「歴史総合」を意識した出題が見られた。一方で、受験生に求められる能力は従来どおりで変化はなかった。今後は、歴史総合を意識して近現代のアジア史を中心とした学習を進めたい。過去問を解いて出題されたテーマへの理解を深めるだけでなく、近年の国際関係においてグローバルサウスの注目国であるインドの近現代史や、中国との関係が注目される台湾の近現代史からの出題も想定しておくとよいだろう。
特派員の声 ~合格の秘訣!!~
法学部 1年 Carp大好き特派員
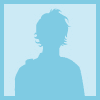
- 一橋世界史記述の書き方
- 世界史の記述は、自分の持つ知識を求められている内容に合うようにアウトプットすることが大事です。この時、問題の聞かれ方にヒントがあります。事柄の「経緯」は最初と最後だけ、過程は最初から最後まで順番に書く必要があるといったように一定の法則があるので、これをヒントにしましょう。また、先生や塾の講師の方に添削をしてもらうことも重要です。これをしてもらうことで自分で気づきにくい改善点が見えてきます。
ソーシャル・データサイエンス学部 1年 もちゃ特派員
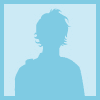
- いつも通りを心がける!
- 私は現役の頃は浪人しても大丈夫だと思い、なるべく気負わずに受験したところ、ほとんど緊張せず全力をほとんど出しきれました!ストレスは受験の敵です。しっかり睡眠をとって健康的に過ごしてメンタルを壊しにくくし、いつも通りに勉強し続けましょう!気合い入れてやりすぎると心身共にストレスがかかり、本番にまで影響します。時には休んでもいいんです。直前期は特に、いつも通り元気でいられることを最優先してください!



