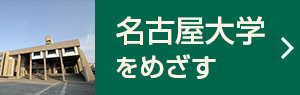名古屋大学 学習アドバイス
河合塾講師からの学習アドバイス
教科別の学習対策について、河合塾講師がアドバイスします。
※出題範囲は募集要項、大学ホームページ等で必ずご確認ください。
英語
最近の出題傾向
- ①構成と問題量
- 試験時間は105分で、2010年度以降、読解総合2題、対話文1題、英作文1題という4題構成が続いているが、2018年度から大問Ⅳの英作文が和文英訳問題から自由英作文に変わった。読解総合と対話文の本文の総語数は2,000語を少し超える程度で、全体として解答するのに無理な問題量ではない。
- ②読解総合問題
- 長文読解問題では、下線部和訳と説明問題に加えて、前置詞、副詞、形容詞などの空所補充問題など、知識を問う問題も出題される。また、段落のトピックセンテンスを選択させるような、段落や文全体の内容や論旨構成を読み取らせようとする問題が増えている。
- ③表現力問題
- 大問Ⅳで出題される自由英作文は、2024年度までのビジュアル資料(表やグラフ、図形など)の情報を読み取って説明するという形式から、意見論述型の問題に変わった。
2026年度入試予想・対策
- ①語彙・文法・熟語の知識の拡充
- 読解総合問題では要求される語彙レベルが高くなっていて、語彙力が得点差に直接反映されるような和訳問題や説明問題が多い。また、客観問題でも単語の知識が解答の決め手になるような問題がある。単語集を利用することに加えて、学習済みの英語長文を何度も読み返し、出てきた語彙が自然と身につくような学習を積み重ねていくとよい。また、読解総合問題や対話文問題で文法・熟語の知識に関わる問題が問われることも多いので、単語のみならず文法・熟語などの知識の拡充にも努めてほしい。
- ②長文読解問題の演習
- 下線部和訳問題では、下線部自体の文構造を正確に把握し、文脈を踏まえて内容を正しく理解することが求められている。文構造の把握に関しては、決して難度が高いわけではないが、単語の意味を表面的につなげただけで何を言おうとしているのかわからないような訳出では得点を得られない。内容の理解に基づいた訳出をするよう心がけたい。内容説明問題では、指示語の内容説明、語句の説明のほかに、理由を説明させる問題などがよく出題される。いずれにせよ、設問の指示文をよく読み、何が解答として求められているのかを考えて答える必要がある。そのうえで、本文のどの部分をまとめたらよいのかを確定することになる。問題によっては該当する部分を抜き出すだけでは答えにならず、広い範囲の内容をまとめたり、複数の情報を織り込んでまとめたりする場合もある。また、段落や文全体の内容、論旨展開を読み取る力を問う問題に対しては、長文を読む際に論旨の展開や文章構成に留意し、特に段落単位で内容を把握することが重要である。
- ③表現力の学習はインプットを中心に
- 過去の出題形式は多岐にわたる。意見論述型の形式や、ビジュアル資料(表やグラフ、図形など)から情報を読み取って説明する形式も出題されてきた。また、年度によっては下線部英訳問題も出題されており、文法的に正しく表現する力も求められる。和文英訳のトレーニングを通して正しく書く力を養うことは、自由英作文にも必要である。まずは和文英訳の問題集を繰り返し解き、英作文の複数の問題形式(和文英訳、意見論述型自由英作文、ビジュアル資料説明型自由英作文)に対応できるようにしていこう。
文系数学
最近の出題傾向
- ①出題分野
- 出題数は3題である。この出題数は、完全に定着している。 3 で選択問題が出題されたこともあるが、2008年度を最後に、その後は選択問題は出題されていない。2025年度の出題分野は、 1 「積分法」、 2 「整数」、 3 「確率」であり、ほぼ近年の傾向に則した問題であった。
- ②論述力を重視した設問が頻出
- 名古屋大学の入試では、問題冊子の最後に「数学公式集」が付載されている。これは名古屋大学独特の形式で、大学側が単に公式や解法の暗記ではなく、論理的思考力や論述力に重点を置いた試験をしたいという姿勢が読み取れる。
2026年度入試予想・対策
- ①入試予想
- 例年、頻出の出題分野として、「確率」「図形と方程式」「微分法」「積分法」が挙げられ、「数列」と他分野の融合問題や、数学Cに移行した「ベクトル」にも注意が必要である。2026年度についても、これらの分野を中心とした本格的な問題の出題が予想される。
各分野について、具体的に検証してみよう。
確率については、思考力、論述力を要する出題が非常に多いので、答案作成力を磨いておく必要がある。近年は、適切に場合を分けて数え上げることにより確率を求める問題が出題されている一方で、過去には確率漸化式も多く出題されており、広い視野で問題設定を把握することが重要である。
図形に関しては、「図形と方程式」からの問題が頻出であり、微分法・積分法との融合にも注意が必要である。ここでは、軌跡・領域を中心に学習しておくとよいだろう。
微分法・積分法については、微分法によりグラフを描き、それを活用する問題や、積分法を用いて、曲線で囲まれた部分の面積を求める問題も見られる。前述のとおり、領域との融合も多く、より正確に図形を把握したうえで迅速な計算を行う力も必要とされる。
ほかにも、多項式に関する問題や空間図形、ベクトルに関する問題も出題されており、幅広い知識を身につけておく必要がある。 - ②対策
- 名古屋大学文系数学は、典型的な出題がある一方で難度の高い問題も含まれており、完答できる問題が多いとはいえない。そこで、まずこれまでに出題された名古屋大学の入試問題を実際に解くことで現在の自らの学力と実際の問題レベルとの距離を把握してほしい。そして、その差を縮めるような学習対策を練り上げるとよいだろう。
まず、各分野の典型的な問題を確実に解けるよう練習してほしい。難しい問題も基礎知識の組み合わせから成り立っている。その基礎知識をより確実にすることで計算力や思考力も向上するだろう。
次に、多分野にまたがる融合問題で練習していこう。名古屋大学の過去問の演習を通して論証力、洞察力を養っていきたい。多くの問題を解き、自分で完成答案をつくることで、答案を作成する力を養うことができる。自分の考えを答案を通して伝えるための表現力も大切である。
理系数学
最近の出題傾向
- ①出題分野
- 出題数は4題である。この出題数は、完全に定着している。過去には 4 で選択問題が出題されることもあったが、2009年度を最後に選択問題は出題されていない。2025年度の出題分野は、 1 「関数の極限、微分法」、 2 「整数」、 3 「積分法」、 4 「確率」であり、ある程度近年の傾向に即していたといえる。
- ②融合問題、応用力
- 名古屋大学の入試では、問題冊子に「数学公式集」が印刷されている。これは名古屋大学独特の方式で、数学的な知識よりも思考力や応用力に重点を置いて受験生の力量を試したいという、大学側の意図の表れと思われる。従来から2つ以上の分野を融合した問題が多く、出題の分野の偏りが少ない。なお、問題による難易差がやや大きい場合もあるので、解きやすい問題の見極めも重要になることがある。
2026年度入試予想・対策
- ①入試予想
- 2026年度も例年と同様に、複数の分野にまたがる問題を含む、全体としては特定分野に偏らない出題が予想される。また、数学Ⅲの「微分法」や「積分法」についても出題される可能性が非常に高い。この分野からの出題内容として、図形量の最大・最小、「数列」との融合問題が頻出である。それ以外に、「数列」と「確率」の融合問題、「複素数平面」や「ベクトル」「図形」と方程式などの図形関連の問題、整数関連の問題も出題の可能性が高い分野として注意が必要である。
- ②対策
- 融合問題が多いとはいえ、まずは単独の分野の解法を身につけることが重要である。基礎力を充実させ、典型的な問題ならば解き方が思い浮かぶようにしておこう。
そのうえで、多面的に問題を考える訓練をしておこう。別解なども積極的に考えるようにすると効果的である。
さらに、正確かつ迅速な計算を行う力も要求される。工夫した計算、見通しを立てた計算を心がけ、問題を解く際は、最後まできちんと計算をやり切るようにしよう。
思考力、応用力については、即効性のある妙案はない。日頃から数学に興味を持って学習していくことが一番であろう。 - ③攻略法
- まず、これまでに出題された名古屋大学の入試問題を実際に解いて、現時点での自らの学力と問題のレベルとの距離を体感してほしい。学力伸長の目標を明確に持って学習を進めるためにも、このステップは大変重要である。その際、できれば問題そのものをいろいろな観点から味わってみるとよいだろう。名古屋大学の入試問題は、数学的な観点から見てよく練られた、いわゆる良問と呼べるものが多い。
次に、名古屋大学の出題傾向を考慮してつくられた適切な問題集を解いてみることを勧める。そのような問題集として、『2026 入試攻略問題集 名古屋大学 数学』(河合出版)が最適である。この問題集の一つひとつの問題にじっくり取り組むことによって、数学の総合的な力、すなわち、正確な計算力、論理的な思考力、問題の本質をつかみ取る力などを養ってほしい。
現代文
最近の出題傾向
- ①評論文からの出題
- 例年、評論文が1題出題される。哲学、文化論、文学・芸術論、現代社会論、歴史論、科学論など、様々なジャンルの評論文から出題されている。2025年度は、人間の感じる「むなしさ」を2種類に分けて考えたうえで、SNS時代の現代における「むなしさ」について論じた文章(きたやまおさむ『「むなしさ」の味わい方』)からの出題であった。難易度は年度ごとに変化する傾向にあり、2023年度はやや難しかったが、2025年度は2024年度と同様、やや易しかった。4問出題された記述問題のうち3問は本文中のどこをまとめて解答を作成すればいいか判断しやすいものであった。残りの1問(問六)は、幅広い範囲を踏まえて解答を作成しなければならないうえに、設問の要求に合うように解答をまとめるのがやや難しかった。内容合致問題では、適否の判断がつきにくい選択肢が1つあった(エ)。例年漢字の読み書きの問題は10問出題されてきたが、2025年度は8問であった。また、2024年度は出題されなかった接続語の空欄補充問題が出題された。
- ②設問の構成は定着している
- 例年、漢字問題(書き取りと読みが10問程度出題される)、30~130字の記述問題が4問、それ以外に、抜き出し問題、空欄補充問題、内容合致問題などが出題される。漢字の読みはカタカナで答えさせるので、注意が必要である。
2026年度入試予想・対策
- ①文章量は3,500~5,000字程度、トータルの記述量は300字台になることが予想される
- 名古屋大学では4,000字台のやや長めの文章から出題されてきたが、2020・2022・2023年度は3,000字台と、これまでよりも短い文章から出題されるようになった。しかし、2024年度は5,000字台と大幅に増大し、2025年度は4,000字台に戻った。
また、2025年度のトータルの記述量は320字であり、ここのところ300字台が続いている。
2026年度は、3,500~5,000字程度の文章から出題され、記述問題は4問、トータルの記述量は300字台になることが予想される。 - ②記述問題の練習をしっかりしておくこと
- 名古屋大学の記述問題では、傍線部の前後を踏まえて解答する問題だけでなく、問題文を幅広く踏まえて解答する問題も出題される。また、問題文中の表現をそのまま使って解答を作成する問題だけではなく、2020年度のように自分なりの表現を工夫しなければならない問題も出題される。これらの問題に対処できるようになるためには、問題集などを使って評論文の記述問題を数多く練習しておくことが必要である。
また、解答時間の割には文章量、記述量が多く、制限時間内に解き切ることが難しい。そこで、過去問などを使って制限時間内に解く実戦的な練習を積んでおくことも必要である。 - ③空欄補充問題、抜き出し問題、内容合致問題、漢字問題なども練習しておくこと
- 名古屋大学では、記述問題、漢字問題以外に、抜き出し問題、空欄補充問題、内容合致問題などが出題される。記述問題だけでなく、これらの問題も練習しておこう。
また、漢字問題(書き取りと読み)は10問程度出題され、得点源になるので、しっかりと練習しておくことが必要である。
古文
最近の出題傾向
- ①2025年度は南北朝時代の歴史物語からの出題
- 2025年度の出典は南北朝時代に成立した歴史物語『増鏡』であった。歴史物語の出題はおよそ30年ぶりである。名古屋大学では、平安・鎌倉時代の作品を中心に、数年に1回ぐらいの頻度で江戸時代の作品も出題される。ジャンルは、一人称で語られる日記・随筆・評論が中心であるが、この10年で、軍記物語・怪異物語・歴史物語と、物語系も3回出題されている。
- ②設問は、現代語訳と説明の問題が中心
- 2025年度の設問は、条件が付されている現代語訳4問(和歌1首を含む)と和歌に絡めた説明問題1問に加え、文法(品詞分解)と2024年度に引き続き文学史も出題された。
2026年度入試予想・対策
- ①出題レベルをつかもう
- 年度により、出題傾向に多少の変化は見られるものの、現代語訳の問題と説明問題を中心に、文法や文学史の問題が出題されている。また、和歌に関する出題がなかったのは、過去10年間で1回だけである。まずは、過去問を2、3年分解いてみて、どんなレベルの文章を、どこまで深く読解すればよいのかをつかみ、自身の弱点をはっきりさせよう。なお、古文の標準的な解答時間は30分程度と考えればよい。
- ②様々なジャンル・時代の作品を読もう
- 江戸時代の作品は、受験生にはなじみのないものであるが、和文体の読みやすい文章なので、文脈を丁寧に追いかければ、読解にそれほど苦労することはない。平安・鎌倉(室町)時代の作品が出題される場合は、過去に他大学の入試で出題された箇所であることも多いので、入試頻出箇所を集めた問題集などで、様々な文章に触れておくとよい。
- ③正確な読解力・適切な表現力を身につけよう
- 毎年必ず問われる現代語訳の問題では、主体や客体の補い・状況の説明的な補い・指示語の内容の具体化などをしなければならない。毎日の学習では、助動詞や助詞の意味用法を丁寧に押さえ、適切な補いをしながら現代語訳する練習を繰り返そう。また、様々な説明問題に対応できるよう、機械的に逐語訳するだけではなく、書かれている内容について深く考えながら読むようにし、人物の心情をつかんだり筆者の主張を捉えたりする丁寧な読解練習を心がけてほしい。解答の記述分量が多いのも、名古屋大学入試の特徴のひとつである。設問の答えは、頭のなかだけで考えるのではなく、必ず書いてそれを推敲するようにしよう。読み取った事柄をわかりやすくまとめて記述する練習は欠かせない。
- ④和歌に強くなろう
- 和歌に絡めた出題が多いのは、名古屋大学入試の大きな特徴である。和歌の読解には、まず、和歌が詠まれた状況を正確に把握しなければならない。そのうえで、修辞などを見つけ、それも踏まえた現代語訳をする。さらには、詠み手の心情などを説明する練習も積んでおきたい。特に和歌の現代語訳は、添削指導を受けながら、よりわかりやすい訳となるよう練習を重ねよう。
漢文
最近の出題傾向
- ①問題文は長文で、ジャンルは多様
- 2016年度以降、毎年220字以上の文章が出題されている。国公立大学でもこれほどの長文をコンスタントに出題する大学は極めて僅かであり、名古屋大学の漢文の特徴といえる。問題文のジャンルは、2016・2017・2019・2021・2022・2024・2025年度は論説文、2018・2023年度は史伝、2020年度は随筆と、論説文が多いものの、多様である。難易度については、史伝や随筆はおおむね標準的である。論説文は難度の高い文章であることが多かったが、2019年度以降は比較的読み取りやすい文章が出題されている。
- ②設問も多様で、150字の要約または説明の問題が必出
- 設問は例年、語句の読み1問、書き下し文1問、現代語訳1~2問、内容、理由や主旨の説明2~3問という構成である。特筆すべきは、2006年度以降、150字以内で本文を要約する問題、または150字以内で内容、理由や主旨を説明する問題が毎年出題されている点である。名古屋大学は、漢文の問題を通して重要語・句形の知識や訓読力・読解力を問うだけでなく、表現力も問おうとしていることをうかがい知ることができる。
2026年度入試予想・対策
- ①様々なジャンルの文章にあたっておくこと
- 問題文は、史伝・文学論・学問論・思想・随筆など多様であり、2026年度入試のジャンルを予想することは難しい。どんな文章が出題されても対応できるよう、過去問や問題集を利用して様々なジャンルの文章を読解する練習をしよう。文章の趣旨と話や論の展開をしっかりと把握することが大切である。
- ②解釈力を身につけること
- 解釈力は、現代語訳の問題はもちろんのこと、内容や理由を説明する問題において完成度の高い解答を作成するためにも必要なものである。解釈する場合には、語意、送り仮名や文脈を踏まえて一語一語適切な現代語に置き換えるとともに、指示語の指す内容や省略された内容を補ってわかりやすく訳すことが大切である。意味内容はわかっているつもりであっても、いざ訳を書いてみるとうまく表現できない場合が多いものである。実際に訳文を書く練習を積み重ねてほしい。
- ③重要語・句形を習得すること
- 語の読み、書き下し文や現代語訳の問題では、重要語や句形の知識が問われる場合が多い。またこれらの知識は、問題文の内容を正確に読み取るためにも不可欠なものである。本文を読解する練習をする際に出合ったものは必ず覚えるように心がけてほしい。
- ④150字以内で要約する練習をすること
- 本文の内容を150字以内で要約する、または説明する問題が必ず出題される。短時間で長文を読んで内容を把握し、150字以内でまとめるのは容易なことではない。日頃から文章の内容を展開と趣旨が明らかになるようにまとめる練習をする必要がある。
物理
最近の出題傾向
- ①出題分野
- 2025年度は、力学から1題(傾斜面上の小球の運動)、電磁気から1題(交流回路と荷電粒子の運動)、熱から1題(2室に分かれた気体の状態変化)の3題の出題となっている。例年、力学・電磁気から1題ずつ、波動または熱から1題の合計3題が出題されている。
- ②解答形式
- 実質的な解答時間は75分(理科2科目で150分)で、基本的に答えのみを書き込む記述式である。また、近年グラフを選択する問題が多く出題されている。答えを導くまでの過程を書く計算欄が設定されることもあるが、2025年度は課されることはなく、近年は減少傾向である。
ほとんどの設問において、「~のうちから必要なものを用いて表せ」という形式で文字指定がなされる。 - ③難易度
- この数年、比較的標準的な出題内容となっている。解答時間に対して設問数もそれほど多くはなく、無理のない出題となっている。合格点までであれば、特別に速い処理速度が要求されるわけではない。一方、2020年度は計算量が非常に多く、合格に必要な得点率は年度によって大きく異なる。
2026年度入試予想・対策
- ①力学と電磁気は高い確率で出題される
- 力学分野と電磁気分野から1題ずつ、熱・波動の分野から1題出題されることが予想される。出題分野が固定されているわけではなく、原子分野から出題される可能性もあるため、学習をおろそかにしてはいけない。原子分野も半分以上は、力学・電磁気・波動の知識や計算技法を利用するため、理解を深めることもできるだろう。
力学は必ず出題されると考えてよい。ほかの分野でも力学的な考え方は基本となるため、単元の偏りなく、基礎事項の理解から問題演習まで、十分に行っておこう。 - ②現象の背景にある物理法則を読み取ろう
- 入試問題は、ある設定・テーマで出題される。肝心なことは、その問題の背景に置かれている物理法則を読み取ることだ。表面的な処理にとどまらず、根底にある物理的な因果関係を正しく理解しておく必要がある。
- ③典型問題から応用問題までの演習量を充実させよう
- 典型問題は入試問題のひな形である。典型問題を一通り演習することで、入試問題に頻出のテーマについて知識と解法を大まかに学ぶことができる。間違えた問題は、解説をよく読んで理解し、類似問題を解き直すようにしよう。実際の入試では典型問題を少し発展させた応用問題が出題されることも多い。したがって、基礎を固めた後は、より複雑な設定や条件の問題にも取り組み、柔軟な発想力と論理的な思考力を養っておくとよい。また、過去問の分析を通じて、出題のパターンや傾向をつかみ、時間配分や解答の優先順位などの戦略面にも意識を向けておくと、本番での対応力が大きく向上するだろう。近年では難易度は安定しているが、ときには難しい問題が出題されるかもしれない。そういうときでも解きやすい問題を確実に解く冷静さも日頃からシミュレーションしておこう。
化学
最近の出題傾向
全分野にわたって幅広く出題されている。出題数は、大問数で、理論、無機融合問題が2題、有機分野の問題が1題である。ただ、有機分野は問1、2に分かれており、実質的には4題の構成である。小問数は、25問前後である。出題形式は、選択式、記述式、計算に加え、30〜50字程度の論述問題や正答数が示されていない正誤判定問題が例年出題されている。また、計算の導出過程を記述させる問題が出題されることもある。出題内容として、思考力を試す意図から知識がなくても問題文の意図を読み取り、誘導に従っていけば解答できる問題が多く見られる。ただ、2025年度の多糖類の非還元末端と分岐数などのように、発展的な知識を必要とする問題も数問出題されている。
2026年度入試予想・対策
- ①理論、無機分野の予想と対策
- 無機物質の細かい知識を要求するような設問はほとんどないが、ある物質を題材にして、理論分野の内容を幅広く問われる。したがって、2026年度は、「ハロゲンF、Cl、Br、I」「両性元素Al、Zn」「遷移元素Fe、Cu」などのいろいろな項目を問える物質を題材にし、2025年度に問われなかった「熱化学」「電池、電気分解」「化学平衡、反応速度」からの出題が予想される。対策としては、無機分野では、教科書レベルの知識と化学反応式をしっかり確認しておくことと、事象の理由を答える論述問題が例年出題されているので、重要な化学用語や考え方などを理解したうえで簡潔に述べられるように練習しておこう。理論分野では、計算量が多く、かなりのスピードが要求されるので、各分野の計算処理方法をまとめておく必要がある。また、計算の導出過程を記述させる問題では、簡潔に計算過程を記述することも求められるので、簡潔に記述できるように練習をしておく必要がある。
- ②有機分野の予想と対策
- 有機分野では、問1で有機化合物の構造決定の問題が、問2で高分子化合物を題材にした問題が出題されている。2026年度では、有機化合物の構造決定の問題では、特に「芳香族化合物」が、高分子化合物では、「合成高分子」を用いた問題の出題が予想される。対策としては、有機化合物の構造決定の問題に数多くあたることと、酸化や脱水などの一般的な反応条件や、工業的製法などに見られる特定の反応による生成物に関する知識を確認しておいてほしい。また、立体異性体については、かなり発展的な項目まで押さえておく必要がある。
- ③全体として
- 試験時間に対して、設問数が多いので、焦る受験生が多い。解答時間の短縮としては、「計算を速くする」とか「問題文を速く読む」などを考えそうだが、これではミスが増える。特に名古屋大学の化学では、問題にヒントや誘導が隠れていることが多いので、問題文はできるだけ時間をかけて読んでほしい。解答時間の短縮として、各項目についての処理方法をできるだけ簡潔にしておくこと、問題文のチェック項目をあらかじめ整理しておくことが重要になる。これらのことを意識して、最後まで頑張ってほしい。成功を期待している。
特派員の声 ~合格の秘訣!!~
農学部 1年 さっちん特派員
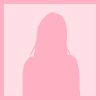
- 復習の徹底!
- 予備校ではその日にやった内容はできるだけその日のうちに復習するようにしました。復習といってもいつまでも時間をかけていてはいられないのでとりあえずノートを見返すとかだけはするようにしました。それだけでも定着度は大きく変わりました。土日に解き直すなどを行いました。
医学部 医学科 1年 サクラティー特派員
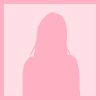
- 過去問分析
- 過去問分析をしっかりして、どの分野が出やすいかなど考えた上で各分野に割り当てる勉強時間を考慮したほうがよい。ただし、過去に出てないからといって対策をおこたってはいけないと思います。
河合塾の難関大学受験対策
名古屋大学をめざすあなたに向けて、受験対策のポイント・イベント情報・合格した先輩たちの声などをご紹介します。