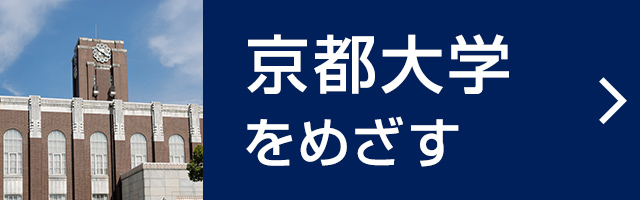京都大学 学習アドバイス
河合塾講師からの学習アドバイス
教科別の学習対策について、河合塾講師がアドバイスします。
※出題範囲は募集要項、大学ホームページ等で必ずご確認ください。
英語
最近の出題傾向
毎年出題形式に変更が見られるのが近年の特色であり、2025年度も読解問題と自由英作文で出題形式に変更があった。具体的には、読解系の問題は、2024年度はⅠの読解問題(creativityについて)で下線部和訳問題に加えて、空欄補充問題が出題された。しかし、2025年度は空欄補充問題は出題されず、Ⅰの読解問題(消失が危惧される言語共同体)で下線部和訳問題のみ、Ⅱの読解問題(ビッグバン理論が表す2つの意味)で、字数指定つきの内容説明問題が出題された。内容説明問題としては3年ぶり、語数指定の形式としては2017年度以来8年ぶりの出題であった。また、2024年度はⅡ(マーケティングにおけるセグメント化)の読解問題文中に組み込まれたかたちで出題された自由英作文の問題は、Ⅳとして独立したかたちで出題されると同時に、これまでにない細かい指示がつき、ある意味で誘導のかかった問題であった。Ⅲの和文英訳問題だけは従来どおりの長文の英訳問題が出題された。年度により出題形式には変化があるものの、難度の高い英文を正確に読んで、理解した内容を日本語で表現すること、与えられた日本文の内容を正確に理解し、できる限り正確にその内容を英語で表現すること。求められていることの中心が基本的にこの2点であることは従来と変わるところはない。年度ごとの細かい出題形式の変化に惑わされることなく、骨太の学力をつけておくことが必要である。
2026年度入試予想・対策
- ①入試予想
- 2025年度に出題された形式が2026年度にも踏襲されるという保証はない。特に自由英作文の問題では、定まった出題形式での受験対策をさせないよう、意図的に出題形式を変えているようにさえ感じられる。これまでに同じ形式の出題が2年続いたのは、自由英作文が出題された初年度の2015年度と2016年度だけであることからも、2026年度は2025年度とは異なる形式の出題がなされる可能性が高い。先に述べたとおり、2024年度は読解問題で名詞の空欄補充の問題が出題され、2025年度は内容説明問題が出題されたが、これはむしろ素材となる英文の性質によるものと考えるべきで、京都大学は素材となる英文のタイプに応じて柔軟に出題形式を変えていると考えるべきである。したがって、下線部和訳問題に加えて、空欄補充問題、内容に関する説明問題も出題される、という前提で準備しておきたい。また、出題される英文は、文系的なものと理系的なものが組み合わせて出題されることが多いので、いずれのジャンルの英文にも対応できるようにしておきたい。従来どおりのひとつのパラグラフの英訳という形式のⅢの和文英訳問題は2026年度も出題が予想される。
- ②対策・英文読解
- 意味のわからない単語や表現がいくつも含まれ、抽象度の高い英文(ただし、従来と比べると抽象度は下がり、具体性が増している)を読み解いていくことは、どの受験生にとっても極めて骨の折れる作業である。しかし、常に文章全体の内容を追いかける姿勢で英文にあたっている受験生であれば、文意を大きく外すことなく理解できるようになるはずである。そこで、日頃の学習では、語彙力の拡充に努める一方で、積極的に難度の高い英文に取り組み、辞書の助けなしに(ただし、解答を合わせる際には、自分が単語の暗記用に使っている単語集などではなく、きちんとした辞書の使用は必須である)、その内容を理解しようとすることが、十二分な対策となる。その際、文法力を十分に活用し、文構造の正確な把握が必要となることはいうまでもない。
英文の内容が理解できたとして、次の課題が日本語による表現である。理解しているはずの英文を、いざ日本語に置き換える段階で、苦労するという経験は誰にでもあることだが、京都大学の読解問題ではそのような局面を迎えることが非常に多い。求められるものは、単なる日本語としての自然さではなく、原文の英語の意味からの逸脱を最小限に抑えたうえでの、日本語として不自然でない訳文である。この訓練にはおおよそどんな英文でも役に立てることができる。日頃取り組んでいるすべての教材を和訳の練習問題として活用してほしい。
このような勉強を重ねていけば、おのずと空欄補充問題や内容に関する記述問題の対策にもなる。受験生の実際の答案を見て気になるのは、内容に関する記述問題となると、和訳問題と比べて構造把握が甘くなることがある、ということである。「細かい部分はよくわかりませんでしたが、概略は捉えられたので解答は書けました」などと言う受験生がいるが、英文自体が正確に読めていなければ、概略が捉えられるとはとうてい思えない。どのような出題形式になろうとも、英文をきちんと読んで理解することが絶対的に必要である。2022年度には、和訳したうえで、その内容を具体的に説明する、という出題がなされた。また2019年度には下線部に含まれる比喩表現の理解を問う問題、2020年度にはminibrainという筆者の造語の説明を求める問題が出題されるなど、内容の深い理解を問う問題が出題されている。本文の内容を正確に理解しようとする勉強がその対策となる。 - ③対策・英作文
- 書くべき英文の量が多いため、力のない受験生がごまかし通すことは不可能である。和文英訳の対策であれ、自由英作文の対策であれ、まず、文法の運用面ではどんなことがあっても破綻を来すことがない、ということが大前提となる。
そのうえで、和文英訳の場合は、与えられた和文を、まず構造面から英語として自然なものとなるよう組み立て直し、次に語句のレベルでも同様に、英語として無理のないものに置き換えていく。これをスムーズに行う力を養うには2方向からの努力が必要となる。ひとつは、自分の英文づくりの「核」となる、例文を精力的に覚えること。これにより、基礎的な知識が鍛えられる。もうひとつは、本番並みの難度の高い問題に、週に1~2題、真剣に取り組むこと(数をこなそうとして、1題1題の取り組みがいい加減なものになるのでは、むしろ逆効果になる危険性がある)。その際は、問題文の内容を十分に理解し、自分の英語の表現力に見合ったかたちに置き換えることがどうしても必要になる。これにより応用力が鍛えられることになる。
自由英作文の出題は、毎年形式が変わっていると先に述べたが、これまでの出題で、ほぼすべての出題形式の自由英作文を出題し尽くしたといえなくもない(もっとも、写真や絵の説明、課題文を与えたうえでの論述、といった出題形式はまだなされていない)。過去に出題のある問題は一通り解答しておきたい。与えられた和文の英訳ではなく自分で自由に書くべき内容を決められるとはいえ、まずは和文英訳の力を十分に蓄えておく必要があることに気づくであろう。それに加えて、自由英作文の場合には、何を書くべきかということをきちんと確定する力が必要である。書くべき内容を外して、大きく失点してしまっている答案は、再現答案でも「京大入試オープン」でも毎回一定数見られるので、この点にもしっかり留意しておきたい。なお、2025年度の問題には、解答用紙の使い方、使用語数の指示のほかに、どのような構成で英文を書くべきか、という指示がついている。今後このような指示がつくかどうかはわからないが、ここで書かれている指示はひとつのパラグラフを構成するうえでのルールのようなものであるので、論述型の自由英作文に答える際には従うべきであろう。
配点的には、英作文の配点50点を和文英訳問題と自由英作文問題で25点ずつ均等に分け合っているが、対策としては和文英訳の比率を高めにして、英語表現力を十分に高めておくのが望ましい。
文系数学
最近の出題傾向
- ①論理的思考力、論証力、効率よく作業する力が問われるセット
- 5題出題され、うち1題が、2025年度のように独立小問2問のセットになることがある。また、理系と共通もしくは類似の問題が1、2題出題されることがある(2025年度は、類題が1題)。
ありきたりの解法で最後まで解けるものは少なく、方針を立てる力、解答の道筋を見通す力、効率よく作業する力、論理的思考の過程を正しく書く力が問われるものが多い。面倒な計算が必要な問題は、あまりない。 - ②確率、図形が頻出
- 確率(場合の数)、図形(特に空間)の分野がよく出題される。確率は、数列の知識を用いる計算を含むことがある。空間図形は、2025年度のようにベクトルを用いて解く問題が多く、座標空間が与えられる場合もある。
2026年度からは完全に新課程科目での出題になるが、前記の特徴は、維持されると思われる。
2026年度入試予想・対策
誘導なしに方針を立てる力や、効率よく作業できるかを問う問題が多く出題され、論理的に考えて説得力ある答案をつくることが求められる傾向が強い。このことから、頻出タイプの問題を覚えた解き方で解く練習が有効な対策ではないことは明らかであり、京都大学レベルの入試問題や模試などの問題を使いながら、次のような対策をとることが求められる。
- ①題意を読み取る力を養う
- 「かつ」「または」「すべての」「任意の」「ある」など論理的な意味を持つ言葉を正しく理解し、使うことが求められる。問題文やその解答を、特にこれらの言葉の意味を確認しながら読む習慣をつけよう。
- ②方針を立てる力を養う
- ほかの大学であれば、(1)の問いで変数のとり方を示唆したり、ヒントになる事柄に着目させることがよくあるが、京都大学ではいきなり(本題を)求めよ、示せということが多い。これは、どういう方針で解答するかを考え発想する力を問うためである。
本来は難しい問題も、(1)のおかげで解きやすくなることが多い。(1)(2)がヒントや誘導になっている問題では、それらをなくして解き直してみると、方針を立てるために考えるべきことが見えてくることがある。有効な練習法のひとつである。 - ③いろいろな解法を考える
- 例えば図形の問題では、三角関数の定理や公式の利用、ベクトルによる計算、座標平面の設定など、異なる分野の知識から有効なものを選んで使うことになるが、1つの問題が複数の解法で解けることはよくある。京都大学で出題された入試問題も解法が1つでないものが多いが、普段から「別の解法で解けないか」と考えるのは有効である。たとえ別の有効な解法がなかったとしても、②の方針を立てる力を養うことにつながるだろう。
- ④見通しがつくまでは計算欄を使い試行錯誤する
- 1つの方針を立てても、解ける見通しがつくまで、試行錯誤することは多い。京都大学の解答用紙は右半分が「計算用」という余白になっている。このスペースを用いて、解答を左側に書く前に、計算結果が求められているものに結びつくか、推測したことが本当に正しいか、結論を証明するために何を示せばよいか、そのための根拠は何かなどを確認することができれば、解法を確立する助けとなる。
どういう方針で、どういう論理展開で、何をどこまで書くかが(だいたいでも)わかったうえで解答を書けば、無駄のない伝わりやすい答案になり、最後まで書けなくても部分点が得やすくなる。問題の要求に関わりない記述は、何行書いても得点にはならない。効率よく答案を書くための計算欄活用の練習を、普段からしておくのがよいだろう。 - ⑤作業を効率よくすることを心がける
- 数値や式の計算をする際に各項を計算してから足すよりも項の共通部分を( )でくくることで手間が減る、場合に分ける際に作業が類似している場合を1つにまとめることで作業量が減る、ある事象の確率を求めるより余事象の確率の方が簡単に求められるなど、効率よく作業するための工夫の余地がある問題は多い。普段から、「答え(結果)が合っていたから良し」とするのでなく、自分の解法、記述法、計算法より効率が良い方法につながる手法があれば、それがどのような場合に使えるかを確認して、習得していこう。効率よく作業する力も、数学の力のうちである。
- ⑥説得力ある答案づくりを意識する
- 京都大学は論証力を重視するので、解答に至る過程がきちんと書かれているかで得点が大きく変わる。結果が正しくても、論理展開に飛躍がないか、必要な根拠は書かれているか、式や記号が正しく書かれているかなど、採点されるポイントは多い。このことを意識して答案づくりの練習をするのはもちろんであるが、ときどきは身近にいる先生に、書いたものを見せて問題点を指摘してもらうのも有効である。
- ⑦教科書の「発展」「研究」にある内容を理解しておく
- 教科書の「発展」や「研究」(出版社により名称は異なる)コーナーに、学習指導要領に含まれない内容が載っていることがあるが、特に京都大学では、このような知識が必要あるいは有効な問題が出題されることがある。しっかり理解しておくべきである。
理系数学
最近の出題傾向
- ①論理的思考力、論証力、効率よく作業する力が問われるセット
- 6題出題され、うち1、2題が独立小問2問のセットになることがある(2025年度は1題)。また、文系と共通もしくは類似の問題が1、2題出題されることがある(2025年度は、類題が1題)。
ありきたりの解法で最後まで解けるものはほとんどなく、方針を立てる力、解答の道筋を見通す力、効率よく作業する力、論理的思考の過程を正しく書く力が問われるものが多い。面倒な計算が必要な問題は、多くない。 - ②整数、確率、図形が頻出
- ①で挙げた力を判定する問題がつくりやすいためか、整数、確率(場合の数)、図形(特に空間)の分野がよく出題される。確率は、数列の知識を用いる計算を含むことが多い。数学Ⅲは少なくとも1題が出題され、最近は2題出題されることも多い。
2026年度からは完全に新課程科目での出題になるが、前記の特徴は、維持されると思われる。
2026年度入試予想・対策
誘導なしに方針を立てる力や、効率よく作業できるかを問う問題が多く出題され、論理的に考えて説得力ある答案をつくることが求められる傾向が強い。
このことから、頻出タイプの問題を覚えた解き方で解く練習が有効な対策ではないことは明らかであり、京都大学レベルの入試問題や模試などの問題を使いながら、次のような対策をとることが求められる。
- ①題意を読み取る力を養う
- 「かつ」「または」「すべての」「任意の」「ある」など論理的な意味を持つ言葉を正しく理解し、使うことが求められる。問題文やその解答を、特にこれらの言葉の意味を確認しながら読む習慣をつけよう。
- ②方針を立てる力を養う
- ほかの大学であれば、(1)の問いで変数のとり方を示唆したり、ヒントになる事柄に着目させることがよくあるが、京都大学ではいきなり(本題を)求めよ、示せということが多い。これは、どういう方針で解答するかを考え発想する力を問うためである。
本来は難しい問題も、(1)のおかげで解きやすくなることが多い。(1)(2)がヒントや誘導になっている問題では、それらをなくして解き直してみると、方針を立てるために考えるべきことが見えてくることがある。有効な練習法のひとつである。 - ③いろいろな解法を考える
- 例えば図形の問題では、三角関数の定理や公式の利用、ベクトルによる計算、座標平面の設定など、異なる分野の知識から有効なものを選んで使うことになるが、1つの問題が複数の解法で解けることはよくある。京都大学で出題された入試問題も解法が1つでないものが多いが、普段から「別の解法で解けないか」と考えるのは有効である。たとえ別の有効な解法がなかったとしても、②の方針を立てる力を養うことにつながるだろう。
- ④見通しがつくまでは計算欄を使い試行錯誤する
- 1つの方針を立てても、解ける見通しがつくまで、試行錯誤することは多い。京都大学の解答用紙は右半分が「計算用」という余白になっている。このスペースを用いて、解答を左側に書く前に、計算結果が求められているものに結びつくか、推測したことが本当に正しいか、結論を証明するために何を示せばよいか、そのための根拠は何かなどを確認することができれば、解法を確立する助けとなる。
どういう方針で、どういう論理展開で、何をどこまで書くかが(だいたいでも)わかったうえで解答を書けば、無駄のない伝わりやすい答案になり、最後まで書けなくても部分点が得やすくなる。問題の要求に関わりない記述は、何行書いても点にはならない。効率よく答案を書くための計算欄活用の練習を、普段からしておくのがよいだろう。 - ⑤作業を効率よくすることを心がける
- 場合に分ける際に式の形が類似している場合を1つにまとめることで作業量が減る、ある事象の確率を求めるより余事象の確率の方が簡単に求められるなど、効率よく作業するための工夫の余地がある問題は多い。普段から、「答え(結果)が合っていたから良し」とするのでなく、自分の解法、記述法、計算法より効率が良い方法につながる手法があれば、それがどのような場合に使えるかを確認して、習得していこう。効率よく作業する力も、数学の力のうちである。
- ⑥説得力ある答案づくりを意識する
- 京都大学は論証力を重視するので、解答に至る過程がきちんと書かれているかで得点が大きく変わる。結果が正しくても、論理展開に飛躍がないか、必要な根拠は書かれているか、式や記号が正しく書かれているかなど、採点されるポイントは多い。このことを意識して答案づくりの練習をするのはもちろんであるが、ときどきは身近にいる先生に、書いたものを見せて問題点を指摘してもらうのも有効である。
- ⑦教科書の「発展」「研究」にある内容を理解しておく
- 教科書の「発展」や「研究」(出版社により名称は異なる)コーナーに、学習指導要領に含まれない内容が載っていることがあるが、特に京都大学では、このような知識が必要あるいは有効な問題が出題されることがある。しっかり理解しておくべきである。
現代文
最近の出題傾向
- ①文系、理系ともに出題の枠組みはほぼ定まっている
- 出題の構成を見ると、文系、理系ともに現代文で一、二、の2つの問題が出題され、一は文理共通の本文を用いた問題となっている。ただし、文系一は設問が5つあるが、理系ではそのうち1問が省略され4問になっている。、二は、文系理系それぞれ別の問題である。文系、二は設問5つ、理系、二は設問3つというかたちが踏襲されている。
本文は、随筆や評論が多いが、小説が出題されることもある。設問は、傍線部についての内容説明や理由説明がほとんどである。ただし、取り上げられる文章によっては、心情の説明、比喩表現の説明が求められることもある。また、全体の主題に関わる説明を求める設問も出題されている。2025年度では、2024年度に引き続き、文系の一の問五において「本文全体を踏まえて」という条件づけがなされていることが注目される。解答欄は罫線が引かれたもので、年度ごとに若干の異なりはあるが、大問ごとに2~5行を埋めるよう求める設問が複数設定されており、1行25字で換算すると、文系では計850字程度、理系では計550字程度の解答分量となっている。 - ②2025年度入試の特徴
- 文理共通問題である一では、都市化の進行が人間と自然の関わり、他者との関わりにどのような影響を与えつつあるかを述べた精神科医の随筆が取り上げられた。「疎外」という概念を用いて、都市化が人間を本質的に変質させていくことを憂えたものである。理系ではこのうちの問五(本文全体を踏まえる設問)が省略されている。
文系二では、読書の営みが持つ意味について述べたうえで、文学が持つ力に言及するという展開をとる俳人の随筆が取り上げられ、理系二では、互いに欠点を抱えながらも無駄ともいえる時間をともに過ごすことになる友達を持つことの意義を説いた絵本作家の随筆が用いられている。
本文の分量や合計の解答行数を含め、年度ごとに増減は見られるが、2025年度も全体として大きな変化は見られず、例年どおりの出題であったと振り返ることができる。
2026年度入試予想・対策
- ①正確に読解し論旨を把握する力を養う
- 2025年度までの入試を振り返ると、出題される本文は随筆あるいは評論と、年度ごとに変化はある。だが、肝心なのは、設問で問われるのはいつも、正確な読解に基づいた明確な記述説明の力であるということだ。したがって、論理の流れ、内容の展開に即応した部分ごとの正確な理解と、それに基づいた全体の趣旨の的確な把握が何よりも重要となる。随筆や評論を中心に文章の正確な読解に取り組んでおきたい。また、文系の二では旧仮名遣いによる古い文章も出題頻度が高く、読み慣れておくことが必要になる。
- ②設問の要求に応じた正確な記述説明の力を養う
- 近年は、傍線部の内容やその文脈から、踏まえるべき本文内容が明確な設問が多く、離れた箇所にある内容をも参照して答案をまとめ上げねばならなくなるような設問は減少している。だが、内容説明であれ理由説明であれ、設問の要求の的確な判断が必要となることはいうまでもない。
特に京都大学では、傍線部の表現、その言葉に注意が必要な設問が多い。内容説明であれば傍線部の要素を本文中の別の表現で言い換えればよいであるとか、理由説明であればそれが書かれている箇所を特定してその内容を抽出すればよいとか、そうした小手先の解法だけでは十分な評価を獲得できる答案を作成することはできない。傍線部が特有の論理を示している場合にはそれを体現できる論理構成(構文)で説明文をまとめる、傍線部に筆者の表現上の工夫が見られる場合にはその“意味合い”をわかりやすく説明できる適切な語を用いて説明する、などの個別の対応が必要となる。また、著者独自の特有の意味を含んだ一般には通じにくい表現にはわかりやすい換言が求められる。 - ③全体の趣旨に関わる設問に対する訓練を
- ひとつの文章において、部分はつねに全体の趣旨、論旨と深く関わっているが、京都大学の入試では、いずれの問題においても、その最後の設問で全体の趣旨に深い関わりを持つ箇所に傍線が引かれ、その説明が求められたり、傍線を引かずに本文の主題について説明が求められたりすることが少なくない。文系、理系のいずれでも、この種の設問に対しては日頃から訓練をしておかないと、中途半端な答案しか作成できない。日頃から文章の全体をその趣旨を踏まえて要約する訓練を積み重ねておきたい。
- ④語彙力の強化に努める
- 最後に、基礎的なことではあるが、日頃から、自身が意味を明確に説明できない語についてはしっかりと辞書で確認し、語彙力の強化に努めてほしい。本試験では本文にほとんど語句注はつけられない。本文にとって重要な語、また、傍線部のなかで使用されている語の理解が曖昧なままでは、明解な解答はとうてい作成できないと考えたい。
古文
最近の出題傾向
文系学部の近年5 年間の出題状況は以下のとおり。
- 2025年度『義経記』中世・軍記物語・約960字
- 2024年度『とはずがたり』中世・日記・約690字
- 2023年度『駿台雑話』近世・随筆・約1,120字
- 2022年度『国歌八論余言』近世・歌論・約820字
- 2021年度『栄花物語』中古・歴史物語・約880字
- 出典傾向:
- 過去には受験生になじみのない出典の近世随筆が目立ったが、近年は有名作品からも出題され、ジャンルも多岐にわたっている。
- 出題傾向:
- 本文字数は700~1,000字で一般的な二次型古文並み。解答数は5つ。解答分量は合計14~17行(1行は25~27字相当)。現代語訳問題と説明問題が主流である。
- トピック:
- 漢文に関しては、2016年度に初めて出題されて3年間連続した後途絶え、2023年度に、漢詩の一部の説明が問われた。共通テスト対策で学習する知識でおおむね対応できる程度の設問ではあるが、記述形式に対応する練習も視野に入れておきたい。
理系学部の近年5 年間の出題状況は以下のとおり。
- 2025年度『玉勝間』近世・随筆・約520字
- 2024年度『草庵集玉箒』近世・和歌注釈・約380字
- 2023年度『後松日記』近世・日記・約600字
- 2022年度 『建礼門院右京大夫集』中世・私家集(個人歌集)・約360字
- 2021年度『正徹物語』中世・歌論・約460字
- 出典傾向:
- 理系が独自に古文を出題し始めた2007年度当初に比べ、近年は本文の難度が上がっている。受験生になじみのない出典の、中世や近世の随筆・評論が他大学に比べて目立つ一方で、ときに中古や中世の有名作品からも出題されている。
- 出題傾向:
- 本文字数はおおむね400~600字で、一般的な二次型古文に比べて短めである。解答数は3つ。解答分量は合計7~9行(1行は25~27字相当)。現代語訳問題と説明問題が主流である。
- トピック:
- 具体的な登場人物の行為や心情を描く文章と異なり、抽象的な内容を論じる評論に関しては、重要古語と文法知識だけで解答を作成できるものではない。このような文種の場合は重要古語や語法の比率が低く、ある程度の内容は読解できるのだが、論旨を正確に読み取り、それを答案作成に反映させられるか否かが合否の分かれ目となる。
2026年度入試予想・対策
トピック2点について、以下、対策のポイントを示す。
- ①現代語訳の問題
- 文系・理系学部を問わず、大前提として、重要古語と文法知識を踏まえた丁寧な逐語訳が求められている。大雑把な読解で勢いに任せた答案を書き、助動詞や敬語の訳出が漏れている、ということのないようにしたい。
単純な「現代語訳せよ」の設問ではなく、「~の指す内容を明らかにしつつ現代語訳せよ」のように条件があれば、それを踏まえること。また「適宜ことばを補いつつ現代語訳せよ」のように補うべき内容を自分で想定しなければならない場合もあるし、特に条件がなくとも、具体化しなければ現代語訳として不十分だと思われる場合には補充すべき場合もある。解答欄の行数が1行以上余るようなら、何か補充が欠けていないか考えてみるべきだろう。
また、近世の文章が課される可能性が高いので、いわゆる重要古語ではない表現について、現代語訳を求められる場合がある。やや古めかしい表現になじみがあるとついそのまま使ってしまいがちだが、現代語訳問題として傍線を付されている以上は、現代語としてよりふさわしい表現が要求されているのではないかと考えてみることも必要である。 - ②和歌に関する問題
- 文系・理系学部を問わず、京都大学の古文では和歌に関する設問が頻出している。直近の3年間でいうと、文系学部では2023・2025年度に和歌一首の現代語訳が問われた。2024年度には和歌の一部の説明と、和歌の一部の修辞を踏まえた現代語訳と、和歌を踏まえた本文の説明とで、5問中3問が和歌に関する設問だった。理系学部では出典の特性から和歌が含まれない文章も多く、直近の3年間でいうと、直接和歌を問うてはいないものの一首の和歌をめぐる議論で、和歌の理解を前提とする出題が2024年度にあったのみ。しかし直近10年間に視野を広げれば、和歌を踏まえた和歌一首の説明や、和歌の一部の現代語訳、和歌を踏まえた現代語訳なども出題されている。文理を問わず、和歌に関する練習は欠かせないだろう。
対策としては、過去問題に限らず学習素材に含まれる和歌に関して、全訳に掲載されている現代語訳と丁寧に照らし合わせるという経験を積んでほしい。和歌は31字からなる詩歌なので、すべてを述べ切っているわけではない。和歌でも日記でも多くの場合、読み手の心情はそれ以前の文章に述べられているはずで、それらを補助線のように活用して解釈する必要がある場合が多い。現代語訳中、和歌にある文言に該当する部分と、補充された部分とを見極め、補充要素は本文のどこから持ってきて補っているのか、あるいは本文からではなく文法的に補っている内容なのか、古文常識から補っている内容なのか、等々を検討することで、和歌の理解が深まり、いたずらに和歌を恐れる気持ちもなくなるはずである。
物理
最近の出題傾向
- ①分野的傾向
- 力学分野では、力学的エネルギー保存則およびエネルギー変化に重点を置きつつ、運動量保存則を絡めた物体系に関する出題や、円運動、単振動に関する出題が多い。2025年度の物理問題Ⅰでは、連結された2物体の円運動および重心の周りの円運動が出題された。指示に従って解き進めればよいが、重心から見た相対運動の解法がポイントとなった。近年では、熱分野と力学の複合的な問題、例えば物体の運動を問う問題のなかで気体の分子運動につながる出題や、気体の状態変化を問う問題のなかで物体の運動の要素を取り入れた出題もされている。
電磁気分野では、コンデンサー、直流回路や電磁誘導、電場と磁場中の荷電粒子の運動など磁気を含めた現象に関するものが多い。2025年度の物理問題Ⅱでは、ソレノイド内の磁場および磁気エネルギーと仕事の関係が出題された。近年、電気回路と電磁誘導が頻出であったが傾向が変わってきている。
波動分野では、ドップラー効果および干渉に関する問題がよく出題される。波の伝わり方の基本テーマや共振を扱ったテーマも出題されているので偏った学習はせず、波動全般についてまんべんなくカバーしておくことが大切である。2025年度は、波動分野からの出題はなかったが、2024年度では、光波の屈折と反射(光ファイバー)が出題された。2023年度も波動分野(光の偏光)から出題された。2021年度は原子分野に関連して干渉の問題が出題されたので、波動分野に関する出題が多くなっている。
熱分野は、熱サイクルなどの熱力学第一法則に関する問題や分子運動論の出題が多い。2025年度の物理問題Ⅲでは、ピストンがついたシリンダー内の気体の状態変化と理想気体ではない気体(光子気体)が出題された。光子気体は高校の学習範囲外であるが、状態方程式や内部エネルギーの式が単原子分子理想気体とは異なる気体と書かれているので、問題文の指示に従って解き進めればよい。第2回京大入試オープンで出題された問題と同じ光子気体を題材にしていたので、模試を受験した受験生には有利だったと思われる。2022年度で、気体ではないヒモの熱サイクルの問題が出題されたことから、一般的な理想気体とは異なる物質を扱うことがあるので注意したい。解法の暗記ではなく読解力とその場での理解力が問われる傾向がある。
原子分野は、問題の中心となるテーマが力学や波動のテーマである場合が多い。2025年度は出題されなかったが、物理問題Ⅲは背景としては光子気体なので原子物理と関係がある。2021・2023年度で出題されているので要注意である。原子分野に関する必要な知識は問題文で与えられていることが多いが、原子分野を一度も学習していないと戸惑うことになるので基本事項を整理して活用できるようにしておくべきである。 - ②設問
- 設問形式で見れば、式・数値などを入れる完成式の設問と、選択肢や選択群のなかから正解を選ぶ選択式の設問がほとんどであるが、記述問題、論述問題および描図問題が、大問ごとに1~3問ずつ出題される。また、問題の文章が極めて長く設問数も例年多い傾向にある。2025年度の設問数は、空所補充が44問、問い形式の記述論述の設問が6問であった(問い形式の1問は選択問題)。分量が極めて多いので、すべての問題を解こうとせず、問題全体に目を通し解ける問題をしっかり選別できる力が必要である。
2026年度入試予想・対策
- ①長文の解読に慣れよう
- 前前述のように、問題文の文章が極めて長いので、まず長文の解読に慣れることが必要である。そして、前の設問を間違えたときは後に続く設問が解けないことが多いので、注意しながら順をおって確実に解いていかなければならない。ただし、途中に膨大な計算を要する設問があっても、その後の設問には無関係である場合もあるので臨機応変の対処が必要となる。とにかく、まず全文を読んで問題の流れを把握することが大切である。また、小問ごとに条件設定も変わることが多いので、その都度、図を描き、記号を書き込んで物理的内容を正しくつかむことが必要である。
- ②演習問題で計算力を養おう
- 計算力においては、正確で迅速な計算力を養っておかなければならない。そのためには、基礎学習で習得した基本的な考え方に基づいて演習問題を多く練習してほしい。三角関数の計算、近似式を用いた計算を含めて、文字式の計算に習熟しておく必要がある。公式については、標準的な問題を、公式を適用して解くだけでは不十分である。基本法則・公式を種々の方法で証明し、適用する方法をまとめておかなければならない。教科書や参考書で調べるのもよいだろう。
- ③力学と電磁気の分野は十分な対策を
- 2026年度も力学と電磁気の分野は必ず出題されると考えておいてよい。毎年大問が3題ずつ出題されるパターンが続いているが、この2分野が3分の2を占めていることから、この分野の対策は不可欠である。近年、波動分野の光波に関する応用問題が頻出であるので注意したい。原子分野の出題率は低いものの、他分野との融合問題として出題されることがあるので基本事項の整理はしておこう。
- ④勉強にするにあたって意識すること
- 京都大学の入試物理では高校物理の範囲から逸脱したテーマに関する問題が出題されることもあるが、そういった問題は問題文中で説明がなされるので問題文をよく読めば対応できる。それ以外は高校物理で扱う分野の問題なので、そのことを理解し問題文の誘導に沿って適切に解いていけばよい。このような出題傾向から、単に問題集を解いて解法を覚えるような勉強方法では得点しにくいような問題が多く、物理法則をしっかり理解できていないと解くことができないような問題設定になっている。問題集を解いて答え合わせをするような勉強方法ではなく、物理法則の理解と解くために必要な着眼点の整理を意識した勉強方法が望ましい。長文形式の演習問題を多く解き、物理法則の適用方法、問題を解くための着眼点の整理をすることが重要となる。また、問題の分量が多いので、正確かつ迅速に解答していく力を養う必要がある。物理法則の理解、問題状況の把握力、正確な計算力を求められるのが京都大学の入試物理である。
化学
最近の出題傾向
- ①理論と有機中心の問題構成
- 出題数は例年4題であり、出題形式は記述、計算、選択、論述が中心である。試験時間は理科2科目で180分である。4題ともかなり長文の問題で、しかも大問が(a)(b)の2つに分かれているため、かなりの出題量である。2025年度は6つの出題であり、2024年度の7つより減少した。しかし、煩雑な計算もあり、時間的余裕はほとんどない。2025年度は、ここ数年出題されていなかった字数制限の論述問題や、計算の導出過程を書かせる問題が出題された。
- ②多角的に問いかける工夫がなされた問題
- 出題形式はこれまで記述、計算、選択がほとんどである。いずれの問題も1つのテーマに対して多角的に問いかけるよう工夫されている。また、計算量に加え、煩雑な計算も多いために時間的な余裕はほとんどない。2025年度は、〔Ⅰ〕環境水や排水中の汚濁物質の定量方法や除去技術を題材に、KMnO4を用いた化学的酸素要求量の測定に関連する内容、H2Cr2O7をNaHSO3によって還元し、Cr(OH)3として沈殿させる内容、および、Mn2+とCr3+を沈殿物として分離する内容である。〔Ⅱ〕(a)ラウールの法則を題材に、糖の加水分解に伴う溶質量の変化と蒸気圧降下の大きさの変化についての内容。(b)炭酸ナトリウムの水溶液中における電気的中性条件や物質収支に関する内容と、水酸化ナトリウムと炭酸ナトリウムの混合水溶液の滴定に関する内容である。〔Ⅲ〕シクロプロパンやシクロブタンの持つ炭素原子間の結合のひずみと開環付加反応、芳香族ラクトンとその誘導体に関する構造決定、および、ポリエチレンテレフタラートに関する内容である。〔Ⅳ〕(a)過ヨウ素酸を用いた反応によるアミロースおよびアミロペクチンの構造に関する内容。(b)シクロデキストリンを題材に、アミノ化による性質の変化、トリペプチドとの包接複合体の分析と、トリペプチドの配列決定に関する内容が出題された。
2026年度入試予想・対策
- ①高校ではあまり扱わない項目も出題テーマに
- 問題のなかには、高校ではあまり深く取り扱わない内容が出題されることもある。「理論」では、ラウールの法則、ファンデルワールス半径、沈殿滴定、溶解度積、電荷バランスと質量バランスの式などの平衡定数の定量的な取り扱い、速度定数、格子エネルギー、エントロピーの考察問題などが出題されている。特に理論では平衡の内容が例年出題されている。
「有機」では、立体異性体の考察、有機化合物の分子の形状、アミノ酸の等電点、エステルの加水分解の機構、ペプチドにおけるアミノ酸の配列順序の考察、糖のメトキシ化、重合開始剤、ベンゼンの共鳴安定化エネルギー、配向性と反応速度の関係などの考察問題が出題されている。特に有機では構造決定の内容が頻出である。 - ②主な物質についての知識を深めよう
- 理論をマスターすることが合格への近道だ。理論は架空の理論ではなく、具体的な物質についての理論がテーマとして取り上げられる分野だ。したがって主な物質についての知識が不十分では、理論的に考えるヒントは見つからないであろう。基礎的な知識を十分身につけておき、日頃の授業や学習でも理解できないことがあれば、すぐに質問するなどして納得できるまで考えを深めるようにしておこう。さらに無機については、周期表の族・周期に基づいて整理しておくと、要点のまとめが簡単にできるはずだ。
- ③有機化合物の推定問題を解ける力が必要
- 有機の問題に対応するうえで必要なことは、各物質の反応を中心に整理することである。そして、そのうえで物質相互の関連、誘導体へと発展させていくこと。最終的には断片的な知識をまとめ上げ、総合的に考える力をつけるよう努力しよう。異性体(特に立体異性体)は頻出事項である。さらにエステルやアミドの構造の推定問題を解ける力をつけるようにしよう。高分子については〔Ⅳ〕で必ず出題される。天然物(糖、アミノ酸とタンパク質)・合成物の両面から基礎的事項をまとめること。この分野の出題内容はお決まりであるので、過去問の演習を行うことにより、内容と出題形式に慣れておく必要がある。
生物
最近の出題傾向
- ①考察問題が中心
- 京都大学の理科は、解答時間が2科目で180分である。生物入試は大問が4題出題され、例年、考察問題の比重が非常に大きく、問題の読解、考察、論述答案の作成にかなり時間を要するため、時間に余裕はないと考えておこう。各大問はA・B分けされている場合が多く、AとBでは異なるテーマが扱われるので、4題の大問のなかで6つや7つのテーマに取り組むことになる。扱われる題材は、問題集で見たことがないような新奇のものが多い。2025年度は、〔Ⅰ〕では「プラスミドへの遺伝子導入」と「サイトカインを受容した細胞におけるシグナル伝達」、〔Ⅱ〕では「ゲノムサイズと遺伝子数の関係」と「反復配列によるDNA型鑑定」ならびに「近交系マウスを用いた交配実験とゲノムインプリンティング」、〔Ⅲ〕では「春化とジベレリン」と「半規管の回転受容と前庭動眼反射」、〔Ⅳ〕では「気孔の開閉とストライガの生態」と「植物の系統と気孔の獲得」といった題材が扱われた。このような新奇の題材を扱った問題は、論述形式で多く出題される傾向があったが、近年では、空欄補充形式や選択形式など、様々な形式で出題されるようになってきている。特に、2025年度はその傾向が顕著であり、前記の新奇テーマを扱った設問の多くが選択形式であった。一方、基本的な内容が論述形式で出題される場合もあり、論理的で簡潔な文章に内容をまとめる力が要求される。2025年度では、〔Ⅲ〕で「半規管の構造上の特徴」、〔Ⅳ〕で「気孔が閉じる仕組み」を説明させる設問が出題された。
- ②「遺伝子」「遺伝」「生態」「進化」が頻出
- 京都大学入試の生物で頻出の分野として、「遺伝子」「遺伝」「生態」「進化」が挙げられる。「遺伝子」については基本的に毎年出題され、複数の大問で扱われる場合もある。次に、京都大学入試では「遺伝」の出題頻度が他大学と比べるとかなり高く、大きな失点につながりかねない要注意分野であり、練習を重ねて慣れておく必要がある。「生態」と「進化」は、単独で扱われる場合もあれば、複合的に扱われる場合もある頻出分野であり、京都大学生物の最も大きな特徴といえるところである。特に「生態」の分野の出題頻度は極めて高く、幅広い知識と論理的な思考が求められる。ほかにも、「代謝」「動物の刺激の受容と反応」「植物の環境応答」などの出題頻度が高く、非常に幅広いテーマが扱われる。
2026年度入試予想・対策
- ①基本事項の徹底
- 京都大学の生物が考察問題中心とはいえ、教科書に記載されている基本事項をおろそかにしてはいけない。生物の学習において、生物用語の正確な理解は非常に重要である。なぜなら、生物用語を正確に理解していない場合、出題者の問いかけを正確に捉えられなかったり、答案でこちらの考えを採点者に伝えられなかったりするためである。大学では論文を読んだり書いたりすることになるが、ここでも正確に生物用語を用いる必要があり、大学側は生物用語を曖昧に扱う人間を求めてはいない。基本事項の徹底とは、重要生物用語の意味を正確に理解し、また、それを説明できるということであり、できるだけ多くの生物用語を覚えようということではないので気をつけよう。近年の京都大学の生物入試では、知識論述に指定語句が与えられる場合がある。これは、生物用語を“覚えている”ことより、“理解している”ことが問われていると考えられる。したがって、対策としては、重要生物用語の定義を説明する練習や、教科書の記述を要約する練習が適当である。
- ②論述問題の対策
- 設問の問いかけに従って、的確にポイントをまとめることが大切である。良くない答案の例としては、問題文に書かれている内容を言い換えただけのものや、実験データを言語化しただけのものがある。このような解答になってしまうのは、設問の意味を捉えられていないことが原因であり、“説明する”ことばかりに気が向いていて“何が問われているか”を見失っていると思われる。論述問題の解答欄は十分大きい場合が多いが、解答欄を埋めることが目的ではない。問われたことに対して、簡潔に解答することが重要である。
- ③考察問題の対策
- 実実験データの解釈の練習において、初見の段階でしっかり考えることも重要であるが、解答・解説を読んで理解した後に、もう一度、実験データを読み直すことも非常に重要である。解答・解説を読んで納得しただけでは、自らデータを読む力はなかなか身につかない。
- ④頻出分野の対策
- 「遺伝子」の分野が関係する問題については、過去問だけでなく、ほかの難関大学の最近の入試問題なども利用して経験を重ね、様々な手法の実験に触れておきたい。「遺伝」の分野については、過去問で“京都大学らしい遺伝の問題”を繰り返し練習するのがよい。「生態」と「進化」の分野については、データの読み取りが難しいことは少ないが、設問に解答する練習が必要である。これらの分野は、教科書の内容の理解が特に重要である。それは、実験データから好き勝手に想像を膨らませて解答するのではなく、教科書で説明されている理論に基づいて解答する必要があるためである。
日本史
最近の出題傾向
- ①大問ごとに異なる出題形式
- Ⅰの史料問題(20点)では、3つの時代の史料3本を用いて空欄補充や下線部設問が出題される(2016・2018年度には図版も使用された)。Ⅱの短文空欄補充問題(20点)では、短文10本程度に2つずつ程度作成された空欄を補充させる。Ⅲの前提文問題(30点)では、3つの時代の前提文3本を用いて空欄補充や下線部設問が出題される(2025年度には表・グラフも出題された)。Ⅳの論述問題(30点)では、200字の論述が2問、原始~戦後のうち2つの時代から出題される(2024年度には図版も使用された)。
- ②全時代・全分野からの出題
- 全時代・全分野から出題され、各大問で扱う時代・分野が重複しないように配慮されている。時代では原始・古代25点、中世25点、近世25点、近代・戦後25点と4時代からおおむね均等に出題され、分野では政治・社会経済からの出題が比較的多く、「律令体制の建設・内容」「鎌倉・室町時代の政治」「江戸時代の政治」「明治・大正・昭和戦前期の外交」などが頻出テーマである。
2026年度入試予想・対策
- ①教科書中心の学習を心がけよう
- 基本事項からの出題が大半なので、教科書の内容を正確に理解・習得していれば、70点以上は確実に得点できる。定期的に問題演習を行って理解度をチェックし、間違えた箇所については教科書などで復習するとよい。
- ② Ⅰ ~ Ⅲ の記述式で確実に得点する
- 記述式では、8割(56点/70点)以上を目標にしたい。Ⅰの史料問題では未見史料からの出題が多いが、史料中や設問文中のヒントを手がかりに、何に関する史料かを特定できれば、解答はさほど難しくはない。過去問のなかから史料問題をピックアップして集中的に問題演習を行い、未見史料問題の解法を身につけよう。Ⅱ・Ⅲの短文空欄補充・前提文問題では、一部に難問も含まれるが、基本用語からの出題が大半なので確実に得点したい。
- ③ Ⅳ の論述問題への対策が高得点の鍵
- Ⅳの論述式は、多くの受験生が苦手としており、得点差が一番開く形式だが、5割(15点/30点)以上は得点したい。京都大学では、例えば、「田沼時代~幕末の三都における幕府の仲間政策」(2017年度)や「明治・大正時代の社会主義運動の展開」(2020年度)などのように、ある歴史事象の一定期間における推移や変遷が多く問われる傾向にある。こうした論述問題では、指定された範囲内を時期区分しつつ論を構成する力が要求される。過去問などを用いて、論述の基本的なテーマに関する理解を深めつつ、論述問題の解法を身につけておきたい。その際、学校の先生などから添削指導を受けると効果的である。
2026年度入試の出題内容を予測することはなかなか難しいが、古代では「8~11世紀の土地制度・税制、国司制度」、中世では「鎌倉~室町期における守護の権限拡大」、近世では「江戸幕府の朝廷統制」、近代では「1870~1890年代の政治(自由民権運動、大日本帝国憲法の制定、初期議会など)」とその関連事項に注意しておきたい。
なお、京都大学では、過去に出題された問題と類似のテーマが出題されることがある。例えば、2020年度入試Ⅳ(1)で出題された「田沼意次の財政政策」は、「田沼意次の政治と松平定信の政治」(1991年度)の、2018年度入試Ⅳ(1)で出題された「弘仁・貞観文化と国風文化の特色」は、「天平文化と国風文化の特色」(1993年度)の、それぞれ類似テーマである。したがって、過去に出題されたテーマについては、時代範囲を前後に広げるなどしつつ、ノートにまとめておくと効果的である。 - ④正確な記述を心がけよう
- 京都大学では、解答を漢字で正確に書くことが求められる。誤字などのケアレスミスで失点することがないよう、歴史用語は常に手で書くよう心がけたい。
- ⑤過去問研究が効果的
- 京都大学では、記述式・論述式を問わず、過去に出題された事項やその関連事項が繰り返し問われる傾向にある。したがって、過去問を解いて問題演習をすることが望ましい。その際、特定の時代・テーマを集中的に解くと出題傾向を把握することができて効果的である。なお、記述式については、間違えた用語の関連語句・事項も含めて復習すること。また、論述式については、京都大学と似たような出題形式をとる大阪大学の過去問にも取り組むとよい。
世界史
最近の出題傾向
- ①出題分野・範囲の広がり
- 大問は〔Ⅰ〕~〔Ⅳ〕までの4題となっているが、〔Ⅱ〕と〔Ⅳ〕がA・Bの2つに分けられ、テーマ・出題分野も異なっていることから、実質的には大問6題が出題されている。頻出分野としては、中国史・北アジア史や古代ギリシア・ローマ史、西アジア史、中世・近世ヨーロッパ史、アメリカ史などが挙げられるが、近年は朝鮮史、インド史、東南アジア史、ロシア史、アフリカ史、ラテンアメリカ史などと、出題分野が広がるとともに、特殊なテーマ史や、冷戦後の現代史の範囲まで、論述式・記述式問題ともに出題されている。
- ②記述式問題・小論述問題に要注意
- 従来、〔Ⅱ〕〔Ⅳ〕の記述式問題は比較的平易なものが多く、あまり差がつかず、論述式問題の出来・不出来が合否を左右していた。ところが2006年度以降、〔Ⅱ〕〔Ⅳ〕では一部の教科書にしか記述がない問題(2023年度「倫理政策」、2021年度「メルヴィル」、2017年度「サヌーシー教団」)が出題されるなど難化の傾向にあり、地理的視点や日本史との関連をうかがわせる問題など、手強い問題の出題が続いている。また、2025年度には〔Ⅱ〕A・Bと〔Ⅳ〕Bで史料問題が出題された。今後も史料問題の出題が続く可能性がある。さらに注意したいのが、〔Ⅱ〕〔Ⅳ〕で小論述(2025年度9問、2024年度1問、2023年度6問、2022年度2問、2021年度3問、2020年度5問)が増加している点である。2025年度の〔Ⅳ〕Bでは史料の読み取りと、文章全体を踏まえて説明させる小論述問題が出題され、いずれも難問であった。小論述は、少ない情報のなかで「何を問われているのか」を瞬時に判断する力が求められるだけに、迷うと大幅に時間を取られてしまう。〔Ⅰ〕〔Ⅲ〕の300字論述問題で比較的取り組みやすい問題が続いているだけに、この傾向には注意したい。
2026年度入試予想・対策
- ①大問ごとの出題傾向と対策
- 前半の〔Ⅰ〕〔Ⅱ〕はアジア史、後半の〔Ⅲ〕〔Ⅳ〕は欧米史が出題される。〔Ⅰ〕は300字論述問題で、中国史が多く出題されているが、1993・1999・2001・2004・2006・2009・2013・2016・2018・2022・2025年度とイスラーム史の範囲も出題されている。出題内容としては、時代の変革期・時代像に着目し、これについて具体的に述べさせるものが中心である。今後も政治史だけではなく社会・経済・文化に関連する歴史の変化などについて、幅広い視野から問う問題が続くと予想されるので、中国史・イスラーム史を中心としたアジア史に関する明確なイメージと、因果関係を押さえた学習を心がけたい。〔Ⅱ〕は記述式問題で、例年、中国史2つ、あるいは中国史、その他のアジア史1つずつという出題が続いている。やはり、歴史用語の正確な漢字表記がポイントになる。〔Ⅲ〕は欧米史の300字論述問題で、19世紀までの問題がよく出題されていたが、最近では第二次世界大戦以降の範囲からも出題されるようになってきている。この傾向は今後も続くと予想され、現代史についての論述対策もおこたらないようにしたい。〔Ⅳ〕も欧米史からの出題で、古代ギリシア・ローマや欧米の特定地域の通史が多く出題されてきたが、近年では2024年度「共通語の在り方」、2022年度「石炭がヨーロッパの歴史に与えた影響」、2021年度「人類と動物」など、特殊なテーマからの出題が続いている。また、なかなか手強い小論述の出題も続いており、教科書の記述や世界史用語集などの内容をチェックし、歴史用語の理解や歴史事象の因果関係を正確につかむようにしておきたい。
- ②教科書を中心とする学習を徹底的に
- 京都大学の世界史は、大学入試問題のなかで最もオーソドックスな内容・レベルで、ほとんどが教科書の範囲内から出題されている。しかし、これが曲者で、高校の世界史の内容を知り抜いている集団が作成しているだけに、実に手強い問題で生半可な理解ではとても歯が立たない。したがって、最大の対策はやはり教科書を中心とする学習を徹底的に進め(地図の内容や図版の説明も含めて)、その内容を理解することにある。
- ③中国史対策を万全に
- 中国史については出題頻度が高く、年度によっては〔Ⅰ〕〔Ⅱ〕とも中国史に関する問題が出題されている。京都大学の世界史では、中国史の学習にめどが立てば高得点を獲得することも可能となる。まず、押さえておきたい項目としては、古代~清代までの王朝交替史である。これを中国社会の変化を中心に整理しておこう。次いで、中国近現代史については、欧米や日本との関係に着目してまとめていきたい。なお、2025年度の〔Ⅰ〕はイスラーム史の範囲から出題されただけに、2026年度の〔Ⅰ〕は中国史が出題される確率が高いと予想される。そうすると過去の出題傾向から、〔Ⅱ〕A・Bのどちらかは、イスラーム史が出題される可能性が高い。やはり中国史・イスラーム史対策を徹底的にやっておきたい。
特派員の声 ~合格の秘訣!!~
工学部 1年 いんぴーだんす特派員
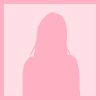
- メリハリと継続の大切さ
- 塾や学校など、勉強できる環境にいる間は携帯は見ずに勉強していました。朝から夜まで自習して家に帰ってからは、携帯を見ていました(勉強していなかった時の方が多いかもしれないです)。
平日に勉強を頑張ったから土日は家から出たくない、と思いがちですが、とりあえず塾に向かうようにしていました。毎日とにかく勉強できる環境に身を置くことを継続していました。直前期は何をやれば良いのか不安になることもあるかと思いますが、変な事は考えずにルーティーン通りに過ごしていました。
法学部 1年 Jupiter数特派員
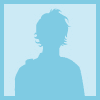
- 基礎と共テをなめるな!!
- 数学は過去問は夏から第二回京大オープンまでと共通テストが終わってから二次試験までだけしかやらない。3月から夏までは基本的な問題集を回して基礎力をつけないと少し変えられただけで破綻するような力しかつかない。また、共通テストは以外にも合格率との相関が高いので配点が低いからと侮らず、絶対に高得点を取る。もし私大を共通テストで抑えたなら100時間くらい余計に京大にかけられることは意識して共通テストをきちんととること。
英語も基礎的な読解は大事。テキストにある京大以外の問題も侮らず解き、直しをすること。
国語はたくさん解く以外に上がる方法はない。古文は単語が難しく読みづらい時も多いので必ず単語力はつける。
世界史は論述ふくめ知識がないとどうしようもないのでテキスト解きなおしなどを通じて基本単語は全暗記を目指す。
河合塾の難関大学受験対策
京都大学をめざすあなたに向けて、受験対策のポイント・イベント情報・合格した先輩たちの声などをご紹介します。