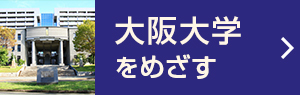大阪大学 学習アドバイス
河合塾講師からの学習アドバイス
教科別の学習対策について、河合塾講師がアドバイスします。
※出題範囲は募集要項、大学ホームページ等で必ずご確認ください。
英語
最近の出題傾向
大問4題という設問構成が20年以上定着しており、その内訳は[Ⅰ]英文和訳、[Ⅱ]長文読解総合、[Ⅲ]自由英作文、[Ⅳ]和文英訳である(外国語学部では[Ⅴ]としてリスニング問題が加わる)。設問の多くは論理的思考力を試すものであり、入試問題としては難しい部類といえる。読解系の問題も作文系の問題も「掘り下げて考える」、また「文章全体の一貫性を考える」習慣を身につけておかないと勝負は厳しい。なお読解系の設問では、科学、心理、言語などに関連する知的レベルの高い英文の出題が目立っている。さらに、英作文系の記述量が非常に多く、また和文英訳問題の日本文が直訳を受けつけない部分を多く含むことは特筆しておくべきだろう。
2026年度入試予想・対策
2026年度も形式・内容とも大きな変化はないと予想される。まず過去問を解いてみて、自分の実力と本試で求められるレベルとの差を実感することから対策をスタートさせるとよいだろう。
- ①大問[Ⅰ](英文和訳)
- いうまでもなく、英文構造の正確な把握力および語彙力強化が最も重要な取り組みとなる。加えて、大阪大学をめざす限り、本格的な英文解釈(英文和訳)の問題集に「じっくり」取り組んでもらいたい。示されたテーマは何なのか、それについて筆者はどう論じているのか、それは自分とどう関係しているのか、といったことを考える作業を丁寧に行うわけだ。そのようにして文内容の本質的理解を求めることこそ、大阪大学突破の近道だと考えよう。さらに、把握した英文の内容を確実に意図が通じる的確な日本語で表現する訓練も十分に積んでおく必要がある。
- ②大問[Ⅱ](長文読解総合)
- [Ⅱ]では、[Ⅰ]で求められる力に加えて、「文脈の大きな展開」を理解することが設問攻略の鍵となる。「要旨(主張・一般論)」とそれをサポートする「具体例」との関係に注意しながら、「この文の訳は何?」ではなく、「この文の役割は何?」という意識を持ち、英文の要旨を要領よく理解することを心がけよう。このような「次元の高い」読解作業を繰り返す過程で、多種の設問への対応力は生まれてくるものだ。設問の解答だけを求めて本文の理解を重視しない姿勢は、逆効果しか生まない。
- ③大問[Ⅲ](自由英作文)
- [自由英作文といっても書くのは英文の集合体なのだから、まず一つひとつの英文を正確に書く力の養成が必須。その力を前提として、自由英作文では複数の英文を組み立てて「説得力と具体性のあるパラグラフ」を構成することが求められる。まずはその「お手本」、つまり模範解答をいくつか吟味・分析することから始めよう。「読む」作業こそが自由英作文学習の出発点になる、ということだ。英文読解教材も「文展開のお手本」として活用するとよい。一方、抽象(主張)とそれを支える具体(例)との連携を意識したパラグラフ構成法をしっかり理解し、実際に答案を作成する作業も進めていこう。2022年度に「80語程度」となった指定語数は、どうやらすでに定着したと考えてよさそうである。これによって語数に若干の余裕が生まれたものの、論をコンパクトにまとめなければならないことに変わりはない。
- ④大問[Ⅳ](和文英訳)
- この設問では、与えられた日本文全体を熟読してその本質的メッセージを把握し、英文に書き出す情報を整理する作業が必要となる。大阪大学の和文英訳問題はこの作業でほぼ勝負が決まる、といっても過言ではない。しかしここで忘れてはならないのは、こうした作業は有用な例文を多数暗唱し、「書きこなせる」表現のデータベースを構築しておかないことには意味がない、ということ。「書きこなせる表現」が貧弱なままでは、日本文を正確に把握し情報を整理できたところで、それを合格レベルの英文へと昇華させることは難しい。まずは英作文を意識したインプット作業を日常的に進めていくことが最優先だ。基本的な英文記述力が固まってきたら、大阪大学レベルの和文英訳問題を解き、自分の答案と模範解答をじっくり比べてみよう。求められている作業の質、そして自分に足りないものが何なのかが実感できるはずだ。
文系数学
最近の出題傾向
- ①出題数・レベル
- 90分の解答時間に対して大問3題の出題が定着している。易しめの問題とやや難しい問題がバランスよく配置されているが、大問数が少ないため個々の問題の難易が全体の難易に影響しやすく、年度ごとの難易に差がある印象も受ける。
- ②出題分野
- よく出題されるのは数学Ⅱの微分・積分分野であるが、それ以外の分野も、数年にわたって見ていくと何らかのかたちで出題されており、どの分野もおろそかにできない。また、理系との共通問題が出題されることもしばしばあり、その場合文系の問題としてはやや難しいことが多い(2025年度は標準レベルの共通問題が1問あった)。
2026年度入試予想・対策
- ①入試予想
- 2026年度も易しめの問題とやや難しい問題を取り混ぜた出題になると思われる。分野としては、数学Ⅱの微分・積分分野が出題される可能性が高く、ほかには、ベクトル、図形と方程式、数列、場合の数・確率などが比較的出題される可能性が高いと思われる。
- ②学習対策
- まずは、易しめの問題を確実に取れる力をつけることが重要である。そのためには、受験対策をうたった問題集や参考書、あるいは予備校のテキストなどで、基本的な問題を重点的に学習することをお勧めする。その際、単に解答を眺めているだけ、あるいは数式だけ走り書きするような勉強法ではなく、実際に手を動かしながら、本番に近いかたちで答案を構成していくと学習効果が高まる。数式と数式をつなぐ日本語部分は、理解が不十分だとなかなか書けないものなので、逆にいえば、それを書こうとすることで理解が不十分なところが浮き彫りになり、理解を深めることができる。また、手を動かすことで計算力の鍛錬にもなる。
次に、やや難しめの問題に対する対策である。大阪大学の文系の場合、複数分野の融合問題が出題されることが多いため、問題の切り分けが重要になってくる。問題の切り分けがうまくできるようになるためには、まず、各分野の典型的なパターンを習得しておく必要がある。これは有名問題を丸暗記するという意味ではない。問題を解いたとき、その解法の流れをつかみ、自分なりに咀嚼して、頭のなかでパターンを整理するという作業を行うことである。咀嚼して十分小さい単位に分解されたパターンならば、融合問題に対しても適用しやすくなる。そして、そういった地力をつけたうえで、過去問にあたって、自分で切り分ける練習を繰り返していこう。
分野についていうと、前述のとおり数学Ⅱの微分・積分分野が頻出であるから、この分野については「得意分野です」と胸を張れるくらいの練習を積みたい。分野の特性としても、典型問題の割合が高いため学習の効果が表れやすく、また、計算量も多いから計算力の鍛錬にも効果的で、やりがいのある分野といえるだろう。
ほかの分野についても、まんべんなく出題されているので、得意分野とはいかないまでも、特に苦手な分野がないようにしておきたい。
理系数学
最近の出題傾向
- ①出題数・レベル
- 150分の解答時間に対して大問5題の出題が定着している。かなりの思考力を要求する問題が複数題含まれ、手のつけやすい問題もかなりの計算力を要求されることが多いため、いずれにせよ完答は容易ではない。
- ②出題分野
- 数学Ⅲ・Cの分野から出題されることが多く、新課程から数学Cに移ったベクトルを含めると、数学Ⅲ・Cを含まない問題は1、2問しかない。
ただし、数学Ⅲ・Cの分野と他分野の融合問題も出題されるので、全体として見ると数学Ⅲ・C偏重というわけでもなく、高校数学の全分野からまんべんなく出題されている。
また、空間図形(または立体の体積)がよく出題される。ここ10年では、2022・2025年度を除くすべての年度で出題されている。
空間図形以外の分野としては、極限も含めた微積分の総合問題、平面ベクトル、場合の数・確率の問題がよく出題されている。
2026年度入試予想・対策
- ①入試予想
- やや難しい問題が2、3題出題され、残りは標準的な問題が出題されると思われる。分野としては、数学Ⅲ・Cの分野を含む問題が4題近く出題されると思われる。また、空間図形を含む高度な図形問題が出題される可能性も高い。ほかに、近年の傾向から考えて、場合の数・確率、複素数平面の問題なども出題される可能性が高い。
- ②学習対策
- 前述のように、数学Ⅲ・Cの分野を含む問題の割合が高い。特に現役生の場合、数学Ⅲ・Cを履修してから入試までの期間が短いので、意識的に数学Ⅲ・Cの問題演習を行う必要がある。
また、空間図形を苦手とする受験生も多いと思われるが、大阪大学の理系では頻出の内容であるから、十分な対策が必要である。整数問題は、教科書の単元としては出題範囲から外れていても、他分野の整数が関わる問題で知識が必要になることはあり得るので、ある程度の対策は必要であろう。これらについては、大阪大学の過去問を中心に学習するとよいであろう。
以下は一般論であるが、学習の際に気をつけてほしいことをまとめておく。
まず、典型的なパターンを習得すること。これは有名問題を丸暗記するという意味ではない。問題を解いたとき、その解法の流れをつかみ、自分なりに咀嚼して、頭のなかでパターンを整理するという作業を行うことである。いかに有名問題でも、まったくそのままの形で出題される可能性は低い。しかし、咀嚼して十分小さい単位に分解されたパターンならば、実際の入試の現場でも使える可能性は高まる。
次に、計算力、論理展開力をつけること。いくら方針が立てられても、正確にそれを推し進める力がなければ正しい結論に至れない。
そして最後に、答案の構成力をつけること。答えの数値が合っていても、それを導いた過程が採点者に伝わらなければ、評価は低くなってしまう。計算力、論理展開力と答案の構成力を身につけるには、普段からきちんとした答案をつくる練習をすることが重要である。解答を眺めているだけ、あるいは、数式だけ走り書きするような答案では、こういった力は身につかない。
入試までの時間は限られている。どういった力をつけるべきか意識した学習を心がけてほしい。
現代文(文学部)
最近の出題傾向
- ①評論と小説による本格的な論述問題
- 2025年度入試の大問 Ⅰ は、評論文(香川檀『想起のかたち――記憶アートの歴史意識』)からの出題。「アーカイヴ型アート」を通して、「アーカイヴ」(文書などを保存する施設)が、そこに集められた資料の価値を保証したり隠蔽したりするシステムであることや、「蒐集」という行為が人間にとって持つ意味などについて論じたもので、例年と同様抽象度の高い議論が続く硬質な文章であった。2024年度は、連続的変化でしかない自然現象を分節化して因果関係を理解し、人間の行動の「責任」を捉える「物語り」能力に、動物や機械とは異なる人間のアイデンティティがあることを論じた野家啓一「ホモ・ナランス(homonarrans)の可能性」からの出題であったことを踏まえると、現代の書き手が人間の在り方について深く掘り下げ思考した文章が連続して出題されている。設問は、論述問題のみの4問構成、解答欄の横幅はすべて3.5センチであった。
2025年度入試の大問 Ⅱ は、吉村昭の小説「彩られた日々」からの出題。第二次世界大戦中の東京で、空襲で亡くなった人の遺体が次々に川を流されていくなか、友人らしき遺体を発見した主人公が、彼の思い出や人生に思いをはせるという内容で、戦争中という時代状況への理解が必要ではあるものの、全体としては読みやすい作品であった。2024年度に出題された坂崎かおる「母の散歩」が、母を亡くしたばかりの主人公が、晩年の母が架空の犬を飼っていたという事実を知り、若くして亡くなった兄を思っていた母について思い巡らすという独特の世界観を持った小説であったことと比べると、2025年度はオーソドックスな小説からの出題であったということができるだろう。設問は、論述問題のみの4問構成、解答欄の横幅は問一と問四が3.9センチ、問二と問三が2.8センチであった。また、大阪大学文学部の小説題の特徴のひとつともいうべき、本文中の表現が持つ「効果」を説明する問題は、2025年度は出題されなかったが、同一の対象を指示する「かれら」「それら」が使い分けられている理由を説明する問題が出題された。 - ②ハイレベルな読解力と論述力を求める設問
- 2025年度の大問 Ⅰ の評論では、4問ある設問の解答欄はすべて3.5センチ幅であり、各設問に100字程度の答案が求められていると予想される。傍線部の内容に関連する本文中の論理を正確に説明することを要求する設問が基本だが、全体の論旨と傍線部表現の細かいニュアンスを正確に捉え、答案に生かしていく力が求められる。2025年度大問 Ⅱ の小説では、二種類の指示語を作者が使い分けている理由を説明する問一が3.9センチ幅(おおよそ120字程度の答案が求められていると予想される)、傍線部における登場人物の心情を説明する問二・問三が2.8センチ幅(おおよそ80字程度)、「十七歳という年齢」についての主人公の考えを本文全体の内容を踏まえて説明する問四が3.9センチ幅(おおよそ120字程度)と、設問ごとに解答欄の大きさに違いがあった。前記の予想に基づいて論述量を計算すれば、大問 Ⅰ ・ Ⅱ を合わせて800字程度と多いうえに、すべての設問に対して濃密な内容を解答することが必要となる。限られた時間のなかで文章をまとめる高度な論述力と、その前提となる正確な読解力を養成しておきたい。
2026年度入試予想・対策
- ①評論・小説問わず、幅広いジャンルの文章に対応する力を
- 大問 Ⅰ は評論文、大問 Ⅱ は小説(随筆)からの出題という従来の傾向が、2026年度も踏襲されると予想される。評論文は哲学、政治、文化、芸術など多様なテーマから出題されており、小説は、現代を舞台にしたものだけでなく、戦前・戦中といった昔の時代状況を背景にした作品も出題されている。どんな内容の文章が出題されても、文章の構造や展開を正確に把握して趣旨をくみ取ることができるよう、普段から様々な文章に取り組む訓練をおこたらないようにしよう。
- ②着実な読解力と論述力の養成を
- 大問 Ⅰ の評論文では、本文全体の趣旨を大まかにつかむことはできても、設問が要求していることを正確につかめないまま答案を作成し、結局傍線部の前後を何となくまとめて終わってしまった、というパターンに陥ることが多い。設問の条件をしっかり確認したうえで、何を説明することが求められているのか、その説明には本文のどの部分を、どのような順番でまとめていけばよいのかを、正確に判断することが必要である。また、100字以上の長い文章をまとめるには、同じ内容を繰り返したり、途中で論理がつながらなくなったりすることのないよう、自分の書いた答案を客観的に捉える視点を持つことも大切だ。普段の学習においては、過去問や論述対策用の問題集などを用いて、じっくりと時間をかけて文章と設問に向き合う訓練を積み重ねておきたい。また、問題集や模試の問題などで作成した自分の答案を、後から自分で分析する作業には、十分に時間をかけて取り組んでほしい。自分の答案は解答例と見比べて何が違うのか、どうしたら解答例のような答案が書けるかを考え、何度も推敲を重ねよう。そうした普段の地道な積み重ねこそが、入試本番で力を発揮するための唯一の道である。
大問 Ⅱ の小説は、基本的な考え方は評論文と同じだが、小説でしか問われない、登場人物の心情や人間関係などを説明する設問に対応できるよう、答案作成の方法を確立しておこう。過去問や論述対策用の問題集で様々な小説題にあたり、登場人物の心情を100字程度で説明する練習を繰り返すことが必要である。小説は自分の頭のなかで理解したつもりになってしまい、様々なことを省略して表面をなぞっただけの答案になりやすい。ある人物の心情には、その前提となる周囲の状況、その人物の行動や心情の流れ、心情を引き起こすきっかけとなった出来事など、外的・内的要因が複雑に絡み合っているはずであり、答案ではそれを具体的に細かく説明していくことが必要である。また、大阪大学文学部入試の小説題の特色ともいえるのが、本文中で用いられている表現を、筆者がどのような意図で用いているのか、それが本文全体のなかでどのような「効果」を持っているか、といったことを説明する問題である。過去問と解答例をしっかり分析し、どのように答案を組み立てればよいかを検討し、対策を立てておこう。
現代文(人間科学・外国語・法・経済学部)
最近の出題傾向
- ①評論を中心とした本格的な読解問題
- 従来、哲学思想や社会科学の分野を中心に、極めて高度な内容の評論文が多く出題されており、2025年度も、大問 Ⅰ ・ Ⅱ ともにそうした傾向を踏まえる出題であった。
Ⅰ は、人間やほかの哺乳類のように特定の機能を割り振られた器官を持たず、水と渾然一体となって浮遊しながら、魚類とは異なる海の食物網を生きているクラゲの特性を踏まえた評論文からの出題であった。
Ⅱ は、個人が排他的にモノを所有する権利を持つという近代社会の私的所有の考えとは異なり、富者から貧者への贈与や分配を基にする社会規範を順守して社会全体の経済実践を成り立たせ、魂の込められたモノを介して社会の紐帯を維持しつつ自己の確立をも促していくという、経済的には発展途上にあるタンザニア社会の意義を論じた評論文から出題された。
Ⅰ のクラゲの生活、 Ⅱ のタンザニア社会の特性がそのまま、現代の人間や社会に対する批評となっている点を確認してほしい。 - ②高水準の読解力と要約力を求める設問
- 〈論述問題〉は、本文の論旨に関わる内容を150~200字程度でまとめる要約型の設問と、100字程度で簡潔に記述する設問が複数課されるという形式が長く定着しており、高水準の論述力が求められる。2025年度も、大問 Ⅰ ・ Ⅱ を合わせた総記述量が800字に達し、2024年度(900字)ほどではないが、従来の700字前後を超えており、時間の点でまったく余裕がない。したがって、解答の要素を的確に把握し、手際よく文章化する〈要領〉も重視される。また〈語句の空欄補充問題〉が出題されたが、年度によっては、〈傍線部の内容に関わる選択肢問題〉〈語句の抜き出し〉〈語句の意味を問う設問〉なども出題されている。〈漢字の書き取り問題〉は必出であり、〈読み取り問題〉もしばしば出題され、いずれの難度も高い。2025年度は、2022~2024年度と同じく4問が出題された。
2026年度入試予想・対策
- ①評論を中心とした練習を
- 2025年度は従来どおり難度の高い出題となっており、原則として、これまでどおりに近現代(日本)社会を批判的に捉えた本格的な評論文が出題されると想定すべきであろう。
- ②本格的な読解力と論述力の養成が不可欠
- 哲学思想・政治社会の分野以外にも、文明論・芸術論・科学論など様々な分野の評論文から出題されているが、いずれも本格的な内容であり、日本の大学の現代文の入試問題としては最難関のレベルにあるといえる。それらを読み解くために、高度の読解力を養成しておかなければならない。問題演習などを通じて、論旨を的確に理解する読解力を鍛えるだけでなく、各問題文の背景となっている様々な知識を、好奇心を伴った〈知的教養〉として身につけることで、高度に専門的な内容にも対処しやすくなるだろう。その意味では、日頃から新聞やニュースなどメディアの報道に接し、現代社会の諸問題に通じておくことなどは極めて有効である。また、問題文の主旨を要約する論述型の設問に対応するために、演習問題の文章全体を200字程度で手際よくまとめるという練習を積み重ねることも必須となるだろう。その場合にも、常に「文章全体」の論旨を念頭において読むことが大切である。〈選択肢〉問題や〈空欄補充〉〈語句の意味〉の問題であっても、傍線部や空欄の前後の文脈を精確に読み解きながら、広い範囲で論旨を把握することが同時に要求されていると心得て、ひたすら文章の主題の理解に努めてほしい。
- ③漢字力および語彙力の養成も忘れずに
- 出題数が減少しているとはいえ、必出の漢字問題は有力な得点源であり、また文章読解の基盤でもある。語彙力を豊かにすると同時に、本試験でも確実に得点できるように、できるだけ早期から、漢字の書き取り・読み取りの練習に取り組んでおこう。また、〈語句の意味の問題〉に対応するためにも、普段からマメに辞書を引いて語義を精確に捉えるという習慣も身につけておきたい。
古文(文学部)
最近の出題傾向
- ①出題文章
- 出典については、過去10年間で、中古から4題、中世から6題が、それぞれ出題されている。中世から出題された2017年度の説話『発心集』は、漢語の少ない和文調の中古文的な箇所が選ばれて出題されている。以上のことから、例年の傾向として、出典作品の成立年代にかかわらず、典型的な古文といってよい、いわゆる中古文が出題されているといえる。2021年度は『八雲御抄』という中世の歌論だったが、文体は中古文なので、例年の傾向に沿った出題だった。なお、2015年度『古本説話集』・2022年度『大和物語』では、入試出題歴も多く教材でもよく採られているような有名な出典の有名な箇所が出題された。2025年度『東関紀行』は、紀行文からの出題で、例年の傾向からは珍しい出典だった。
- ②設問内容
- 設問では、古文に典型的な、現代語訳問題や傍線部の内容説明、理由説明問題などが出題されている。出題される文章がジャンルにかかわらず物語性のある文学的文章が多いので、そこに登場する人物や作者自身の心情表現が説明問題としてよく問われているという傾向が見てとれる。ただし、2021年度の『八雲御抄』は、歌論からの出題で内容が論理を説いた抽象的な文章だった。過去の傾向からはかなり珍しいが、今後も注意しておきたい。
現代語訳問題は、比較的長い傍線箇所を訳出するものに加えて、単に語句の意味を問うような基本的なものも出題されている。ただし後者については出題されない年度もある。長い部分の現代語訳になると、多少補充や具体化を施さなければならない問題も課されている。大阪大学文学部は、情報開示によって大学が作成した解答例を示しているが、それを見ても、主語や省略表現の補いなどを施している場合が見られ、文脈を踏まえた細やかな現代語訳を要求しているように思われる。
和歌の含まれた文章はよく出題され、設問としても何らかのかたちで出題がある。2018~2020・2022・2023・2025年度で和歌の解釈(現代語訳)、2018・2019年度で和歌に含まれる修辞の説明、2016・2019・2023~2025年度で和歌の解釈を踏まえた内容説明などが出題されている。
また、ここ10年ではないが、文学部では、ほかの文系学部の出題には今のところ見られない、記述説明式の文法問題が、まれにだが出題されたことがある(2012年度「らむ」の識別)。
2026年度入試予想・対策
- ①重要古語と語法、古典常識の再確認を
- 単語帳などを利用しての頻出重要古語(だいたい600語くらい)の対策は万全かという点は、常に注意しておくこと。また文法に関しては、単独の文法問題として過去に出題されたこともあるが、それ以上に、解釈のうえでは欠くことのできない基礎学習だから、助詞・助動詞の意味について解釈に着目した学習はしっかり押さえておきたい。また、古文を解釈するうえでは、当時の習慣や精神的背景といった古典常識の知識もある程度は必要である。そういった面の学習にも目を向けること。
- ②内容説明の演習を
- 記述説明問題の演習を徹底することが重要である。現代語訳問題は、さほど難しいものが出題されているわけではないので、ここではあまり受験生の差がつかないことも考えられる。してみると、ほかの受験生と差がつき、合否を分けるものは、内容説明問題でいかに点数を取るかということにかかってくるだろう。文章の主題と、登場する人物の心情に踏み込んだ深い読解力を要求する説明問題が出題されていることに注意しておくべきである。ここ10年だと、例年の傾向としては字数制限の設問が出題されていないが、20年以上を遡さかのぼることになるが、2002年度に50・120字といった形での記述説明が課されたこともある。
- ③和歌の対策を
- 和歌の修辞や解釈(現代語訳)の問題は、その対策の有無が大きな差を生む。典型的な修辞の理解、特に掛詞や縁語の理解は徹底を極めなければならない。またそれに加えて、和歌全体を解釈するといった演習(現代語訳)も心がける必要があるだろう。
古文(人間科学・外国語・法・経済学部)
最近の出題傾向
- ①出題文章
- 出典については、過去10年の傾向として、中古から3題、中世から3題、近世から3題、明治期文語文1題が、それぞれ出題されている。10年間の傾向としては、中世や近世といった読みやすい文章から多く出題されているが、ただし、年度によって、作品の成立年代に限らず、『源氏物語』『枕草子』に代表されるような王朝文学としての典型的な中古文からの出題もあり、2019年度『増鏡』がそういった例になる。これは、中古の作品である、2017年『浜松中納言物語』、2018年度『和泉式部日記』、2021年度『紫式部日記』などが出題されたものと同傾向といえ難度が高い。2022年度の近世紀行文『西遊記』や2023年度の明治期文語文『秋香歌かたり』などのような非有名出典からの出題がある一方で、2024年度の『古今著聞集』のように、入試出題歴も多く各種教材に採られているような有名な文章からの出題もある。なお、2025年度『玉勝間』も有名出典ではあったが、国語学を論じた抽象度の高い文章で難度は高い。なお、2016・2022年度は紀行文の出題、さらに、2020・2024年度は説話の出題といった文種の傾向も視野に入れておくべきである。以上のような出題傾向を見据え、2026年度入試に向けて注意しておきたい。
- ②設問内容
- 長い傾向から見た場合、設問数は4~5問程度がよくある形式だが、2022年度のように問七までの出題があった例もある。内容は現代語訳と説明問題。両者で半々の割合で出題されることが多い。ただし、年度によっては、すべて現代語訳であったこともあるし、現代語訳より説明問題が多く出題されたこともある。なお、2023年度は5問中4問が説明問題だった。また、説明問題の場合は、2018・2019・2022~2025年度を除いて字数制限が課されている。文章全体の主題に関わるような説明問題がよく出題されており、これはある意味で文章の要約問題的な性質もある。説明問題について、2016年度は40字程度1問・80字程度1問・制限字数なしの説明問題1問、2017年度は70字程度1問・制限字数なしの説明問題1問、2020年度は100字程度1問・制限字数なしの説明問題4問、2021年度は50字以内1問・100字以内1問、2022年度は制限字数なしの説明問題2問、2023・2024年度は制限字数なしの説明問題4問、2025年度は制限字数なしの説明問題3問である。年度によってばらつきはあるが、説明問題の総字数はほぼ200字程度と見てよいだろう。2018・2019・2022~2024・2025年度のように、まったく制限字数のない説明問題が出題された場合も、解答分量ということではほぼ同じである(2023年度はやや多い)。なお、2023年度では、傾向的にはまれな出題といえる俳諧の解釈に関わる説明問題が出題された。また、10年以上を遡さかのぼることになるが、2011年度では、他年度に例を見ない文学史も出題されている。さらに、2017・2024年度には、やはり他年度に例を見ない古典教養が問われる問題も出題されている。2017年度は『百人一首』の作者を答えることと、それが詠まれた背景を踏まえた説明問題であった。2024年度は菅原道真を解答に含めることが要求される問題だった。今後も視野に入れて注意する必要がある。
2026年度入試予想・対策
- ①重要古語と語法の再確認を!
- 出典については、前記のように、10年間では説話・軍記などの比較的読みやすい文章も出題されているが、2017~2019・2021年度のように、中古文で若干難度の高い文章が出題されることに注意しておくべきである。よって、ここは基本的な古文学習の理解を確かなものにして入試に臨む必要がある。基本的な古文学習とはおおむね単語と文法の理解ということになるが、とりわけ単語の学習は確かなものにしておくこと。単語帳などを利用しての頻出重要古語(だいたい600語くらい)の対策は万全かという点には常に注意しておくこと。また、文法に関しては、設問として文法問題そのものが今後出題されるかどうか未定だが、解釈のうえでは欠くことのできない基礎学習である。助詞・助動詞の意味や、解釈に着目した識別などの文法学習はしっかり押さえておかなければならない。
- ②和歌や古典常識への視点を!
- 和歌に関する問題は、何らかのかたちでよく出題されているという点でひとつの傾向といってよいだろう。2017~2021・2024年度では和歌解釈(現代語訳)、2017年度では和歌の内容を踏まえた説明、2022年度では和歌修辞を踏まえた説明、2020年度では比喩を踏まえた説明などが出題されている。和歌の解釈や説明は、対策の有無が大きな差を生む。典型的な修辞の理解、特に掛詞や縁語の理解は徹底を極める必要がある。2023年度で出題された俳諧に関する出題も基本的な考え方としては和歌に準ずるものである。またそれと同時に、古典常識などの古典世界の背景を知るといった学習も読解の一助には必ずなる。そういった方面にも目を向けて万全の態勢で入試に臨むべきである。
漢文
最近の出題傾向
- ①読み取りやすい文章の出題が続く
- 2025年度は前漢の『説苑』からの出題で、命を救ってくれた人物をその人とは知らずに、主君の命令で殺しそうになったが、直前に恩人であるとわかって、自分の命を捨ててその恩人を救ったという話で、とても読み取りやすい。本文の文字数は183字とやや長めであった。過去10年の出典と文字数は以下のとおり。
2016年度『風俗通義』(156字)説話
2017年度『夷堅志』(191字)小説
2018年度『韓非子』(132字)思想
2019年度『独醒雑志』(144字)随筆
2020年度『誠意伯文集』「苦斎紀」(103字)随筆
2021年度『琴操』と『論語』(124字)史伝と思想
2022年度『幽明録』(133字)小説
2023年度『百喩経』(152字)仏教説話
2024年度『笑林』(133字)小説
2025年度『説苑』(183字)史伝
出題の文章に一定の傾向は見られず、様々なジャンルの文章が出題されている。 - ②設問内容は年ごとに変化あり
- 設問数は、5で固定されている。
問いの種類について、2025年度は、枝問があり書き下し文1、現代語訳1、理由説明4であった。2024年度は書き下し文1、現代語訳3、理由説明1。2023年度は書き下し文1、現代語訳2、内容説明2。2022年度は書き下し文1、内容説明2、理由説明2。2021年度は書き下し文1、現代語訳2、内容説明1、理由説明1。以上から書き下し文は必ず1問、現代語訳は1~3問、説明問題は、文章の内容によって数に変化がある。返り点をつける問いは2021年度以降出なくなった。
書き下し文の問いの傍線部は、返り点も送り仮名もついていない白文である。2025年度は、「現代仮名遣いでもよい」というただし書きがなかった。書き下し文のポイントについて、2025年度は文の構造と文意、2024年度は二重否定「無不~(ざるはなし)」、2023年度は「雖~(~といえども)」と「欲~(~んとほっす)」、2022年度は受身形「為A所~(Aの~〔する〕ところとなる)」、2021年度は再読文字「将~(まさに~んとす)」と「所以(ゆえん)」である。基本句形を問う傾向がある。
現代語訳のポイントについて、2025年度は反語「何ぞ~んや」、2024年度は再読文字「将」・「宜」・「以為」、2023年度は疑問「何以」、2022年度は再読文字「将」、2021年度は各語の意味と対句である。やはり基本句形を問う傾向がある。
2026年度入試予想・対策
- ①正しく読み取る力が必要
- 出典のジャンルは予想しにくいが、最近は小説や説話といった読み取りやすい文章の割合が高く、また過去にほかの大学で出題された文章も目立つ。また本文の長さは100字前後から200字までの文章が出題されると予想される。200字近い長めの文章を読みこなす力も求められる。
設問の種類は、書き下し文、現代語訳、そして内容説明や理由説明という設問が予想される。書き下し文は、白文で出題されるので、基本句形を含んだ例文などを使って、白文で訓読する練習をしてもらいたい。説明問題では、字数制限が設けられることはないが、設問の要求に過不足なく簡潔に説明する表現力が必要である。解答欄の大きさに惑わされてはならない。 - ②基本を確実に習得せよ
- 学習対策としては、まず基本をしっかりと身につけること。書き下しや現代語訳の問題には必ず基本句形が含まれると予想されるので、基本語の読みや意味から基本句形まで漢文の基本的な知識を習得することが第一である。
次にできるだけ多くの文章を読解しておくこと。二次試験用の問題集を解くときも、ただ問いの解答を確認して終わりというのではなく、問題文全体の現代語訳を自分でつくってみたり、漢和辞典なども活用し、自分の力で漢文を読み解く訓練をしておく必要がある。必ず過去問を解いて、内容説明や理由説明を要領よくまとめる練習をしておこう。
物理
最近の出題傾向
- ①出題分野
- 第1問は力学分野、第2問は一部に原子物理の範囲を含む電磁気分野、第3問は波動・原子の各分野からA,Bの独立した2問が出題されている。したがって、実質的に大問数は4題といってよい。
- ②出題形式
- 大問1題あたりの設問数は10問前後であり、出題の形式は問い形式がほとんどだが、空所補充形式の場合もある。解答の形式は、答えのみを数式で記述する設問がほとんどで、正しい図表や文章などを、記号から選択させたりする設問も見られる。以前は、グラフの概形を描く問題も出題された。
- ③難易度と分量
- ここ数年、問題の難易度は飛躍的に上昇し、問題の分量も大幅に増加している。そのため、解答時間内で完答することは非常に困難である。今後もこの傾向は続くと思われる。
2026年度入試予想・対策
- ①物理の基本事項を完全に理解しよう
- 各設問の難度は非常に高い。だからといって、問題集から難問ばかりを選んで解けばよいというわけではない。何よりも重要なことは、物理の各分野において、物理の基本事項を徹底的に理解することにある。物理の基本公式や法則などを、自らの手で導出、証明し、その成り立ちの根本を理解することが肝要である。基本事項の完全な理解があってこそ、初めて接する様々に状況設定された問題を、道を誤ることなく、正しい手順で解答を進めていくことができる。
- ②スピードより正確さを大切に
- 各設問は難度が高いだけではなく計算量も多い。すると、各設問を素早く解こうとして、計算ミスをしてしまうことが多くなるだろう。こうなると、計算の見直しなどが必要となり、かえって解答に要する時間が増えてしまう。また、計算ミスに気づかず解答を進めていくと、ミスした問題以降の問いが、すべて不正解になってしまう可能性もある。したがって大切なことは、計算を落ち着いて丁寧に進め、一度の計算で正答できる正確な計算力を身につけることである。そのためには、普段から問題を解答する際に、式を正確に書き、計算過程を丁寧に書き進める練習が必要である。
- ③標準的な問題を正確に解答する
- 前述したように、問題集から難問ばかりを選び、解答を参考にしながらポツポツ解いても、学力の向上にはつながらない。真の学力を身につけるためには、物理の基本事項を徹底的に理解したうえで、標準的な問題が集まった問題集を用いて、基本事項の理解度を確認しながら、1つの問題の最後の小設問まで解答する練習が大切だ。こういった地道な作業こそが、学力の向上につながる勉強の仕方である。
- ④時間を計って過去問を解こう
- 標準的な問題の演習がある程度進んだら、過去問の演習に取りかかろう。その際、時間をしっかり管理して解答を進めることが大切である。各設問の難度は高く、計算量も多いので、与えられた解答時間内に、全問を解くことは非常に難しい。したがって、まず初めに問題全体を見渡し、比較的解答が容易そうな設問から解答に着手したい。各問題の前半部分の設問を先に解いて、後半部分は後回しにしてもよいだろう。解答時間を有効に使う練習の場として、過去問の演習は必要である。基本事項の徹底理解を目標に置いて、これからの学習を頑張ってほしい。
化学
最近の出題傾向
- ①出題形式
- 空欄補充、記述、論述、作図など多様な形式で出題される。特に30~80字程度の論述問題は毎年必ず出題されている。また、計算過程を書かせる問題の出題頻度も高い。
- ②出題内容
- 理論化学、無機化学、有機化学の各分野のバランスは年度によって異なり、一定ではないが、有機化学分野では、アミノ酸、糖、タンパク質についての出題が多い。また、大阪大学では教科書では扱っていない、思考力を要する内容に関する内容も出題されており、さらに、教科書で扱われている物質についてのより広範な知識も問われているので、学習対象により興味を持って積極的に知識を吸収する姿勢が望まれる。出題範囲および傾向は大きく変動しても慌てないようにしたい。
例:2025年度[1]
亜鉛は金属の腐食防止(防食)に用いられている。例えば,図2に示すように,③水分を含む土の中に埋められた鉄の構造物の防食を目的として,絶縁体で被覆した導線で亜鉛を接続し一緒に埋めるという手法がある。- 問4下線部③について,鉄の腐食が起こりにくくなる理由を40字以内で記せ。
- 解答鉄よりも亜鉛の方がイオン化傾向が大きく,亜鉛が優先的に酸化されるため。
- 解説イオン化傾向についてのより深い理解を問うため、身近な応用例としての犠牲電極の働きと原理について出題された。表面的な知識の「お勉強」で終わることなく、本質的な理解とともにその応用例に興味を持って学習する姿勢が望まれている。
2026年度入試予想・対策
- ①分量への対策
- 試験時間に対して問題量は多く、時間的余裕はほとんどない。確実に得点できる問題から時間内にしっかりと解答する練習を十分に行うこと。
- ②出題分野への対策
- 理論化学分野では、分子間力が働く理由など、教科書に書かれている内容のより深い理解を問うような出題が見られる。また、有機化学分野では、合成高分子に関する内容や、DNAの構造など生命科学に関する内容も積極的に出題されてきた。また、近年、反応機構など教科書の記述を超えた内容の出題も増加している。
- ③論述、記述問題への対策
- 論述問題対策として、基本的な論点を扱った問題について、20~80字程度で論述を行う練習を十分に行うことが重要である。その際、自分の答案を化学の先生に添削してもらい、不適切な表現を修正することが確実な得点力の向上につながるだろう。論述問題では、模範解答以外でも正解となることも多いので、自分で答案を書き、しっかり指導してもらうことが重要である。また、計算過程を書かせる問題も毎年のように出題されている。これも、どの程度の計算式を書けばよいか的確に判断しなければならないため十分な練習が必要だろう。
- ④思考力を要する問題への対策
- 問題文中に特に指示がなくても必要な近似を行って計算する必要がある計算問題も出題されているので、普段から公式に頼るのではなく、なぜその式が成り立つのかを確実に理解しながら演習することが必要である。また、有機化学反応の反応機構など、教科書で扱われていない内容が出題されるときは、問題文中でその内容に関する理論、知識が与えられる。つまり、初見の内容を素早く正確に理解し、既習の内容と照らし合わせて論理的に思考する能力が求められている。過去問にしっかり取り組んだうえで、模範解答との違いを確認することにより、どのような能力が求められているのかを実感してほしい。
- ⑤2026年度入試予想
- 理論化学分野については、無機化学分野との融合問題が例年出題されている。特に、酸化還元反応、化学平衡が関連する無機化学の内容に関しては、理論化学の理解に裏づけられたより深い理解が重要であろう。また、浮力、状態変化などの物理的な内容についても要注意である。有機化学の分野では、糖、アミノ酸、タンパク質、合成高分子がいずれも難度の高いものが出題されている。特に2026年度はエンタルピーを用いた熱化学の計算もエントロピーを含めた応用的な内容の出題も予想されるので、十分に対策をしておく必要がある。
生物
最近の出題傾向
- ①出題傾向
- 大阪大学の理科は、解答時間が2科目で150分である。生物入試はおおむね大問4題が出題される。論述問題が多く出題され、解答作成に時間を要するため、試験時間に余裕はないと考えておこう。出題形式は、空欄補充などの生物用語を答える問題、知識的な論述問題、実験データからわかることを選択形式で問う問題ならびに論述形式で問う問題、計算問題、描図問題と多岐にわたり、教科書の内容の理解とともに、思考力や表現力が総合的に問われる。2025年度では、〔1〕で葉緑体の原核生物型リボソームと細胞内共生説に関する考察問題、〔2〕でプラスミド上での遺伝子発現操作に関する考察問題、〔3〕で興奮性シナプスと抑制性シナプスに関する考察問題、〔4〕でワクチン接種に関する考察問題が出題された。〔2〕は遺伝子関連の高難度の考察問題であったが、〔3〕と〔4〕は標準的な設問が多く、得点できる設問を取りこぼさないことが重要であったと思われる。
- ②分子レベルの題材が頻出
- 大阪大学の生物入試で頻出の分野として、「細胞・タンパク質」「遺伝子」「免疫」「酵素・呼吸」「受容器・神経」が挙げられる。「細胞・タンパク質」というテーマはほかの様々な分野と混ざって扱われることになり、言い換えるなら様々な生命現象を分子レベルで捉える問題が多いということである。実際に大阪大学理学研究科生物科学専攻では分子に着目した研究が盛んに行われており、これらの研究室の研究内容は大阪大学の生物入試に扱われる題材と関わりが深い。「遺伝子」については基本的に毎年出題され、遺伝子発現の仕組みやバイオテクノロジーを扱った実験考察型の問題が出題される。「免疫」については、大阪大学が研究に非常に力を入れている分野であり、生物入試でも頻出の分野になっている。古典的な実験を扱った問題から、最先端の分子レベルの研究まで、多様な題材が出題されている。「酵素・呼吸」を扱った生化学分野も頻出である。「受容器・神経」については、難問が出題されることは少ないが、平易な問題ばかりというわけではないので、差がつきやすい分野である。
2026年度入試予想・対策
- ①基本事項の徹底
- 大阪大学の生物入試では、空欄補充形式と論述形式で生物の知識が問われる。空欄補充は得点を落とすわけにいかないので、頻出分野の生物用語については、やや細かいところまでしっかり覚えておこう。また、論述形式の知識問題については、問題集などで典型的な知識論述問題の練習を重ねよう。
- ②考察問題への対策
- 大阪大学の生物入試の多くを占める考察問題で得点できるようになるためには、問題演習を通じて、新しいテーマの説明の読解や、実験データの解釈の練習を行う必要がある。このとき、初見の段階でしっかり考えることも重要であるが、解答・解説を読んで理解した後に、もう一度、実験データを読み直すことも非常に重要である。解答・解説を読んで納得しただけでは、自らデータを読む力はなかなか身につかない。また、大阪大学の生物入試では古典的な実験が扱われる場合もある。教科書に記載されていたり、標準的な問題集で扱われていたりする実験については、実験の概要と結論を頭に入れておくべきだろう。
- ③論述問題への対策
- 論述問題については、「○字以内で述べよ」という字数指定の年度と、「○行以内で述べよ」という行数指定の年度が混在している。2020年度からは字数指定の年度が続いていたが、2025年度は行数指定であった。設定字数や設定行数については、少し多めになっており、余裕があることが多い。目安として重要であるが、解答欄を埋めることに必死にならないようにしてほしい。必要のないことを書いて解答欄を埋めてもまったく加点にはならない。また、「書く」力も重要であるが、問題を「読む」力も非常に重要である。設問の意図や条件をつかめずに、ポイントがずれた答案を書いてしまう受験生は多い。指定語句を用いるのは当然であるが、「理由とともに」「○○をふまえて」といった指示に従うことや、「その理由を説明せよ」の「その」が何を指しているのかをしっかり確認することなど、答案を書き始める前に設問文をきっちりと読むことが重要である。
特派員の声 ~合格の秘訣!!~
理学部 1年 りんご特派員
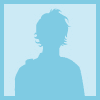
- 基礎≠簡単
- どれだけ演習をしても見たことのない問題はどの教科でも出る可能性があります。その時に役に立つのはやはり学問の根本的な理解です。基礎が疎かでは到底太刀打ちできません。基礎だからと言って侮ることなく、基礎だからこそちゃんとするのが大切です。
基礎工学部 1年 ひつじ特派員
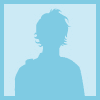
- 丁寧に答案を作る!
- 記述回答の問題、特に数学に言えることだと思いますが、答案を丁寧に(字の丁寧さもですが、内容面も)作成することが必要だと思います。理論の飛躍や説明不足がないように、見やすい回答を作ることを意識しましょう。
河合塾の難関大学受験対策
大阪大学をめざすあなたに向けて、受験対策のポイント・イベント情報・合格した先輩たちの声などをご紹介します。