神戸大学 学習アドバイス
河合塾講師からの学習アドバイス
教科別の学習対策について、河合塾講師がアドバイスします。
※出題範囲は募集要項、大学ホームページ等で必ずご確認ください。
英語
最近の出題傾向
- ①大問構成
- 多少のマイナーチェンジはあるものの、〈長文読解総合問題3題+英作文問題1題〉の大問4題構成が基本である。
- ②出題分野
- 長文問題3題は、論説文が2題、会話を多く含む小説もしくはエッセイ(完全な対話形式の場合もある)が1題という構成が基本である。論説文のテーマは多岐にわたっており、あらゆるジャンルから出題される。例えば2025年度は、大問Ⅰの論説文が「JAXAの月面探査技術」についての英文、大問Ⅱの論説文が「老化」についての英文であった。また、大問Ⅲの小説文は、ある家族のクリスマスにおける場面を描いた、例年どおり会話を多く含む英文であった。英作文は自由英作文で、「ニュースを知る手段としてのソーシャルメディア」という時勢に合ったテーマについて論ずる問題であった。
2026年度入試予想・対策
2026年度の出題パターンの安易な予想は危険であるが、いずれにせよ厳しい制限時間内で大量の英文を読んで、記述式を含んだ多くの設問を処理する能力を要求されることには変わりないであろう。それぞれの設問に関する対策は以下のとおり。
- ①論説文
- 日頃は一文一文を正確に解釈する訓練をおこたってはいけないが、制限時間のある実際の入試においては、下線部和訳の箇所でない限り、頭のなかで「上手な訳」をしながら読んでいく時間的余裕はない。センテンスの内容を瞬時に捉えながら読み進んでいく練習も積む必要がある。ただしその際、センテンス同士の論理関係、パラグラフ同士の論理関係を理解することが大切。日頃から論説文を読むときに、漫然と英文を訳すだけでなく、論旨を頭のなかで整理しながら読んでいく「論理的速読」の練習が必要である。
- ②小説または対話文
- 小説では「いつ、どこで、誰が、何を、どうして、どのように」という5W1Hを具体的に思い浮かべながら読んでいくことが基本。日頃から物語文を読むときに、場面設定・登場人物の人間関係・心情などを考えながら読んでいく「想像する速読」の練習が必要。対話文の場合は、論点と、それぞれの発言者の立場を押さえながら読んでいくことが重要である。
- ③和訳
- 英文の正確な構造分析に基づき、文脈をヒントにしてなるべく自然な訳語を選択する練習を積んでいこう。常に品詞、文型、修飾関係、構文などを意識して英文を観察する姿勢が大切。
- ④説明
- 説明問題の解答のヒントは必ず本文中にある。下線部の前後の文脈を精読して、論理的に該当箇所に迫ろう。解答は発見できても設問の条件に沿って最終的な答案をまとめる段階でのミスが多いので、書くことを惜しまず答案作成の練習を十分に積んでほしい。
- ⑤英作文
- 神戸大学は近年自由英作文の出題頻度が増しているが、和文英訳ができない受験生は、きちんとした自由英作文も書けない。まず文法的に正しい英語を書く練習をすること。それには文法の学習も不可欠。さらに、日本語表現のとおりに英訳するのが困難で、意訳しなければならない場合は、常に文脈に最大限の注意を払い、できる限り元の問題文から意味がずれないよう注意すること。
- ⑥自由英作文
- 自由英作文には様々な形式があるが、どの形式が出題されても慌てないように対策を立てることが大切。答案の内容・表現は「自由」だが、答案が第三者に理解できるように「論理的な文章」を書くという基本は外せない。日頃から先生に答案を見てもらうことが効果的である。
文系数学
最近の出題傾向
- ●実力差が現れる入試
- 80分で3題の出題形式が定着している。2018年度以降、標準的な難易度の問題が出題されており、受験生にとって取り組みやすい設定にはされているが、複数分野の融合問題に注意したい。2025年度には確率・三角関数の融合問題が出題された。過去にも2018年度は微分法・数列・指数・対数、2019年度は数列・整数、2021年度は複素数・数列、2022年度は指数・対数・整数、2023年度は図形と方程式・整数、2024年度には微分法・数列・対数、確率・整数の融合問題が出題されている。
- ●整数が頻出
- 前述のように整数との融合問題がよく出題されているので、数学A「数学と人間の活動」の整数の分野も対策しておこう。ほかにも、微分法・積分法、場合の数・確率も頻出分野なので注意したい。
2026年度入試予想・対策
- ①入試予想
-
- ●微分法・積分法を得点源に
- 微分法・積分法、場合の数・確率に関する問題の出題が予想されるが、このなかでも微分法・積分法は典型問題が出題されることが多く、学習量が直接点数に跳ね返ってくるので、ぜひ得点源にしよう。場合の数・確率は工夫されている問題が多く、思考力が試されるので、過去問を使って研究しておくとよい。また、図形問題もよく出題されるので、図形やグラフ・座標に関する問題およびベクトルの問題などを中心に幅広く対策しておきたい。
- ●整数問題・論証問題に注意
- 整数との融合問題が過去に何度も出題されているので注意したい。高度な内容に手を出す必要はないが、基本的な整数の扱いはきちんと頭に入れておいてほしい。2025年度は整数部分と小数部分に関する論証問題が出題された。過去にも2022年度は整数と指数・対数、2023年度は整数と図形と方程式の融合問題、2024年度は整数と確率の融合問題が出題されている。また、必ず論証の設問が出題されるので、数学的帰納法・背理法を用いた証明や不等式の証明に関してもしっかりと学習しておきたい。
- ②対策
-
- ●まずは基本事項の徹底理解
- 特殊な解法が必要な問題はほとんど出題されておらず、教科書で基本をしっかりと身につけ、その後、良質な入試問題を幅広く演習していけばよい。ただ、漫然と演習を重ねるだけでは、思考力の必要な論証や場合の数・確率の問題への対処は難しいかもしれない。ここ数年、融合問題も続けて出題されている。そのような問題に対処するために、どんな問題を解くときも方針から式変形に至るまでしっかりと考えてほしい。地道な作業によって論理力と思考力を強化しよう。
- ●論証力、計算力のアップを
- 論証問題では答案作成力もポイントになるが、論理性が身につけば答案も自然とよいものが書けるようになる。逆に答案を書くことは論理性を強化することに役立つので、論証問題でなくても答案をしっかりと書くようにしよう。普段の学習で式だけを羅列しているようでは、論証問題攻略は難しい。時間に関しては3題の問題を80分で解くので難しくはないが、考察に時間が必要な問題も多いため、計算に時間を取られないよう計算力強化も心がけたい。
理系数学
最近の出題傾向
- ●数学Ⅲ重視の出題
- 120分で5題の出題形式が定着している。前期試験において2018年度以降、数学Ⅲに関する内容を含む問題が、2019・2021・2025年度は2題、2018・2020・2024年度は3題、2022年度は4題出題されている。2023年度の前期では1題しか出題されなかったが、後期では4題出題されていることから、数学Ⅲからの出題が多いといえる。
- ●論証問題では思考力・論理力が試される
- 前期・後期試験ともに、大問5題のなかに論証の設問が含まれるのも特徴である。2025年度は4問出題された。過去には2021~2023年度の前期では2問ずつ、2023年度の後期では6問も論証の設問があった。微分法・積分法や不等式を題材とした標準的な問題だけでなく、整数と数列の融合問題やデータの分析と空間ベクトルの融合問題といった高度な思考力・論理力が試される論証問題も出題されている。
2026年度入試予想・対策
- ①入試予想
-
- ●2026年度は2018~2020年度および2022~2025年度ベースで
- 2017年度は計算量も多く思考力が求められる難しめの問題が出題されたが、2018~2020年度は全体的に標準的な難易度の問題が出題された。2021年度はコロナの影響により進度の配慮などのためか、数学Ⅲからの出題が少なく内容も易しめであったが、2022年度以降は再び標準的な難易度の出題に戻った。以上より、2026年度の難易度は2018~2020年度および2022~2025年度と同程度であると考えたほうがよい。また、後期受験を考えている人は前期よりも問題の難度が高いことに注意したい。
- ●微分法・積分法と場合の数・確率に注意
- 出題が予想される分野として可能性が高いのは微分法・積分法と場合の数・確率である。微分法・積分法に関しては、3題以上出題される可能性もあると思ってしっかりと対策をとっておきたい。場合の数・確率は他分野と融合されることも多く、思考力養成が不可欠である。また、論証力を見る問題が分野を問わず出題される可能性が高い。
- ②対策
-
- ●基本事項の徹底理解と計算力アップ
- まず教科書で全分野の基本事項をしっかりと押さえたい。過去には微分可能の定義が問われたこともある。場合の数・確率は基本の理解が不十分だと大きく点を失うことになる。基本事項を学習した後は、標準的な入試問題集で典型問題を攻略していけばよい。その際に、どのように基本事項が用いられ解法が組み立てられているかを理解するようにしたい。融合問題や新傾向の問題が出題されることも多く、解法のパターンを覚えるだけではそれらに対処できない。また、問題を解くときは自分の手を動かすようにしてほしい。微分・積分に関しては特に計算力をつけておく必要がある。論証や新傾向の問題は、方針の検討などにどうしても時間がかかってしまう。そのため、速やかに計算することが重要となる。
- ●答案作成のトレーニングを
- 基本事項や典型問題の解法を習得した後は、微分法・積分法、確率などの分野を中心に得点力を高めたい。新傾向の問題や思考力の必要な問題も出題されるので、十分な演習をこなし、実戦力を養ってほしい。また問題を解く際には、しっかりと答案を書くようにしよう。答案を書く訓練は、論理力を高め、論証対策にもなる。数学的帰納法・背理法などもその運用に慣れてほしい。
現代文
最近の出題傾向
- ①出題文の重厚長大さこそが神戸大学現代文の特徴
- 大問は1題のみだが、例年思想的なテーマを扱った重厚な長文評論から出題されている。2025年度に出題された文章は、生死をめぐる「ヒトの論理」と「人間の論理」という二重の論理を論じた、4,600字程度の評論であった(2024年度より300字程度減少した)。年度によって多少のばらつきはあるにせよ、相対的に見てかなり難度の高い出題といえる。
- ②設問はオーソドックスな二次型記述・論述問題中心
- 設問は、漢字問題が1問(小問5問)で、説明問題が4問の、全5問構成が定番となっている。説明問題では、本文全体の趣旨に関わるまとめ問題(140~180字ほどと年度によって多少ばらつきはあるが、出題頻度は160字が最も多い)が必ず出題されている。それ以外は文脈読解型の説明問題で、全体の記述量は400字前後である。
2026年度入試予想・対策
- ①出題文の予想と対策
- 2023年度は4,600字程度の「社会論」が、2024年度は4,900字程度の「社会論」が、2025年度は4,600字程度の哲学的文章が出題された。本文量に関しては、多少の例外はあるものの、4,000~5,000字強の長文が出題されている。他大学と比較したとき、こうした「長文からの出題」を無視して対策を立てることはできないだろう。内容に関しては、若干の例外はあるにせよ、基本的には「近・現代の社会/文化状況やそこでの人間の有り様」に焦点をあてた文章を念頭に置くべきだろう。また、難易度的には、前述したようになかなか手強いものではあるが、まったく手が出ないわけではない。各人の読解力のレベルに応じて、標準~難しめのレベルの評論文に、できるだけ数多く取り組んでおくこと。具体的には、市販の問題集や予備校のテキスト、あるいは記述型の模試などを通じて、文章の論の展開の仕方に留意しつつ、文章全体の趣旨を的確に把握していく読み方を身につけていくことだ。焦らず、着実に読解力をつけていこう。
- ②記述・論述問題の予想と対策
- 若干の違いはあるものの、この10年間、設問の構成に大きな変化はない。したがって2026年度も記述・論述問題が中心になるはずだ。まったく手が出ないといった難問・悪問は見られないが、だからこそ、正統的な記述対策をきちんと積み重ねておこう。文脈把握型の記述問題に関しては、傍線部に関連する箇所を、短い字数で的確にまとめる練習を繰り返そう。そのうえで、気をつけなければいけないのは、本文全体の趣旨に関わる問題(通常は問四)である。これに対応するためには、問題演習の際、単に個々の設問を解くだけでなく、文章全体の趣旨を160字程度でまとめる要約練習もやっておくこと。いうまでもないことであるが、過去問の研究をおろそかにしてはいけない。しっかり地力をつけてから、最近5年間ほどを中心に、時間を計って繰り返し取り組んでみること。
古文
最近の出題傾向
近年5年間の出題状況は以下のとおり。
- 2025年度『更級日記』中古・日記・約950字
- 2024年度『俊頼髄脳』中古・歌論・約1,020字
- 2023年度『発心集』中古・説話・約1,650字
- 2022年度『伊勢物語』中古・歌物語・約950字
- 2021年度『平家物語』中世・軍記・約1,320字
出典の傾向:有名作品の説話や軍記、あるいは説話的な文章を主軸とし、中古の物語や日記などの有名出典が交じる。
本文字数:2025年度は平均的な字数だった。おおむね、本文に和歌がない場合に長文化の傾向が見られる。
設問数:おおむね5、6問。
和歌:長らく、本文に和歌があっても和歌に関する出題は軽めだったが、2025年度は和歌に傍線を付した心情説明と、傍線の直前の和歌を踏まえた内容説明が問われた。2024年度には第4句の現代語訳が問われ、2022年度は歌物語からの出題で、和歌の下句についての心情説明と、和歌1首の大意が問われている。和歌に関する出題を視野に入れた学習が望まれる。
2026年度入試予想・対策
主要な設問形式に即して、以下、対策のポイントを示す。
- ①文法問題
- 品詞分解・付属語の識別・助動詞を活用させる空欄補充・敬語の種類と敬意の対象などが問われる。動詞の活用の種類や、助動詞を活用させる空欄補充など、かなり基本的な分野からの出題が予想されるので、万全を期しておきたい。
- ②現代語訳問題
- 3、4箇所。従来はおおむね条件なしの出題にもかかわらず、大学公表の「出題の方針」によれば、前後の文脈を踏まえた解釈を求めているケースもあり、どこまで書き込むかの判断に迷う場合もあったが、近年は設問に指示がつくケースが見られる。
- 2025年度:4 箇所すべてについて「わかりやすく現代語訳しなさい」。
- 2024年度:短い4箇所の現代語訳と、指示内容の具体化を求める現代語訳1箇所。
- 2023年度:4箇所とも条件がつかなかったのは、慣用表現などが眼目で、特に補充を必要としない箇所だったからだろう。
- 2022年度:3箇所すべてについて「わかりやすく現代語訳しなさい」。
- 2021年度:4箇所中1箇所について「具体的な内容を明らかにすること」。
- ③説明問題
-
2、3 問。字数制限のあるものが多い。
- 2025年度:50字以内、60字以内
- 2024年度:50字以内、80字以内
- 2023年度:50字以内、60字以内
- 2022年度:50字以内、40字以内、字数制限なし
- 2021年度:50字以内、60字以内
これらの設問に対応する力を養うためには、本文の正確な解釈に加え、述べたいことを字数内で的確にまとめ上げる表現力が必須である。作成した答案を他者の目になって検討し、曖昧な箇所や誤読されそうな箇所はないかチェックする。正解例を見て素直に納得するだけではなく、各要素が本文のどこを根拠として導き出されるのかを吟味すること。
漢文
最近の出題傾向
- ①史伝の出題が多い
- 過去10年間のジャンルは、2017年度の『太平広記』は伝奇小説、2018年度の『唐摭言』は詩話、2021年度の『夢渓筆談』は随筆だが、2016年度の『史記』、2019年度の『資治通鑑』、2020年度の『貞観政要』、2022年度の『望溪集』、2023年度の『蒙求』、2024年度の『史記』、2025年度の『隋書』は史伝で、近年は史伝の出題率が高い。
- ②語句の読み、書き下し文、現代語訳、説明の問題が定着
- 過去10年間の設問数は4~5、解答箇所は6~8で、問いの種類は語句の読み3~4、書き下し文1~2、現代語訳1~2、説明問題1~2で定着しており、説明問題には50~70字の字数制限があった。
2026年度入試予想・対策
- ①やはり史伝の出題が予想される
- 2026年度の入試は、最近の傾向を踏まえれば史伝または小説などのストーリー性のある文章が出題される確率が高い。また文字数は140~200字程度の比較的短い分量の文章が予想される。問いの種類は語句の読み、書き下し文、現代語訳、そして字数制限のある内容説明や理由説明が予想され、この点でも過去の入試問題と大きな変更はないであろう。史伝など物語性のある文章を解く際には、登場する人物の関係を押さえ、前後の文脈から各文の主語や指示語、省略語の内容を補うことで正確に訳し、文章全体の展開や趣旨を的確に読み取る力が求められる。
- ②白文を読む力が必要
- 神戸大学の漢文では、現代語訳と書き下し文の問題を中心に傍線部が白文で出題される傾向がある。年度によっては傍線部に返り点だけがついていたり、また送り仮名もついていたりした例もあるが、傍線部が白文で出題されるのは神戸大学の漢文の大きな特徴である。そのため、日頃から返り点・送り仮名のついていない白文を読む力を身につけておく必要がある。
- ③基本知識を押さえ、書き下し文と現代語訳をつくる
- 学習対策としては、まず基本を身につける必要がある。書き下し文や現代語訳の問題には基本句形が含まれることが多いので、重要語の読みや意味から基本句形までの漢文の基本的な知識を身につけたうえで、基本句形を含む例文を用いて句形の読み方と訳し方に習熟しておく。また、白文を読みこなす際には、重要語や基本句形の知識に加え、語順を基に文の構造を把握することにも注意して練習してほしい。
次に過去問や記述式の問題集などを解くことによって多くの文章を読解する練習を積むこと。問題を解くときには、問いの解答を確認して終わりにするのではでなく、問題文全体の書き下し文と現代語訳をつくってみることが大切である。次に内容説明や理由説明の問題は、文章中からポイントとなる箇所を探し出し、その内容を直訳するだけではなく簡潔に要約し直すことで、最終的に制限字数内に収まるよう要領よくまとめる訓練をしておこう。
物理
最近の出題傾向
- ①出題分野は3年変わらず、テーマも大きく変化なし
- 出題される大問数は例年3題である。「力学」と「電磁気」の各分野から1題ずつ出題され、残りの1題は「波動」「熱力学」「原子」の分野から選ばれるが、「原子」はここ10年で1度(2018年度)しか出題されていない。なお、2023~2025年度と3年続いて「波動」分野からの出題が続いた。出題されたテーマを見ていくと、「力学」分野では円運動、2物体の衝突や放物運動が、「電磁気」分野では荷電粒子の運動やコンデンサーがよく出題されている。
- ②出題形式は他大学と異なる
- 大問1題あたりの小問数は4~6問程度であり、ほとんどの出題は問い形式である。解答の形式は記述式で、解答の導出過程を書く設問が多い。また、グラフなどを描かせる設問もよく出題される。解答する際には、その過程で使用する物理量を自ら定義する必要がある。
- ③難度は低め
- 問題の難易度は平易なものが多いが、標準的なレベルの問題も含まれる。入試問題として典型的な問題だけでなく、しっかりと問題文を読み込んで、正しく状況を理解しなければ解くことができない問題も出されている。
2026年度入試予想・対策
- ①物理の基本事項を完全に理解する
- 比較的平易な難易度の問題が出題される。解答するために必要な知識はそれほど高度なものを要求されないが、物理の基本事項が正しく理解できているかどうかを、丁寧に問う問題が多い。したがって、教科書をきちんと読み、各分野の様々な定義を正しく理解し、物理の基本事項を着実に身につけておかなければならない。
- ②読解力を身につける
- 平易な問題とともに、いわゆる典型的な入試問題とは異なる問題も出題される。こちらも高度な知識は必要とされないが、与えられた状況を正しく理解するためにかなりの読解力を要求される。グラフの読み取りも含め、問題文が伝えようとしていることを妥協せずに理解しようとする意識を、常日頃から持ち続けることが必要である。
- ③普段から記述形式で解答をつくる
- 神戸大学入試の最大の特徴は、解答過程を記述する問題が出題されることにある。「答え」を得ること自体はできたとしても、その解答の過程を、論理的にわかりやすく、そして試験時間内に「答案」としてまとめることは、そうたやすくできることではない。したがって、普段から解答の過程を記述する訓練をしておくことが必要不可欠である。具体的には、初めに、解答に使用する文字を定義し(このとき図などを用いるのもよい)、式を立てる根拠となる法則名など(運動量保存則より、など)を明記した後にその式を書く。次にその式を用いて導く要点だけ示して答えを書く(計算過程を詳細に記述する必要はない)。この手順を守りながら、答案を書く訓練を積むことが、記述力を身につける最も基本的かつ効率的な方法である。問題集などを用いて行う問題演習を通して、この方法を習得してもらいたい。
化学
最近の出題傾向
- ①形式や出題分野のバランスは変わらず
- 例年、60分75点の配点で、大問4題が出題される。2025年度の出題内容は、大問ⅠはH2Oの状態図とその関連、大問Ⅱは二酸化炭素に関する知識、炭酸の電離平衡、アンモニアソーダ法など、大問ⅢはC5H6O4の構造決定、大問Ⅳは天然繊維と化学繊維であった。出題分野は、大問Ⅰは理論、大問Ⅱは無機および理論、大問Ⅲ・Ⅳは有機(Ⅲは低分子、Ⅳは高分子)で、出題分野のバランスも出題される大問順も2024年度とまったく同様であった。
- ②分量や難易度も変わらず。
- 2025年度の設問数は19で、2024年度(設問数22)や2023年度(設問数23)に比べてやや減少したように見えるが、複数の問いを含む設問が多く存在するため、総量としてはほぼ例年どおりである。計算を含む設問数も4(2024年度は5、2023年度は6)と例年よりも少ないように見えるが、4つの問いを含む設問があり、やはり全体として例年どおりである。難易度も特に変化は見られず、例年どおり標準~やや難のレベルであった。
- ③計算過程と論述が出題された
- 2025年度は久しぶりに、計算過程を示す設問が出題された。また、2023・2024年度と出題されなかった論述問題が出題された。
2026年度入試予想・対策
- ①まずは、頻出の理論分野を押さえておこう
- 例年、大問4題のうち2題は理論分野から出題され、1題は無機を含む(場合によっては無機分野が中心で理論を含む)出題であるケースが多い。近年は、2021年度(反応速度と化学平衡、電気分解)、2022年度(沸点上昇、溶融塩電解)、2023年度(電気分解、金属イオンの分離と溶解度積)、2024年度(気相平衡、電離平衡、熱化学、電気分解)、2025年度(物質の状態、ヘンリーの法則、電離平衡)など、ほぼ理論の全範囲から出題されている。したがって、理論分野全体を幅広く演習しておく必要がある。特に、平衡、熱化学、気体ではやや難度の高い問題が出題される傾向が見られる。また、電気分解の問題も頻出している。まずは、これらの単元を重点的に演習しておきたい。
- ②有機分野は、エステルなどの構造決定の出題頻度が高い。高分子はやり残しのないように
- 大問Ⅲでは、脂肪族または芳香族の化合物が扱われることが多く、内容は、構造決定や反応経路に関するものが多い。特にエステルが扱われることが多い。難易度はほとんどが標準的で、高校レベルを超える難問や奇問は出題されない。したがって、過去問や標準問題の徹底演習が最も効果的な対策である。ただし近年、異性体、特に立体異性に関する関心が高まっているので、そのことには十分に留意しておきたい。
大問Ⅳでは、天然または合成高分子が出題される。特に、アミノ酸やペプチドおよびタンパク質に関する出題頻度が高く、次いで糖が多く出題される。いずれも難度はそれほど高くなく、教科書程度の知識を身につけておけば十分に対応できる。合成高分子化合物などは未習であるために得点できない場合が多いので、浅くても一通り学習してやり残しをつくらないことが大切である。 - ③無機分野の対策も十分に行っておこう
- 無機の問題は、一部に理論分野を含んで、あるいは理論分野の一部に含まれて出題されることが多い。配点はそれほど多くはないが、当落線上では数点で順位が大きく変わるので、油断して失点しないよう万全の対策をしておきたい。教科書中心のまとめと標準問題の演習で十分に対応できる。
- ④計算過程や論述問題の対策をしておこう
- 計算過程を求められることがある。理路整然としていなくても自力で解いたことがわかる答案が書ければよい。有効数字が2桁の場合も3桁の場合もある。日頃から注意しておこう。
論述は字数制限がある場合も、ない場合もある。必ず使うべき化学用語があるので、それを見つけることが大きなポイントとなる。過去問などで練習する効果は大きい。
生物
最近の出題傾向
- ①論述問題が多い
- 大問4題構成であり、いずれの大問にも1~数問の論述問題が含まれる。年度によって指定字数は異なるが、30字程度のものもあれば100字を超すものもあり、計10問程度出題される。指定字数の合計は、ここ数年300字程度に落ち着いていたが、2024年度は500字程度、2025年度は750字程度に増加した。出題テーマは、以前は既存の内容を題材とする問題が多かったが、2025年度は新規のテーマを扱う問題も多く出題された。生物用語を問う問題も毎年出題されている。
- ②遺伝(遺伝計算)・進化・生態分野が頻出
- 遺伝(遺伝計算)の問題が出題されやすい。年度にもよるが、かなり時間がかかる本格的な問題が出題される場合もある。2025年度も小問1問が出題された。高得点をめざすためには、遺伝(遺伝計算)の対策が必須である。また、進化・生態分野が、毎年大問1題以上出題されている。
2026年度入試予想・対策
- ①様々なパターンの標準的な問題を、もれなく演習しよう
- 神戸大学の入試問題に頻出分野はあるが、一方で、出題が極めて少ない分野はあまりない。したがって、苦手分野をつくらないような学習が必要である。また、空欄補充、選択、論述、計算など、様々な形式の小問が出題されるので、特定の形式の問題を避けたりすることなく、あらゆるタイプの問題をまんべんなく練習しておこう。ただし、データ量が多い実験考察問題が出題されることはあまりないので、そのような問題の演習に時間を割くよりは、標準的な問題を何度も解き、それらを確実に解き切る力を養う、といった、地道な学習が求められる。
また、試験時間は60分であり、そのなかで10問程度の論述問題を含む20数問を解き切るためには、論述問題の練習が必須である。神戸大学で出題される論述問題は、難易度は標準程度のものが多いが、論述問題を解くのに慣れていないと、解答用紙上で一部を消したりしながら解いてしまい、思いのほか時間がかかってしまうことがしばしばある。本番でこのようなことにならないために、論述問題の練習の際には、書く内容を明確にすることと、それを速く書き出すことの両方を意識しよう。 - ②遺伝(遺伝計算)・進化・生態分野は特に念入りに学習しよう
- 直近の8年間では、遺伝(遺伝計算)は2019・2022・2023・2025年度に、進化は2019~2024年度に、生態は2019~2023年度、および2025年度に出題されている。これらは頻出かつ差がつきやすい分野である。特に、遺伝(遺伝計算)には様々なパターンがあり、一朝一夕には実力がつかないので、時間をかけ、様々なパターンの問題を解く練習を積んでおこう。また、大学によっては進化・生態があまり出題されない場合もあるので、これらの分野は勉強がおろそかになりがちであるが、神戸大学を受験する受験生は、特に意識してこれらの分野の問題を繰り返し練習しよう。なお、これら以外の頻出分野としては遺伝子があり、直近8年間では、2018・2020・2021・2023・2024年度に出題されているので、こちらも意識して学習しておこう。
特派員の声 ~合格の秘訣!!~
国際人間科学部 1年 りこ特派員
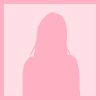
- 共通テストで高得点を目指す
- 共通テストでできるだけバランスよく確実に点数を取れるようにしておくことです。
共通テストで転んでしまうと自信を失ってしまうので、しっかり対策しましょう!!
法学部 1年 うりぽん特派員
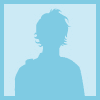
- 数学と向き合う
- 私は数学をずっと苦手科目としていました。
国公立大学二次試験前まで苦戦していましたが、自分が解ける問題は取り残さないよう心がけていました。まずは自分が解けるものだけでいいので、一歩ずつ着実にポイントを押さえていきましょう。



