広島大学 学習アドバイス
河合塾講師からの学習アドバイス
教科別の学習対策について、河合塾講師がアドバイスします。
※出題範囲は募集要項、大学ホームページ等で必ずご確認ください。
英語
最近の出題傾向
試験時間は120分で、2021年度から大問4題の出題が続いている。[Ⅰ]は要約問題、[Ⅱ]は長文総合問題、[Ⅲ]・[Ⅳ]は自由英作文。客観式の問題も含むが、記述問題中心で記述量は多い。
- ①要約問題
- 課題英文を指定字数の日本語で要約するもので、2025年度は「メディアで用いられる言語と平和指数の関係」を論じた400語程度の英文の5つの段落を各60字以内で要約することが求められた。これは2023・2024年度と同じ形式・分量だが、2022年度は4つの段落を各100字以内、2021年度は5つの段落を各30字以内で要約する問題であった。
- ②長文総合問題
- 関連したテーマの2つの英文を読み、内容説明、空所補充、抜き出し問題などに解答する問題で、2つの英文の関連性を理解し、情報を複合的に把握することが求められる。2025年度は「民間企業による月面探査」について書かれた2つの英文(445語+718語)が出題された。
- ③自由英作文
- 100語程度の意見論述問題([Ⅲ])と、100語程度でグラフの傾向と分析を述べる問題([Ⅳ])が出されている。2025年度は、[Ⅲ]が「仕事の未来の変化」について与えられた条件を基に自分の意見を述べる問題、[Ⅳ]が「音楽媒体の売り上げの変化」を示したグラフの傾向と分析を述べる問題。
2026年度入試予想・対策
2026年度も2025年度と同様の形式・分量・難易度の出題 が続くと考えられるが、以下のアドバイスを基に柔軟に対処できるように準備しよう。
- ①要約問題
- 広島大学の要約問題は、(a)「文章全体を要約する問題」と(b)「指定されたポイントに沿ってまとめる問題」に大別できる。(a)の形式はさらに、(a-1)「文章全体をまとめて要約する問題」と(a-2)「段落ごとに要約する問題」に分けられる。2021年度以降は(a-2)の形式の出題が続いているが、どの形式の問題が出題されてもいいように練習しておくことが必要である。
なお、要約問題とは指定された字数に応じて情報の重要度を比較・取捨選択してまとめる問題なので、1つの文章を50・100・200字と字数を変えて要約する練習をすることで、情報の取捨選択の訓練にもなる。 - ②長文総合問題
- 関連した内容の500~700語程度の英文が2つ出題され、2つの英文の内容を総合的に理解して解答する形式で、この形式では従来の語彙力、文構造分析力、内容理解力に加えて、2つの資料の情報を関連づけて分析し、一方の英文の内容がもう一方の英文の内容とどう関連し、どのように言い換えられたり対比されたりしているのかといったことにも注意しながら解答する練習が必要である。
- ③自由英作文
- 例年、(a)「自分の意見を述べる問題」と、(b)「グラフ・表を説明する問題」の2種類が出題されている。今後もこの形式の出題が続くと考えられるので、両方の形式に備えておく必要がある。また、苦手なテーマが出されても対応できるよう、多様なテーマの課題に取り組み、可能であれば添削を受けよう。
(a)の意見論述型の自由英作文では〈意見→理由→具体例→結論〉といった展開が一般的だが、語数が限られているため、論じたい内容を絞って「狭く深く」述べることが必要である。
(b)については「増加」「減少」「最大・最小」といったグラフや表の内容を説明するために必要な英語表現の知識を身につけ、文法的に正しく、かつ内容を的確にまとめて伝える力を養おう。過去にはグラフや表の背景にある社会情勢を踏まえて解答する問題が出されたこともあるため、日頃から社会について一般的な知識を蓄積し、それを英語でどう表現するかを調べたり考えたりすることも必要である。
文系数学
最近の出題傾向
- ①標準的な問題から難度の高い問題まで出題される
- 試験時間は120分で、2017年度から大問4題の出題が続いている。解答はすべて記述式で、出題範囲は、数学Ⅰ・Ⅱ・A・B・C(Aは図形の性質、場合の数と確率、Bは数列、Cはベクトル)である。2025年度は、2024年度に比べて分量はやや増加し、難易度もやや難化した。出題形式に関しては例年どおり各大問とも3問以上の小問に分かれていた。2024年度は4題すべてが単独の分野からの出題であったのに対して、2025年度は4題中3題が融合的な問題であったことが特徴的であった。
- ②迅速な計算力、融合問題に対応するための総合力が必要
- 出題は、数学Aの確率と、数学Ⅱ・B・Cが中心であり、特にここ数年は数学Aの確率、数学Ⅱの微分・積分、数学Bの数列の分野を中心とした出題が続いている。小問も多く計算量もかなりのものになるため、いかに手際よく処理するかが重要となる。また、年度による差もあるが、2分野以上にまたがる内容を含んだ融合的な問題が多く出題されることもあるため、全分野にわたる幅広い知識が必要である。
2026年度入試予想・対策
- ①融合問題の練習と計算力の強化をしよう
- 2020年度からは融合問題の減少傾向が見られ、さらに、ここ数年は難易度も易化傾向にあったが、2025年度は2024年度に比べて融合問題の出題も増え、やや難化した。
過去の出題傾向から考えると融合問題への対策はしっかりと取り組んでおきたい。また、教科書や共通テストの問題と比べると、煩雑な計算も多いため、普段から計算の工夫、最後まで計算をやり切る粘り強さを養うことが必要である。
入試対策としては、出題分野がほぼ固定化していることから、過去の出題傾向を分析し、頻出分野を重点的に学習するのがよいだろう。 - ②数学Ⅰ・A対策
- 数学Ⅰは、共通テストを体験している受験生にとっては特別な対策は必要ないが、データの分析は2016・2024年度に出題されているため注意が必要である。数学Aでは、確率は2024年度を除いて毎年出題され、数列の和や漸化式との融合問題もよく出題されている。このようなタイプの問題も含めて十分練習しておく必要がある。また、整数の性質については、入試の出題範囲に指定されていないが、小学校や中学校で学習する「約数や倍数」「素数」「割り算における余り」などの知識は必要である。過去の入試でも、数列や確率の問題のなかで、整数に関する性質が用いられることが多いため、このあたりに目を向けて学習しておこう。
- ③数学Ⅱ対策
- 数学Ⅱは、特に微分・積分が頻出である。図形と方程式や三角関数、指数・対数関数などの他分野との融合問題が多く出題されている。様々な分野との融合問題を中心に練習しておこう。三角関数、指数・対数関数については、大問としての出題は少なく、設問の一部として用いられることが多い。基本的な公式は誤りなく使えるように確認しておこう。
- ④数学B対策
- 数列はほぼ毎年出題されている。確率や整数、三角関数、対数関数などの分野との融合問題が多く、難度の高い問題が出題されている。どの分野と融合されても対応できるように、他分野の知識をまんべんなく習得しておこう。
- ⑤数学C対策
- ベクトルは近年大問としての出題は少ないが、油断せずに対策しておきたい重要分野である。ベクトルの内積に関する問題が多いので、このあたりの内容を中心に対策しておこう。
- ⑥過去問を時間をかけて解こう
- 全体的には標準レベルだが、一つひとつの設問は決して易しいわけではない。分量も多く、計算力も要求される。出題傾向を分析し、それに合わせて、頻出である典型問題の練習を繰り返すことが必要である。また、過去問をできるだけ多くの時間をかけて解くことで融合問題に慣れていこう。
理系数学
最近の出題傾向
- ①数学Ⅲ・Cの割合は多く、難度の高い問題も出題される
- 試験時間は150分で、大問が5題出題される。解答はすべて記述式で、出題範囲は、数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B・C(Aは図形の性質、場合の数と確率、Bは数列、Cはベクトル、平面上の曲線と複素数平面)である。2025年度は、2024年度に比べて分量・難度ともに大きな変化は見られなかった。出題分野については、数学Ⅲの極限、微分・積分が3題、数学Cの複素数平面が1題、数学Ⅱ・Bの範囲からは1題の出題であった。2024年度は数学Ⅲ・Cからの出題が5題中2題であったのに対して、2025年度は5題中4題であり、数学Ⅲ・Cの比重が高かったことが特徴的であった。
例年、標準的な内容の問題だけでなく、数学の総合力を試すような融合的な問題も出題されている。また、年度による差もあるが、大問5題に対する数学Ⅲ・Cの割合も多いことが特徴に挙げられる。 - ②正確かつ迅速な計算力が必要、新傾向の問題も目立つ
- 出題は、数学Ⅲの微分・積分、数学Aの確率、数学Bの数列、数学Cの複素数平面が中心である。小問数が多く、計算量が多いため、いかに手際よく処理するかが、広島大学の理系学部で合否を左右する大きなポイントとなる。また、近年は過去の広島大学の入試では出題されなかったタイプの問題が出題されるようになってきたため、過去に出題されたことがないタイプの問題も積極的に練習しておきたい。
2026年度入試予想・対策
- ①頻出分野を中心に幅広い学習をしよう
- 広島大学の理系学部の入試において、出題される出題分野はほぼ固定化している。2026年度においても、数学Ⅲの微分・積分、数学Aの確率、数学Bの数列、数学Cの複素数平面を中心に出題されるだろう。また、数学Ⅲの微分・積分や数学Cの複素数平面は数学Ⅱの図形と方程式との融合問題がつくりやすい。これら微分・積分、複素数平面、確率、数列および図形と方程式の5分野を中心に重点的な学習を進めるのがよいだろう。
- ②数学A対策
- 確率は、数列の和や漸化式、無限級数などの数列の内容を含んだ融合問題が出題され続けている。過去問の類題演習をしておこう。また、整数の性質については、入試の出題範囲に指定されていないが、小学校や中学校で学習する「約数や倍数」「素数」「割り算における余り」などの知識は必要である。過去の入試でも、数列や確率の問題のなかで、整数に関する性質が用いられることが多いため、過去にどの分野でどんな形で使われてきたかを見ておくとよい。
- ③数学B対策
- 数列は、一般項やその極限、無限級数を求めるような数列自身をテーマとする問題、確率や整数など他分野との融合問題など様々な形で出題されている。過去問を参考にしながら、類題演習を行うのが望ましい。
- ④数学Ⅲ対策
- 微分・積分は、関数を微分して増減を調べ、グラフの概形を考えたり、平面のある部分の面積を求めたり、不等式を証明するパターン的な微積融合問題が出題されることが多い。基本的には、標準的な微積融合問題を繰り返し解くことで、正確かつ迅速な計算力をつけておけばよいだろう。
- ⑤数学C対策
- 複素数平面は、毎年出題されているわけではないが、他大学で出題された様々な問題にも目を通しておくとよい。ベクトルは、他分野との融合が比較的少ない分野なので、内積の内容を含む標準的な問題を練習しておけばよいだろう。
- ⑥過去問を分析し、これからの方針を立てよう
- どういう問題が頻出で、どのような形の融合問題が出題されているのかを、過去問を実際に解いて確認しよう。その際、年度ごとではなく、分野ごとにまとめて解いていくことで各分野の出題傾向が十分理解でき、これからどういう勉強をしていけばよいかの方針が立てられるだろう。
現代文
最近の出題傾向
- ①全体としてやや易化
- 2025年度、現代文は例年にない構成に。全学部共通問題のⅠが、歴代続いていた評論ではなく随筆となる。したがって現代文3題型(法・医・歯・総合科学部)では、ⅠとⅢが随筆となった。各問題はⅠ随筆:島田潤一郎「大学の教室で」、Ⅱ小説:古谷田奈月『風下の朱』、Ⅲ随筆:貴戸理恵『「コミュ障」の社会学』。ⅡとⅢの構成は例年と変わらないが、Ⅰが随筆となり随筆が計2題となる(新課程の影響と見られるが、2026年度以降の構成は不明)。
本文の分量は、Ⅰ:5,380字(2024年度比3,100字増加)、Ⅱ:4,050字(同330字増加)、Ⅲ:2,050字(同1,040字減少)。全体として2024年度より約2,400字増加し、3題の本文総字数は11,480字と、例年どおりの長さとなった(2024年度が大幅に減少していた)。
設問の記述量は合計で1,300字程度と2024年度より減少したが、従来の字数の範囲に収まっている。設問総数は21問とほぼ例年どおり。設問の種類は、広島大学の基本である①漢字の書き取り、②論述問題は例年どおりだが、③抜き出し問題は1問に減少した(例年、計2~5問程度あり)。字数制限つきの論述問題は150・100・60字と計3問。制限のない記述は25~170字程度の幅で出題された。また、小説で擬態語を入れる空欄補充問題が出題された。
本文の読みやすさや設問の易化を踏まえると、全体の難易度は易化したといえる。 - ②基本的な設問
- 例年どおり、本文に書かれている内容を正しく読解し設問の意図を理解したうえで、それに適切に対応するという現代文の基本的な解法の力を問う出題である。
2026年度入試予想・対策
- ①頻出作者、幅広いジャンルからの出題
- 過去の出題傾向の連続性を踏まえると、2026年度も、Ⅰ(共通問題)評論、Ⅱ小説、Ⅲ随筆の3題構成が予想される。しかし2025年度のように随筆が複数出題されることも視野に入れ、随筆や随想的な評論についても読み慣れておきたい。
また、出題される内容や作者については、自然科学系の文章がまれなことや、女性作家の作品(小説・随筆)が多いという傾向はあるものの、取り上げられる筆者や作家の多彩さ、文章内容の多様さが大きな特徴といえる。以上のことから、随筆を含め普段から多種多様な文章に慣れておく必要があるだろう。 - ②(原則は)基本的な出題パターン
- 解答形式は、漢字の書き取り、抜き出し、論述の3つに大別できる。個々の設問については、文脈の読解に関わるもの、全体の主旨の読解に関わるもの、とあり、原則基本的な問題だが、後者の場合は長い論述となり難しめの設問となる。また、設問の多くは本文中の語句を用いて記述することが可能だが、小説や随筆では自分の言葉で答える必要がある設問も出題される。これは受験生の間で差がつく設問であり、十分な対策が必要となる。
なお、設問の多くは本文中の語句を用いて答えることができるが、まれに自分の言葉で答えさせる設問も出題される。いずれにせよ、文章を正確に読む、傍線部前後の文脈を押さえる、といった基本的な読解を試す設問であると考えておいてよい。 - ③正確な読解と記述の練習が重要
- 評論だけでなく随筆も含めて様々な文章に親しんでおくことが大切である。文章を自己流に読みがちな人は、本文に即して筆者の主張を正確に理解することを心がけたい。問題集や新書などで3,000~4,000字程度の文章を一定時間内に速読し、全体の構図や主旨をつかむ練習をしておくこと。記述量の多さに対しては、何よりも「書く」ことが対策となる。問題集や過去問を使い「書く」練習を積み重ねてほしい。
古文
最近の出題傾向
- ①出典・難易度・内容量
- 2025年度は、平安時代の作り物語『堤中納言物語』からの出題だった。平安時代の同ジャンルからの出題は、2008年度『浜松中納言物語』以来。広島大学は、長年、近世(江戸時代)と中世(鎌倉・室町時代)の作品が交互に出題されており、2025年度は十数年ぶりにその傾向から外れた。近年は、評論や紀行文など受験生になじみの薄い文章が多く、読解に労を要したが、2024年度の軍記物語『義経記』と続き、2025年度も有名出典からの出題で、文章自体が読みやすく取り組みやすい内容で、難易度は易化傾向にあるといえる。
内容量は『堤中納言物語』は約1,200字。例年1,000~1,300字程度であることから、傾向に添った分量だった。 - ②設問の記述量
- 広島大学では、例年50~100字と、重厚な字数指定のある説明問題が複数見られたが、2025年度は50字が1題、そのほかの説明問題も解答欄が1行程度のものが2題と、記述量の減少が特徴的だった。
2026年度入試予想・対策
- ①時間制限を設け、長文の記述問題に慣れる
- 例年の傾向を踏まえ、1,000字以上の長文は覚悟しておくこと。そして、近年記述量が減少傾向にあるとはいえ、20~100字という字数制限つき、または字数制限こそないが、同等の分量の記述説明問題は必ず複数出題されると想定しておいてほしい。理由・心情説明を中心に、問われるかたちは様々だが、レベルは標準的なものである。特に、文章全体を見据えてまとめていくような問題に対応するために、事前に十分な練習を繰り返しておきたい。また、直前期には、古文は30~35分に制限時間を設定し、時間内にすべての設問を解き切る訓練が必要である。
- ②基礎知識の確認
- 例年、現代語訳と文法問題は必ず複数箇所出題される。事前準備が可能な基礎知識の問題こそ、確実に得点に結びつけたい。文学史は、2021~2025年度までの5年間で、2024年度を除き毎年出題されている。万全の対策が必要である。
- ③和歌の対策
- 和歌に関しては、掛詞や枕詞などの修辞法の知識を問うものや、和歌の現代語訳だけでなく、和歌の解釈を通じて登場人物の心情や立場などを本文全体から読み取って説明するような設問も出題される。それは基本事項を押さえたうえでようやく踏み込める領域でもあるため、余裕のあるうちに修辞法などを攻略し、解釈問題に時間を割いてほしい。
- ④複数テクストの設問
- 共通テスト導入後の2021~2023年度までの数年間、広島大学でも複数資料を整理し関連づける設問が出題された。今後も出題されるかもしれないので、過去問を解いて対策をしておくとよい。
漢文
最近の出題傾向
- ①本文は多様
- 本文のジャンル、分量や難易度には一定した傾向がないので要注意である。2025年度は入試頻出出典『説苑』から出題された。「愚公之谷」のことを桓公から聞いた管仲が自らの政治を省みる話で、過去に何度か入試出題歴がある。
- ②文法力と読解力を問うオーソドックスな設問構成
- 2025年度は設問数8で、語の読み、書き下し文、日本語訳、理由説明、省略された語の抜き出し、内容説明が問われた。記述の総量は例年どおり多めである。客観型の設問は2つ(理由説明と内容説明)だが、そのうちの内容説明の設問が解きにくく、高い読解力が求められている。様々な設問で漢文の学力を問い、全体として、受験生が本文を正しく理解できたかどうかを確認する設問構成に変化はない。
2026年度入試予想・対策
- ①本文内容は予測困難
- 出題傾向が一定しないため、何が出てもおかしくないと心得て準備すべきである。漢詩と散文を組み合わせるなど、複数の漢文を提示する形式の場合もある。2021・2022年度のような300字を超える長文の出題も念頭に置いておきたい。過去問などを演習する際に、常にスピードを意識して、どんな文章が出題されても動じることなく最後の設問まで解き切る姿勢と力量を身につけて、本番に臨んでもらいたい。
- ②設問構成は定番
- 設問の形式や構成は毎年ほぼ一定している。文法や重要単語などの基礎知識を問う設問として、語の読みや意味、書き下し文、日本語訳、訓点付与など定番のものが3~4問、読解を問う設問として、内容・理由・心情・趣旨・人物像・詩の主題といった本文内容に即した説明問題などが3~4問で組み立てられる。前者では、2025年度は語の読み、日本語訳、書き下し文が出題された。こうした定番の設問に対応できる基礎知識を習得することが第一の学習目標である。
- ③文法に習熟し、記述力をつける
- 漢文の基礎知識とはやはり語彙力と文法である。語彙は単語集などを活用しながら漢文の重要単語を暗記し、文法は重要句法(構文)を、書き下し文や現代日本語に直すなどのトレーニングを繰り返すことで、しっかりと習熟することが肝要である。語彙力を高め文法をよく理解し、まずは定番の設問で着実に得点を積み上げよう。そのほかの説明問題は、本文を精読し、設問の意図をつかみ、本文中から解答の根拠を見つけること、キーワードやキーセンテンスを捉えること、場面を想像すること、人物関係を正しくつかむことなどが求められる。問題演習を通してこうした作業に慣れ、精度の高い解答を作成する力をつけるよう精進してほしい。
- ④様々な漢文に親しむ
- 文法は文章を正確に読解するための手段であり、文法力は数多くの文章を読むことで強化される。幅広く様々な漢文を読んで漢文に慣れ親しみながら読解力を高め、設問を解くことで文法力を鍛えていくことが不可欠である。
物理
最近の出題傾向
- ①3 または4 分野からの出題
- 2025年度は、第1問は力学、第2問は熱力学、第3問は電磁気であった。一方、2024年度は、第1問は力学、第2問は熱力学、第3問は電磁気、第4問は波動であり、2023年度は、第1問は力学、第2問は波動と熱力学、第3問は電磁気であった。2024年度までは試験時間は60分であるが、2025年度からは75分に変更された。原子分野は近年出題されていない。
- ②物理法則の理解度を測る工夫された内容
- どの問題も標準的なレベルの出題が中心である。ただし、問題集などでしばしば見かけるような典型問題の占める割合は多いとはいえない。高度な知識は要求されないが、設問の物理状況を正しく把握しているか、与えられた仮説の物理的妥当性を検証できるか、など理解の深さを測るよう工夫された出題である。また、計算力を要する問題も随所に見られる。
- ③記述、空所補充、語句選択、グラフ選択・描図など多様な解答形式
- 力学・電磁気は記述式中心であり、波動・熱力学は空所補充形式となることが多い。記述式ではしばしば「導き方も示せ」と指示される。また、グラフ選択や記号選択において理由の記述を求められることもある。
2026年度入試予想・対策
- ①分野別出題傾向と予想
-
- 〈力学〉
- 2025年度は、衝突・単振動が出題された。前半は、完全非弾性衝突により一体となった物体がばねの力を受けて単振動する様子について、衝突直後の速度や運動方程式を問われ、衝突・単振動の基本的理解を確認する内容であった。後半は、ばねにつながれた2物体の運動を相対運動の視点から考える問題であり、少し難度が高い。さらに、運動量保存則と力学的エネルギー保存則を連立して解答する問題もあり、計算力が試された。2026年度に向けては、円運動を中心とした総合問題を警戒したいが、いずれにせよ物理法則の理解の深さが問われるであろう。
- 〈熱力学・波動〉
- 2025年度は、熱力学分野のみが出題され、熱量計をテーマとした、熱量の保存に関する内容であった。物理基礎分野の基本事項を押さえておけば十分に解答可能な内容だったが、文字式だけでなく、数値計算させる設問も多かった。今後は、熱力学・波動の両分野から出題される可能性も高いであろう。ただ、従来この2分野は、比較的典型的な設問が多く出題されており、学習した成果が反映されやすい分野であったことにも注意したい。気体の状態変化、光の屈折などの定番の問題に取り組んでおきたい。
- 〈電磁気〉
- 2025年度は、電流がつくる磁場と電磁誘導が出題された。前半は、電流がつくる磁場と、磁場中を流れる電流が受ける力についての設問であり、典型的な設問といえる。後半は、時間的に変化する磁場による電磁誘導についての設問が中心であり、丁寧な誘導に従って解答する必要がある。2026年度は、コンデンサーからの出題の可能性が高いと予想するが、電磁誘導に関する出題にも備えておくべきであろう。
- 〈原子〉
- 全国的に原子分野の出題が増加している傾向からも、原子分野からの出題は今後ありうる。少なくとも放射性崩壊やボーアの水素原子模型などの定番の問題については練習しておきたい。
- ②入試対策
- 解答形式に慣れるためにも、少なくとも過去5年分の広島大学前期試験の問題は解いておこう。標準レベルの問題集に取り組むことも有益である。ただし、問題を解くだけでなく、物理法則の意味を確認する、問題文から物理状況を正しく読み取り物理公式の適用条件の可否を判断する、など理解を深める努力を積み重ねたい。典型問題の解法を暗記するだけでは広島大学特有の「理解の深さを問う」問題に対処できない。読解力・洞察力を鍛えよう。また、記述問題に対処するために、日頃から解答としての文章・計算を簡潔にまとめるよう意識しておくとよいであろう。
化学
最近の出題傾向
- ①分量・難易度
- 大問数は、例年4題であり2025年度は、比較的取り組みやすい問題も多く出題されたが、試験時間が60分から75分と変更になったためか分量は増加した。難易度は、標準的な問題が多く、教科書の「参考」「発展」まで十分に理解していれば、解答できる問題がほとんどである。発展的な内容も出題されることがあり、高度な思考力を要する問題も出題されている。また、年度によっては難易度の差は大きく、解答する順番などを工夫する必要がある。
- ②総合・融合問題が多い
- 総合・融合型問題の形式で全分野から広く出題されている。また、一部には分野を絞った難しい問題も出される。総合・融合型問題は、設問ごとに必要な知識を素早くまとめて解答をしなければいけないため、演習量の差が解答時間の差として表れる。
- ③論述問題も出題
- 例年、20~40字程度の論述問題が出題されている。文字数があまり多くない論述問題なので、要点(キーワード)を押さえた簡潔な論述が要求される。
2026年度入試予想・対策
2026年度入試では、試験時間が75分となって2回目の入試であり、2025年度と同様の分量となることが予想される。
- ①分野別の出題傾向について
-
- 〈理論分野〉
- 45%程度出題される。化学反応と熱、酸塩基、酸化還元、気体、反応速度、平衡が頻出。酸化還元は無機各論や反応速度と組み合わせて出題されるケースもある。分野を絞った出題では、難しくなることもある。2025年度は、発展的な内容も出題されたので、過去問よりやや難度の高い問題の演習をしておきたい。
- 〈有機分野〉
- 40%程度出題される。総合問題としての出題が多く、性質や反応から化合物や構造を推定する問題が中心になる。近年は問題文から部分構造を推定し、それに合致する異性体を解答する問題や、糖、アミノ酸を含む構造決定も出題されている。有機化合物の性質と反応は、個別ではなく、官能基ごとにまとめて理解することが大切である。また、糖、アミノ酸・タンパク質、合成高分子化合物などでは細かな知識を問われることもあり、計算問題は難しくなることもあるので要注意である。
- 〈無機分野〉
- 15%程度出題される。理論分野との融合問題が多い。無機分野のみの出題では、金属の単体やイオン、気体の発生と性質などが主なテーマ。対策としては、代表的な物質の性質と反応を整理し、演習を通じて、知識を活用する訓練を積んでおくことである。また、理論分野と関連したかたちでの出題が多いので、物質の性質などを酸化還元や酸塩基と結びつけて理解しておくことが大切である。
- ②入試対策
- 理論分野では、原則や法則に基づく計算や、現象を理解することが求められる。有機・無機分野では、構造や化合物を推定するために、個々の知識を活用する能力が要求される。これには、まず、基本法則や知識を整理し、次に、標準的な問題集の演習を通じて、思考を進めていくことが大切である。また、論述問題については要求されているキーワードを正確に読み取ることが重要である。全体を通して演習量の差が解答時間の差となるために、問題演習をしっかりとしておきたい。
生物
最近の出題傾向
- ①出題形式
- 問題数は、2021年度は大問4題であったが、2022年度以降は大問5題の出題が続いている。問題の出題・解答形式としては、文章空欄補充、選択、記述といった形式の問題の割合が高い。近年は、論述形式の問題の割合が低かった(2022年度1問/論述字数80字、2023年度4問/総論述字数100字、2024年度4問/総論述字数140字)が、2025年度は大幅に増加して9問/総論述字数430字であった。また、2022・2024・2025年度では、計算を要する問題が出題されている。
- ②難易度
- 全体的に基本~標準レベルの知識問題の割合が高い。考察問題も出題されるが、考察した内容として最も適切なものをいくつかの選択肢のなかから選んで解答する形式の問題が多い。
2025年度は、1科目あたりの試験時間が60分から75分に増加したためか、考察問題や計算問題の数が増加し、論述問題の数や総論述字数も増加したため、2024年度に比べてやや難化した。
2026年度入試予想・対策
- ①分野別出題傾向と予想
- 「生物基礎」と「生物」から幅広い内容の問題が出題されており、大問1題のなかに様々な内容の問題が含まれていることが多い。この傾向は2026年度も変わらないだろう。広島大学の前期試験で2022~2025年度に出題された問題を見てみると、「生物」の「生物の進化」と「生態と環境」の分野から頻繁に出題されており、「遺伝情報の発現と発生」や「生物の環境応答」の分野からも多く出題されている。逆に、2022~2025年度であまり出題されていない、「生物基礎」の「ヒトのからだの調節」などの分野については注意が必要である。理系受験生のなかには、「生物基礎」の範囲を軽視する傾向が見られるが、「生物の特徴」「ヒトのからだの調節」「生物の多様性と生態系」の全分野について、十分理解を深めておきたい。
- ②入試対策
- 「生物基礎」と「生物」から幅広い内容の問題が出題されるので、苦手な単元や分野をつくらないようにすることが重要である。標準的な問題で取りこぼしをしないために、教科書内容を完全に理解することと、標準的な問題演習を十分に行うことが必要である。問題演習を行うことで、自分の弱点分野や苦手な問題形式を知ることができる。したがって、むやみに多くの問題を解くのではなく、自分の間違えたところをいかに完全なものにしていくかに重点を置いて問題演習を行ってほしい。実験考察問題を苦手とする人は、実験の目的を正しく把握し、実験条件の変化と結果との対応を見る練習をするとともに、どのデータとどのデータを比較すればよいかを判断する力を身につけていこう。また、論述問題は配点が高いので、論述問題の対策もおこたらないようにしておこう。論述問題の対策としては、正確な生物学用語を用いて、要点を簡潔にまとめ、正しい日本語表現で文章を書く練習をしてほしい。また、可能であれば、論述答案を学校や予備校・塾の先生に添削してもらうとよいだろう。
特派員の声 ~合格の秘訣!!~
法学部 1年 伊東たけし特派員
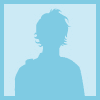
- 最後の最後は、自分の過去の努力よりも、今の強い気持ち
- 後期まで諦めず、頑張ったこと。後期の総合問題は小論・英文ともに難易度が高すぎて涙が出たが、最後は気合だった。
後期まで受ける人は少ないと思う。私は行きたい私大に合格していなかったため、やるしかなかった。人生で一番苦労するのは今だと信じて、頑張った。
経済学部 2年 やーの特派員
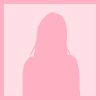
- 簡単な問題で落とさない
- 英語は、英作文が必ず出題されるので、ドラゴンイングリッシュは全て覚えて書けるようにし、赤本の使えそうなフレーズを覚えた。
数学は、大問の(1)、(2)くらいまでは簡単な問題なので、そこは確実に取るようにした。
河合塾の難関大学受験対策
広島大学をめざすあなたに向けて、受験対策のポイント・イベント情報・合格した先輩たちの声などをご紹介します。




