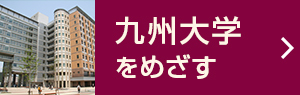九州大学 学習アドバイス
河合塾講師からの学習アドバイス
教科別の学習対策について、河合塾講師がアドバイスします。
※出題範囲は募集要項、大学ホームページ等で必ずご確認ください。
英語
最近の出題傾向
- ①長文総合問題
- 例年3 題出題される。2025年度は3 つの大問の総語数(英文と設問を含む)が1,925語で、2024年度に比べて77語増加した。記述式(和訳・内容説明・要約)と客観式(空所補充・内容一致)の問題が出題され、英文の内容理解と語彙が試されている。
- ②英作文
- 例年2題出題され、自由英作文・和文英訳・英文要約から多岐にわたる出題が行われる。2021~2025年度は自由英作文2題で構成され、その配点は全体の35~40%に及んでいる。1題は一貫して「意見を述べさせるもの」が出題される。もう1題に関しては、2024年度に引き続いて「自分が九州大学の学生であると仮定し、2つのプランのうち一方を選び、その理由をプラス面・マイナス面を踏まえて書かせるもの」が出題された。
2026年度入試予想・対策
長文総合問題については、長いものでは700語を超える英文が問われる傾向にあり、小説・随筆・論説文など、ジャンルに関係なく、ボリュームのある英文への対策が必要である。
設問の形式は記述式・客観式を問わず、きちんと語彙を身につけ、英文を理解できれば解答できるものが大部分。豊富な語彙力や適切な文構造の把握に加えて、速く正確に本文の流れをつかむことと、適切な日本語を用いて解答を作成する力が要求されることは確かだ。
英作文問題については、自由英作文だけでなく、和文英訳の対策もおこたらないこと。自由英作文で優れた答案を作成するには、重要表現や論理展開を模範解答から学ぶことが大切であるが、様々なテーマについて自分の考えを英文で説明できるように練習を積んでおこう。また、2024・2025年度は出題されなかった「図表説明型自由英作文」の対策として、「増減」「比較」「割合」「差」「倍数」といった表現の習得も忘れてはならない。いずれにしても、日本語を理解する力と英語で表現する力が要求されるという点で、和文英訳と本質は同じである。
以下に、九州大学の英語を攻略するうえで効果的な学習法を紹介するので参考にしてほしい。
- ①同じ英文素材の反復練習
- 英文を速く読み進めるには、的確な文構造の把握と語彙力が欠かせないが、それに加えて、論説文などによく見られる文章展開に習熟することも大切である。その対策として、授業や模擬試験で扱った英文を、何度も反復して読み返すことで英文のリズムに親しんでおく必要がある。実験内容や具体例などが、筆者のどのような主張を裏づけるためのものであるかを意識しながら、ただ漫然と読み返すのではなく、文章と文章との有機的なつながりを把握しながら読むように心がけよう。
- ②正しい解答のプロセスを知る
- 九州大学で出題の多い内容説明問題の対策として、解答のポイントとなる該当箇所を本文中に的確に発見できる力を身につけよう。模擬試験の解答・解説などを有効に活用し、正しい解答のプロセスを意識することが大切である。適切な解答作成には日本語の記述力も不可欠であるため、日頃から書く訓練もおこたらぬよう心がけたい。こうした地道な努力を軽視せずに、記述力の強化に取り組んでほしい。
- ③基本的な例文に親しむ
- 英作文では、高度な語彙や複雑な構文は必要ない。平易ではあるが正しい英文を書くように心がけよう。そのためには、短い例文を中心に自信を持って使いこなせる英文のストックを増やす必要がある。辞書などで単語の意味を調べる際には、その単語を用いた例文や用法についてもチェックしよう。英文を読む際にも、自分で使いこなせそうなフレーズはノートに書きとめるなどして、英語表現のバリエーションを増やす工夫も大いに役立つだろう。
文系数学
最近の出題傾向
- ①出題形式と出題範囲
- 文系数学の解答時間は120分で、全問記述形式である。出題範囲は数学Ⅰ・Ⅱ・A・B・Cで、数学Bは「数列」、数学Cは「ベクトル」が指定されている。
- ②出題傾向
- 毎年4題出題されている。2025年度入試においては、「微分法の応用(数学Ⅱ)」「図形と方程式(数学Ⅱ)」「三角関数(数学Ⅱ)」「整数(数学A)」「確率(数学A)」の内容が出題された。
ここ数年「微分法・積分法の応用」「整数」の分野の出題は定着しており、「二次関数」に関連した出題も多い。また、図形に関する出題は「ベクトル」「三角比・三角関数」「図形と方程式」「平面幾何」など多岐にわたって出題されている。
2025年度入試においては、小設問がない形式での出題が2題あり、特定の分野に偏らず出題範囲全体からまんべんなく出題されていた。複数分野の融合問題が多く出題されたことや具体的に数え上げる確率の問題が出題されたことが特徴的であった。 - ③問題の難易度
- 教科書に載っている基本事項だけで解けるように出題しているが、教科書と同じスタイルでの出題ではなく、九州大学独自の味つけをしようという意図が感じられ、問題文にかなりの工夫を凝らしている。典型的な題材をベースにした標準的な良問が多いが、文系としてはやや難しいレベルでの出題が1~2題含まれることもある。
2025年度は、易~標準のレベルでの出題が3題(「微分法の応用」「図形と方程式」「整数」)、標準的なレベルでの出題が1題(「確率」)であり、7割程度の得点が合否を分けるラインであったであろう。
2026年度入試予想・対策
- ①標準的な典型問題を中心に学習しよう
- 九州大学の入試に限らず、一般の大学入試における合否は、難度の高い問題の出来で決まるのではなく、基本~標準レベルの問題の出来によるものが大きい。したがって、このレベルの問題において、正確で迅速な計算力を身につけ、安易なミスをなくし正答率を高めるような演習を重ねていこう。
- ②普段の問題演習において
- 教科書の各分野の章末問題と同程度の内容が中心であるが、複数分野の融合問題形式での出題が予想される。また、小設問がない形式での出題も起こり得る。これは、各分野の基本事項の習得度合いのみならず、考察力・思考力を問う意図によるものである。学習法としては、まず教科書の章末問題をしっかり復習し、そのうえで入試問題集などを活用し、できる限りいろいろなタイプの問題にあたっておくのが望ましい。標準的な問題を演習する際は、小設問や誘導がないことを想定して問題に取り組むとよい。
また、過去の九州大学の入試は、かなりの計算を要する問題が多くあり、文字を含む計算も含まれ、丁寧に計算を進めることが必要となる。2026年度も計算力を問う出題は予想される。日頃の学習では、単純計算だけでなく、問題の流れに沿った計算を遂行する力を養っておこう。 - ③合格に向けて
- 特定の分野に偏らずまんべんなく出題されることが予想される。微分法・積分法、図形、二次関数、場合の数・確率、整数の範囲を軸にして、数列、指数・対数関数、複素数と方程式、図形と方程式、三角関数の分野など、どの分野も基本概念はしっかりと定着させておかなければならない。難しいレベルの問題には小設問を設け、流れを誘導してくることが予想されるので、問題意図をよくくみ取り、できる限り部分点を取れるような態度で考えるようにするとよい。
何より大切なことは、粘り強くやりきる計算力と、諦めずに頑張り抜く気力である。最後まで合格に向けて頑張ってほしい。
理系数学
最近の出題傾向
- ①出題形式と範囲
- 理系数学の解答時間は150分で全問記述形式である。出題範囲は数学I・Ⅱ・Ⅲ・A・B・Cで、数学Bは「数列」、数学Cは「ベクトル」「平面上の曲線と複素数平面」が指定されている。
- ②出題傾向
- 毎年5題出題されている。2025年度入試においては、「空間ベクトル(数学C)」「積分法(数学Ⅲ)」「整数(数学A)」「三角比(数学Ⅰ)」「確率(数学A)」のそれぞれのテーマと分野から出題された。
特に、いくつかの複数分野の融合問題やパターン化された解法のなかにあるちょっとした工夫を要する問題が多く出題されることが特徴である。数学Ⅲ・Cからの出題は多く、2025年度は著しく易化したものの本来は全体的にレベルの高い問題が多く、定番の解法はもちろん、思考錯誤しながら工夫して解く訓練と正確な計算力の養成をしておかないと対応は難しい。 - ③出題形式と問題の難易度
- 非常によく工夫された良難問がそろい、計算量も多く、なかには数学的に興味深い内容を題材にしたものも出題されている。論理的な思考を要する本格的な論証問題の出題が目立ち、「やや難」「難」のレベルの問題がやや多い傾向にある。
出題形式としては、いくつかの小設問に分かれていて、前半の内容をしっかりと理解したうえで後半の設問に取り組むタイプの問題が多い。2022・2023年度入試において、影つき枠内にある長文を読んで、アンダーラインのある部分を論証させる非常に独特な新傾向問題が2年連続で出題されており、より難度の高い思考力と論証力が試されている。
2026年度入試予想・対策
- ①幅広い知識の活用
- 九州大学の理系数学は、数学Ⅲ・Cの分野を中心にいくつかの複数分野の融合問題が非常に多いため、分野ごとの得意・不得意があると対応が難しくなる。分野ごとに標準的な頻出問題は日頃からしっかりとまんべんなく演習しておく必要がある。
- ②たくましい計算力をつける
- 合否が分かれる大きな要因が計算ミスの有無である。容易な部分での油断から生じるミスや、次の式への書き間違いなど、計算ミスというよりケアレスミスによることが多い。このようなことは致命的な結果につながることが多く、特に序盤における立式や計算は2度、3度やり直すなどのケアレスミスに対する対策が必要である。普段の学習においても、計算は最後まで根気よくやり抜くように心がけたい。また、ただやみくもに行きあたりばったりの計算をするのではなく、計画性のある明確な方針を持って進めることも心がけてほしい。
- ③数学的な読解力と思考力を磨く
- まず、問題文を読んでどのような設定になっているかを正確に読み取ることが最も大切である。ここで誤解や勘違いをすると大きな失点につながることは間違いない。与えられた設定や条件を図示したり、具体的な値で実験することによって方針が明確になり見通しがよくなる。さらに、問題を正確に把握した後、『求めるもの、示すものは何か、そのためにどうするのか』を明確にすることが大切である。奇をてらった特殊な解法を考えるのではなく、まずは与えられた条件や設定に沿った素朴な方針を考えて、そこから自然な流れで立式していくことが望ましい。
- ④合格に向けて
- まず各分野における基本事項の徹底理解と、重要問題のマスターが必要不可欠である。このような重要問題を繰り返し演習することによって、数学的な構造やイメージ(問題の本質を見極める読解力)がつかめるようになるであろうし、いろいろな問題に対応できる幅広い知識の活用力が養える。ただし、自分で解くということが肝要で、数学的な論理展開を意識しながら、繰り返し再現していくことが大切である。くれぐれも【解答】にあるような模範解答の丸暗記に頼ることのないように注意しよう。
2025年度は著しく易化したものの、本来は出題される問題のレベルは高い(手軽にさっと解ける問題が1題もない)ので、今後の合否のボーダーラインの予測は難しいが、ひとつの目安として、医学科は65~75%、その他の理系学部は45~55%の正解率を目標にしたい。
日頃から発展的な演習問題を【解答】などに頼ることなく根気よくじっくり思考する習慣が必要であり、答えにたどりつくまでの過程のなかで『なぜ、このような論証が必要になるのか?』『なぜ、このような工夫をして計算していくのか?』『もっと別のアプローチがあるのではないか?』など、単に正解を導くだけでなく、問題のなかにある様々な特徴や難しさを本質的に理解し、丁寧に解明していくことでさらなる実力向上が望めるであろう。
入試本番までまだ少し時間と気持ちに余裕のある時期ではあるが、気を緩めることなく、できることをとことんやり抜いて本番に臨んでほしい。それまでやってきたことや身につけた学力がしっかりと反映できることを心から祈っている。桜の咲く頃に諸君らの多くの朗報を待つ。
現代文
最近の出題傾向
- ①全体として2024年度並み
- 2025年度も例年どおり、現代文からの出題は、教育・法・経済(経済・経営、経済工学科)学部で2題、文学部で1題であった。第一問(文学部との共通問題)は、尹雄大『聞くこと、話すこと。人が本当のことを口にするとき』である。インタビューセッションにおいて、相手に質問したり相手の話を聞いたりすることの難しさを論じた文章である。第二問は、山下範久「資本主義にとっての有限性と所有の問題」である。資本主義が環境危機により「有限性の壁」に直面し、無限成長を前提とした従来システムの持続可能性が問われていることを論じた文章である。
本文の分量は、2題合わせて2024年度より160字程度微増し約7,100字、80分(現代文2題のみの経営工学科の試験時間を基準とする)で解く分量としては標準的であり、内容も読みにくいものではないため、本文の読解に関しては2024年度並みといえる。
設問のパターンは、2題ともにおおむね論述問題からの出題であった。論述問題以外の設問形式としては、2023・2024年度に2年続けて出題されていた空所補充は出題されず、全設問が論述問題となった。小問数は第一問が6問、第二問が6問、合計12問で2024年度と同じだった。また、書き取り問題は2018~2025年度の8年連続で出題されなかった。しかし、漢字の熟語は現代文を読むうえでの必須の基礎知識なので、漢字の学習はおろそかにしないようにしたい。例年出題されていた制限字数のある設問は出題されず、すべての設問で罫線型の解答欄の論述問題となった。全体の記述総字数は1,135字から1,225字へと2024年度から90字程度微増した(罫線1行につき25字とした場合の字数)。
本文が難易度としてやや易しかった2024年度並みであったこと、設問の記述量がそれほど変わらなかったことなどから、全体として2024年度並みの難易度であった。 - ②基本的な設問・記述量の多さ
- 本文内容と設問意図を正確に理解し、適切に答えるという、現代文の基本的な力を試すものであった。2025年度は減少したとはいえ、九州大学の特徴は全体として論述問題の解答字数の総量が多めに設定されている点には留意しておきたい。
2026年度入試予想・対策
- ①頻出作者、幅広いジャンルからの出題
- 出題のジャンルは、硬質の評論・エッセイである。哲学・思想・文化・文明・芸術・言語・政治などのジャンルにとらわれず、様々な文章を読む力が試されている。なお入試頻出作家からの出題が多いことは九州大学の特徴として気に留めておこう。
- ②基本的な出題パターン
- 解答の形式は論述問題を基本とする。個々の設問については、正確な文脈の理解に基づくものばかりで、本文全体の趣旨を問うたり、傍線部から離れた箇所の内容を問うたりするなどの“変化球”はそれほど問われない。設問数は大問1題に対して6~7問になっている。なお、答えの大半は本文中の語句を用いて答えることができるが、論旨や文脈を踏まえて自分なりに言語化してまとめなければならないものも出題されている。いずれにせよ、文章を正確に読む、傍線部の前後の文脈を押さえるといった基本的な読解を試す設問であると考えておいてよい。特筆すべきは、論述の総分量は試験時間に対してかなり多いということであろう。生半可な準備では太刀打ちできず、制限時間に間に合わないので、豊富な演習量を確保し、制限時間内に解答し切れるように訓練しておく必要がある。2018~2025年度まで8年続けて漢字の書き取り問題が出題されなかった。また、過去の問題を通覧すると、論述問題以外にも、空所補充問題、選択肢問題、抜き出し問題、語句の意味説明問題といった設問が出題されたことがある。もちろんこうした設問に正解することも必要ではあるが、配点の高い論述問題に対応できる力を身につけることが何よりもまず大切である。
- ③正確な読解と論述の練習が重要
- 硬質な文章で多様なジャンルを考慮するなら、日頃から様々な、しかも硬質の評論に慣れ親しんでおくことが大切である。特に文章を自分勝手に読み込んでしまいがちな人は、筆者の主張を正確に理解する読解力を身につけておこう。また、問題集などで3,000字前後の文章を一定時間内に速読し、全体の構造を読み取る練習をしておくことも効果的である。その際に気をつけることは個々の文脈の理解が個々の設問を解く際には重要であることを忘れないこと。また、記述量の多さに対しては、何よりも「書く」ことがその対策となる。過去の問題や問題集を使って、「書く」練習を積み重ねてほしい。
古文
最近の出題傾向
- ①出題数と配点
- 教育・法・経済(経済工学科を除く)学部では40点問題が1題、文学部は30点問題が2題出題される。文学部の2題のうち1題は教育・法・経済(経済工学科を除く)学部の問題と共通しているが(=共通問題)、配点の違いもあり、設問が一部異なる場合もある。2025年度の共通問題は、教育・法・経済(経済工学科を除く)学部と文学部で同一の設問が出された。共通問題の文学部の配点が10点少ないのは、国語の総点が文学部だけ50点少ないことによる。
- ②共通問題は鎌倉時代からの出題。2024年度よりやや難化
- 共通問題は、中世・近世からの出題が多いが、中古の場合は、本文が読み取りにくいうえに、設問にも難しいものが多い。2025年度は、鎌倉時代の日記である『うたたね』からの出題であった。本文の量は2024年度よりやや増加し、内容は、2024年度に比べ読み取りにくかった。設問は、現代語訳、文法問題、指示語の問題、和歌の句切れの問題、文学史問題は標準的であったが、理由説明問題、内容説明問題はやや難しかった。全体的には2024年度よりやや難化した。
- ③文学部のみの問題は安土桃山時代からの出題。難易度は2024年度と変化なし
- 文学部のみの問題は、まんべんなくどの時代からも出題される。共通問題より難度が上がることもある。2025年度は、安土桃山時代の紀行である『九州の道の記』からの出題であった。本文の量は2024年度よりやや減少し、内容は、2024年度と同様に読み取りやすかった。設問は、現代語訳、和歌に関する問題、理由説明問題、内容説明問題などであったが、いずれも標準的であった。全体的には2024年度と難易度は変化なしと考えられる。
2026年度入試予想・対策
- ①幅広いジャンルからの出題を考えておく
- 共通問題・文学部のみの問題ともに、どの時代、どのジャンルからも出題される可能性があり、まんべんなく学習しておく必要がある。ただ、近年は、共通問題・文学部のみの問題のどちらかに江戸時代の文章が出題されることが多い。特に、両方の問題を解くことになる文学部の受験者は、江戸時代の文章に積極的に取り組むようにしよう。文章の難易度は、年度によって違いはあるが、難しいものが出される場合を想定して、ハイレベルの文章にも取り組もう。
- ②基本の学習をおこたらない
- 基本の文法力、単語力を身につけ、それに基づく正確な現代語訳を自らの力で書く練習を積み重ねよう。どのような記述問題も、正確な訳に基づいた解釈力があってこそ解答できる。問題を解くだけではなく、本文をきちんと全訳するようにしよう。
- ③多くの問題を解いてみる
- 国公立二次型の問題を解いて、記述力を養成しよう。九州大学の記述問題は、傍線部の前後を解釈できれば解けるものから、文章全体を通して考えなくてはならないものなど、様々なタイプで出題される。多くの問題にあたり、どのようなかたちで問われても対応できる力を身につけよう。
- ④和歌の対策
- 和歌修辞(枕詞・序詞・掛詞・縁語)の学習はもちろんのこと、場面や状況に合わせ、主語などを補いつつ、きちんと解釈できるようにしよう。また、俳諧の解釈もできるようにしておこう。
- ⑤文学史の対策
- 九州大学では、ほぼ毎年のように文学史問題が出題される。基本的な問題が多いが、文学部では記述式の問題など、難しいものが出題されることもある。しっかりと学習し、確実に答えられるようにしよう。
漢文
最近の出題傾向
- ①出題数と配点
- 配点は文学部45点、法・経済・教育学部40点。近年、文学部では小問7問、法・経済・教育学部では小問5~7問が出題されている。文学部では40~80字の記述問題が出題されている。
- ②2025年度の出典
- 2025年度の問題文は、歴史書『三国志』呉書巻七「諸葛瑾)」(西晋・陳寿)とその注(裴松之))からの出題。途中一部カットしている。諸葛亮孔明の兄、諸葛瑾と呉の君主孫権との固い結びつきについて述べられている。
- ③設問の傾向
- 書き下し文・現代語訳・説明問題に関わるところに難しい語句が出題されていた。2023~2025年度の3年連続で返り点をつける問題も出題された。また文学部のみの60字の記述問題は難しかった。文学史・思想史問題は文学部のみで出題された。
2026年度入試予想・対策
- ①読解のポイント
- 漢文は本文全体を理解してから解き始めること。焦らず急がず傍線部よりも後の文章と注もしっかり読むことによって十分に解答できる。
- ②書き下し文に改める問題
- 漢文句法と漢文の語順の徹底した学習が必須である。漢文句法は共通テスト対策程度では通用しないので、共通テスト後にもう一度細部まで確認をしておくこと。漢文の語順は英語の語順に近く、主語+述語+目的語という語順をとる。これを理解してから学習を進めてほしい。
- ③解釈(現代語訳)や説明問題
- 1.解答に必要な箇所を抜き出し、2.正確な直訳をし、3.必要な言葉(指示語や主語・目的語など)を補って、4.設問の要求にあわせて解答をつくる、という練習を繰り返してほしい。解釈(現代語訳)問題と説明問題では要求される解答が違うので、必ず設問と自分の解答を見直すこと。解釈(現代語訳)問題では、例えば「汝(なんぢ)」は「おまえ」と訳す必要があるが、説明問題では、「汝」が何者かを説明する必要がある。また、漢文句法・漢字の語義はもちろん、古典文法、特に接続助詞「ば」や「に」などの訳が不正確だと主語を取り違えることにもなりかねない。
- ④語彙力
- 共通テストやセンター試験の過去問も含め、漢文重要語集などで学習してほしい。
2025年度は「負」を含む文を書き下し文に改める問題が出題された。「負」には①「まく」(まける)②「そむく」(逆らう・裏切る)③「おふ」(背負う・引き受ける)④「たのむ」(頼りにする)などの読みと意味があるが、文脈上「そむく」と読まねばならなかった。2005年度のセンター試験本試に「そむく」の読み方が出題されている。
また読みを問う問題で、2025年度は「不易(かはらざる)」「為人(ひととなり)」「若(もし)」が出題された。「不易」の正答率が低かったが「不易流行」つまり「不易(かわらないもの)」と「流行(流れ行くもの)」を知っていれば読めたはずである。「易」に関する問題は2005年度のセンター試験追試、1996年度のセンター試験本試、1980年度の共通一次本試験で出題されている。
2024年度は「私(ひそかに)」「対(こたへて)」「俄(にはかに)」、2023年度は「固(もとより)」「然(しかれども・しかるに)」「弥(いよいよ)」「不倦(うまず)」、2022年度は「幾(ほとんど)」「乃(すなはち)」「頗(すこぶる)」などが出題されている。 - ⑤文学史・思想史問題
- 常識程度の文学史・思想史の知識は本文読解にも必要であるため、どの学部を受験しようとも対策はおこたらないでほしい。本文の出典と同時代の作品や人物を選ぶ問題が多い。
物理
最近の出題傾向
- ①「思考力」に加え「状況把握力」「計算の処理能力」を確認することを意識した問題構成
- 2025年度の出題傾向も2024年度に続き「思考力」「判断力」「表現力」に加え「状況把握力」「計算の処理能力」を確認することを意識した問題で構成されている。大問は長文になっており、1つのテーマを掘り下げるのではなく、複数のテーマを含む総合問題のかたちになっている。2025年度の問題のテーマは2024年度と同様に、目新しい問題や融合問題など取り組みにくいテーマは出題されなかった。標準レベルの問題が主で、問題量と設問数は減少しており、難易度はやや易となっている。問題形式については2024年度までの過去5年間は、問いと誘導穴埋め形式が3対2の割合で出題されていたが、2025年度には誘導穴埋め形式は出題されなかった。解答形式は2023・2024年度には論述問題に加え、解答の根拠を文章で説明させたり、グラフの作図など「表現力」を確認するための設問が見られたが、2025年度は解答のみや与えられたグラフの選択という形式で出題された。2026年度以降の出題傾向も2025年度の傾向が踏襲されると思われるが、2023・2024年度で出題されたような「表現力」を確認するための設問が出題される可能性もあるということも念頭に入れておく必要がある。また、2019~2025年度の7年間には2019年度の身近な自転車の運動を題材にした問題、2020年度の実験資料に基づく実験レポートの完成問題、会話文形式での問題などが出題されている。そのことを踏まえて、今後もこれらのテーマの問題が出題される可能性は高いと考えておく必要がある。
- ②力学と電磁気は必出
- 試験時間75分(2科目で150分)で大問3題構成である。〔1〕力学〔2〕電磁気〔3〕は波動・熱力学・原子のいずれかである。力学と電磁気の分野からは毎年必ず出題される。〔3〕については、2025年度は熱分野からの出題であった。2024年度は波動分野からの出題、2023年度は熱、波の融合問題としての出題であった。2023年度の融合問題以外は波動と熱力学が隔年で出題されていたことを考慮すると、2026年度は波動分野からの出題となる可能性が高い。それに加えて、力学と原子、熱と原子、波動と原子などの融合問題での出題の可能性もあるので注意が必要である。
- ③長文問題であり、解答形式も多種多様
- いずれも長文問題であり読解力が必要である。解答形式も多種多様であり、75分の解答時間では時間不足になることを考慮しておく必要がある。2025年度の問題は答えのみを書かせる記述式が中心の問形式であったが、2024年度までは誘導穴埋め形式の問題や、字数制限の論述問題、グラフの描図もほぼ毎年出題されていた。解答形式としては、2024年度は100字程度での論述と解答の根拠を説明させる問題が、2023年度は15字の論述、グラフの描図が、2022年度は80字の論述、描図が2問出題された。また、力の図示、式の証明問題および実験レポートの完成など多種多様な形式が見られる。さらに、解答に際しては文字数を指定したかたちで答えさせるものが主流であるが、2019年度からは解答の際、文字の指定をなくした形式も含まれるようになった。
2026年度入試予想・対策
- ①分野別出題傾向と予想
-
- 〈力学〉
- 力学の分野では、様々なテーマを融合させた問題が非常に多く、力学全般についての理解力を確認するような問題になっている。演習問題などで見慣れた設定が複数組み合わされて出題される。2025年度は2つの振り子による衝突と単振動、2024年度は鉛直面内での円運動、仕事とエネルギーの関係に加えて液体中での浮きの単振動についても問われており、力学の総合問題となっている。また、2023年度の「最速降下曲線上での単振動」、2022年度の「万有引力」の出題など新しい傾向の設問もあり、出題の意図を読み取り思考する工夫がなされている。2026年度は「力のモーメント」「粗い面上の単振動」「万有引力」に注目したい。例年の出題例を挙げると、鉛直ばね振り子上の物体の運動、放物運動と衝突、円弧を含む斜面上の運動と衝突、斜面上の放物運動、動く重心のまわりの回転運動、単振動と衝突、慣性力と斜面、慣性力とばね、円運動と放物運動、回転軸上の単振動、エレベーター内の単振り子、推進力一定の円運動とばね、円運動とばね振り子のように、いろいろ工夫が凝らされており、式の変形も面倒で、相当な計算力や応用力が必要とされる。問題設定や題意を把握して状況の変化に即応できる物理的な洞察力と、スピーディーかつ正確な計算力が必要である。『導き方も記せ』では、解答までのプロセスを要領よくまとめる記述力も必要である。
- 〈電磁気〉
- 電磁気の分野でも、様々なテーマを融合させて出題されている。2025年度は、電場・磁場中での荷電粒子の運動とコイルに生じる誘導起電力の問題、2024年度はコイルの過渡現象と自己誘導と相互誘導の問題、2022年度はコイルが磁場から受ける力のモーメントとその仕事をテーマとした会話文形式の問題が出題されている。いずれも各テーマの理解力が試されるのと同時に、その場で思考する力を必要とする問題となっている。直近の4年の問題は2020・2021年度より難化している。さらに過去の出題内容を振り返ると、2018年度のように電気分野と磁気分野がそれぞれ個別に出題されたり、あるいは2019年度のように電気分野と磁気分野が融合されて出題されたりしており多種多様な出題傾向が見られる。2026年度はよく出題される「電磁誘導」の問題のほかに「電位差計の直流回路」「オームの法則の電子論」「コンデンサー」などが予想される。2019年度までは難化傾向で、2020・2021年度は標準であったが2022~2025年度は難化している。難易度は年ごとに上下しているが、ここ4年の電磁気分野の難度が高くなっていることを念頭に入れた幅広い学習が必要である。
- 〈熱力学〉
- 2025年度は熱機関(カルノーサイクル)での熱効率が出題された。状況判断力と計算力が試される問題であった。2023年度は波動分野との融合で出題されている。熱分野はここ7年間、隔年で出題されており、2021年度は「熱機関」の問題で、断熱変化で用いるポアソンの法則が見慣れない圧力と温度で表されていた。熱効率を求める文字の指数計算が複雑でかなりの計算力が必要である。ここ7年間は熱と波動が隔年で出題されていたことから、2026年度は熱分野をメインとした問題が他分野との融合問題として出題される可能性は低いが、過去の例を見ると、波動と原子の融合問題や2年連続で波動分野、3年連続で熱力学が出題されたことがあるので、熱分野だけでなく波動、原子分野についても準備が必要である。
- 〈波動〉
- 2025年度は波動分野からの出題はなかった。2024年度は音のドップラー効果と流速測定器の問題、2023年度は熱との融合問題のなかで「音速の測定」をテーマとする出題で読解力とかなりの計算力を必要とする問題であった。2022年度は「光波」からの出題で、レンズの像の作図、屈折と全反射、反射防止膜の干渉と幅広いテーマの出題となっている。過去の出題テーマを振り返ると、2016年度に「レンズ」、2013年度はやや複雑な「波の式」が出題されたこともある。また、2017年度は原子分野が融合された問題が出題されており、誘導穴埋め形式ではあったがヒントが少なく、対応しづらい問題であった。2026年度は波動分野からの出題の可能性が高いと思われる。また、波動とほかの分野との融合問題として出題される可能性もある。過去には融合問題として波動と原子の分野のテーマを組み合わせて出題されたこともあるので注意が必要である。例年、波動は標準的な問題が出題されているが、やや見慣れない問題や、取り組みにくい問題が出題されることもある。「波の式」「波の干渉」が予想され、実験に関する内容を踏まえた問題の対策や、やや難しい典型問題の演習が必要である。
- 〈原子〉
- 原子分野については、2006年度から出題されておらず、2025年度も出題されなかった。過去の例を見ると、2017年度は波動分野の一部として出題されており、今後は原子分野の内容が融合問題として出題される可能性もある。以前は典型的な原子、原子核分野の問題が数年おきに出題されていたことから、2026年度は「光電効果」「原子核反応」熱の「分子運動論」と「光子の鏡との衝突」の融合問題なども注意しておきたい。
- ②入試対策
- 合否の分かれ目は力学、電磁気の記述問題になるであろう。計算量が増加傾向にあるのでケアレスミスで失点しないことが大切である。熱力学、波動分野は取り組みやすいが、基本事項(縦波と横波の相違、分散、回折、干渉などの意味)を正しく理解しておかないと思わぬ失点をする。また、ここ7年の新傾向として、日常生活に関わる物理現象を題材とした実験に関する問題や、会話文としての出題も予想される。具体的な対策としては、まず、教科書の例題、章末問題を完全に制覇すること。さらに、標準問題集に取り組んで問題を読みこなして物理的な洞察力を身につけることである。自分勝手な思い込みで問題を曲解し、むやみに公式を振り回してこじつけたような解答は厳禁である。問題文の読解・題意の把握→立式→計算という手順を意識することにより、読解力や計算力が養われる。さらに、論述力をつけるために計算結果の物理的な説明を15~100字程度でまとめる練習に加えて、描図やグラフの作図も練習しておこう。また、高校でする実験に真剣に取り組み積極的に実験レポートを作成しよう。九州大学の場合、問題の解法には微積分はほぼ用いないが、電磁誘導や交流を定量的に表現するのに微積分を用いるので、物理学における微積分の意味を知るためにも教科書の発展は一度目を通しておいた方がよい。
化学
最近の出題傾向
- ①2025年度入試
- 大問数は5題で、分量と難易度は2024年度並みであった。各大問に思考力を問う設問が組み込まれており、2023年度入試までと比較すると、2024年度に引き続き、難易度はやや難化している。
配点について、2024年度までは25点の大問5題だったが、2025年度は分量に応じて20~30点の大問5題へとやや構成に変化があった。
2024年度は、正答数が示されていない正誤判定問題が4問も出題されたが、2025年度も3問出題されており、解答に時間を要したと思われる。
新課程を踏まえた出題として、〔3〕問2では、溶解エンタルピー、乱雑さ、エントロピーの語が問われた。 - ②出題傾向
- 過去5年間の出題分野と傾向を分析すると、理論化学の大問が2題、理論化学と無機化学の融合問題が1題、脂肪族・芳香族化合物の大問が1題、高分子化合物の大問が1題の全5題の構成である。分野別の出題比率は、理論化学50%、無機化学10%、有機化学40%である。標準的な大問が半数以上を占めるが、大問1題程度の「やや難」の設問と、各大問に思考力を問う設問を組み込む形式で全体が構成されている。医学部などの高得点が要求される学部では、この「やや難」の大問をいかに攻略できるかが合格への鍵となる。
2026年度入試予想・対策
- ①分野別の出題傾向とその対策
-
- 〈理論化学〉
- 例年、理論化学は、大問が2題出題される。反応速度と化学平衡、希薄溶液の性質、電池・電気分解が頻出分野である。
2025年度入試は、コロイド、燃料電池、電気分解、溶解エンタルピーからの出題であった。〔1〕の問6、〔2〕の問3・5、〔3〕の問2・4の正答率は低かった。
2026年度入試では、反応速度、電離平衡、溶解度積に特に注意を払いたい。
この分野の多くは計算問題で、難度の高い設問および、やや計算が煩雑な設問が出題されることが多い。短時間で正解に到達できる「たくましい」計算力も必要である。また、題意に沿って計算式を文字色で誘導するタイプの出題形式も頻出である。この形式では前半でのケアレスミスが後半にまで影響することが多いため、大量失点をしないように細心の注意を払い、丁寧に解答する必要がある。さらに、近年、化学反応が起こる理由を考察する設問も増加しており、表面的な理解だけでは太刀打ちできないため、基礎・基本を徹底的に理解することに努めてほしい。 - 〈無機化学〉
- 化学結合に関する空欄補充や、結晶構造に関する計算問題、酸化還元反応が頻出テーマであり、このなかに無機化学の知識を問う設問が幅広く盛り込まれている。
2025年度入試では、定番の金属結晶が、2024年度入試では、イオン結晶(閃亜鉛鉱・方鉛鉱)が問われた。
2025年度入試では、定番ではない過リン酸石灰を題材としており、また、2021年度入試では、黒鉛(グラファイト)を構成する各層の名称「グラフェン」が問われるなど、無機化学全般にわたり、丁寧な学習をする必要がある。 - 〈有機化学〉
- 有機化学では、脂肪族化合物と芳香族化合物に関する大問がほぼ隔年で出題されている。
2025年度入試は、脂肪族化合物からの出題であり、比較的解きやすい設問が多く、ここで高得点を取れたかがポイントである。KMnO4を用いた炭素間の二重結合の酸化開裂で差がついていたが、このテーマは、2022年度にも出題されている。しっかりと過去問演習を行うことが肝要であった。2024年度入試は、2-ブテンへの臭素のトランス付加および分子式C4H4O4の化合物に関する出題であった。〔4〕問4の正答率は低かった。問4・6では、ラセミ体・ジアステレオ異性体・メソ体など一部の教科書にしか記載がない用語が扱われた。
これまで、有機分野は標準的な出題が多く、短時間で確実に得点できる、いわゆる得点源の分野であったが、近年は、2-ブテンへの臭素のトランス付加(2024年度)、KMnO4酸化開裂(2022年度)、メソ体(2020年度)などやや難度の高いテーマからの出題も増加の傾向にあり、注意しておきたい。
高分子分野では、天然高分子化合物(糖類・アミノ酸とタンパク質)と合成高分子化合物に関する大問が出題されている。出題テーマに沿った空欄補充問題のなかに、やや難度の高い計算問題が含まれる。
2021年度入試では、芳香族ポリアミドである「アラミド」の名称を問う空欄補充問題も出題され、幅広い正確な知識が要求される。高3生にとっては、入試間近に慌てて学習しがちな分野でもあり、対策に十分な時間が取れない点で厳しい分野となるが、得点源としたい。
- ②入試対策
- 九州大学の入試では、標準的な設問を確実に得点する力をつけることが合格への近道である。基礎事項を徹底的に理解し、標準的な問題の演習を通じて化学的な思考力や想像力を高めながら、「やや難」の問題にも対応できる「しなやか」な実力を身につけて2026年度入試に臨んでほしい。
生物
最近の出題傾向
- ①全分野からバランスよく出題される
- 代謝、遺伝子、生殖・遺伝、生物の環境応答、進化と系統などからの出題が多くはあるが、全分野からバランスよく出題されている。
- ②100字程度の論述問題が出題される
- 近年は大問5題で構成されており、全体を合わせた総論述字数はおよそ700字程度である。多くは80~120字と長めであり、知識に基づいて論述する問題と、実験結果や図表を基に考察して論述する問題のどちらも出題される。
- ③計算問題の出題が多い
- 近年は「減数分裂時の染色体の組合せ」「標識再捕法」など典型的な計算問題や、設問文から情報を整理して計算する問題、また、遺伝を含む計算問題などが出題されている。2025年度は、「分子時計」を利用したアミノ酸座位1個に置換が起こる率を計算する問題が出題された。
2026年度入試予想・対策
- ①分野別の出題傾向と予想
- 全分野からバランスよく出題されており、この傾向は2026年度も変わらないと考えられる。一方で、2025年度は2024年度に続き遺伝子、発生、ニューロンをテーマとした問題が出題され、多少の偏りも見られる。2026年度も、過去によく出題されている「遺伝子」「生殖・遺伝」「体内環境」「生物の環境応答」「進化と系統」などの分野については注意しておきたい。
また、2025年度の総論述字数は例年よりも少なく210字であり、最も長いものは「酵素活性の違い」について立体構造と関連づけて説明する80字の考察論述であった。100字程度の論述問題は、今後も頻繁に出題されるであろう。 - ②入試対策
- <知識問題で失点しない>
- 九州大学の入試問題では、難度の高い考察問題や、複雑な計算問題が出題されることも多いが、問題文の穴埋めや正誤問題、知識論述なども数多く出題される。問題量に対して試験時間が十分でないことから、時間のかからない知識問題を短時間で正答し、難しい問題を解く時間の余裕をつくることが重要である。教科書レベルの知識問題でミスしないよう、教科書傍用問題集などを利用して、基礎となる知識を身につけておいてほしい。
- <論述問題に対応する力をつける>
- 論述問題には、知識に基づいて論述する問題と、実験結果や図表を基に考察して論述する問題があるが、九州大学ではその両方が出題される。論述字数も100字前後と比較的長いため、論述対策をしていない受験生は苦労するであろう。知識論述は、日頃から練習していれば減点されずに解答することが十分に可能である。模範解答を想像して、採点基準となり得るキーワードを入れた文章がつくれるように、論述力を高めて試験に臨むとよい。また、考察論述は難度が高く、文章で表現しにくい問題も多く出題されることから、高得点を狙う受験生は過去問などを利用して実験結果を整理したり、図表を正確に読み取ったりする練習をしておこう。
- <典型的な計算問題の解法を身につける>
- 年度によるバラツキはあるが、九州大学では計算問題がよく出題される。典型的な計算問題は、解法を覚えている受験生であればきっちりと正答できる。生物の計算問題の多くは簡単な計算で正答を導くことができることから、解法を覚えて典型的な計算問題で失点しない努力をしよう。
- <解答する問題を取捨選択する>
- 九州大学の入試は理科2科目で150分、生物に使える時間は75分程度である。この時間で大問5題を完答するのはかなり厳しいため、難度の低い問題を優先的に解き、状況によっては難度の高い問題に手を出さないという選択が必要になる場合もある。日頃から、正答できそうな問題とできなそうな問題を見極め、問題を取捨選択する練習をしておこう。
特派員の声 ~合格の秘訣!!~
共創学部 1年 R特派員
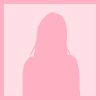
- 量
- 何事も量と質が大切だと言われる。確かに受験にも当てはまると思う。しかし、最初から質がついてくるわけではない。
料理と一緒である。最初はぐちゃぐちゃても、おいしくなくても、作る。そうしているうちにコツをつかんで、きれいで美味しい料理を作れるようになる。
勉強も最初から質の良い勉強ができる人はいない。量をこなしたからこそ、コツをつかむことができ、効率の良い勉強ができるようになるのだ。だから、まず量をこなすべきである。
法学部 1年 じょーじ特派員
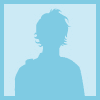
- 量と質のバランスを大切に!!
- 復習や予習にこだわらず、数をこなす教科や質を大事にする(予習や復習に時間をかける)教科を自分で決めて、最後まで自分の立てた計画を遂行できるように頑張ってください。
河合塾の難関大学受験対策
九州大学をめざすあなたに向けて、受験対策のポイント・イベント情報・合格した先輩たちの声などをご紹介します。