- 2024年12月16日

この記事をシェアする
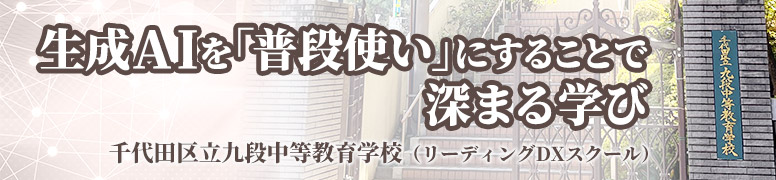
「リーディングDXスクール」は、GIGA端末の標準仕様に含まれている汎用的なソフトウェアとクラウド環境を十全に活用し、児童生徒の情報活用能力の育成を図りつつ、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実や校務DXを行う先進的な取り組みを全国に展開することをめざした文部科学省の事業である。2023年4月にスタートし、2024年度の採択校は256校。
千代田区立九段中等教育学校は、このリーディングDXスクールにおいて生成AIパイロット校にも指定され、さらにDXハイスクール(高等学校DX加速化推進事業)にも採択されている。同校では、生成AIの「習得」「活用」「探究」というフェーズを通して、主体的・対話的で深い学びを実現する授業を構築し、情報活用能力の育成に取り組んでいる。
同校では、主体的に学び行動する力や、将来の生き方を考える力を養うための6年間を通したキャリア教育プラン「九段探究プラン(九段中等教育学校Webサイト)」をカリキュラム・マネジメントの軸に置いている。 ここでは「学び方スキル」として、前期課程(中学校1~3年生)で課題解決学習の手順とともに情報活用能力を身に付けるトレーニングを行い、6年を通して各教科の中で繰り返し活用することで定着を図っている。2024年度からは、ここに生成AIの利活用が加わった。独自の校内生成AI「otomotto」を導入し、全教職員・全生徒が校務や授業で活用している。
今回は、2024年10月17日に開催されたリーディングDXスクールの公開授業にうかがい、情報科とDXご担当の須藤祥代先生と市川淳尉先生にお話をうかがった。
各教科の特徴や授業のねらいに応じて
GIGA端末や生成AIをさまざまな形で活用する
今回の公開授業では、1年生から5年生のさまざまな教科・科目が紹介された。
生物:生徒が「呼吸」の問題を作成し、全員で共有
5年生(高校1年生)の生物(選択)では、「呼吸」の単元で学んだ内容をもとに、生徒がFormsを使って多肢選択型の問題を作成する活動を行っていた。タブレットやスマホなどで検索したり校内生成AIに質問したりする生徒が多いが、教科書や資料を調べる生徒もおり、各自が思い思いのやり方で作業を進めている。今回は時間内に1人5問つくることを目標として、作成した問題はTeamsで共有する。各クラスで作成した問題を共有すると、5問×180人で900問が集まることになり、他の生徒がつくった問題を解いてみることで、知識の定着を図ることもできる。
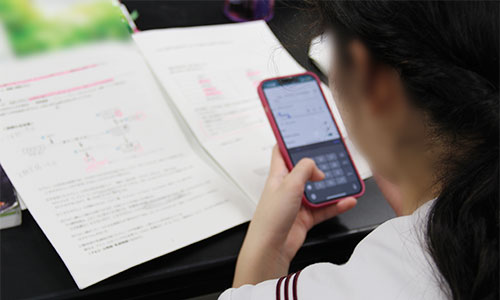
世界史探究:イスラム教の特殊性と普遍性についてペアでディベート
同じく5年生の世界史探究(選択)では、なぜイスラム教が世界を席巻することになったのかを考える授業の中で、イスラム教の特殊性と普遍性について、隣同士の生徒がペアになり、それぞれ「特殊」と「普遍」の立場でディベートを行っていた。ここでは多くの生徒が校内生成AIとの「対話」を何度も繰り返して、自分の納得できる回答を求めていた。

これらの授業では、生徒が質問したり検索したりするためのツールの1つとして、生成AIを使いこなしていることが見て取れた。
情報Ⅰ:英国大使館とのコラボ授業 マルウェア解析に挑む
4年生(高校1年生)の情報Ⅰはイギリス大使館とのコラボ授業で、イギリスの多くの学校で行われているサイバーセキュリティのカリキュラムから、マルウェア解析の実習(2時間連続)を行っていた。
アメンタムジャパン株式会社のパットン・アレグザンダー氏が講師を務め、3~4人のグループでデータ変換アプリを使ってプログラムのコードの中から悪質なコードに見立てた特定の文字列を探し出す、というものである。作業の説明はパットン氏がすべて英語で行い、使用する教材やアプリも英語表記だ。最初は何をすればよいか理解できない生徒も多かったが、初めから先生に頼るのではなく、翻訳機能を使ったり、検索したりして、判明したことについて、生徒同士で相談したり、校内生成AIに聞いたりしながら作業を進めていた。

個人で進める人もいれば、数人で相談しながら取り組むグループもあり、取り組み方はそれぞれだが、分かったことは自然に共有されていく。先生やパットン氏に質問するのは、さまざまな手段で調べた上で分からなかったことを訊ねることになり、その際も「どこが・どのように分からないのか」ということを明らかにするように促されていた。
最終的に、1~2グループがゴールまでたどり着いたようだ。今回の授業は、試行錯誤しながら手順を探す作業が中心であったが、この実習で体験したセキュリティの仕組みや、コーディングは、この後に学ぶ「情報通信ネットワーク」や「アルゴリズムとプログラミング」にも登場する。それらの授業で、この実習の経験を振り返ることになるため、今回は必ずしもゴールに到達することが目的ではない、とのことであった。

生成AIを普段使いの学習ツールとして
個別最適な学びを深める
公開授業のあと、情報科の主幹教諭の須藤祥代先生と、主任教諭の市川淳尉先生に、同校での生成AIの活用についてお話をうかがった。
独自にカスタマイズした校内生成AIで
安全性を確保
—まず、九段中等教育学校のDX環境について、教えていただけますか。
須藤先生 本校では、1人1台端末としてSurface Proをすべての教員と生徒に貸与しています。学習プラットフォームとしてMicrosoft Office365を2014年度から導入し、2020年1月から「情報の科学」のPBLでTeamsの利用を開始。同年4月の新型コロナウィルス感染症による臨時休校を機に、全学年でTeamsを利用したオンライン学習を進め、現在に至ります。
生成AIは2023年11月から専任教員と4年生(高校1年生)を対象に、校内生成AIの校務利用・教育利用のトライアルを実施し、2024年4月から全生徒・教職員に全面導入しています。今年度リリースした学校独自システムの校内生成AI「otomotto」は、ChatGPTやGemini、ClaudeなどのLLMモデルを自由に選択し、利用回数制限・文字数制限がなく使用できる、教育用にカスタマイズしたものです。
授業で使用するために収集したさまざまなデータは校内限りで扱い、校外のLLMモデルには学習・利用されないので、校内情報等も安心して利用することができます。また、学校内のデータを校内生成AIでRAG利用(※)できるようにし、それをもとに回答を生成するので、情報源が信頼でき、無関係な情報によって学習活動に支障が出ることも防いでいます。さらに、生徒や教員の作成したプロンプトを保存・共有できる仕組みもあり、教員が授業で使うプロンプトを作成し、指定することでスムーズな学習につなげたり、生徒が作成したプロンプトを皆で共有し、活用することもできます。
※RAG(Retrieval-Augmented Generation):プロンプトに基づき、データベースに登録された情報を検索・選択して回答を生成することで、回答の精度を向上させる仕組み
全校一斉のセーフティ教室で
生成AIの特性を体験的に学習
—生成AIを授業で使うにあたっては、情報の正確性や、ハルシネーション(事実に基づかない情報を勝手に生成すること)の問題が懸念されます。これらのことについて、生徒にどのように伝えていらっしゃいますか。
須藤先生 2024年度は、全生徒が校内生成AIを利用するため、4月初めに全校一斉のセーフティ教室を開催しました。そこで生成AIの特徴やプロンプトの入力の仕方のコツ、生成AIが得意なこと・向かないことなどを体験してもらい、その中で生成AIの回答が必ず正しいわけではないことを、使いながら体験しました。そのうえで、「生成AI活用の3か条」を生徒自身が話し合いながらまとめました。さらに、情報科では校内生成AI活用に向けてプロンプトエンジニアリングを学ぶ授業を実施し、「役割付与」や「条件設定」などの重要なキーワードを学び、生徒自身が効果的な使い方や注意点を調べてまとめ、発表しました。
—教員間での事例やノウハウの共有についてはどのようにされていますか。
須藤先生 使い方については、生徒とほぼ一緒で、2024年度当初に全教員に対して、使う上でのルールやハルシネーションなどの生成AIの特性の話をした上で、まずは触っていただいて、自分の授業でどのように使えそうかを考えたり、実際にハルシネーションが起きることも体験するガイダンスを行いました。今のところは、「とにかく使ってみよう」という感じなので、職員室のコミュニケーションが中心ですが、少しずつ事例も出てきましたので、私たちDX担当が先生方の事例を集めて、他の先生や校外の方に紹介するための準備をしているところです。
生成AIを普段使いのツールとして、
生徒が自分で判断・解決
—生成AIを使うことで、生徒の反応や行動が変わってきたことはありますか。
須藤先生 生徒を見ていると、よく使っている人ほど変な使い方はしていないことが分かります。今日の授業でも、困ったときに生成AIにまず聞いてみる、ということがよくありました。英語の授業では、英語でうまく表現できないフレーズを生成AIに相談して、「もっと簡単な言い方にして」「もっとシンプルに」と指示しながら、自分が言いやすいフレーズを一緒に考えることができ、それによってプレゼンテーションがしやすくなった、ということがあったそうです。生徒にとっては、今までは相談相手が先生一人だったのが、まず生成AIに聞いてみることで、生徒自身で判断できるようになり、良い意味で個に応じた学び、多様な学びができるようになったと思います。
市川先生 生成AIは単なる検索と違って対話型なので、「自分で調べてみる」という部分で、学びの深まりがあると思います。生成AIを使って解決できるものは自分で解決して、その後に、私たち教員に質問してくるときには、より本質的な部分を聞いてくるようになっていると感じています。
—最後に、今後の生成AIを使った活動の展望を教えてください。
須藤先生 特別に生成AIに特化する、いうことではなく、普段使いの学習ツールとして活用できるようにしていきたいです。GIGA端末とスマホ、紙と鉛筆の使い分けのように、検索して調べること、グループの友達や先生たちに教えてもらったり相談したりしながら解決すること、生成AIとの対話の中で深めていくことを、生徒たちが自ら日常的に使い分けて、それぞれの課題に取り組めるようになっていけたらよいと考えています。生成AIを導入することで、学びの質や速度は確かに上がっています。これからは効率化してよい部分と、そうではない部分を見極めて、いろいろなツールを組み合わせて課題に挑んでほしいと思います。
この記事をシェアする



