- 2025年02月25日

この記事をシェアする
高校教員が振り返る
新課程初年度の共通テスト
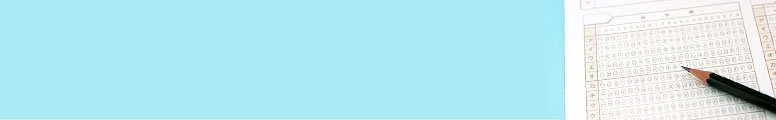
教科・科目の新設や再編、試験時間の延長など、多くの変更があった2025年度大学入学共通テスト(以下、共通テスト)。そこで今回は、変化の大きかった4つの教科について、ご担当の先生方を対象に本試験実施後にアンケートを実施。先生方が新課程初年度の共通テストの問題について、どのように受け止めたのかをうかがいました。
なお、河合塾では、試験当日に解答と分析を速報として公開しています。本記事とあわせてご確認ください。
数学
2025年度の共通テストでは、数学②が「数学Ⅱ,数学B,数学C」の1科目に再編され、選択項目数が2から3に増加するとともに、試験時間が10分増となりました。今回は「数学Ⅱ,数学B,数学C」について、「難易度・出題分量」「出題傾向」はどうであったのか。今回の問題を踏まえて、今後どのような対策が考えられるのかについて、うかがいました。
難易度・出題分量
やや難しい問題も丁寧に誘導。出題分量は適切
難易度について、先生方からは「ちょうどいい」あるいは「やや難しい」、出題分量については「ちょうどいい」あるいは「やや多い」との意見が寄せられました。難易度については「文系生にはやや難しい」というご意見、出題分量については大問数そのものの多さや、問題設定や思考過程の記述が丁寧すぎるというご意見が挙がりました。なお、大学入試センターが発表した平均点は51.56点と、昨年の「数学Ⅱ・数学B」の57.74点と比べて低下しています。
- 各大問の量や難易度はそれほどだが、大問5つ分は多いように感じた。 (東京・私立)
- ①それぞれの問題の難易度は高くないものの、問題の設定に関する記述や思考過程の補助記述が多く、丁寧に読み進むと時間が足りない。②素早く解き進めることが求められるため、第4問で格子点の端点を含んでしまうなど、問題の設定を読み落としてしまう等の本質と違うところでのミスで失点している生徒がいた。③第7問の「ZZバーを掛けて」のように、思考過程が丁寧すぎて「そこを考えさせるんじゃないの?」という所が誘導されている所が腑に落ちなかった。④余白が少ないページが多く、計算スペースに関して不親切なページもあった。⑤ページをめくる回数が多くて解きにくい。 (神奈川・公立)
- 教科書に書かれている事項をしっかり理解しておかないと対応できないので、問題の難易度は高めと思われる。しかしながら、問題の分量が多すぎたり少なすぎたりする印象も受けなかったので、問題の分量はちょうどよいと思われる。 (和歌山・私立)
- 国立大学志望の文系の生徒にとっては難しく感じたように思える。分量については計算も許容範囲内であり適切であったと考える。 (福岡・私立)
出題傾向
新設の複素数平面は基本に忠実な内容
今年度から導入され、第7問で出題された注目の複素数平面については、基本に忠実な例題を問われたような内容とのことで、それほど難易度は高くなかったこともあり、次年度の難化を警戒する声もありました。形式面でいえば、極端に長い説明文等は減ったようですが、一方で思考過程の記述量に関する指摘もありました。
- 極端に長い会話文や説明文は減ったように感じる。微積の内容では、グラフを交えた問題や、公式をそのまま問う問題があり、かつてのように積分の計算力勝負は完全になくなった。2次曲線・複素数平面は、基本に忠実な例題を問われたような内容であった。 (東京・私立)
- ①「数式での処理が、図形的にはどのような変化にあたるのか」を考えさせる問題は良いと思う。積分やベクトル、複素数平面の問題に見られたが、今後も続けて欲しい。②統計的な推測の問題は、教科書レベルを逸脱しておらず、適切なレベルだったと思う。③複素数平面の難易度がそれほど高くなかったので、理系は複素数平面を選択し、文系は統計を選択する傾向になりそうな気がする。④分量が多いゆえの丁寧すぎる思考過程の記述のせいで、「いわれた通りやっていたらなぜか解けた」状態になってしまい、得点と理解度がやや比例していない傾向が見られた。⑤共通テストの問題は、深い理解を問う意味で「授業で使う」には良い問題だが、70分という短い時間で解く問題には適さない。理想を詰め込みすぎているように感じる。 (神奈川・公立)
- 必修問題の出題分野はこれでよいと思われる。ただし、微分・積分に関しては普段からグラフをかいて考えさせる習慣をつけさせないと厳しいと思われる。選択分野も数列・ベクトルは二次試験まで見据えて演習しないと厳しいが、統計はセンター試験の頃からおおむね変わらない印象がある。なお複素数平面については、次年度の難化と二次曲線の出題を予想せざるを得ない。 (和歌山・私立)
- 微積についてはもう少し出題の仕方があったように思う。ベクトルについてはベクトルの知識を問う問題が後半はほとんどなかったので準備をしていた生徒はかわいそうだった。 (福岡・私立)
今後の対策
解法の応用や根本からの正しい理解が必要
今年度から、70分で5題という限られた時間の中での解答を求められますが、共通テストの形式に合わせ、解法通りに類題を解かせるような「トレース」する活動や、学習事項の根本からの理解を促す授業、解法・数式処理の正しい理解を伴う授業が必要となってくるとの指摘がありました。
- 解法を示し、「そのやり方」で類題を解かせるなど、トレースする活動が必要と感じた。 (東京・私立)
- ①学校で利用している教材の問題と共通テストでの問われ方が大きく違うため、「教科書を教える」ような教え方では、共通テストで点数が取れる生徒を育てていくことは難しい。出版社や予備校の教材が、共通テスト風の問い方・視点にできるだけ早く変更していくことを期待する。②「なぜこの解法で解けるのか」「この数式処理にはどのような図形的意味があるのか」など、正しい理解を伴うような授業をしていくことが必要である。③最も深刻な問題は、授業時間が足りないことである。統計が新たに増えたが、共通テストに出題されない整数も授業で扱わないといけないため、単純に時間が足りなくなっている。簡単に言うと、1.2倍のスピードで進み、2倍の深さで理解させる授業を行わないといけない感覚である。④文系に複素数平面を教える時間はとれない。⑤1、2年ではセンター試験の時代と同じように、基礎の理解と典型問題の習得に努めつつも、定期試験等で共通テストを意識した「正しい理解を必要とする問題の出題」を実施することで、生徒の思考力を高めていきたい。 (神奈川・公立)
- 「計算して答えが合えば良し」は共通テストでは通用しない、の予想通りである。生徒からは評判は悪くても、単元の授業では学習事項を根本から理解させる授業を、演習の授業ではどうしてそのような解法で解くのかを掘り下げる授業、を引き続き行っていく。 (和歌山・私立)
- 国立型であれば二次の内容と共通項をとりながら二年次より少しずつ始めていけばそんなに負担感を感じずに臨めると考える。本校理系の生徒は共通テストの演習は4回であったが平均が160点だったことを考えると実現可能であると考える。 (福岡・私立)
国語
「国語」では、2025年度の共通テストから第3問が追加され、試験時間が10分増となりました。第3問は、2022年に大学入試センターが発表した「試作問題」の「第B問」に似た部分のある、グラフなどを用いた問題でした。第3問が追加されたことに伴い、「難易度・出題分量」「出題傾向」はどうなったのか。今回の問題を踏まえて、今後どのような対策が考えられるのかについて、うかがいました。
難易度・出題分量
「選択肢減少」「平易な読み取り」で取り組みやすく易化の印象。問題量は「やや多い」
難易度については、「全体」と「第3問」と分けてうかがいましたが、先生方からは「易しい」あるいは「やや易しい」、出題分量については「やや多い」あるいは「ちょうどいい」との意見が寄せられました。注目を集めていた第3問が平易だったこともあり、易化した印象が強いようです。また、選択問題の大部分が、5択から4択に変更されたことや、選択肢の違いも明確で、受験生にとって取り組みやすい内容だったとの意見が挙がりました。大学入試センターが発表した平均点も126.67点と、共通テストとしてはかなり高く出ています。ただし、次年度以降は難化することも想定されるため、注意が必要です
- 大問が一つ増えた代わりに、選択肢の数が一つ減ったことで、解答にかかる時間はセンター試験並みに感じた。 (宮城・公立)
- 全体としては、資料の読解と分析を第3問に任せたことによって、素材文の理解を純粋に問う形式になった印象がある。そのため、過去の本試験と比較して易しくなったと感じる。第3問も、世間の衆目を集めるためであろうか、平易な読み取りと設問に終始した印象がある。 (福井・公立)
- 大問5題、90分枠の中における分量は妥当だと感じました。新設の実用的文章のテーマも認知されている分野からの出題であり生徒たちも戸惑うことなく対処できた、と言ってました。 (神奈川・公立)
- 今年度から試験形式が変わることもあってか、非常に易化した印象。選択肢が4択となっただけでなく、選択肢の違いも明確で、ほとんど迷う問題がない。第3問はグラフの読み取りにやや意地の悪さを感じたが、間違えるほどではない。大問1と2では複数資料も見られず、古文と漢文がかなり易しいため、時間も不足することはなかったと考えられる。 (京都・公立)
- 第3問が予想以上に平易であったことから、10分の増加に対して10分かからずに解けると考える。 (兵庫・私立)
- 難易度はあまり高くないが、読解ではない。日本語能力を聞いているのかわからない。クイズなのか? (徳島・公立)
出題傾向
第3問が新設されたものの、全体的にシンプルな出題
第1問、第2問は1つの文章からの出題となったことに代表されるように、先生方からは、「センター試験の流れをくむような出題」「シンプルな出題」という印象や、「易化しすぎている」「見通しが立てにくい」という意見も寄せられました。
- 第1問と第2問は、従前のセンター試験に戻った印象を受けた。個人的には、この傾向のままで良いと感じる。 (宮城・公立)
- 今回、シンプルな出題に戻ったことから、共通テストはよりシンプルになってよいのではないかとの思いを強くした。漢字や語句の知識を問う問いの割合はもっと多くてもよく、基礎的な力をつけているかを確認する試験であるのが理想だと感じている。 (福井・公立)
- 選択肢4択になった問い、全体量を鑑みた上での出題者側の意図を感じました。当初、センター試験から共通テストに移行した後は[分量、分野が増え、到達点(平均点)は6割から5割に。難易度が上がり、更なる情報処理能力が求められる。]と告知された記憶がありました。が、そういう方針ではなかった? 次年度以降は上げる? 見通しが立て辛くなりました。 (神奈川・公立)
- 現代文は全体を通して、現代的な問題についての平易な文章を読ませ、受験者に考えさせようという意図が見られる。現実の社会問題にリンクさせた文章を出題しようという傾向が続けば、抽象度が高い文章が出題されることはなくなっていき、社会学的問題を扱ったものが増えると思われるため、小論文頻出テーマなどについて学んでおけば、対策しやすくなるだろう。大問1・2に〈資料〉や〈ノート〉といった、本質的でない資料が無かった点は評価できる。 (京都・公立)
- ①第1問はセンター試験からの流れを汲んだ共通テストらしい問題であった。問題の難易度は昨年通りであったが、同一マークを3連続で解答することに受験生は疑心暗鬼にもなったと考えられる。②第2問の小説語句の意味に関する問いがなくなったのはありがたい。2年間であったが受験生の負担はあったと思う。問6・7の傍線部は99年度山田詠美「眠れる分度器」を彷彿とさせる一見難解な傍線部であったが、選択肢はかなり甘く作成されていた。③第4問は極めてオーソドックスな問題であったと思う。問1の語句解釈問は易化しすぎている。④第5問は論語に関連した文章で抽象度は高かったが、例年と難易度は変わらないと感じた。個人的に問4は非常に良問であったと感じる。句法で単純に解ける問題でもなく、ただ文脈判断をするだけの問題でもない。漢文の構造を意識させた問題であったと思う。 (兵庫・私立)
- 基礎に立ち返ったのだろうが、簡単すぎて、設問だけで答えがわかるものも多い。韻文がないのは取り組みやすいが対策してきた生徒には肩すかし。 (徳島・公立)
今後の対策
一定の知識は担保しつつ、文章を読み取る力をつける
先生からは、一定の知識ベースを維持しつつも、文章の内容を正確に読み取る力が重要だとのご意見がありました。急激に指導方針を転換するのではなく、日々の授業を大事にしていくことが、共通テストの対策としては重要だと思われます。
- 第4問に関しては、細かい文法や単語の知識をもとにした読解に加えて、ざっくりと話の流れを追うための読解(古文の要約のようなもの)も必要だと感じた。 (宮城・公立)
- 複数資料の読解力を伸ばすことよりも、一つのテキストを正確に読み、解釈できる力を育てることが先決であろうとの印象を抱いている。 (福井・公立)
- 出題者側の全体的到達点(平均値)が何処に置かれているのか明らかにしていただきたいです。私の認識不足でしたらお恥ずかしい、が、改めて次年度以降の通知が出ている様であれば教えていただきたいです。なお、センター試験時代に得たデータ、毎年の平均値はほぼほぼ同じレベルを維持。その出題については敬意を表します。つまるところ、【高校1、2年生迄の教科書レベル】の理解力が測られているだけの事ですから、高校現場では【いかに日々の授業が大切である】か、を繰り返し繰り返し発信していく事に尽きると思います。 (神奈川・公立)
- 今年度の平均点が高かったことから考えて、次年度は難化することが予想されるため、急な指導方針の転換は危険だと思われる。大問1については、社会学的テーマについて触れさせることが有効であろうし、大問3への対策にもなる。大問2に関しては従来通りの指導で十分。古文に関しては、「言語文化」の編成意図から考えて、現代でも評価の高い名作への回帰や、近世あたりの思想・随想を現代との繋がりを問う問題などが考えられる。漢文は句形や語法の徹底もさることながら、文章・内容理解に軸足を置いた指導が必要と思われる。 (京都・公立)
- 処理しなければならない情報量が多いことは以前から変化はないが、難易度が推移していたここ数年から、昨年と今年では難易度が同程度であったことは非常に大きな意味を持つと感じる。また一昨年度までと比較すると大幅な易化ではあるが、この難易度で推移すれば高得点が確実に狙える教科となるだろう。2点大きな懸念があります。 1つが選択型の問題の限界を露呈する問題になりつつあるという実感があります。測る力が変化する中でセンター試験から共通テストで作問の変化が見られましたが、今年度はすべての設問で選択肢が4つになったことで、選択肢の内容構成がかなり易くなりました。その結果、共通テスト特有の選択肢の癖も簡単に発見する問題となりました。全国の塾講師や進学に鋭い国語教員は今年度の問題でほぼ確実に解き方を確立すると予想されます。テクニカルな練習をすることで、これまでの共通テストよりも、形式的にハイスコアが狙いやすい問題になってしまったのではと感じています。2点目は異なる文書の読み合わせが形骸化しつつある点です。特に古文漢文では同じパターンの作問が続いているように印象を強く受けます。選択肢の問い方も似たような形が続いています。今後共通テストが新たなパターンをどのように作問するかに期待せざるをえません。まとめますと、一定の知識ベース(かつてよりは大きく減少)、「選択肢の癖」に対する攻略法、共通テスト作問の基本。この3点をおさえるとかなりの高得点が狙えると感じています。 (兵庫・私立)
- 他教科が負担増であり、国語も増えているが、授業時間は削減されて増えることはない。地力があるかどうか、文章を普段から読んでいるかなどで決まってしまうようで、よくはない。志望理由や小論文でてんてこまい。 (徳島・公立)
地理歴史・公民
「地理歴史・公民」では、2025年度の共通テストから科目が再編されました。今回は、「地理総合,歴史総合,公共」を中心に「難易度・出題分量」「出題傾向」はどうであったのか。今回の問題を踏まえて、今後どのような対策が考えられるのかについて、うかがいました。
難易度・出題分量
一部資料の読み取りに時間は要するが、全体として無理のない出題
難易度・出題分量は、「ちょうどいい」というご意見が大半でした。難易度については、一部、資料をよく読まなければ解けないものがあり、思考力が求められる設問もあったようですが、全体として無理のない内容という印象のようです。問題分量としては、試作問題と比較しても、大幅に増加していないという理由から妥当だという意見もありました。
- 難易度は奇問が少なく良いと思いました。分量も適切だと思います。 (東京・公立・地理)
- 資料から情報を読み取ったうえで思考力を働かせて解答する問いがバランスよく配置されている。 (兵庫・公立・地理)
- 問題の難易度については、地理総合、歴史総合、公共ともに基本的な概念が問われていた。分量については、地理総合は資料からの読み取りが基本となる関係で多くなるのは仕方ない。ただ、歴史総合と公共について、文章が多いため、どこを読めばよいかわからない生徒にとってみれば多く感じたといえる。 (千葉・私立・地理)
- 読み取りに時間がかかるものもあるが、試作問題や昨年度までの共通テストに比して分量が大幅に増加しているなどということはない。 (東京・公立・日本史)
- 難易度は、地理総合、歴史総合、公共すべて全体的には標準的だった。地理総合では第4問でやや難しい設問もあった。歴史総合では試作問題と比べて世界史の知識のみで解く問題が増加してしまったのが残念だった。公共ではアーレントとハーバーマスがやや細かい知識だと感じた。分量については、地理総合、歴史総合、公共すべて妥当であろう。 (埼玉・私立・日本史)
- 日本史探究とセットだった第1問は、ちょうどよい難易度だと思う。高校レベルの知識が問われている。世界史探究とセットだった第2問は、簡単すぎると思う。中学までの知識でも解けてしまう。どちらも分量は適切だと思う。 (埼玉・私立・日本史)
- サンプル問題と比べて設問数が減っていた。リード文での設定がシンプルであった。 (愛知・公立・世界史)
- 歴史総合は世界史探究や日本史探究をやっていれば即答できるので「問題」としては簡単だが、歴史総合だけ、しかも授業が話し合い活動中心で教科書を網羅的にやっていない生徒にはしんどい。公共は倫理、政治・経済と被らない部分の出題になっているが、それだと3年ぐらいで問題が尽きるのではないか。特にここで憲法の出題を多少なりともしないと「歴史総合,地理総合,公共」と「公共,倫理」の人は憲法のことを勉強しなくていいという誤解を与えてしまうのでは。 (三重・公立・世界史)
- 公共 倫理や政治・経済と共通する大問1と大問4は適切だと感じたが、大問2と大問3は易しすぎる。 (東京・私立・公民)
- サンプル問題、試作問題と比較しても用いる資料に割く紙幅がコンパクトになっている印象です。また、旧課程よりも各リード文自体の長さは短くなっている、もしくはより設問に直結しているものになっている印象があり、難易度と分量が適切に調整されているように感じました。 (千葉・公立・公民)
出題傾向
「資料の読み取り」が多く、教科間で関連する内容も
全体としては、グラフや表などの資料の読み取りが多かったという意見が多くあがりました。また、他教科と重なる内容や、知識を援用するような出題もあったという指摘や、「歴史総合」の出題内容についてはさまざまなご意見がありました。
- 基礎的な世界史の知識を援用する問題があり、これは評価しています。歴史総合も必修科目なのですから、歴史で得た知識を地理を解く際に使うのは好ましいと思っています。 (東京・公立・地理)
- 出題傾向について、地理総合は地理探究の内容は知らなくても解ける出題傾向で、大項目を軸に出題されていたため、妥当であるといえる。歴史総合は、グローバル化と私たちの問題がテーマ史等と絡んでいるため、意識はなされていたが、年代配列は従来と変わらず、資料があまり根拠とならない問題も存在した。公共については、出題形式は知識に傾く傾向が見られる。ただ、知っていかないといけない基礎的な部分も存在するため、なんともいえない。 (千葉・私立・地理)
- 問題の内容も現代社会でクローズアップされている事象と合致しており、生徒たちが解きやすいものとなっている。 (千葉・私立・地理)
- 資料の読解が多く、解答に時間がかかったが、予想通りの傾向と言える。 (埼玉・私立・日本史)
- 歴史総合が「近代化」「大衆化」「グローバル化」の「グローバル化」分野の時系列並び替え問題が多く、しかもそれぞれに因果関係がないので、結局、年代暗記なのかというメッセージになってしまった。 (東京・公立・世界史)
- 多様な資料の読み取りが求められていた点は、授業の質的転換を促すものになっていたように感じる。一方、清仏戦争やカストロ、男女雇用機会均等法(これは公共との重なりがあるところ?)など、歴史総合としては細かい情報の年代が求められたという点は出題者と教師間のミニマムに関するズレがあったのではないか。大きな枠組みで捉えること、あるいは因果を考察することで判断できるような出題であってほしいものである。内容としては、日本史と世界史を区分するようなテーマや出題ではなかったということは強調したい。日本史が多いとか、世界史が多いとか、そういう視点ではなくて、歴史総合らしいかどうかを意識していきたい。 (愛知・公立・世界史)
- 大問4(「公共,倫理」や「公共,政治・経済」では大問2)で倫理分野の出題があったが、倫理と政治・経済を公平にするために倫理分野からの出題であり、この方向性はいいと思うが、ハーバーマスとアーレントは公共選択者における倫理分野としては少し難しいのではないか。また、公共の教科書で頻出の思考実験や公正、義務論などは出なかったのは意外であった。 (東京・私立・公民)
- どの科目もコンピテンシーベースの設問になっているように感じました。「国語」がわかれば解ける問題も多く感じるのは、コンピテンシーを問う問題になっているからかと思います。公共であればもちろん、アーレント⇔ハーバーマス、実質的平等⇔形式的平等といった知識を前提にはしているので、コンテンツを無視するわけにはいきません。ただ、単に「帰納法」を知っているかどうかではなく、帰納法的な思考法を使うと哲学対話で出てくる感想をどのように分類できるのかという思考力が問われています。また、サンプル問題、試作問題でも取り組まれていた、おそらく教科書に出てこない新出キーワード(フードドライブ等)についてその内容を推察させる問題は「クラウドファンディング」が該当すると思いますが、これは知っている/知らないが時事問題への関心に影響を受けるものになってしまっているかと思いました。 (千葉・公立・公民)
今後の対策
「資料の読み取り」は丁寧に、知識偏重になりすぎず思考力をはぐくむ
指導を大きく変更する必要はないとしつつも、知識を直接問うだけではなく、資料の読み取りを行ったうえで、知識・技能と関係づける思考力・判断力が必要になるとの意見が寄せられました。また、知識偏重になりすぎることなく、大きな枠組みで捉えていくような指導が重要になってくるとの指摘もありました。
- 地図を観てさまざまな考察をする必要性。 (東京・私立・地理、日本史)
- 根拠を持った思考力が問われていると感じる。授業ではなぜ?をしつこく問うていきたい。 (福島・公立・地理)
- 地図帳、GoogleEarth、地理院地図、新旧地図、データ統計をできるだけ授業中に取り入れ習慣化する、タブレット活用は不可欠、今までとあまり変わらず。 (新潟・公立・地理)
- 地理総合については引き続き諸資料との関連付けと、マルチスケールを意識させて着目する点を生徒と学んでいく。歴史総合については、軸となる歴史的事象を利用しつつ、他国の歴史や日本の歴史を見ていく必要があるといえる。公共については、選挙や裁判、ジェンダー、経済という分野を織り交ぜて学んでいく必要があると考える。 (千葉・私立・地理)
- 地図や統計、写真、文書をはじめとする各種資料の読み取りなどのスキルがますます重要となり、そのための時間を普段の授業で確保していく必要がある。知識習得型の学びから探究型の学びへのシフトが必要であることを切に感じる。 (千葉・私立・地理)
- これまでの「共通テスト」対策と比べた時に大きく変更すべき点はないだろうが、おそらく1年次に置かれることが多いであろう歴史総合の内容を、特に日本史選択者が3年次に振り返る機会は設定した方がよいかもしれない。 (東京・公立・日本史)
- 歴史総合を1年次で全範囲きっちりやること。それに尽きるかなと思います。 (埼玉・私立・日本史)
- 「歴史総合,日本史探究」の第1問(歴史総合の第1問と共通問題)では、世界史分野が多いようにうつるが、実際には日本史探究で近現代史をしっかり学習していれば解答できる問題が多い。問2は清仏戦争の知識がなくても解答にはたどりつけるし、問3も穀物法の知識がなかったとしても解答は可能である。問7の年代順配列問題のみ、世界史の知識がなければ解答は不可能である。この問7を気にしすぎて、歴史総合の授業を知識偏重にする必要はないだろう。今回の問題を見る限り「歴史総合,日本史探究」は満点が取りにくいが、膨大な知識の暗記を必修科目の段階で始めて満点をめざすのではなく、落ち着いて9割以上をめざす学習を推奨したい。複数資料の読解に対応する力を身につけるために、国公立大学の問題を有効活用していきたい。生徒の学力レベルにあわせてヒントを加えるなどの工夫をすればさまざまな学力層で使用は可能であると考えている。これまでも名古屋大学などの問題を活用していたが、そのような指導が今回の共通テストでさらに有効になったと自信を深めている。 (埼玉・私立・日本史)
- 資料というか文章の読み取りを注意するよう指導する。 (東京・公立・世界史)
- 年代整序の2問を除き、求められる知識は中学校レベルの内容、あるいは歴史の転換点として大きな枠組みで捉える上で必要な事象程度であった。一部の教科書に見られる、知識偏重型の教材を用いて、知識を獲得することを目的とした授業をしていては生徒の不利益になるということが明らかとなった。多様な資料を活用する授業にしていかねばならないと感じさせられた。 (愛知・公立・世界史)
- 旧課程の過去問と、今回の問題を参考にしたい。 (秋田・公立・公民)
- 日常の授業から、得た知識を活用して文章化する必要があると考えます。またこれまでもグループ学習をしてきましたが、対話によって思考を深める学習活動は今後も必要だと考えています。知識は反転学習で習得して、授業では生徒の活動を主体にしていくことが今後ますます重要になると考えています。 (東京・公立・公民)
- どの科目もコンピテンシーベースの設問になっているように感じました。地理総合、歴史総合、公共ともに、従来型の一問一答というよりも、統計や資料を読み込む中で、必要な知識・技能の伝達という手順のひっくり返しが効果的だと感じています。また、地理総合と公共の親和性も改めて感じました。統計資料の活用方法など、教科横断的なカリキュラムマネジメントの必要性を感じました。 (千葉・公立・公民)
情報
2025年度の共通テストから新設された「情報Ⅰ」。国立大の一般選抜においてほぼ必須受験となった一方で、過去問がないため対策に悩んだ受験生は多かったことでしょう。また、指導する情報科の先生方も、共通テストの指導はほぼ初めてのことであったと思われます。 「難易度」「出題分量」「出題傾向」はどうであったのか。今回の問題を踏まえて、今後どのような対策が考えられるのかについて、うかがいました。
難易度
「素直な問題」で取り組みやすく、試作問題より易化の印象
ほとんどの先生方から、「易しい」あるいは「やや易しい」との意見が寄せられました。河合塾による分析速報では「試作問題と同程度」としていましたが、アンケート回答では、特にプログラミングやシミュレーションについては、試作問題よりも易化した印象が強いようです。 全体的には問題文が読みやすく、ひねった問題も少なく、受験生にとって理解しやすい内容だったとの意見が多数を占めました。模試でしっかりと準備してきた受験生は、易しいと感じたことでしょう。 大学入試センター発表の平均点も69.26点と、共通テストとしては、かなり高く出ています。ただし、これまでも、新課程初年度は、やや易しい問題が出題される傾向がありました。旧情報の出題がなくなる2026年度入試以降は難化することも想定されるため、注意が必要です。
- 情報を読み取ることで解答できる問題で、思考する問題についても素直な問題が多かった。 (東京・公立)
- 知識を問う問題が限定的であり、プログラミングの領域も素直な問題であったため、易しいと感じた。 (神奈川・公立)
- 情報Ⅰの内容が少なかった。 (千葉・公立)
- あまりひねっていない、すぐに答えを出しやすい問題が多い印象。 (神奈川・私立)
- 特にプログラミングが読み取りやすく、素直なアルゴリズムの読み取りであったことと、リード文が丁寧で、本番の問題の方が今後の情報の試験の方向性を示しているように感じた。 (岡山・公立)
- プログラミングもシミュレーションも解きやすかった。 (鹿児島・公立)
- 知識問題やプログラミングの難易度がかなり易しかった。 (京都・公立)
- 読解量が少ない。選択肢が絞り込みやすい。単調な問題であった。 (大分・公立)
- 「シミュレーション」「プログラミング」については試作問題よりも易化した印象。逆に「データの分析」に関しては、煩雑さは試作問題とあまり変わらず、むしろ各社の模試問題に比べて難化したように感じます。 (群馬・公立)
- モデル化とシミュレーションのリード文にある出現確率の乱数は、試作問題の到着間隔の累積相対度数よりも理解しやすく、受験生にとって問題文が読みやすかったと思う。 プログラミングは関数が出題されず、アルゴリズムの説明が問題文にあるので、プログラムを理解しやすかったと思う。 試作問題では、「上手な払い方」の考えを理解できない生徒が一定数いた。それに比べると共通テストの問題は理解しやすい内容だったと思う。 (北海道・公立)
- シミュレーションのように典型的な問題が出題されたり、マウスの操作のように設問を読み取れば解答できる問題が多く見られた。 (鹿児島・公立)
- 大問3、4に関しては関数の有無や回帰直線の有無などがあるが、試作問題と比較してプラスマイナスゼロで難易度(時間の消費も含む)は同程度かと考えられる。 しかし、大問1、2については文章や図表から理解して処理する強度が低くなっている(数学的要素を勘案しても)ので、全体的に見て「やや易しい」と判断した。 (東京・公立)
- 二進法の計算・論理回路などコンピュータサイエンスに関する知識を問う問題がまったくなく、プログラミングも特殊な関数もまったく使われない極めて単純なものだった。 (千葉・私立)
- モラルの問題がなく、知識問題に変わっていたが、他はあまり難易度が試作問題から変わっていないように感じ、しっかり準備できていた生徒は点数が出たと思う。 (岡山・公立)
- 試作問題と同様に設問文を丁寧に読んで考えれば解答を導き出せるようになっていた。もう少しヒントが少なく作成されるかなと思っていた。 (岡山・公立)
- 総合的な知識が求められたので、やや難しい。たとえば、共通テスト第4問では、散布図と相関係数と四分位数など組み合わせた思考が求められたが、それに対して試作問題では、それぞれの項目ごとの思考だけで解答できた。 (兵庫・公立)
出題分量
問題量は「ちょうどよい」。問題を読み取る力次第では時間不足も
解答マーク数は試作問題から3つ増えて51でしたが、問題量としては試作問題と同程度でした。先生方からも「ちょうどよい」との回答が多く寄せられました。しかし、思考・判断させる問題はどうしても問題文の文章量、図・表が多く、受験生にとっては負担に感じられるといった意見もありました。試作問題と比較すると理解しやすい問題であったとはいえ、問題を読み、情報を整理し、判断するスピードが求められました。
- 試作問題よりも素直な問題が多く、生徒が解答する時間が短縮したと思われる。 (大阪・私立)
- 見直しの時間まで確保できそうな配分でした。 (鹿児島・公立)
- 時間が足りなかったという声は少ない。 (愛知・公立)
- 問題文の文章、図・表の量はやや多く、解答に時間を要した受験生は多いと思う。解き直したり、じっくりと考える時間はあまりなかったと思う。 (北海道・公立)
- データ分析のところが特にそうであるが、きちんと問題文を読んで意図を誤解なく読み取るのには時間が必要だと思われる。そこにそれなりに時間を使える構成に思えた。 (愛知・私立)
- やはり、文章を読んで思考・判断させる問題はどうしても問題文が長くなり、「理系の国語」的な印象を受けました。ややもすれば、本来の情報Ⅰで見取りたい能力よりは、文章を素早く読んで処理する能力に特化した問題になっているような印象です。 (群馬・公立)
- 難易度が低いため時間は余るかもしれないが、問題量としては妥当だと感じる。 (長野・私立)
- 時間に対し問題量は多めだが、その分負荷が高く、受験者の力量を測れる。 (京都・私立)
- 場面設定等の説明の文章が長い。 (京都・公立)
- 慣れていないと時間内には解けないだろう。 (岡山・公立)
出題傾向
問題構成、出題分野など試作問題から変化なし。今回出題のなかった分野に注意
第1問=小問集合、第2問=中間的な設問、第3問=プログラミングの大問、第4問=データの活用の大問と、試作問題と同じ問題構成で出題されました。 「教科書の内容からまんべんなく出題」「実社会との結びつきを重視した問題」といった傾向も継続しています。先生方からも、試作問題と同様の傾向であったとする回答が多く見られました。 一方、数学的な思考に依存する問題が多かったとの意見もありました。また、ネットワークや知的財産権など、今回の本試験では触れられなかった分野について指摘する声も多くありました。 「まんべんなく」とはいっても1回の試験ですべての分野を網羅することは不可能であり、このような分野については2026年度入試以降に出題される可能性もあるため、注意しておきたいところです。
- 傾向は試作問題とほとんど同じだった。 (長野・私立)
- 試作問題の流れを継承しており、試作問題に取り組んでいた者は問題なく対応できたであろう。 (富山・公立)
- 試作問題と同じ傾向だと思う。難易度が低いのは、「旧情報」との平均点の差が少しでもつかないようにしたためで、その結果プログラミングの問題が易しくなったと思う。 (北海道・公立)
- 知識が必要な問題は少ないが、知識があったほうが解きやすい出題傾向だったと感じる。 (神奈川・私立)
- 情報Ⅰの内容が少なく、読解力・分析力に偏っている。 (千葉・公立)
- 場合の数やグラフの性質など、数学的な思考に依存する問題が多かった。 (大分・公立)
- 次年度以降を意識して出し惜しみした印象です。 (鹿児島・公立)
- 二進数やネットワークの知識が必要となる問題がないことを感じた。 (神奈川・公立)
- 法律関係がないのは意外。それ以外は順当だったかと。 (愛知・私立)
- データの活用に偏重している。個人情報や著作権など情報社会に関する問題がほとんどなく、内容に偏りがあった。 (京都・私立)
- 情報モラルや著作権等の法的知識に関する出題(情報社会の問題解決)がなかったが、情報モラルやAIなどは現時点での大きな社会問題である。少しでいいので出題があっても良かったのではないかと感じている。 (兵庫・公立)
- ネットワークと法規、アルゴリズムではなくてプログラミング言語によるコンピュータ内部の動作の仕組み、デジタル表現(計算限界)等の分野が抜けているが、すべてを網羅することは難しいため、次年度以降になると考える。 (岡山・公立)
- 最初の設問で電子署名とIPv6の話が出題されていてちょっと戸惑った。プログラミングやデータ分析の問題は簡単で解きやすくなったと思う。 モデル化とシミュレーションの問題はよくある題材だったので、生徒は解きやすかったと思う。スーパーのPOSデータの話は難しいかなと思ったが、生徒の得点状況などを見ると、きちんと考えられた生徒が多かったと思われる。 (広島・私立)
- 新課程の方針が具体化されたものだと感じた。情報処理技術者試験などで見たことのある題材や問題としてやや混乱を招く部分があった。 試作問題や今回の本試験から見て取れるのは、受験前の付け焼刃的な学習ではなく小・中・高と積み重ねた読解力や処理能力が発揮できるかどうかにかかっているのではないか。 他の教科も拝見して感じたのは、教科横断的な側面を必ず取り入れる工夫がなされている。将来を担う人材に求めている最低限のスキルが出題傾向として表れているのは確かだと感じる。 (東京・公立)
- 解いた感じは「旧情報」の方がおもしろい。「情報科」という舞台(障害切り分け・認証システムの吟味)の中で、思考力が問われている気がする。 あるいは、「全範囲をまんべんなく」という縛りが情報Ⅰより薄かったのも大きいのかもしれない。次年度の指導では「旧情報」「情報Ⅰ」の両方を参考にした方が良い。 (千葉・私立)
今後の対策
実習を中心に、体験の中で考えて理解する授業を
知識を直接問うだけではなく、学んだ事柄を問題の発見や解決に活用する思考力や判断力を必要とする問題が、今後も多く出題されるものと予想されます。 先生方からも、特にプログラミング、シミュレーション、データの活用の分野においては、実習を中心に、生徒が体験しながら考えて理解することを重視するといった回答が多く見られました。 授業の中で完結するのではなく、学校生活、日常生活の中で目にする事象や仕組みを、授業で習ったことと結びつけて、自分自身で考える習慣をつけることが、共通テストへの対応力を伸ばすことにつながるものと思われます。
- 情報Ⅰの授業で、実習を中心としながら、思考力・判断力等を向上することを重視します。 (東京・公立)
- 実習中心の探究型授業を続けていくことが大切。探究の中で知識を深めたり繋げたりする活動をしていくことこそが共通テスト対策。 (岡山・公立)
- 知識偏重の授業ではなく、実習型の授業が重要であると感じた。 (愛知・公立)
- 見慣れない設定の下で、情報の授業で学んだことをどのように生かせるかを考えさせることを重視したいと思います。 (鹿児島・公立)
- 知識問題は比較的簡単に終わらせ、シミュレーション・プログラミング・データの活用を、実習を交えて演習するのがいいと感じました。 (群馬・公立)
- 細かな知識の注入に深入りせず、実際にデータ分析やプログラムを組む時間を大事にする。 (千葉・私立)
- シミュレーションやプログラミング、データ活用の分野は実習もふまえて体験的に理解させた方がいいと思った。 (大阪・私立)
- プログラミング、シミュレーションに関しては、これまで以上に「引き写すのではなく、実際に考えさせ、手を動かしてみる」実習が必要かと感じました。 (富山・公立)
- 問題への応用力と思考力が対策かなと思います。 (岡山・公立)
- 大問1にある計算問題が予想よりもできていなかった。場合の数の問題や、今回は出題されていないが画像や音のデータ量の計算もおさえておきたい。 データの活用の問題を具体的にグラフを読み取らせる、プログラミングは実際にPythonで組ませるなど、いろいろと手を動かして考えていくような活動をしていきたい。 (広島・私立)
- 共通テスト対策を講じると予後良好ではない。対策を練れば練るほど単純な椅子取りゲームとして受験を取り扱うならば悪手。授業等で、遠回りに思える一歩一歩が、実は一番の対策になると確信できた。 各教科が各教科の特性を利用して思考力や読解力、処理能力を伸ばすこと、その足並みをそろえることがキーになると考える。 (東京・公立)
- 数学科との連携。 (鹿児島・公立)
この記事をシェアする



