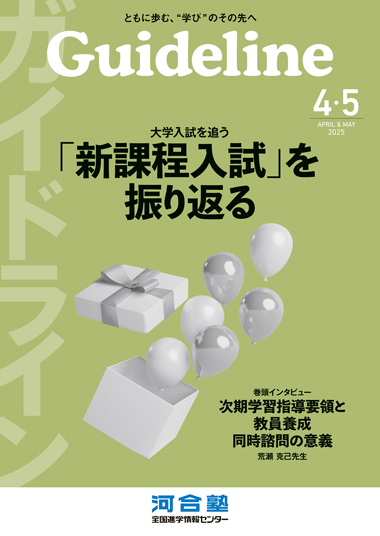- 2025年05月12日
- (Guideline 2025年4・5月号)

この記事をシェアする
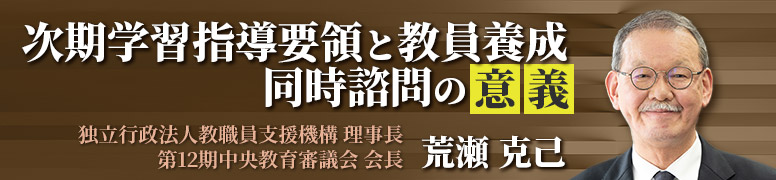
- この記事は、Guideline2025年4・5月号「次期学習指導要領と教員養成 同時諮問の意義」より作成しました。
教育課程と教員養成の在り方を同時に議論
昨年末の12月25日、文部科学大臣から中央教育委員会(中教審)に対し、「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について」および「多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成を加速するための方策について」の2つが、同時に諮問されました。前者は、初等中等教育における次期学習指導要領の方向性についての議論、後者はその学習指導要領に沿って指導を行う教員の養成、採用、研修等についてで、教職課程の在り方や、多様な専門性や背景を有する社会人等が教職へ参入しやすくなるような制度の在り方についての議論が要請されています。
諮問の背景については、それぞれの諮問理由に示されていますが、今回注目していただきたいのは、この2つの諮問が同時に出されたということです。当然、これら2つの議論は並行的に行われ、ほぼ同時期に答申が出されることになります。文科省はその答申に基づいて学習指導要領を改訂するとともに、教員養成、採用、研修に関する在り方に変更を加えることになります。教育職員免許法の改正も視野に入ってくるでしょうから、かなり大きな変化をもたらすことになるであろう議論が同時に展開していくことになります。ぜひ、そのあたりに注目していただきたいと思います。
そもそも、教育課程をどうするのかという問題と、それを運用する教員の養成をどうするのかという問題は、切り離すことのできないものです。中教審の初等中等教育分科会の中には、教育課程部会と教員養成部会が常設されていて、両部会を兼任している委員もかなりいます。両方を視野に入れながらの議論を期待したいと思います。
過去の答申を踏まえたうえでの諮問
2つの諮問は、これまでに出された中教審答申の流れを受けたものです。令和3年に出された答申「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して 〜全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現〜」では、子どもの資質、能力をどう育てていくのかをテーマに、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を図ることで、学習指導要領が求めている主体的、対話的で深い学びを実現し、自立した学習者を育てる道筋を示しました。
令和4年の答申「『令和の日本型学校教育』を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について 〜『新たな教師の学びの姿』の実現と、多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成〜」では、「令和の日本型学校教育」を実現していくには、どのような教師の在り方が必要なのかを考える中で、教員免許更新制度を発展的に解消するとともに、教師自身の学びを充実させることを提言しました。
さらに、令和6年の答申「『令和の日本型学校教育』を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について 〜全ての子供たちへのよりよい教育の実現を目指した、学びの専門職としての『働きやすさ』と『働きがい』の両立に向けて〜」では、質の高い教職員集団を実現するためには、学校における働き方改革の更なる加速化、教員数の増加を含めた学校の指導・運営体制の充実、そして教師の処遇改善の3つを一体的、総合的に推進することが重要で、教師が誇りを持って働ける職場をいかに整えるべきかについて示しました。
今回の諮問はこれらを踏まえて出されたものですから、諮問の中で示された論点は、これまでに見たことのない、まったく新しいものであるということでは必ずしもありません。すでに中教審でも、有識者会議でも議論されている内容も多くあります。ただし、今後の議論は、次期学習指導要領に反映し、大学での教職課程を含めた教員養成や、多様な人材確保のための幅広い採用や学びの在り方に大きく影響することになります。
高等学校の必履修に関する議論は必要
次期学習指導要領の検討では、何を変えるか、何を変える必要がないかという議論が行われます。
高等学校に限定しますと、高等学校教育の在り方ワーキンググループでは、学習指導要領はほとんど変えなくてもよいのではないかという意見が出ていました。
私も、現行学習指導要領の前文に示された教育課程に対する考え方を堅持しつつ「何も変えない」ということを、今回の最大の特色として打ち出してもいいと思っています。その一方で、現行学習指導要領の前文に示された教育課程に対する考え方を堅持しつつ、いずれ大きく変えるべきだとも考えています。
矛盾しているようですが、今回はしないにしても、高等学校の「必履修」という考え方はどこまで必要なのかという議論は、しないといけないと思っています。
義務教育の学び直しの部分については、現行の学習指導要領にも書かれていますし、今後も必要でしょう。その意味で、広く学ぶということは重要です。しかし、義務教育段階までに基礎は広くやっているわけですから、高等学校では生徒の興味関心に基づいてテーマを決め、履修する教科を絞れるようにしてもいいのではないでしょうか。自分のやってみたいことや得意なものを深める高等学校教育に転換していく必要はないでしょうか。
深い穴を掘るには、まわりも掘らなければなりませんから、一つのことを進めるにしても多くのことを学ぶことになります。今の教科の枠組みでいえば、複数の教科について学ぶことになるでしょう。学ぶことと学び方を自分で選ぶ。総合的な探究の時間が中心になる高校の学びを考えるべきではないかと思っています。

大学入試があるから無理だという話が出てくるかもしれません。しかし、大学入試がこうだから高等学校の教育課程はこうあるべきだというのは、逆の発想です。高等学校の教育課程がこうなっているので、それに沿って大学での学びに必要な能力を見るというのが本来であるはずです。このことは、大学との間で十分に議論していくことが大切だと思います。大学入試改革は、高等学校にとっても大学にとっても重要な課題です。
なお、これまでも「学習指導要領って本当に読まれているのか」という疑問の声が何度も出ていました。読まれていないとしたら、それさえ読む時間がないのではないかという見方もあります。それならばなおのこと、先ほど申した学校における働き方改革や、教員増を含めた学校の指導・運営体制が望まれます。
また、教師の負担になるようなことをどんどん足し算していくのではなく、これからは引き算をしていくことが大切なのではないかということも指摘されています。
教育課程部会・企画特別部会の石井英真委員(京都大学大学院教育学研究科准教授)がよく「less is more」という言葉を使われます。あれこれとたくさんのことを並べるのでなく、重要なものを概念化しておく。そうすることで、広がりのある、豊かなものを、それぞれが展開できるのではないかということでしょう。
ただし、そのためにも、教師が実践を工夫して、振り返って改善していく時間的余裕があること、そしてよりよい取組を展開するために、学べる機会が保証されていることが求められます。校内でも、教職大学院や一般の大学院などでも、学ぶ場のあることが重要です。学び続けるためには、周囲が環境を調えなければなりません。
教員の「養成観の転換」が必要に
2月に実施された教員養成部会において、教員養成に関して、興味深い視点が示されました。森田真樹委員(立命館大学大学院教職研究科教授)から、「養成観の転換」が必要ではないかとの意見が提示されたのです。子どもの「学習観の転換」やそれに伴う「授業観の転換」の必要性が強く求められており、私が所属する教職員支援機構(NITS)ではそのためには「研修観の転換」が必要だと主張してきましたが、それなら「養成観の転換」も図るべきではないかとのご報告でした。
森田先生のご意見は、大学卒業直後に教壇に立つ教師にはどんな力が必要なのかというところから、学部における教職課程を組み立てていく必要があるのではないかということであり、非常に重要な指摘だと思います。
教師に、基本的な知識や技能は絶対に必要です。ただし、知識や技能は経験とともに増えていくものでもありますから、教師が初めて生徒と向き合うときにどんな力が求められるのかということをまず考える必要がある、ということでしょう。
ならば、少なくとも相手の言い分や考えを理解しようとする姿勢や、自分の考えを相手に丁寧に伝えようとする姿勢は、きっと前提になるでしょう。アサーティブ・コミュニケーションですね。
さらに、ものごとをしっかり見つめ、問いを立てて取り組む力、また、何らかの課題に対して、それをどう受け止め、どう取り組んでいくかを考えたり、実行して改善したりしていく力は、どうしても欠かせないものだと思います。まさに「探究する力」です。
現行の学習指導要領の総合的な探究の時間が謳っている育成したい力と重なるこれらの姿勢や力は、さらにいえば、大学の初年次教育で学生に身につけさせたいと考えられている力にもつながっているのではないかと思います。

「探究する力」を結節点として議論を展開
このように考えると、「総合的な探究の時間」で育む「探究する力」は、高等学校や大学において、自分の進路や自分の在り方も含め、自分の学びを自分でデザインして進めていくときの軸になりうるものであると同時に、大学を卒業して社会人になってからも大事なものだといえそうです。そしてこれが、教師になる人にとっても大事な力であることはいうまでもありません。
高等学校の総合的な探究の時間は、生きていくための、あるいは仕事に就いてから仕事の質を高めていくうえで重要な取り組みなのだということを改めて意識する必要があると思います。予測不能な社会で生きていくには、自分で考え、行動していくことが求められます。情報の収集、活用、選択・決定、振り返り、やり直し…といったあらゆる場面で必要な「探究する力」。
教育課程をどうするかという議論と教員養成をどうするかという議論を結びつけるカギもまた「探究する力」だと思います。
荒瀬克己(あらせ かつみ)
独立行政法人教職員支援機構 理事長、第12期中央教育審議会 会長
京都市立堀川高校 教頭・校長、京都市教育委員会教育企画監を経て大谷大学文学部教授、兵庫教育大学理事、関西国際大学学長補佐などを務める。堀川高校在職時の1999年に「探究科」を設立。組織的に「課題探究型の学習」に取り組む学校改革を進め、生徒の希望する国公立大学などへの進路が実現したことで、「堀川の奇跡」として注目された。
- あわせて読みたい
-
- 進学情報誌「Guideline」2025年4・5月号
-
進学情報誌「Guideline(ガイドライン)」では、最新の入試動向はもちろん、広く教育界に関わる動きなど進路指導のための情報をお届けしています。
この記事をシェアする