- 2019年11月23日開催
学校と社会をつなぐ調査第4回調査 分析結果報告会
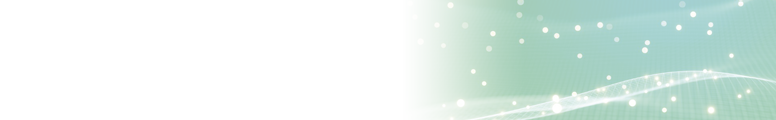
高校2年生から大学4年生まで 生徒はどう変わったか?
「学校と社会をつなぐ調査」は、2013年に京都大学高等教育研究開発推進センターと学校法人河合塾が共催で開始した、高校生を対象に10年間追跡する調査です。
この調査は、調査の企画・分析者の溝上慎一先生が桐蔭学園へ異動したことで、2018年9月より溝上先生と河合塾との共同で継続して実施しています。
調査協力者は全国378校の高校2年生45,311名にまでのぼり、2018年に実施した大学4年生時点の調査には、2,742名の大学生が継続して協力してくださいました。
溝上先生の言葉を借りるなら、「過去をふり返って回答させるふり返り調査はこれまでもありましたが、これほどの大規模な調査で、高校生の姿と大学生の姿を縦断的に繋いだ調査研究は皆無に等しく、昨今の高大接続、学校から仕事・社会へのトランジション(移行)の改革のなかで貴重な資料になるはず」です。
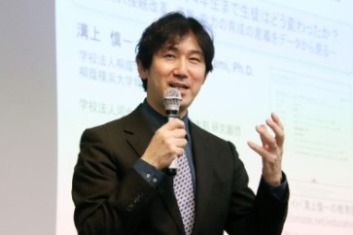
プログラム・講演内容
第4回調査 分析結果報告会では、2013年(高校2年生時点)から2018年(大学4年生時点)までの追跡調査の結果によって、高校生のときの学習や対人関係・キャリア意識が、大学生になっての学習や成長にどのように影響を及ぼしているのか、新学習指導要領の目玉である資質・能力はどのくらい変化するのかについて、報告いたしました。さらに、高等学校の実践事例や実際に調査に協力してくださった方に自身の結果に対してコメントをいただきました。
本記事では、プログラムとともに当日の講演内容の一部をご紹介します。
※所属・役職・講演内容は開催当時のもの
| 登壇者 | 講演内容 | |
|---|---|---|
| 調査報告 | 桐蔭学園 理事長 溝上慎一先生 |
|
| 高校事例報告1 | 桐蔭学園 佐藤透先生 |
|
| 高校事例報告2 | 中央大学附属中学校・高等学校 齋藤祐先生 |
|
| 公開インタビュー | 調査協力者(2名) | ― |
| 研究協力者コメント | 神奈川大学 特別招聘教授 安彦忠彦先生 |


齋藤祐先生

報告会参加者の声
- 学校と社会をつなぐ調査についてさまざまな角度から報告があり参考になった。長期的調査でありかつ規模も大きいので日本でもほとんどない調査で興味がある。
- 現時点での結果報告内容と高校の現場における課題解決の結びつきが明確にイメージできた。エビデンスを把握するための手法を具体的な報告事例に学ぶことができた。
- 溝上先生や調査協力者のお話から中高生・大学生のうちに育むべき資質・能力や空間的拡張の必要性がよくわかりました。キャリア教育は将来のことを考えさせればよいというわけではなく、将来を見据えるための土台をつくること、言い換えれば教科教育や探究活動を通した社会文化探求心を伸長させることを狙いとしなければならないと感じました。
- 大規模かつ継続的調査による分析結果のご報告は大変説得力があり資質・能力、二つのライフについての大きな変化はないとの結果があるものの、大学生に対してできる教育・施策について考えさせられるものがありました。分析の結果を協力者インタビューにより具体性を持ってより深く理解できました。齋藤先生のご発表には探究学習の具体的な方法について大きなヒントをいただきました。
当日アンケートの質問への回答
当日のアンケートに記載いただいた質問に、溝上先生から回答をいただきました。
溝上先生講演資料に記載されている低クラスの生徒への具体的な指導や教育についてはどうすればいいのか? アドバイスや参考になることがあればいただきたい。
低クラスは、いろいろな意味で達成感や自己肯定感の低い生徒でもあります。習得の達成を中心に教育・指導していくのがいいと私は考えています。正誤の明確な問題や理解をしっかり達成しているかを中心にして、考える問題など正誤があいまいになるのは徐々に増やしていくというイメージです。1つひとつの課題への取り組みの動機や達成を見ていく、最大限頑張ったところをほめていく、といったこれまでよく言われてきたことに尽きます。
溝上先生講演資料のスライド19からの低クラス~高クラスは、n=4,626で低、中、高とも一貫して同じ数字となっている。
(1)このn=4,626はいつの時点のものですか?
(2)低、中、高の数字は変わっていないので、クラス分けはn=4,626の調査時点で固定されているのでしょうか?
5時点すべての得点を一括で用いて潜在クラス成長分析しています。その度数がn=4,626ということです。多くの回答者は5時点の得点すべてを持っていますが、前に出たインタビュー参加者のように、大学のある学年を受けなかったという場合もあります。その場合は、全体の平均傾向から欠損値推定を統計的におこなって分析しています。
決め手となるのは、持って生まれた資質なのか、育った(育てられた)環境なのか。
一卵性双生児の遺伝と環境の研究からも、発達に関する説明要因の多くは「環境」だという結論です。誕生以来の環境によります。
中高一貫教育の優位性について、お考えがあれば教えてほしい。(中学からの)内部生は学力に自信がない子が多いように感じますが、大卒時の進路は、中学からの内部生の方が高校からの生徒よりも良い傾向にあり、溝上先生が最後にお話されたPタイプ2にあたる生徒が多いからなのかとも考えました。これまでの調査から言えることがあれば教えてほしい。
高校時に中高一貫校の生徒かどうかを尋ねています。統計的には、中高一貫の生徒だから発達が弱いとか勉強が弱いとかは言えません。逆も然りです。
- このページは日本教育研究イノベーションセンター(JCERI)によって制作されました。
お問い合わせ
- 学校法人河合塾 教育研究開発部 学校と社会をつなぐ調査事務局
- Email:kkt@kawai-juku.ac.jp
- 対応時間:10:00~17:00(土・日曜・祝日を除く)
- ※お問い合わせの際にご提供いただく個人情報は、お問い合わせへの対応のみに利用いたします。



