大学のおもしろい講義
- 大学のおもしろい講義
- 大学のめずらしい講義
Questionあなたの大学にある、おもしろい講義は何ですか。
※特派員のプロフィールはアンケート回答時点(2023年度)のものです。

東北大学 経済学部 4年 ぴ~ちゃん特派員
【ビジネスデータ科学】
講義の内容としては、前半でAIや機械学習について学び、後半は地元企業とタッグを組み、地元企業の悩みをデータ分析やAIを使って解決するというもの。文系ながら実際に手を動かしてデータ分析を体験出来たり、企業に対してプレゼンする機会があるなど、社会人になるまえに貴重な経験が出来たためおもしろかった。
筑波大学 人文・文化学群 3年 Y.K.特派員
【デザインと芸術】
問題が生じたときどのように解決する手段があるのかを絵で描いて説明する。例えば渓谷を渡りたいと考えており、その模式図が提示された場合、絵を半回転させ渡らなくてもいいと答えたり、実は巨人であり一歩で越えられたと説明したり、課題のペーパーに山折り・谷折り線を示し、折って提出するなど発想に驚く。人文科学をやっていると言語表現で論理的に説明することに注力し、思考が凝り固まってしまうが、芸術専攻の学生の発想が自由で面白いと感じる。
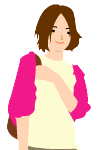

東京大学 文科三類 2年 サボテン特派員
【英語中級】
ノーベル文学賞受賞者によるスピーチを題材に、その解釈をみんなで進めていく授業で、講義というよりは各自発表したり議論したりする形式でした。高校までの、英語を日本語と一対一に対応させて訳すという作業では太刀打ちできないような、抽象的かつ哲学的な内容を扱いました。言語は一対一に対応しないそれぞれ独立のものだと思い知らされましたし、書いた人の文化的背景まで考慮しなければその表現している内容は受け取れないことを実感しました。
信州大学 医学部 2年 グリーン特派員
【生理機能検査学】
座学と実習の両方の授業があって、前期の前半は座学で心電図や超音波検査についての知識を学び、後半の実習では、実際に学生同士で検者、被検者となって心電図、心臓エコー、腹部エコーをとりあって、知識を定着していくという形の授業です。実際に検査の仕組みを知りながら、自分の体のことを知ることができるという点でとても興味深い授業だなと思いました。


名古屋市立大学 人文社会学部 2年 倫特派員
【児童・家庭福祉論】
子どもや家庭の貧困問題や虐待問題を扱う授業です。前半の講義では映像資料や文献をもとに子どもの置かれている状況について学びます。後半の講義では「ようこそ大学へ!」プロジェクトを運営するための活動をします。これは児童養護施設などで暮らす子どもを大学に招き、1日大学生体験をしてもらうプロジェクトです。前半で子どもの貧困や虐待について学んだ後、その知識を活かした活動ができるのがこの講義の面白い点だと思います。
慶應義塾大学 薬学部 4年 ベン特派員
【個別化医療】
1人1人に合わせた薬物選択を学ぶ授業。例えば同じ部位のがんでも、その患者さんの持つ遺伝子変異が違うと薬が変わることがあるということや、患者さんの年齢によって薬の量を調整することを学ぶ。決められた量ではなく、患者さんの特性に合わせて薬を調整するという、薬剤師の能力の重要性を感じられ、やりがいがある。

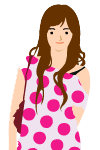
東京理科大学 理工学部 3年 Y.H.特派員
【機械計測学】
MATLABという数値解析ソフトを用いて、2次元だけでなく3次元点群のデータを読み取り物体の検出をします。他にも近似曲線(最小二乗法やRANSAC)の出力ソフトなど自分でコードを考えて実行すると言う授業です。この間はAmazonなどで実際に使われている技術である「興味のあるものを数値化する」というものを作りました。
愛知大学 法学部 2年 M.M.特派員
【判例研究(憲法)】
20人程度のゼミ形式です。憲法学における有名な判例(ポポロ事件やチャタレー夫人の恋人事件など)の原文を読み、論点について意見を出し合います。堅苦しい憲法上の論点だけでなく、生活保護で最低限必要と感じるものは?など、より身近に引きつけて考えることも多いです。最高裁が出した考えでも、ちょっと不思議・疑問かもと感じることも多く、判例に対する向き合い方が変わる面白い授業です。




