- 2024年04月15日

この記事をシェアする
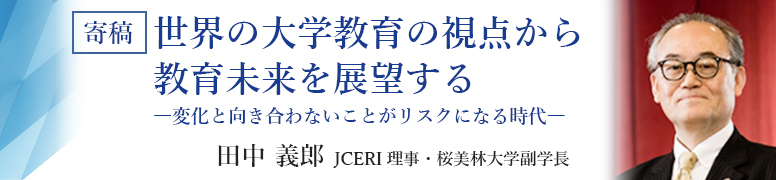
- この記事のポイント!
-
- この記事は、2023年度JCERIレポート「寄稿「世界の大学教育の視点から教育未来を展望する ―変化と向き合わないことがリスクになる時代―」」より作成しました。
多様化・グローバル化と高等教育の役割
教育はどこへ向かうのか?
日本には現在、概ね300万人、世界には3億人の大学生がいます。2億9,700万人の世界の大学生が、日本とは同じ価値観を必ずしも共有しない教育システムの下で学んでいます。今日の若者たちにとって「どう生きるか?」は大変に重要なテーマです。同時に、学校(教育)選択やキャリアプランニングにおいては、「なぜ、それを選択するのか?」は、「何を、選択するのか?」よりもずっと重要なテーマとなっています。
中等教育では、イギリスの名門パブリックスクール(13-18歳が在学する中等教育学校である)イートン・カレッジの教育について、イートンの卒業生で教育者のウイリアム・コーリーが以下のように述べています(注1)。
Learning is “Great Adventure”。君たちがこの偉大な学校へ通うのは知識を得る為ではない。技術と習慣を身につける為だ。関心を持つ習慣、表現する技術、何か注目すべきものを見た瞬間にすぐ頭脳を新しいものに向かわせることのできる技術、他人の思想にすぐさま入り込んで行ける技術、非難や反駁を素直に受け入れる習慣、賛成・反対をその度合いに相応しい言葉で表明する技術、細かい点も正確に見極める習慣、手持ちの時間内で何ができるかを見極める技術—それらを身につける為、また、分別を養う為、眼識を持つ為、頭脳を奮起させ、覚醒させる為だ。なにより、自己を認識する為に、君たちはこの偉大な学校に通っているのだ。
こうしたイートン・カレッジの教育姿勢は、今なお、中等教育のグローバル・スタンダードを象徴しているのです。
あらためて、高等教育の役割
世界は変化しています。寿命が長くなりました。予測は簡単ですが、結果は必ずしも予測を後押ししてはくれません。複数のキャリア、グローバリゼーション、予期せぬ緊急の社会問題は常に発生しており、早急に解決に向けて対応する必要があります。テクノロジーとメディアのおかげで、問題と解決策はより急速に拡散するでしょう。しかし予測不可能で予想外の環境では、問題は非常に複雑になります。世界的ビジョンの構築、世界中の高等教育機関間の国際交流活動の強化や共有プラットフォームの開発、学生・教職員の交流や共同研究プロジェクトの推進、高等教育リーダーの意見や活動の国際社会への発信など、 我々は、高等教育を通して国際的に競争力のある持続可能な社会を発展させ、平和と国際理解を促進することをめざす必要があります。
私たちのグローバル・ビジョンは非常に重要
そのような状況下で、高等教育システムがグローバルな視点をどの程度その教育システムの中に取り入れているかが重要になります。最良の方法はコラボレーション(協働)です。これにより、研究者、学生、機関などが単独で作業するよりはるかに大きな成果が生まれることが期待されます。そして協働は国境を越えた問題を克服するために必要な手段なのです。Reich (1991)(注2) はこう述べています。 「私たちは今、来世紀の政治と経済を再編する変革の時代を生きています。国家製品や国家技術、国家企業、国家産業は存在しなくなります。私たちがその概念を理解するようになったので、もはや国家経済は存在しません。国境の中に根を張り続けるのは、国家を構成する人々だけなのです。」 そして、今は2024年です。戦略的かつ成功裡に多様化とグローバル化を達成することで、大学は社会における知的リーダーとしての地位を維持し、発展させることができるでしょう。世界中で同時進行する多様化とグローバル化にどう対処するかの議論がされがちですが、これは方向が間違っています。 多様化とグローバル化は、地球社会の持続的発展にとって優れた原動力であり、大学にとっても、不確実な世界の未来を切り拓く人材を世界に送り出すための優れた戦略となるはずです。
しかし我が国の場合、大学はアドミッションの領域のみが議論されがちで、しかも如何に選抜するかにフォーカスされますが、何のためになぜそのように選抜するのかについてはなかなか明解な回答を見つけることができないのが現状です。まずビジョンありきの原則を再認識すべきです。
人の心を動かし、世界のイノベーションをリードする「リンガ・フランカ」
今私たちの世界には、環境や平和など、関連する将来の問題も含めて、将来の世界の枠組みを議論するための新たな言語(リンガ・フランカ)が必要であると、私は考えています。たとえばSDGsは、今や世界共通言語として機能し、実際、大きな意味を持っています。また、新しいGLOCAL な (高等教育) プラットフォームの概念として「アジア・バカロレア(注3) 」を構築するというアイデアが生まれつつあります。それは、多様化とグローバル化が人類の共存を実現するために達成すべき目標であるという認識から導かれたものです。多様性とグローバル化の実現と成熟によって、人類は持続可能な形でさらなる発展をめざせるのです。高等教育はこの目標を達成するための強力な原動力であり、すべての社会と人々の希望であり、かつ機会でなければなりません。
変化と向き合わないことがリスクになる時代の教育
初中等教育を担う教員の資質とは―獲得すべき未来志向の能力(Skills)

現在、そして将来の初中等教育は、こうした高等教育に進学する若者たちに対して学修に伴う社会的責任を伝え、相応の大学進学準備(予科)教育を提供できなければなりません。そこで学ぶ者たちは、しなやかに思考し、平均的であることに満足せず、自身の特長や可能性の未来を信じて、大学という場(機会)を自身の成長のために最大限に活用し、自らが主体的に創るその後の豊かな人生の準備ができる、若者たちとなるはずです。
高等教育の転換課題に直面して、新たな時代で求められる若者が育つには、教員自身もまた幼児・児童・生徒たちの教育に対して、アクティブに行動できる能力を獲得することが必要と考えます。私は、諸外国の教育者たちとのディスカッションを通じて、子どもたちの学習成果に特に大きな影響を与えると思われる専門職としての教員のスキルには、以下のものがあると考えています。
- Skill 1
- 自身が担っている教育課程より上位課程の高次の学びに精通し、それを踏まえて教育を実践できる
- Skill 2
- 探究アプローチによる学習動機づけを理解・実践できる
- Skill 3
- 子ども個々の自然な好奇心や創造性を理解し、育むことができる
- Skill 4
- 子どもたちが情報を鵜呑みにせず、深く思考し表現できるように、培うことができる
- Skill 5
- 子どもたちが深く理解する思考・姿勢を形成することができる
- Skill 6
- 子どもたちがすべての人たちの正義、公平性、多様性、包括性を尊重する姿勢を育み、そして、国際秩序(政治、経済、教育、文化、等)の創造に貢献する姿勢を醸成することができる
- Skill 7
- 子どもたちが学び続ける日常が当たり前になるように導くことができる

これらのスキルを獲得していくことが、初中等教育を担う教員の未来志向の能力といえるのではないでしょうか。
「高等教育」の質保証の共通フレームワークを通じて、目標と目的を再評価する
21世紀に入り、すでに世紀の4分の1が過ぎ、世界中の高等教育機関は、質保証の共通の枠組みを通じて目標と目的を見直しています。課題は、アクセス、拡大、民営化、遠隔教育、テクノロジー、分散化、グローバリゼーション、平和、SDGsなどの言葉として知られています。私たちがこれまで受けてきた教育は、予想される問題の解決方法を教えるのには効果的でしたが、予想外の問題を解決する方法・解決策は示されていません。多くの場合、高等教育は依然として保守的な価値観(自主性、エリートの地位など)を維持しながら、同時に新たなグローバル化の状況に適応しなければならないという課題に直面しています。
今、私たちは「教育」において新しい知恵を働かせなければなりません。制度を改革することは簡単ではありませんが、人々の考え方(マインドセット)を変えることはさらに困難です。教育は世界と考え方を変える強力な原動力です。私たちは教育を通じて、個人が決意と覚悟を持って理想に向かって進んでいくと信じています。今、私たちは何もしないことがリスクとなる時代に突入しており、人類には備えが求められています。教育は、この人類革新に大きく貢献することができるのです。
グローバルな視点と高等教育の意味
グローバルにトンガル!とは?
高等教育が国連憲章に由来する学術コミュニティのグローバルな視点をうまく受け入れるためには、時代遅れの孤立形態を打ち破り、国境の持つ制限を乗り越えた学生、研究者、機関の真の協力を促進する必要があります。
そうすることで、高等教育は、国境を越える労働力として学生が価値ある成功(自己実現)を収めることを支援できるでしょう。これにより、学生は、ダイナミックで自由な、だが、あまり職能が明確ではない職場でもパフォーマンスを最大限に発揮できるようになります。これは、問題と解決策がこれまで以上に急速に拡散する現在の枠組みを考慮することをも意味します。SDGsはそのような価値ある試みの重要な一つです。では、このために今我々が貢献できることは何でしょうか?グローバルなプラットフォームを構築し、その中で一緒にやれることを見つけ、互いに協働して、良い仕事ができることを望みます!
Are you ready to keep learning?
最後に、検討すべき大きな課題を述べておきます。なぜ多くの人が高等教育を受けなければならないのでしょうか? 私たちの現在の不安は、「将来の社会」の要件を予測することが難しいことから生じます。私たちはより変化しやすく、より複雑で、かつ不透明な時代を迎えることになるでしょう。時代は、国際的な協力と共生と同時に、国際競争力の強化も求めています。少子高齢化社会は、生産年齢人口が大幅に減少し、産業構造や雇用に大きな影響を与えます。専門職の教育・再教育を含めたアップスキリングに対する社会的ニーズはますます高まっていくでしょう。
しかし我が国において、いわゆる教養教育答申(注4) 以降の教養教育(Liberal Arts)重点化の影響は大きなものがあり、その結果、専門学術・専門職(Professional)教育は、アメリカの様に大学院レベルで設計・実行しなければなりません。いわゆるアメリカ大学モデルであり、大学院(Graduate Schools)教育を発明したアメリカの経験に学ぶものですが、制度設計が全く追いついてない現実に直面しています。結果、専門学術・専門職(Professional)教育の空洞化が進行します。豊かな未来社会の発展の原動力である科学研究は急速に進歩し、高次の知識やスキルを獲得する教育と共に学際的かつ総合的な学術研究がこれまで以上に求められます。これは、高等教育を取り巻く環境が大きく変化し、新しい時代では、高等教育機関における「知」の抜本的な再構築が必要となることを示しています。そして、高次の21世紀型スキルは誰に対しても求められます。高次の21世紀型スキルとは、知識、スキル(コミュニケーション、意思決定、適応的問題解決、適応性、状況認識)、属性・能力(適応的専門知識力、創造的思考力、メタ認知力、チームワーク力)を表します。では、 「(高等)学習」はいつ始めるのが最適でしょうか、「(高等)学習は何のためにあるのでしょうか」、つまり・・・、それは、学校への準備、大学への準備、キャリアへの準備、そして人生への準備、・・・でしょうか?世界は高等教育に未来志向のリーダーシップと戦略的思考を期待しています。さて、こうした時代、私たちはこれらの課題とどう向き合いますか?
- 注1.
Eaton Reform (London: Longman, Green, Longman & Roberts, 1861),pp.6-7. イートン校のウイリアム・コーリーの言葉。
- 注2. Robert Reich
Robert Reich, THE WORK OF NATIONS, Knopf, 1991
- 注3. アジア・バカロレア
EUのERASMUS計画のように学生の流動化を活性化させる、アジア域内大学共通入学資格「(大学進学準備教育としての)カレッジ教養力育成」プログラム。2023年台湾の大葉大学で開催された「国際大学教養教育会議」や韓国「大学教養教育研究会議(LibEduCol)」で田中が提案した。アジア域内の多様な文化的価値をグローバル化時代の長所として捉え、クロスポリネーション・アプローチ(アジア域内の多様な文化的価値を背景に生み出される固有のアイデアや新しい発想を相互に尊重し受け入れ合うことで、新たな価値の創造や相互依存への貢献を実体化する方法)を特徴とする。
- 注4. 教養教育答申
平成14年(2002年)の中教審答申「新しい時代における教養教育の在り方について(答申)」。
田中 義郎(たなか・よしろう)
桜美林大学大学院教授・副学長(国際・キャリア担当)。学校法人桜美林学園理事。UCLA教育学大学院博士課程修了(Ph.D.,1985)。2013-20年UNAI国連アカデミックインパクト・SDGsプロジェクト推進ディレクター。2014-21年IAUP(世界大学総長協会) Executive Committee Member。教育成果の測定・評価に関するアメリカ大学共同研究プロジェクトおよびUCLA=CRESST、UCLA国際教育開発研究センター国際アドバイザー、EWC=APHERP(East West Center = Asia Pacific Higher Education Research Partnership)Executive Committee Member、韓国KEDI(Korean Educational Development Institute)中等教育におけるリベラルアーツプログラムの開発に関する国際アドバイザー、等を務めてきた。専門は、比較・国際高等教育学。主に、大学教学マネジメント、大学入試制度デザイン、高大接続、大学カリキュラムの分析、開発、運用、評価を国際比較およびグローバル・スタンダードとの距離感を軸に研究している。
※所属・役職は2024年3月時点のもの
- あわせて読みたい
-
- ウズベキスタンでの体験を通して感じた「日本型教育」の強みと課題(しもまっちハイスクール・盛岡白百合学園 下町壽男 先生)
- 充実した教員研修で学校の質向上を図る台湾(昭和女子大学附属昭和中学校・高等学校校長 真下峯子先生)
- ウェルビーイングから考える日本の学校のあり方(内閣府 白井俊氏)
- JCERIレポート
日本教育研究イノベーションセンター(JCERI)による、これからの高校教育・大学教育・大学入試をテーマとした研究者・実践者との対話の内容をレポートしています。
この記事をシェアする



