- 2023年06月26日

この記事をシェアする
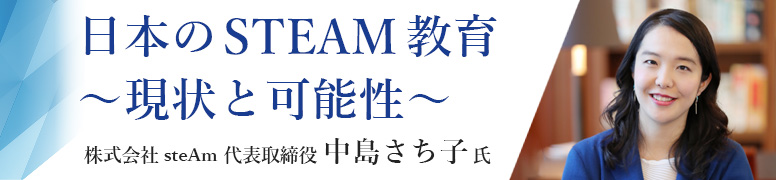
- この記事のポイント!
-
- 3
- メンターの重要性
- この記事は、2022年度JCERIレポート「STEAM教育の導入が、本来あるべき学びの姿を問い直すチャンスになる」より作成しました。
日本のSTEAM教育の課題
答えが一つではない時代に突入した危機感からSTEAM教育が広まる

21世紀初頭から、爆発的なテクノロジーの進化に伴って、世界中で広まったのがSTEAM教育(注1)です。その背景には、答えが一つではない時代に突入し、従来の知識注入型の教育では、未来の価値の作り手は育成できないのではないか、という危機感があったと思います。
ところが、日本でも同様の問題意識を共有していたはずなのに、なかなか導入が進みませんでした。これは当初のSTEM教育の文脈が伝わらず、「理数教育なら、日本はすでに十分に充実している」と、勘違いされたからかもしれません。A(Art)が加わったことによって、ようやくその思想が理解され、取り組みが活発化しています。
ただし、海外とは多少事情が異なる面もあります。海外では人種やジェンダー、障害の有無、経済格差などを超えた形でのSTEAM教育を標榜しています。こうした格差是正は国家的課題でもありますから、国や自治体主導で政策的に取り組んでいるケースが多いのが特色です。
この多様性の面については、日本はまだ立ち遅れています。どうしても価値観や育った環境が似た生徒同士の活動に終始しがちで、ダイナミックさに欠けると言うか、まったく新たな発想のものが生まれない傾向がある気がします。

文理を融合させた活動がSTEAM教育の最大のメリット
私はSTEAM教育を戦略的に推進してきた一人ですが、それはこの教育に多大な可能性を感じたからです。とりわけ大きなメリットと言えるのが、文理を融合させた活動が展開されることです。
日本では文系、理系が早めにきっちり分かれるとともに、いわゆるオタク文化で、良く言えば興味を持った一つの分野を深掘りするのが得意です。嵌まると没頭・追究するので、クリエイティビティやオリジナリティが高まり、それが日本のものづくり産業を支えてきたことも確かです。
「探究学習」でも、SSH(スーパーサイエンスハイスクール)などでは世界に誇れるようなハイレベルな成果をあげています。
一方で、日本の弱みになっているのが横の連携です。
新しい価値とは、いろんな分野が多角的に混じり合う中で創り出されるものです。けれども、日本人は文系と理系を融合させた問いが、なかなか立てられないのです。
今後は、STEAM教育が広まることによって、多様な人々と協同して、複数の分野が絡み合うような課題にチャレンジする、プロジェクトベースの活動が増えることが期待されます。
STEAM教育で大切な「問い」と「ワクワク」
生徒に問い続けることで問いの質が深まっていく
STEAM教育では、まず自分なりの問いを立て、プロジェクトを立ち上げ、多様な協力者と助け合いながら、テクノロジーやエンジニアリングなどを駆使して、問題解決を図っていきます。
世界の子どもたちは、幼い頃から「あなたはどう考えるのか」を聞かれるのが習慣になっているところも多くあります。
幼稚園児でも、けっこうロジカルに、かつ親や先生に忖度せずに意見を言います。それが当たり前の環境ですと、必然的に問いも深まっていきます。
それに対して、日本の子どもたちは、親や先生の言い付けを守って育ってきたことが多いので、踏み込んだ問いになっていなかったり、問いそのものが生まれない場合もあります。
この点については、海外との生活習慣の違いが原因ですから、慣れで解消するしかありません。生徒の問いの質が悪くても、先生方はがっかりせず、「なぜそう考えたのか」と、問い続けることが大切です。
そうやって突き詰めていけば、生徒にもやがて自分の考えの本質が見えたり、自分なりの意見を持ってもいいと分かって自尊心を高めたりするようになります。そうすればだんだんと生徒の問いも深まってくるでしょう。
生徒も先生もワクワク感を持つことが重要なポイント
STEAM教育を実りあるものにするためには、ワクワク感が大切になります。「自分のアイデアで何かを作れるかもしれない」「誰かが自分の意見を面白いと言ってくれた」といった経験が、自己肯定感も高めます。
それに加えて、先生方のワクワク感も重要なポイントです。
本来、先生方は教えることによって生徒が分かるようになる喜びだけでなく、生徒たちと向き合うこと自体にもワクワクされていたはずです。その原点に立ち戻ることが大切になるのではないでしょうか。
とはいえ、現状、STEAMや探究など新しいワードばかり降ってくる先生方のストレスは相当なものと推察されます。STEAM教育の経験がなく、ほとんど手がかりのない状態で、授業を作っていかないといけないからです。
幸い、経済産業省「未来の教室」の「STEAMライブラリー」で、具体事例が少しずつ紹介されつつあります。「これなら多少アレンジすれば、本校でも取り入れられる」といった事例もあるはずで、活用していただきたいと思います。
メンターの重要性
誰でも自由にものづくりが体験できる「ライブラリ・メイカースペース」
ところで、世界のSTEAM教育はいまや、学校の枠を超えたところで動き始めています。
私が注目しているのが「ライブラリ・メイカースペース」です。図書館に3Dプリンターやロボットなどを配備し、誰でも自由に使ってものづくりが体験できます。
これは先ほど申し上げた格差是正の狙いもあります。テクノロジーに出会う機会が不平等なことが、将来のキャリアに影響し、格差につながっている面もあるからです。このスペースで遊ぶ中で、自分なりの問いを見つけて、深い学びにつなげる子どももいるようです。
日本でも同様のスペースはあるのですが、残念ながらあまり使われていません。メンターの不足が一つの原因です。
子どもたちが問いを立てて、何かを作ろうとすれば、長い時間が必要になります。優しそうなメンターがいて、分からないことがあればすぐに応じて、応援してくれる雰囲気があれば、何回も訪れたくなるものです。
そこで現在、千葉県八千代市と香川県善通寺市の図書館で、週1回、大学生メンターを配置して、実証実験を実施しています。メンターの効果は大きく、たくさんの人が利用するようになっています。
STEAM教育ではメンターの果たす役割が大きい
海外では国の枠を超えた活動も進められています。その一つがニューヨーク科学アカデミーの「ジュニアアカデミー」です。
世界中から千人の若者が選抜され、協賛企業から提示された課題の解決に取り組んでいます。人種や宗教、ジェンダー、経済格差などの垣根を超えて、世界中の若者たちとオンライン上でコミュニケーションを図り、プロジェクトを進めていきます。
当然、テクノロジー、エンジニアリング、アートやデザイン、さらにはリベラルアーツまで、多様な分野を融合させて課題解決をめざします。最終的には協賛企業の前で発表を行います。

この活動で重要な役割を果たすのが、先述したメンターです。NY科学アカデミーに在籍する大学生、大学院生、卒業生、シニアで、理系分野を専攻したことがある人が中心です。専門知識を有するメンターがヒント、示唆を与えることによって、活動がスムーズにいく効果は絶大です。
海外では日本と違って、メンターの経験はキャリアに生かすことができます。入学や就職の際のアピール材料に使えるのです。自分のメリットになるため、メンターの活動に積極的に参加しようとする雰囲気が醸成されています。
日本の学校でSTEAM教育を行うときにも、メンターの配置が望まれます。けれども、メンターの経験が評価されない日本では、外部の人材を確保するのは一般的には難しくなるでしょう。
個人的には、余裕のある企業が、人材育成を兼ねて、給与を担保しつつ、メンターを派遣する仕組みが構築されれば良いと考えています。それが実現されていない現状では、上級生やOB・OGの大学生などをメンターとして活用するのも一案かもしれません。

評価や学びの変化というチャンスを活かすには
どういう人物を求めているのか大学側には「思想」が必要になる
過渡期にあるのは教育だけでなく、大学入試も変わらざるを得ないでしょう。
単に正解が答えられる生徒より、自分で考えて、行動して、ときには失敗して、その理由を考えたり、他の人とコミュニケーションを図りながら自分なりのテクノロジーやプログラミングを作ったりといった経験を有する生徒のほうを、大学も望んでいると思います。
総合型選抜の増加もあって、これからの子どもたちには、早い段階から、探究やプロジェクト型学習など、自分で何かを創造することが求めれますし、それを入試の際にアピールする力も必要になります。
大学側も、そうした体験をきちんと評価し、「選抜」から「マッチング」へと、意識を転換させることが大切です。
そのために参考になるのが、海外で重要視されているポートフォリオやドキュメンテーション(ウェブ上での試行錯誤の記録)です。
自分の経験、成果をアピールする履歴書のようなものですが、ドキュメンテーションでは失敗も含めて自分が試行錯誤したことを記録します。失敗しても、そこからどう乗り越えたか、その強さ、たくましさが評価されるわけです。
こうした活動歴で「マッチング」する側の大学・企業には、どういう人物を求めている大学・企業なのか、思想が必要になります。どんなに思い切った入試制度を導入しても、そこに深い思想がなければ、良い人材を獲得することはできないでしょう。
まとめ
先生方の中には、探究や、STEAM教育のような学際的な学びに、恐怖心を抱いている向きもあるかもしれません。それはご自身が培われてきた教科を教えるスキルが生かせないと感じておられるからではないでしょうか。それは大きな誤解です。STEAM教育はむしろ、先生方の経験が生かせる教育なのです。
ただし、知識を教えるのではなく、違う形で生かせる教育です。たとえば、先生方が感じている数学や国語の楽しさを、生徒に伝えれば、すごく価値の高いものになるはずです。
いま、先生方が主体になって、答えが一つではない時代の新しい学びとは何か、あるいは本来あるべき学びの姿とは何か、改めて問い直すチャンスが到来しています。そこにうまくSTEAM教育が利用できればいいのではないかと、私は考えています。
- 注1. STEAM教育
科学・技術分野の経済的成長や革新・創造に特化した人材育成(Science, Technology, Engineering, Mathematics)教育に加え、芸術、⽂化、⽣活、経済、法律、政治、倫理等を含めた広い範囲でAを定義し、各教科等での学習を実社会での問題発⾒・解決に⽣かしていくための教科等横断的な学習。中島氏は「理数教育に創造的な教育を加えた分野横断的な学び」と規定している。『知識ゼロからのSTEAM教育』(幻冬舎)
中島 さち子(なかじま・さちこ)
株式会社steAm代表取締役。内閣府STEM Girls Ambassador。大阪・関西万博テーマ事業プロデューサー。 国際数学オリンピック金メダル受賞。東京大学理学部数学科卒。NY大学芸術学部ITP修士 (メディアアート) 。ジャズピアニスト兼数学研究者であり、科学・技術・工学・芸術・数学を融合した「STEAM教育」に取り組んでいる。
※所属・役職は2023年3月時点のもの
- あわせて読みたい
-
- 教員に求められるリベラルアーツ力(東京工業大学 副学長 上田紀行 教授)
- ICTで変わる高校教育と大学入試(授業デザイン研究所代表 三浦隆志 氏)
- 寄稿「2032年の学びと大学入試」(JCERI理事 名古屋大学名誉教授 安彦忠彦 先生)
- JCERIレポート
日本教育研究イノベーションセンター(JCERI)による、これからの高校教育・大学教育・大学入試をテーマとした研究者・実践者との対話の内容をレポートしています。
この記事をシェアする



