- 2023年07月18日

この記事をシェアする
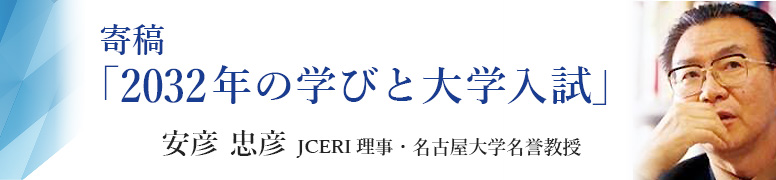
はじめに
これからの社会で求められる資質・能力を培う学び、そして大学入試はどう変化するのだろうか。河合塾グループの一般財団法人
日本教育研究イノベーションセンター(JCERI)では、この問いに対する思考を深めるべく、生徒・学生の学びについて実践を重ねて、現場の状況を知り尽くしている方々と意見交換を行いました。
本記事では、これらの意見交換について、JCERI理事で名古屋大学名誉教授の安彦忠彦先生に寄稿いただいた内容をご紹介します。
- この記事のポイント!
-
- この記事は、2022年度JCERIレポート「寄稿「2032年の学びと大学入試」」より作成しました。
「2032年の学びと大学入試」3氏の見解について
昨年度はこのテーマについて、主な研究者の方々5人(石井英真氏、溝上慎一氏、中村高康氏、西郡 大氏、白水 始氏)のご意見について拝読し、より長い原理に立つ観点からコメントをさせていただいた。今回は同じテーマについての、教育関係者の3氏、中島さち子氏(株式会社steAm代表取締役)、上田紀行氏(東京工業大学副学長)、三浦隆志氏(授業デザイン研究所代表)のご意見を拝読して、私なりの視点からコメントさせていただくことにする。
日本のSTEAM教育~現状と可能性~(株式会社steAm 代表取締役 中島さち子 氏)
まず、中島氏のご意見については、STEAM教育の推進者としての立場から、「答えが一つではない時代」に必要なものとして、STEAM教育の重要性が語られ、その具体的な導入の条件として「教員の方のワクワク感」「自由なモノづくり体験のできるライブラリ・メイカースペース」「メンター」の必要性に加えて、「大学側の思想」の必要性も提言している。
ただ、筆者の印象では「答えが一つではない時代」という通俗的な見方の背後には、「技術的関心」が隠れていると考える。つまり、「科学的」であるよりも「それを効果的に活用する際に、いろいろな組み合わせや構造化が可能になる」という意味で、「技術」開発的な関心の問題であると言ってよい。また、大学側の「思想」というのは、最近の日本の大学が行政から求められている「ポリシー」というものとほぼ同じではないだろうか。最後に触れている「マッチング」という用語では、筆者も、「大学側の求める学生像」と「受験生が求める大学像」とのマッチングとして、「入試=相互選択」に内容性格を変えるべきだと主張してきたので、この点には共感する。
さらに言うなら、最後のまとめに語られている「答えが一つではない時代の新しい学びとは何か、本来あるべき学びとは何か、改めて問い直すチャンス」の到来に関して、「どのような新しい学び」を問えると良いのか、ぜひお伺いしたかった。
教員に求められるリベラルアーツ力(東京工業大学 副学長 上田紀行 教授)
上田氏のご意見では、「中高の先生方に、生徒に『生きる意味』や『自分なりの軸』を、共に考えていく姿勢」を求めている。中身は「イノベーションを起こせる人材」の養成のために必要な条件を述べていると言ってよい。
東工大では独自の「リベラルアーツ教育」が行われていることが広く知られているが、「立志プロジェクト」や「教養卒論」を4人のグループ活動で展開し、現在では大学院にも拡張しているとのことである。その際、やはり教員の多様性と「リベラルアーツ力」の高さが問われるとされ、どれだけ多様な先生がいるかが重要なポイントだという。
筆者が関心を持ったのは、一つは「生きる意味」を取り戻すには「苦悩することとワクワクすること」の二つが重要だとの指摘と、「教員が自分の権力性を備えていることの自覚」により、自分と考えが合わない生徒の存在の多様性の承認・支援の必要性の強調であり、それを受けての大学入試の方法の多様化を望ましいと見ていることである。
また、カウンセラーの仕事が重要だとして、教員にそれを求めているのも注目される。ただ、「生きる意味」や「自分なりの軸」づくりのための具体策を、より明確に言ってくださるともっと有難かった。
ICTで変わる高校教育と大学入試(授業デザイン研究所代表 三浦隆志 氏)
三浦氏のご意見は、元公立高校の校長を経ているためか、教育行政の流れを前提にした上で、「学ぶ力を見るチャレンジングな入試が増える」ことを求めている。
「雑多の情報の中から必要な情報を読み取り、物事を立体的に考える力が重要」なので、そのためには「ICT活用による授業改善」と「主体性評価のためのタイミング・シーンの明確化と共有」「多様な情報から必要なものを取り出す力も読解力として育成」を強調し、それに資する「総合型・学校推薦型選抜などの年内入試など」の速やかな導入が勧められている。できれば、それを十全に可能にする現場の条件を示していただけたら、なおよかった。
3氏のご意見に触発された私見:学習の将来像と大学入試
予測不可能な「正解のない時代」に留意すべきこと
これら3氏の方々のご提案が一定の有効性をもつことは、筆者も認めざるを得ない。しかし、2032年と言えば、これから10年後の時期であり、その時の日本と世界の状況、さらには地球的規模の環境の変化による人類的課題等が、どのようなものであるかが容易には予想できない。
しかし、確実に起こる重大なことはいくつか挙げることができる。一つは気候危機・災害・疫病を含む地球環境の悪化、二つはエネルギー需要における電気エネルギーの支配、三つはICTやAIを含む仮想現実の拡大による人間社会の変質、四つは人間の寿命の長寿化・高齢化、五つは人類が抱える問題の総合的・重層的複雑化などである。

筆者は、この10年ほど「正解のない時代」になったのは自然な流れではなく、人間が生み出した状況であることを指摘しておきたい。言って見れば「天然・自然が人間の活動のマイナス面をカバーしてきた時代が終わり、その天然・自然によるカバーを超えるレベルまで人間の活動が進んで来てしまった時代に突入した」のである。
SDGsを国連が唱えざるを得なくなり、地質学者が「人新世」と呼び始めたゆえんである。「天然・自然」の枠内に守られ、抑えられていた人類の生活が、その枠の外に逸脱し始めたにもかかわらず、その枠外での生活の規範が定まらないために「正解のない時代」になったとも言えるからである。
しかし、「神ならぬ不完全な人間のなすこと」が「完全な解決を生む」という保証はまったくない。「人間の自己認識」の修正が必要ではないか、という問題意識を持つべきであろう。

そう考えると、単に近未来の社会が「複雑な問題の解決を求めて、粘り強く総合的に探究していく能力」を求めると言っても、まさにその中身が問題である。より本質的なレベルの教育の質を問わなければ、子どもは2032年以降も生きていくのだから、その後の自らの人間生活の在り方を念頭に、それを望ましいものに変えることができなければならない。
たとえ現在の国や企業が抱えている諸問題の解決のために必要な探究能力の育成方策として、STEAM教育やアクティブラーニング、そしてそれを受けての入試方法の改善・改革が唱えられているとしても、そのような技術的・方策的なことが、本当に2032年後の世界と日本の将来のために、プラスとなる保証があるのだろうか。
まずは、このような懸念すべき「陰の部分」をも念頭に置いて考える必要がある。若い世代はこの「陰の不安部分」に強い関心をもっているのに、大人の世代が技術的・方策的なことしか口にしないことを不満に思っている。
3氏のご意見について考える
実は、3氏の方々の提言の内、中島氏の大学入試の「マッチング」については、すでに筆者も以前から言ってきたことであること、大学側の「思想」の必要性についてはすでに「ポリシーやミッション」の明確化で一部始められているが、それ以上のものが必要だとすることも賛成であり、上田氏の「生きる意味」「自分独自の軸」とそのための「リベラルアーツ」中心の教養教育の必要と、そのために、まず教員が教養豊かで多様性を受容する存在でなければとの主張も同感である。
また三浦氏の主張も、多様な入試方法や年内入試の主張も、考え方・方策としては筆者も共感する。
それに加えて、筆者はその中身や実現可能性について述べておきたい。
例えば、中島氏の主張にある「大学側の教育の中身」について、筆者の求めるところは「大学教育の質を変えて、出口を厳しくすること」の方が、現在の入試=入口を問題にするよりも実りある成果が得られるのではないか、ということである。それには大学が大胆にその「教育」の中身と質を向上させねばならない。
上田氏の「リベラルアーツ」教育も、世界や文理の区別なく視野を広げさせるものとして、大学だけでなく高校でも行ってほしいとのことだが、筆者は以前から「liberal arts」教育は「子どもを、高校までの検定教科書中心の知識から解放して精神を自由にし、学問研究を通してそれまでの知識に吟味をかけること」に重点を置き、その際「教養」というものを、「自分の知識を、分野を超えた基礎部分にある、ある種の究極概念(例えば、死・生、無限・有限、絶対・相対などという概念)に突き合わせて、哲学的に世界や人生を考えることができるようにすること」と規定し、そのような観点から自分や周囲を見直すことが、高校・大学時代の青年期の主要な関心となるので、それに応えることが必要だ、と主張してきた。
また、三浦氏の「ICTやAIを活用して、多様で雑多な情報から真に必要な情報を読み取る読解力を育成すること」については、そのためにもっと「メディア・リテラシー」や「データ・リテラシー」を育てる教育を、国語教育か情報教育の中に含めて行うことが必要だ、と考えている。
これは、単なるreading skillの問題ではない。文脈や思想と結びつけて育てるものでなければならない。

以上、3氏の主張については、別に共通のこととして、「教員の力量」の問題が挙げられる。これは正当な指摘であり、最も解決困難な問題の一つである。また現在の教員が、現在の大学入試の方法で、果たして高校までで上記のような生徒を育成する余裕と能力があるか、と疑問に思わざるを得ない。
また二つ目として、高校教育までの「カリキュラムの過重(curriculum overload)=過密な内容」について学習上の心配が挙げられる。これは国際的に問題になっており、日本の子どもたちも「学習上の消化不良」を起こしていないだろうか?目標としている「探究能力」「問題解決能力」はめざすレベルで育成できているだろうか?
筆者は「学習の上滑り」を起こす心配はないかと問うてきたが、誰もそれを指摘していないけれども、この心配は決して杞憂ではないだろう。

そして、三つ目として、カリキュラムの主要部分を占める教科学習は「人工知能」のような「思考ロボット」を育てるだけで、端的に「人間性・人格性」を育てることができるのだろうか。「人材(財)養成」論が高校以下にも拡張されてしまった結果、子どもたちは「学ぶ機械=問題解決マシーン」として育つことを求められ、他の問題関心、特に子ども自身の「自己確立」といった、「自己意識」による自己実現へ向けての、種々の人生上の諸問題を考えることは軽視されてよいのだろうか。
最近の子どもの学習は、たとえ探究的であっても、何か社会が求める探究能力を身に付けさえすればよい、自分・自己は棚に上げておいて、その種の能力を身に付ければよい、といった形で求められ、学習者本人から見れば「一種の売り物としての能力」であって、自分自身の成長を感じる部分になるものとは見ていない傾向がある。
自分の自立のための学習ではないのである。いわば「何のための学習か」という「目的」が問われているのである。「人材(財)養成論」の落とし穴はここにあるように思われる。
自己の確立と「人材」としての育成のために
この点について、この10年以上筆者が主張してきたのは、「主体」としての自己の確立=「自立」を図る学習を保障するとともに、「客体」たる「人材」としての育成のためにも、高校以後をすべて「生涯学習」機関とし、年齢に関係なく出入り自由な、誰にも開かれた単位制の学習・教育の場所とすることである。

最近のICTの発展は学校の内と外を区別することを、まったくとは言えないが、かなり不要にしつつあり、高校・大学を生涯学習の場として利活用できる機関にした方が、それらの機関が少子化の影響を受けずに済む上でも望ましいと思われる。
その際、前者の自己確立が不明確だと、周囲の人は、後者のような探究能力のある人材であっても、そのような自立心のない学習者を信用せず、企業人も採用には慎重となり、一緒に働くことを好まないであろう。

入試方法は、基本的に入学する上級の学校で学ぶ能力として、国語・数学・外国語の3教科を必須とし、それ以外は、上述のような、分野を超える基礎教養と、専門とする志望分野の基礎知識があればよいのであり、その他は大学に入ってから学ぶこととすればよいと思われる。
まずは、一度にすべての大学で、というのでなく、どこかの大学・学部が、試行的にでもあえてやってみたらよいと考えている。その際、ペーパーテストのみでなく多様な方法を使ったらよい。その結果、多様な生徒や学生が入ってくることも望ましいことである。(例:名古屋大学附属学校の場合=下級の学校の教科の成績(内申)・教科外活動の成果(内申)・適性検査・小論文および面接、の4つを平等に配点。結果として多様な生徒が入学)
そして、出口である卒業試験を厳格にすることも、合わせて行うと良いと考える。それにより、その学校・大学が社会的に信用されるからである。
これまでの経緯から、入試という入口を100%問題ないものにすることはできないと考える。そこで逆に、出口である卒業・修了を厳格にして、大学教育の成果を高めることの方が現実的だと考える。参考例として挙げられるのは、秋田の国際教養大学であり、アメリカ風の大学だと言ってよい。
繰り返すが、今後の高校、大学は完全な単位制の生涯学習機関として活用されるべきではないだろうか。
安彦 忠彦(あびこ・ただひこ)
東京都生まれ。1964年3月東京大学教育学部卒業。同大学大学院教育学研究科博士課程1年中退後、大阪大学、愛知教育大学、名古屋大学、早稲田大学を経て、2021年3月まで神奈川大学特別招聘教授。名古屋大学教育学部附属中・高等学校長、同大学教育学部長などを歴任。博士(教育学)。名古屋大学名誉教授。2005年2月より第3期中央教育審議会正委員(第6期まで)。専門はカリキュラム学(主に中等)を中心に教育方法・教育評価。
※所属・役職は2023年3月時点のもの
- あわせて読みたい
-
- 教員に求められるリベラルアーツ力(東京工業大学 副学長 上田紀行 教授)
- ICTで変わる高校教育と大学入試(授業デザイン研究所代表 三浦隆志 氏)
- 日本のSTEAM教育~現状と可能性~(株式会社steAm 代表取締役 中島さち子 氏)
- JCERIレポート
日本教育研究イノベーションセンター(JCERI)による、これからの高校教育・大学教育・大学入試をテーマとした研究者・実践者との対話の内容をレポートしています。
この記事をシェアする



