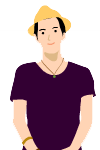数学の学習法
Questionあなたが行った効果的な数学の学習法を教えてください。
※特派員のプロフィールはアンケート回答時点(2023年度)のものです。

東北大学 薬学部 1年 K.W.特派員
※受験での必要度:共通テスト・2次私大ともに必要
典型問題を解けるようになったら、それをアウトプットする(2次レベルに応用する)練習をしました。そのときに、問題を見て解法が全く思い浮かばなければ答えを潔く見てしまっていいと思います。そして似ている典型問題を思い出したらそこに戻ってどう考えたらその2つの問題を紐づけられるのか考えていました(似ている問題がないものもあります)。入試で同じ問題はほとんど出ません。ですので、解法の引き出し方をいかに過去問で学ぶかが重要だと思います。
東京大学 理科一類 1年 R.I.特派員
※受験での必要度:共通テスト・2次私大ともに必要
問題を解く時に、なぜ自分はこの解き方を選んだのかを明確に確認するようにした。基礎的な段階では、まず自分が様々な思考回路をたどれる訓練をする。その次はその中で最も効率が良いものを取捨選択する訓練をする。


名古屋大学 医学部 1年 A.H.特派員
※受験での必要度:共通テスト・2次私大ともに必要
高校1年生の時から学校の授業の前には予習をして、授業が終わったその週までにその範囲の問題を学校でもらった参考書で解いた。そこで解けなかった問題にはチェックマークを付けた。そして学校のテストの前には、チェックマークがついているところを中心に問題を解けるまで2周、3周と何度も解きなおした。受験生になってからも同様。これで数学の偏差値が中学校卒業時に50だったのが、90まで上がった。(2回名大オープンで取りました)
九州大学 共創学部 1年 M.Y.特派員
※受験での必要度:共通テスト・2次私大ともに必要
分からないところは、友達や先生に質問して分からないままにしないようにした。どんなに基礎的でも、先生に質問したら自分で調べる以上のことが返って来ることが多かった。だからこそ、相性の良い先生を見つけて、どんどん聞きに行くことが大切。基礎問題は覚えるまで解いていた。


大分大学 理工学部 1年 わんぱく幼稚園a.k.aマッスルジム特派員
※受験での必要度:共通テスト・2次私大ともに必要
受験数学は一部の難関大学を除いて典型的な解法を理解し使えるようになるだけで合格点は取れるぐらいに戦えると思います。下手に難しい問題をやりがちですがそれは趣味であり、受験勉強ではありません。かくいう私も高校生の頃は定理を証明し、理解するまで次の分野に進めない等じっくりやりすぎて苦労したことが多かったです。受験勉強は学問的勉強とは別物であると割り切って、受かることだけにフォーカスする必要があると感じます。
大阪公立大学 現代システム科学域 1年 K.Y.特派員
※受験での必要度:共通テスト・2次私大ともに必要
苦手な人は最初は解答を見ながら勉強してもいいと思う。解答の方針、解法、解答の書き方を解答を見ながら勉強し、次に解くときには自力で解けるようにする。チャートや河合塾のテキストなど、教材を一冊決めてこの方法で自力で解ける問題を増やしていけば良いと思う。3周すればかなり力になるはず。共通テストは共通テスト形式の問題を数多く解いてスピード感や問題の傾向に慣れていくことが大切。
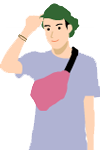

東北医科薬科大学 薬学部 1年 Y.S.特派員
※受験での必要度:共通テスト・2次私大ともに必要
数学は苦手だったため、基本的な問題の解法や公式を覚えることを大切にしていました。スキマ時間に公式を覚えたり、毎日1つでも数学の問題を解くことを心がけていました。模試の復習を大切にしていたので、数学は全ての問題を解き直し、解説と照らし合わせて自分の解き方が合っているかを確認しました。間違えた問題については、どこでどのように間違えたのかを書き出し、わからなかった公式を調べたり、解法を確認しました。自分だけでは解決できない問題があったときはそのままにせず、すぐに塾の先生に質問をし、早めに解決するようにしていました。そのような問題には付箋をはり、3日後に解き直して本当に定着しているかを確認していました。
東京経済大学 経営学部 1年 青赤特派員
※受験での必要度:共通テスト・2次私大ともに必要
まず、高三に入る前に基礎はできるようにしておくといいでしょう。僕はできていなかったため苦労しました。苦しいかもしれないけど、青チャートなどを使って大量の問題を解いておく、というのが結局一番伸びます(時間があれば)。確率、整数は文系数学には必須レベルで重要です。僕は1年生だった時これらが大の苦手だったのですが、絵を描くなど、数式から逃げることで理解できるようになりました。また、modは効果的です。ある程度の大学の整数問題ならこれを多用するだけで答えに辿り着けることもあります。余力があればぜひ取り組んでみてください。